
 10月3日は、十五夜でした。
10月3日は、十五夜でした。当地の昨日のお天気は、昼間は雨、雷、どうなるのかと思いましたが、夜には雲の間から、きれいなお月さまが顔を見せてくれました。
ビデオもカセットもなかった子供の頃、誰かにもらった古い童謡のソノシートを何度も何度も聞きました。
明るく楽しい歌ばかりの今の童謡に比べると、昔の童謡って…哀愁のあるメロディーもそうだけど、その歌詞は子供の歌なのに、物悲しいものが多かった。
「叱られて叱られて、あの子は町までお使いに、この子は坊やをねんねしな」
「金襴緞子(きんらんどんす)の帯しめながら、花嫁御寮はなぜ泣くのだろう」
なんとも極めつけは、そうです、「十五夜お月さん」だったよな~。歌詞は野口雨情のもの。
十五夜お月さん 御機嫌(ごきげん)さん
婆(ばあ)やは お暇(いとま) とりました
十五夜お月さん 妹(いもうと)は
田舎(いなか)へ貰(も)られて ゆきました
十五夜お月さん かかさんに
も一度わたしは 逢(あ)いたいな
「わたし」にどんな事情があったのかは知らないが、かっ、悲しすぎる…

時代背景もあるのだろうけど、日本もドラマ「おしん」のような貧しい時代があって、各家庭の事情も様々で子供も辛抱を強いられていたのでしょう。
ふられたときに、中島みゆきを聞いて、敢えてどんどん落ち込むのが癒しになると聞いたことがあるけど、苦労している子供たちの中には、お月さんを見上げては、この歌を歌って慰められた子もいたでしょうか。
お月さん、お月さん、子供たちのいじらしい願い、ちゃあんと聞いてくれましたよね。
今晩の満月も、とても美しいです。


















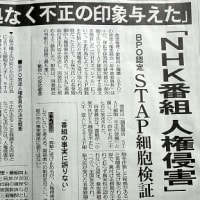







いつも、コメントを書きたくなる記事を(笑)
ありがとうございます。
わたくしめも、十五夜も十六夜も、しっかり堪能致しました。(^^♪
エネルギーの強い、すてきなお月さまでしたね。
>どんな事情があったのかは知らないが、かっ、悲しすぎる…
童謡や民謡って、けっこう哀しい歌詞が多いですよね。
それだけ私たちが人類として、民族として抱えている
過去の傷やトラウマ(痛み)が大きかったということなのかも。。。
それを癒すための美しい音楽という意味も、
きっとあるのだと思います。
(判りづらい文章でごめんなさい。)
歴史の長さだけ、人の営みはくりかえされます。
古今東西、その国や民族特有の音楽ってありますが、人々の心に寄り添って、歌い継がれ、奏でられてきたものなんでしょうね。
今でも、アジアやアフリカなどの子供たちは、昔の日本のような貧しい環境に置かれています。
また、今の日本でも、離婚率も高くなり親と離れて暮らす子供も、今は今でいることでしょう。
>それを癒すための美しい音楽という意味も、
きっとあるのだと思います。
音楽に力があると思うのは、やはり心を癒してくれるからですよね。
何もなくても、歌は歌うことができるし、お月さまは顔を出してくれます。
ありがたいなあ・・