:::
かんべえ(吉崎 達彦) :双日総合研究所チーフエコノミスト
:::
:::
アメリカのドナルド・トランプ大統領

は6月14日に79歳の誕生日を迎える。
そこはトランプさんのことなので、普通に「おめでとう、ミスタープレジデント!」では済まされない。
この日はなんと、首都ワシントンで軍事パレードが実施される。
もともと陸軍が創設250周年を予定していたものが、巨大な祝賀行事となるらしい。
ワシントンで軍事パレードが行われるのは、湾岸戦争があった1991年春以来のことである。
ちなみに翌日の6月15日は中国の国家主席である習近平氏
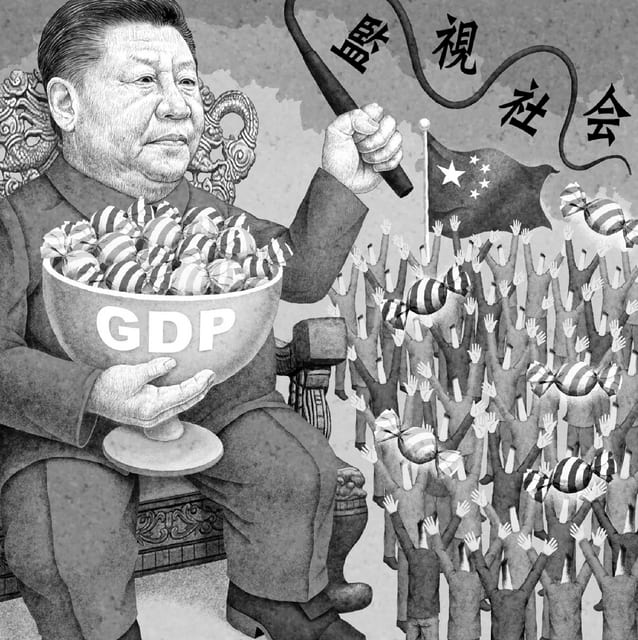
の72回目のお誕生日である。
米中2大国のトップは電話会談を行ったとのことだが、おそらくは「お誕生日エール」なども交わしつつ、建設的な意見交換となったもようである。
■ホワイトハウス内でにらみを利かせるミラー補佐官
ところでご高齢の大統領を支えている政権スタッフの中には、要所に40歳前後のミレニアル世代がキーパーソンとなっていることに気がついた。
これから政治、安全保障、金融、経済という4つの分野で、それぞれユニークな政策を目指している顔ぶれをご紹介するが、彼らを「ミレニアル四天王」と呼ぶのも一興であろう。
ミレニアル世代、その1人目。
大統領次席補佐官として、ホワイトハウス内ににらみを利かせているのはスティーブン・ミラー氏(39歳)である。
第1期トランプ政権ではスピーチライターとして頭角を現し、「忘れられた人々」などの印象的なフレーズを生み出した。
首席戦略官を務めたスティーブ・バノン氏とともに、「2人のスティーブ」と並び称されたのは語り草である。
第2期トランプ政権では多くの大統領令を起草し、大量の政策を一斉に発動して反対を未然に防ぐ「洪水戦略」(Flood the Zone)を主導している。
強烈な反・移民論者であり、関税政策でも強硬派として知られる。いわば「MAGA派」の筆頭だ。
ご本人はカリフォルニア州サンタモニカのリベラルな家庭と風土に育ったが、高校時代から急速に保守化した。
デューク大学で政治学を修め、共和党のジェフ・セッションズ上院議員(第1期トランプ政権で司法長官)の秘書を務めた。
そしてトランプ選対入り以降は、文字通り「水を得た魚」のごとくの活躍となった。
■「優先主義者」コルビー次官台頭、衰える「優越主義者」
ミレニアル世代、その2人目。
国防次官に就任したエルブリッジ・コルビー氏は45歳。
ハーバード大卒、イエール大院卒の秀才で、核戦略や軍備管理、情報分野などに精通する。
国防総省内では長官、副長官に次ぐナンバースリーだが、政策面の実務を担う。
過去にこのポストを経験した者としては、イラク戦争で「ネオコン」の代表格となったポール・ウォルフォビッツ氏、「ヒラリーが勝てば初の女性国防長官」と噂されたミシェル・フロノイ氏などがいる。
コルビー氏は自らを「優先主義者」(プライオリタイザー)と規定する。
アメリカの国力は低下しているのだから、欧州や中東への関与を減少させ、インド太平洋地域に専念して中国に対抗せよと説く。
ただし同盟国に対しても自助努力を求め、
「日本はGDP比3%の防衛費が必要だ」と指摘している。
ちなみに従来通り、アメリカは覇権国として世界ににらみを利かすべし、という「優越主義者」(プライマシスト)の勢力は、今や風前の灯火となっている。逆に力を増しているのが「抑制主義者」(レストレイナーズ)だ。
アメリカは対外不介入主義でいい。自国防衛にのみ専念して、駐留米軍も縮小してしまえ、と説く。
コルビー氏はいわばその中間の立場である。
シンガポール生まれで、少年期は東京で暮らしたという経歴を持ち、それだけにアメリカにとってアジアの重要性を熟知している。
「中国に対抗するためにもアジアへの関与を」と主張するのだが、トランプ政権内ではかならずしも主流派となっていない点には注意が必要だ。
■経済政策の「理論的支柱」ミラン経済諮問委員会委員長
ミレニアル世代、その3人目。
経済政策の理論的支柱となっているのは、スティーブン・ミラン大統領経済諮問委員会委員長(40歳)である。
マサチューセッツ州ボストン出身。
ボストン大学からハーバード大学で経済学博士号を取得。
そして財務省勤務を経てヘッジファンドへ。
そこまではよくある経歴だが、昨年11月に論文「国際貿易再構築のためのユーザーズガイド」を発表して注目を集めた。
アメリカは覇権国として、世界に対して安全保障と基軸通貨を提供してきた。しかしその結果、アメリカの負担は増大し、特に必要以上のドル高によって製造業が衰退してしまった。
そこでコストを同盟国に負担させるべく、関税と多国間通貨協定が必要であると説く。
ドル高を是正する「マールアラーゴ合意」の発案者、と言えば話が早いかもしれない。
ここで多くの読者は、「おいおい、アメリカは基軸通貨国であるお陰でメリットも得ているじゃないか」と突っ込みたくなるだろう。
①外国が外貨準備として米国債を買ってくれる、
②その結果、アメリカの長期金利は低下する、
③しかも為替レートを気にしなくていい、などである。
日本のような国から見れば、しみじみ羨ましい。
が、こんな風に「被害者意識」を共有している点が、今のトランプ政権内の気分である。
真面目な話、
今はスコット・ベッセント財務長官が「強いドル政策」で食い止めてくれているけれども、トランプ大統領以下が「ドル安願望」を抱えていることは気になるところである。
■「改革保守派」キャス氏は「次期共和党政権」での活躍も
ミレニアル世代、その4人目。
政府の役職には就いてはいないが、保守系シンクタンク「アメリカン・コンパス」の創設者オレン・キャス氏(42歳)を挙げておきたい。
自由貿易主義がアメリカの製造業を破壊して労働者を傷つけ、家庭やコミュニティまで崩壊したことを問題視する。
「相互関税」における一律10%の関税は、彼の意見具申によるものだという。
ボストン出身でハーバード大学ロースクール卒。
ベイン・アンド・カンパニーでコンサルタントとして勤務し、
2012年大統領選挙ではミット・ロムニー選対において、
国内政策の立案に従事した。
以前からJ・D・ヴァンス副大統領やマルコ・ルビオ国務長官と親交があり、「改革保守派」をもって任じる。
仮に2028年、2人のうちどちらかが次期大統領に当選するとしたら、
高い確率で次期政権内にポストを得るだろう。
キャス氏、今年3月に国際交流基金の招聘で来日し、
4月6日の「NHKスペシャル」 に登場し、
朝日新聞や中央公論など多くの媒体でインタビューを受けている。
ご覧になった方も少なくないだろう。
日本滞在中に視察した「高専」にいたく感銘を受けた由で、製造業の復権を目指す気持ちが切なる証拠であろう。
以上、「四天王」は筆者による勝手な命名である。
単にトランプ政権内のミレニアル世代、ということであれば、ヴァンス副大統領は40歳、ピート・ヘグセス国防長官が45歳とか、もっと大勢挙げることはできるのだ。
しかるに上記の4人は、いかにも第2期トランプ政権内の「気分」を伝えてくれるし、新世代の共和党スタッフとして今後も長く活躍していきそうである。
逆に言えば、民主党側に同様な存在が見当たらないことが、今ひとつ物足りなく感じられる。
そもそも「ミレニアル世代」とは、1981年=昭和58年(44歳)から1996年=平成8年(29歳)生まれを指す。
2000年=平成12年の「ミレニアム」(新世紀)を挟んで成人したことから、
この呼び名が定着した。
大人になる過程で2001年=平成13年の「9・11テロ事件」や2008年=平成20年の「リーマンショック」を経験し、「パックス・アメリカーナ」とはほとんど縁がない。
むしろ「親の時代よりも豊かになれない」ことに悩み、
学生ローンはキツイし、
住宅は値上がりしてしまって買えないし、
薬物フェンタニルによる中毒で多くの仲間を失ってきた。
彼らの世代が構想する政策が「明るい」ものにならないのは、なるほど無理からぬことかもしれない。
日本風に言えば「氷河期世代」という言葉がピッタリだろう。
■これからは「次世代のアメリカ」に注意を払う必要
キャス氏は日本でのインタビューにおいて、「トランプ大統領は過渡期的な人物」と評している。
次の2028年選挙では、新たな共和党連合が生まれるであろうとも。
つまり彼の眼中にあるのは、すでに「トランプ後」のアメリカ政治なのである。
すでにミレニアル世代は、数の面で「ベビーブーマー」(1946〜1964年生まれ。
日本風に言えば団塊世代)を上回っている。
その間の「X世代」(1965〜1980年生まれ。
日本風に言えば「新人類世代」)が目立たないので、
「次は自分たちの出番」と考えていそうである。
こうしてみると「後生畏るべし」である。われわれもトランプ氏の一挙手一投足ばかりではなく、「次世代のアメリカ」に対して注意を払っていく必要がありそうだ。
それに真面目な話、
トランプさんの言動をいくら追いかけても、疲れるばっかりなんだもん
(本編はここで終了です。この後は競馬好きの筆者が週末のレースを予想するコーナーです。あらかじめご了承ください)。以下略














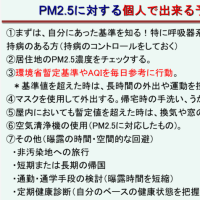
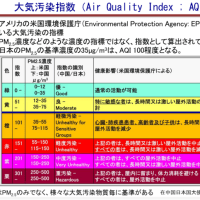
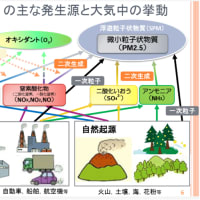



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます