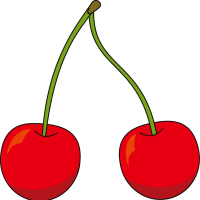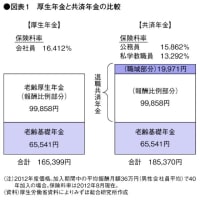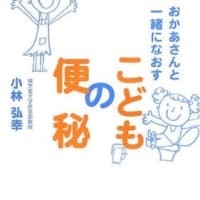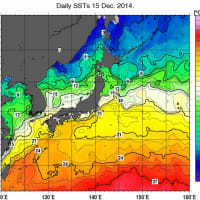先日、東京タワーに遊びに行った際、近くの増上寺にも足を運んでみました。徳川家の菩提寺として有名なお寺ですね。最近はきゃりーぱみゅぱみゅさんがライブをしたり、お寺全体を使ってプロジェクションマッピングを実施していたことでも話題になりました
さてこの増上寺。この間テレビで紹介された時、「浄土宗の大本山」と説明がされていました。
ん?確か高校の日本史で学んだ記憶によると、浄土宗の大本山は京都の知恩院だったような…。でもまてよ?知恩院は大本山ではなく、総本山だったよな…
大本山と総本山。似ている言葉が出てきてしまい、混乱してしまいました
そんなわけで調べてみると次のようなことが分かりました。
まずこの総本山とか大本山というのは、各宗派に属するお寺の位置づけを表す言葉なのだそうです。現代風の言葉で「ランク付け」と言っても良いかもしれません。
一般的に総本山が最も高い位置にあたり、その下に大本山・本山と続くようです。先述の浄土宗の場合、日本史で習った通り総本山は知恩院でした。それに続く大本山に、今回取り上げた増上寺や、金戒光明寺(京都)、善光寺大本願(長野)があります
さらに次に続く本山として、蓮華寺(滋賀)があり、総本山→大本山→本山→一般寺院といったピラミッド型のような並びで宗派のお寺が管理されていました
なるへそ。同じ宗派の中にも“格”みたいなものがあって、一定の序列があるんですね。この辺はそれほど違和感はありません。
ただし全ての宗派が同様の体制をしいているわけではないようです
例えば曹洞宗の場合、総本山は指定されていません。大本山として永平寺(福井)・総持寺(神奈川)の2つの寺院が設定されています。この辺は宗派の考え方もあるのでしょう
これらお寺の格付けができたのには、江戸時代の幕府による政策が影響しているようです。
幕府が幕藩体制を揺るがしうる存在として警戒していたのが「宗教」です。踏み絵に見られるキリスト教の弾圧は有名ですね。
その目は古来から日本に根付いていた仏教にも向けられました。全国各地に建つ寺院が各々勝手な行動を取らないよう、各宗派に本山を設定し、厳しく統制しようとしたのでした。これがいわゆる本山末寺制というやつです
なるへそ、なるへそ。つまり全ての寺院はどこかの本山につながっているんですね
さっそく近所にあるお寺がどの本山ちながりがあるのか、調べてみようと思います

さてこの増上寺。この間テレビで紹介された時、「浄土宗の大本山」と説明がされていました。
ん?確か高校の日本史で学んだ記憶によると、浄土宗の大本山は京都の知恩院だったような…。でもまてよ?知恩院は大本山ではなく、総本山だったよな…

大本山と総本山。似ている言葉が出てきてしまい、混乱してしまいました

そんなわけで調べてみると次のようなことが分かりました。
まずこの総本山とか大本山というのは、各宗派に属するお寺の位置づけを表す言葉なのだそうです。現代風の言葉で「ランク付け」と言っても良いかもしれません。
一般的に総本山が最も高い位置にあたり、その下に大本山・本山と続くようです。先述の浄土宗の場合、日本史で習った通り総本山は知恩院でした。それに続く大本山に、今回取り上げた増上寺や、金戒光明寺(京都)、善光寺大本願(長野)があります

さらに次に続く本山として、蓮華寺(滋賀)があり、総本山→大本山→本山→一般寺院といったピラミッド型のような並びで宗派のお寺が管理されていました

なるへそ。同じ宗派の中にも“格”みたいなものがあって、一定の序列があるんですね。この辺はそれほど違和感はありません。
ただし全ての宗派が同様の体制をしいているわけではないようです

例えば曹洞宗の場合、総本山は指定されていません。大本山として永平寺(福井)・総持寺(神奈川)の2つの寺院が設定されています。この辺は宗派の考え方もあるのでしょう

これらお寺の格付けができたのには、江戸時代の幕府による政策が影響しているようです。
幕府が幕藩体制を揺るがしうる存在として警戒していたのが「宗教」です。踏み絵に見られるキリスト教の弾圧は有名ですね。
その目は古来から日本に根付いていた仏教にも向けられました。全国各地に建つ寺院が各々勝手な行動を取らないよう、各宗派に本山を設定し、厳しく統制しようとしたのでした。これがいわゆる本山末寺制というやつです

なるへそ、なるへそ。つまり全ての寺院はどこかの本山につながっているんですね

さっそく近所にあるお寺がどの本山ちながりがあるのか、調べてみようと思います