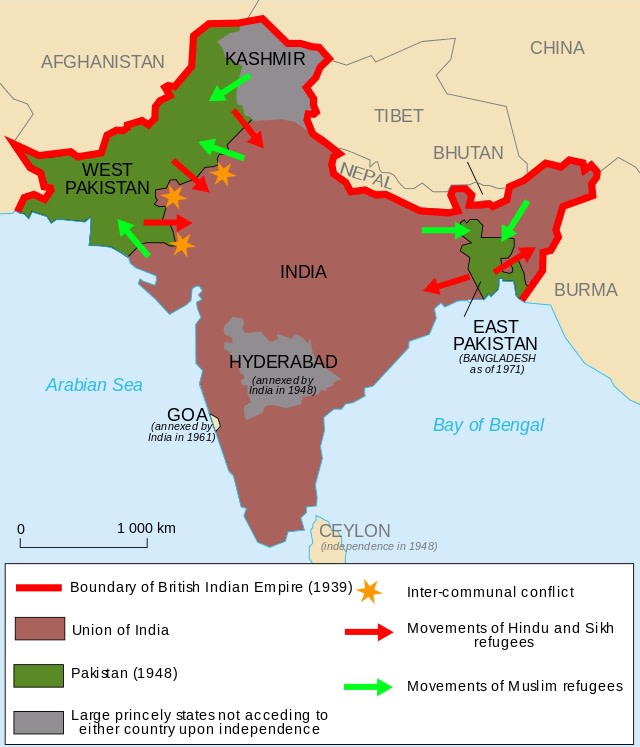4月9日、天皇皇后両陛下がパラオを訪問されました。このパラオは太平洋戦争の激戦地で、10000人以上の日本兵が命を落とした場所です。
今回の訪問は天皇陛下の強いご意向があったと言われています。ご高齢なうえに、宿泊先はホテルではなく、海上自衛隊の船の上でした。お身体に負担をかけてまで慰霊を実現させたかったのでしょう。多くの人が陛下の姿に心を打たれたことと思います。
さて、今回の訪問を受け、テレビや新聞では、パラオの歴史について報じる場面も多かったように思います
私も知らなかったのですが、パラオは第一次世界大戦時に日本が進出した島です。当時、日本は日英同盟の流れから、イギリス・フランス・ロシアが結んだ連合国側をフォローする立場にありました。
連合国が相手にしていたのが、ドイツ・イタリア・オーストリアで構成されていた三国同盟の国々です。第一次世界大戦は、日本から遠く離れたヨーロッパで起こった戦争です。しかし日本は上記の理由で、ドイツの統治下にあった地域に目をつけたのです。
それが、中国の山東省や南洋群島と呼ばれるエリアです。そしてこの中に、今回天皇陛下が訪問されたパラオも含まれていたのでした。
やがて第一次世界大戦は連合国側の勝利に終わります。戦後のパリ講和会議において、日本がその後も引き続き、パラオを含むいくつかのドイツ領を運営していくことが決まりました。
これを機に、パラオには多くの日本人が移住します。ドイツ領の時には進められなかった病院や学校の建設も行われます。また、現地の日本化もすすめられ、例えば現地人に対しての日本語教育なども行われていたようです。
日本の統治は、第二次世界大戦で日本が敗戦するまで続けられました。その期間は約30年です。
なるへそ、僕はてっきり太平洋戦争が始まってからパラオにも侵攻したのだと思っていました。なので30年も日本が統治していた事実にとても驚きました
長い歴史から見れば、30年はあっと言う間かもしれません。しかし、当時を懸命に生きてきた人にとっては、30年という期間は人生の大部分を締める色々な出来事がつまった濃厚なものだったに違いありません。
遠くパラオに渡った日本の人たちはどんな想いで暮らしていたんだろう。ふと、そんなことを考えてしまいました。
最初にも述べましたが、第二次世界大戦が始まると、パラオは激戦地へと変わります。特にペリリュー島での戦いが、被害が大きかったと聞きます。
今回、天皇陛下が訪問されたことによって、多くの人がパラオの歴史を知ることになったはずです。僕もその1人です。陛下はご自身の行動がきっかけとなり、日本国民が戦争について学んでくれることを望んでいたのかもしれませんね。
最後に、パラオの人々の中には、今も日本に親しみを持ってくれている人が多いそうです。過去に統治していたドイツや、戦後の管理者だったアメリカに比べると、日本はインフラを整備したりと現地の人たちにとっても有難い国だったようです。
これには、日本人の勝手な解釈が含まれているのかもしれません。ただ、信ぴょう性のある事実として、パラオ共和国の国旗は日本の日の丸に似たデザインになっているのです。
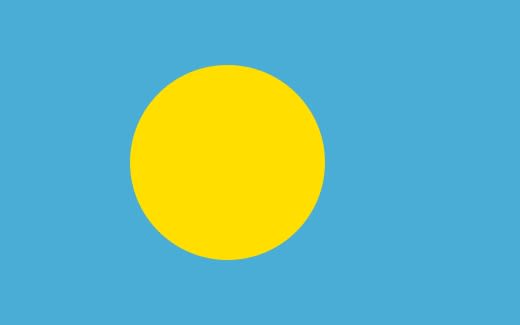
(ウィキペディアより
もし、日本を憎んでいたとしたら、国旗のデザインがこんなに似ることはないはずです。青い色の部分は海を、黄色い丸は月をモチーフにしているようです。
今回のニュースをきっかけに、パラオが1度は訪れてみたい国の一つになりました
今回の訪問は天皇陛下の強いご意向があったと言われています。ご高齢なうえに、宿泊先はホテルではなく、海上自衛隊の船の上でした。お身体に負担をかけてまで慰霊を実現させたかったのでしょう。多くの人が陛下の姿に心を打たれたことと思います。
さて、今回の訪問を受け、テレビや新聞では、パラオの歴史について報じる場面も多かったように思います

私も知らなかったのですが、パラオは第一次世界大戦時に日本が進出した島です。当時、日本は日英同盟の流れから、イギリス・フランス・ロシアが結んだ連合国側をフォローする立場にありました。
連合国が相手にしていたのが、ドイツ・イタリア・オーストリアで構成されていた三国同盟の国々です。第一次世界大戦は、日本から遠く離れたヨーロッパで起こった戦争です。しかし日本は上記の理由で、ドイツの統治下にあった地域に目をつけたのです。
それが、中国の山東省や南洋群島と呼ばれるエリアです。そしてこの中に、今回天皇陛下が訪問されたパラオも含まれていたのでした。
やがて第一次世界大戦は連合国側の勝利に終わります。戦後のパリ講和会議において、日本がその後も引き続き、パラオを含むいくつかのドイツ領を運営していくことが決まりました。
これを機に、パラオには多くの日本人が移住します。ドイツ領の時には進められなかった病院や学校の建設も行われます。また、現地の日本化もすすめられ、例えば現地人に対しての日本語教育なども行われていたようです。
日本の統治は、第二次世界大戦で日本が敗戦するまで続けられました。その期間は約30年です。
なるへそ、僕はてっきり太平洋戦争が始まってからパラオにも侵攻したのだと思っていました。なので30年も日本が統治していた事実にとても驚きました

長い歴史から見れば、30年はあっと言う間かもしれません。しかし、当時を懸命に生きてきた人にとっては、30年という期間は人生の大部分を締める色々な出来事がつまった濃厚なものだったに違いありません。
遠くパラオに渡った日本の人たちはどんな想いで暮らしていたんだろう。ふと、そんなことを考えてしまいました。
最初にも述べましたが、第二次世界大戦が始まると、パラオは激戦地へと変わります。特にペリリュー島での戦いが、被害が大きかったと聞きます。
今回、天皇陛下が訪問されたことによって、多くの人がパラオの歴史を知ることになったはずです。僕もその1人です。陛下はご自身の行動がきっかけとなり、日本国民が戦争について学んでくれることを望んでいたのかもしれませんね。
最後に、パラオの人々の中には、今も日本に親しみを持ってくれている人が多いそうです。過去に統治していたドイツや、戦後の管理者だったアメリカに比べると、日本はインフラを整備したりと現地の人たちにとっても有難い国だったようです。
これには、日本人の勝手な解釈が含まれているのかもしれません。ただ、信ぴょう性のある事実として、パラオ共和国の国旗は日本の日の丸に似たデザインになっているのです。
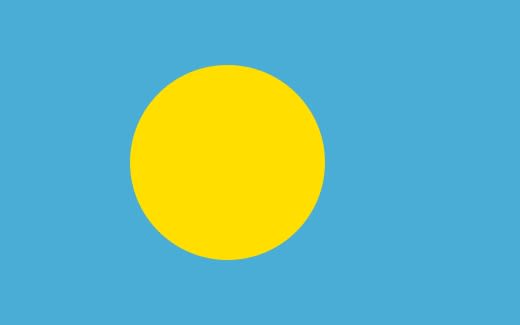
(ウィキペディアより
もし、日本を憎んでいたとしたら、国旗のデザインがこんなに似ることはないはずです。青い色の部分は海を、黄色い丸は月をモチーフにしているようです。
今回のニュースをきっかけに、パラオが1度は訪れてみたい国の一つになりました