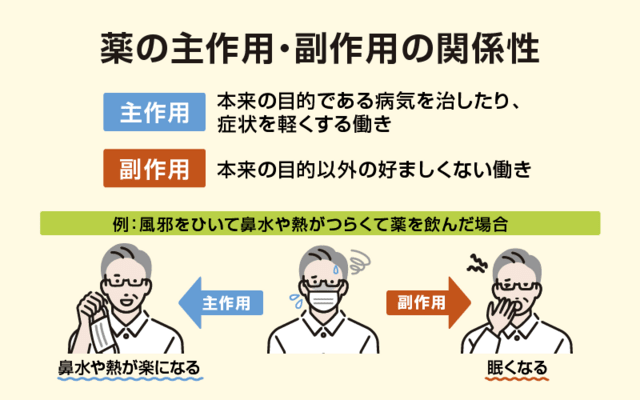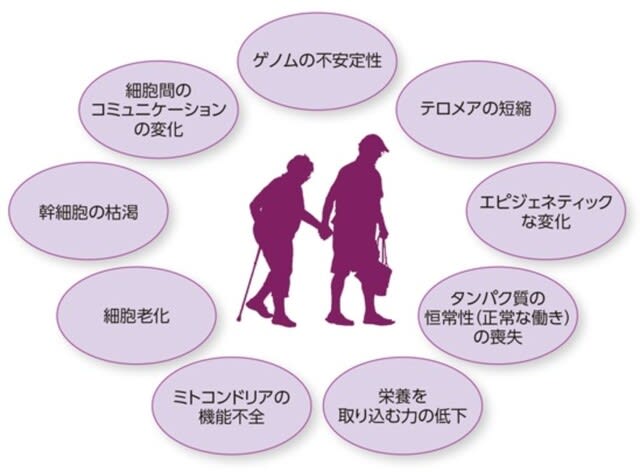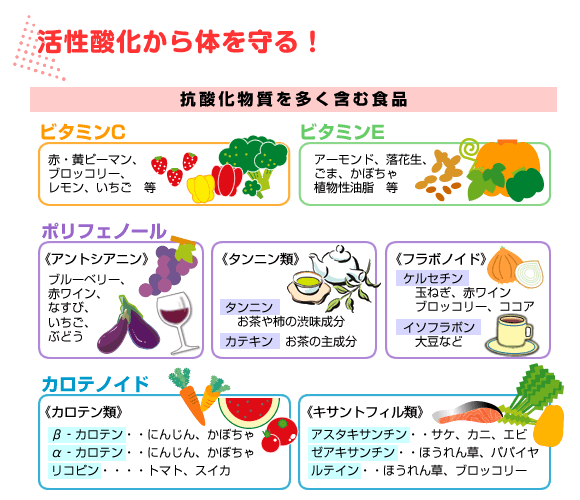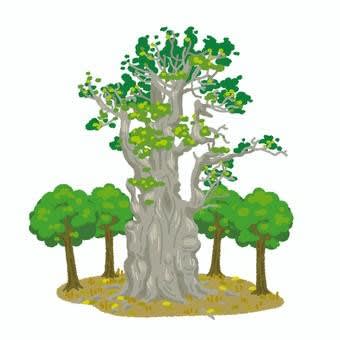体には「病気」や「怪我」をしても自然に治る「恒常性機能」が備わっていて傷ついた細胞は何もしなくても時間が経てば自然に治るように出来ています。

■病で傷ついた細胞が免疫によって治るのは勿論、傷が治る仕組みも同じで何かのはずみや事故でケガをすると、「血管」が破れて「出血」します。皮膚が傷つくと傷口に「血小板」が集まり、血液を固めて「止血」します。


■それは「好中球」や「マクロファージ」という白血球が患部に集まり、傷付いて死滅した細胞や細菌を貪食し、除去するからです。
■次にコラーゲンなど真皮の成分を作り出す「繊維芽細胞」が集まり、傷口をくっつけます。そして「表皮細胞」が集まり、傷口を覆って塞ぎます。

■傷が治る為には様々な細胞が連携プレーをしながら傷口に集まって働きます。止血をする「血小板」は、「繊維芽細胞」や「好中球」を呼び寄せる細胞成長因子を分泌し、「マクロファージ」は繊維芽細胞を増殖させる細胞成長因子を分泌します。

<細胞成長因子>
「細胞成長因子」とは、体の様々な細胞で作られるたんぱく質の一種で主な役割は、成長ホルモンの分泌に関わり傷を治す役割を担っている「自然治癒力」の事です

<マクロファージ>
「マクロファージ」とは全身のあらゆるところに存在する「白血球」の一種で、体に入り込んだ細菌やウイルスなどの病原体や、腫瘍などの異常細胞を排除しています。

<好中球>
「好中球」とは白血球の1種類で顆粒球の1つ。「顆粒球」とは主に生体内に侵入してきた細菌や真菌類を貪食(飲み込むこと)殺菌を行うことで感染を防ぐ役割を果たし、血液中の白血球の半数以上が好中球です。

<血小板>
傷を治す為の「血小板」は「骨髄」から作られ、傷が出来ると血小板は血管内皮に接着し、血小板どうしが凝集し傷口を塞いで「血栓」を形成します。

<リンパ腺>
私達の体には「細菌」や「ウイルス」、「癌細胞」などの異物をせき止めて排除し外敵から体を守る「リンパ節」という体を守る場所があります。

<リンパ>
「リンパ」とは不要になった老廃物や蛋白成分・ウイルスなど病原体を回収しながらリンパ管を通して心臓へ送る下水道の様な役目をする液体のことです。

■「リンパ節」は、細菌、ウイルス、がん細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する「関所」のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫・アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などがあげられます。

<免疫を強化する為には>
免疫を強化する為には何よりもストレスをコントロールする事にあり、バランスの良い食事と適度な運動や充分な睡眠を基本に、ストレスのある時には、あえて「プラスの言葉」(嬉しい・楽しい・幸せ)を脳に言い聞かせ感情を司る偏桃体が暴走するのを「理性」で守ります。


💛プラスの言葉はハッピーホルモン
(ドーパミン・オキシトシン・セロトニン)によって
ストレスホルモンを抑えて病を早く治す助けをする働きがあります。😉