「NHK好きです。」そう言いきってしまうと、いろいろと批判もあるかもしれませんが、過去に何度心を揺さぶられる番組を見たか分かりません。
今議会中の9月21日のETV特集は「手の言葉で生きる」というタイトルでした。神奈川県平塚ろう学校で幼い頃から耳の聞こえない小学部2年の5人の子どもたちのクラスを時間とともに追ったドキュメンタリーです。先生自身もろう者の加藤小夜里(さより)先生です。
「ろう教育」は手話を使うことを禁じて、聴覚口話法という、聴者が使っている「正しい日本語」を教え込むことを長いことしてきました。ところが、つい先ごろ明晴学園という「手話で全授業、日本初のろう学校」が誕生しました。以前のブログでも明晴学園のことは書いたのですが、ろう者を主とする団体から、生まれた私立の学校です。ところが平塚ろう学校は、公立の学校です。すばらしい!正直驚きました。
小夜里先生がろう者たちの言葉である日本手話で、日本語の文法を一生懸命工夫しながら教えていました。時間で追っていくうちに、最後はみんな上手に文章を書けるようになっていました。
過去、ほとんどのろう者が、てにをは等の、助詞・助動詞のむずかしさ、聴覚口話法では、使いこなすまではなかなかいかず、サイレントマイノリティを生み出してきました。それを思うと、小夜里先生の授業は見事でした。感動的でした。先生ご自身もろう学校で学んできた経験と反省から、後に続く子どもたちに信念を持った教育ができたのでしょう。
今に、小さい時からいきいきと気持ちを表せるろう者の手話を使って日本語を学習するバイリンガル教育の優位性が証明され、研究されて、 平塚ろう学校のような学校が増えてくれることを、心待ちにしています。
総合テレビ(10月30日深夜25:25~26:24に、ETV特集「手の言葉で生きる」再放送されますよ。)
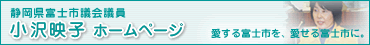
「愛する富士市を、愛せる富士市に」小沢映子公式ホームページ
http://www4.tokai.or.jp/ozawa/
| Trackback ( 0 )
|
さて、失礼ながら、議員というお立場の方の言論としては少し看過できず、是非とも見方を改めていただきたいと思い、書き込ませていただきます。
手話による教育はすでに広島ろう学校や奈良ろう学校で十年ほど前に導入され、きちんとした成果を出せていません、NHKの番組は、ディレクターが日本手話びいきなためか、そこは意図的に捨象したようです。広島ろう学校に至っては、手話(日本手話)を主体とした教育方針を2年前に転換し、聴覚重視に軸足を移しつつあります。
番組では触れられていませんでしたが、聴覚口話法、特に人工内耳などを活用した方法の実績はここ10年ほどで素晴らしく上がっています(私の子供なども最重度難聴ですが、国語は健聴児と比較しても得意科目といっていいほどです)。番組の加藤先生が教育を受けた時代とは劇的に状況が違います。学力を比較すれば、今であれば、まず聴覚口話法の子供たちの方が手話で教育を受けている子供より上だと思います。世界的な傾向もこの通りで、番組で紹介されていた高木医師の考え方は、教育界の常識でもあります。実際にろう学校の先生方に聞けば、バイリンガル教育の行き詰まりを口にされる方が多いと思います。
細かい点ですが、子供たちの作文のてにをはが間違っているのを、大竹しのぶさんが正しい日本語に直して読んでいたのも演出なのでしょうが、気になりました。
失礼ながら、もう少しこの世界について勉強された上で発言いただき、また、手話を使わない子供たちへの共感も持たれ、日々のお仕事に当たっていただければありがたいと思います。
今後のご活躍をお祈りします。
平塚ろう学校でも日本手話で授業をしているのは小夜里先生のクラスだけだろうと思って観ていました。
限られたブログでは、細かいことまでは書けず、主に言いたいところをピックアップして書いてしまうのですが、いろいろな選択肢があっていいと思っています。
番組では、人口内耳をつけているお子さんのお母さんが、人口内耳を辞めて、日本手話によるバイリンガル教育を選択したことで否定的にとられたかもしれませんが、聴覚障がいの度合い、失調した時期、両親等環境で教育の形はいろいろあるのかなと思います。アメリカで有名なろう者の大学はどちらも手話ではなく、通常の英語です。
ただ生まれつきの重い聴覚障がいの子どもたちが、いきいきと自分の気持ちを表して幼児期を過ごしている姿を見ると、まだまだ今後に課題はあるもののバイリンガル教育は、選択肢の一つとして有効だなと思えるのです。
日本手話は過去、言語として認められてきませんでした。しかし、手話が言語として独自の文法を持ち優れている事が知られてきました。
私の子どもは知的にも身体的にも最重度の子どもです。23年間介護して育ててきました。歩けるように,言葉が少しでもしゃべれるように、夢中でリハビリもしてきました。
でも聴覚や身体、知的と大人になった障がい者たちと付き合っていると、親の思いと当事者の思いと大きな隔たりがある事が分かりました。
は、障がいに関する市民運動をしてきて、今は議員としていかに当事者の立場でものを考えられるか肝に銘じてきました。
情報保障の面でも、日本語の習得は大事なことです。しかし、仲間とのコミュニケーションもとっても大事です。気持ちをいきいき表現して共感できる仲間の存在は社会へ出るほど必要になります。
私の友達のろう者たちも、通常の学校へ行って手話が得意でない人、読書家、様々です。みなそれぞれ悩んだり葛藤しながら日々暮らしています。そのとき共感できるのは、やはり、同じ仲間ではないでしょうか。
社会的にマイノリティだったろう当事者が、日本手話による教育を訴えてきて明晴学園が設立されました。私どもの富士市から新幹線で通学している子もいます。
返しますが、ろう教育は、人口内耳のような科学の進歩や、日本手話による教員の養成や授業方法の研究が進むことで、これからも多様な選択肢があってもいいと思っています。
さて、日本手話の活用にも人工内耳等聴覚の活用にも同じように理解を示すということは、現実的にも理念的に可能なことなのでしょうか。私はあり得ないことと思います。
「多様な選択肢を保障すべき」というのは模範解答(確かに議員というお立場としては、この回答しかないでしょう)でしょうが、まず、ろう学校の現在のリソースを考えると、いろいろな選択肢を用意することはほぼ不可能であり、平塚ろう学校でも人工内耳等に適した選択肢は用意されておりません。また、理念的にも、日本手話を使用する教育はある種の思潮・イデオロギーと表裏一体の関係にあり、原理的に聴覚重視の教育(さらにいえば聴覚を重視して育てられる子供の幸福を願う気持ち)と相容れないものがあります。たとえて言えば、共産主義に傾倒する人がハイエクあたりの思想もいいなと思うことがありえないのと同様です。
このあたりは、NHKがこれまで手話を活用した教育を好意的に取り上げてきた一方、人工内耳等で聴覚を活用した教育を教育・福祉系番組で好意的にとりあげてきたことが一度たりともないことを見ても一目瞭然です(聴覚を活用する教育を求めることも切実な希望なはずです)。
また、子供時代に他の子供等と生き生きとコミュニケーションを図りつつ、日本語の力を身につけるという「二兎を追う」ことも、今の補聴技術を前提にすれば十分に可能になってきており、30年前ならいざ知らず、今の時代にバイリンガル教育の選択肢をとる必要性は、一部の子供を除いて乏しいように思われます。端的に言えば、そんな手段、それも奇怪なイデオロギーと一体となった手段をとらずとも、ほとんどの子供にとって「十分両立可能」なのですよ。どのような手段で具体的に両立させるか、そこに一番知恵を絞っておられるのかが、現在の聾教育の先生方だと理解しています。日本のみならず世界でそういう動きになっているはずです。もっとも、聴覚口話法はお金がかかりますので、途上国では手話法が主流になることもあるでしょう。
今後、障害を持つ自分の子どもの発達(トータル)に責任を負い、切実な思いを持つ保護者が聴覚活用を求める動きは加速するでしょう。一方では聾教育の外側で手話への賛美がエコーチェンバー現象となり、公共放送を含むメディアががっちりメディアスクラムを組み、人工内耳や聴覚活用への好意的な報道が自粛される、さらには手話を活用しないろう学校への批判がなされるという、きわめて不健全な事態が、憂慮されてなりません。
「障害を持つ自分の子どもの発達(トータル)に責任を負い、切実な思いを持つ保護者が聴覚活用を求める動きは加速するでしょう。」たしかにそうなるかもしれません。
随分手話による教育に抵抗がおありのようですが、多様な選択肢は可能ではないのでしょうか。
人口内耳は、重要な選択肢ですし、聴覚を活用する教育を求めることも切実な希望なはずです。とおっしゃる意味は分かります。そのための教育をろう学校でするべきなのは当然と思います。
ろうの子ども全員が人口内耳をつけて、通常の聴覚を獲得できれば何の問題もないとは思います。
人口内耳をしていても手話と併用する人もいます。科学の進歩でさらに性能のいい人口内耳ができてくるかもしれません。が、今はまだ手話は大切なろう者のことばです。やはり教育に携わるものは、どちらかではなく、選択肢は必要なのではないでしょうか。
まず、私は手話自体に抵抗があるわけではありません。聴覚をきちんと活用してもらえるのであれば、ろう学校で手話も併用しつつ教育されるのは望ましいくらいだと思います。子供が日本語を身につけた後(中学生くらい以後)は、手話を本格的に勉強したいと思っています。聴覚だけで子供の幸せを築いていけるケースも限定されるでしょうからね。また、今は忘れてしまいましたが、人工内耳手術前は手話も使用しており、入院時に同室だった親御さんたちは、私もろう者だと思っていたそうです(笑)。
私が強い抵抗を感じているのは手話ではなく、「日本手話原理主義」とでも呼びたくなる一種の思潮です。
手話使用と、日本手話原理主義とは、はっきり分けて考えていただきたいと思います。
そして、バイリンガルろう教育を主張するイデオロギーと、手話を併用しない人工内耳等による教育って、本当に共存可能なのでしょうか。ここをつきつめて考えてみていただきたいのです(議員というお立場の方なので、あえてこういう言い方をいたします)。今までの例をみても、バイリンガルろう教育に理解が示された場合、間違いなく手話を併用しない聴覚を活用した教育を求めることはままならなくなっています。それは、バイリンガル教育が単なる教育法ではなく、一種の思潮かイデオロギーだから、そうなるのは必然性があります。そこが問題だと私は言いたいわけです。一つの学校なりで、バイリンガルろう教育と、例えば人工内耳+手話による教育、人工内耳のみで手話を併用しない教育などが完全に並存していれば、何の文句はありません。他のやり方に足を踏み入れて文句をつけるなんて、趣味ではありませんから。
さて、ここで2つご質問があります。
1 メディアをはじめ世論は全く味方になってくれず、聴覚障害者団体からは後ろ指をさされながら、手話による教育を選択せずに難聴児の子育てに奮闘している母親についてはどう思われますか?障害に直面したばかりでやむをえないのかもしれないが子供の視点からみると幸福になるためには別の選択もあるのに・・・ということでしょうか?また、子供の幸福のために手話使用は必要なのに、ということなのでしょうか?
2 NHKが教育・福祉番組で人工内耳を好意的に紹介したことがないことや、人工内耳の子供たちの役に立つような情報を一度も提供したことがないことについて、何らかのご感想はおありでしょうか。
深夜にまで書き込まれるとお体にさわりますので、落ち着いたときで結構です。
日本手話原理主義とでも呼びたくなる一種の思潮です。という激しい言葉に少し驚いています。
確かに、こどもが日本語を母語として身につけるのと、日本手話を母語として身につけるのとでは全く違う、相対する考えですね。70年の口話教育の中で、手話を言葉として否定されてきたろう者にとって、教育だけでなく文化も人間としても否定されてきたという感覚があったのではないでしょうか。「耳が聴こえない人」ではなく「手話を使う人」という考え方からも伺えます。ろう文化に誇りを持って、生きていくという考えにはうなずけるものがあります。
その主張が、近年大きくなって、日本でのバイリンガルろう教育という形が、全国津々浦々(ちょっと大げさな表現ですが)のろう学校で行われている口話法による教育の中で、ほんの一部でやっと芽が出た状態ではないでしょうか。指導法もまだまだこれから研究されていく途上です。
NHKやマスコミが取り上げられるのも、このあたりの共感ともう少し暖かく見守っていこうという考えなのではないでしょうか。
『メディアをはじめ世論は全く味方になってくれず、聴覚障害者団体からは後ろ指をさされながら、手話による教育を選択せずに難聴児の子育てに奮闘している母親』という言葉にも驚きました。そんなに嫌な思いをしているとは知りませんでした。
たしかにろう者たちは聴者に近づけることを望まれて、手話に対する偏見の中で生きてきた長い歴史があります。その逆の発想で手話を使う人、ろう文化に誇りを持って生きたいという願いは、声を大にして時に原理主義といわれるほどに強く訴えなければ、聴者たちは気付いてくれなかったかもしれません。
明晴学園の校長の言葉です。『過去のろう教育は、手話に対する無知と偏見によって、多くの子どもたちの可能性を奪いました。言語学や認知科学の専門家に指摘されるまでもなく、私たちは日本手話が日本語とまったく同等の自然言語であることを知っています。日本手話をもとにした教育は、日本語をもとにした教育となんら変わることのない成果をあげうるものです。(中略) バイリンガル教育はしかし、明晴学園の手段ではあっても決して最終的な目的ではありません。ろうの子どもたちが日本手話の話者であることを誇りとし、ゆたかな人間性を育み、自己実現に向けて力を発揮できるようにすること、それが明晴学園の本来の目標です。』
上記の言葉がろう者たちの主張するすべてだと思います。それに対して私たちはついつい共感してしまいます。
市役所障害福祉課の手話通訳の方とも話をしたのですが、最終的には、社会の中でそのこがどう生きていくか大事なのは本人の気持ちです。あれがだめ、これがだめは言えないような気がします。
コメントを書いてくださっているおかあさん、お子さんのことを思って本当に一生懸命日々子育てに取り組んでいらっしゃるのですね。文章を読んでいて、たいへんな聡明な方だとよく分かります。ETV特集で人口内耳を使うのをやめて、日本手話を選択する件は、人口内耳をつけて頑張っているお母さんたちには、否定されたとも取れる内容で気分を害されるのももっともです。
これからもいろいろな意見や言葉に傷つくこともあるかもしれませんが、どうか、自信を持ってお子様のためにも頑張ってください。
この番組に限らず、「ろう文化」や「バイリンガル教育」を紹介するのに、あえて人工内耳を持ち出してそれを貶めて対比するという手法が多いことにいささかうんざりしていたため、失礼を顧みず書き込ませていただいた次第です。私のような立場もあることを幸いにご理解いただけたようですので、感謝しつつ私の書き込みは終わらせていただきます。
人間、おのずから立場の違いはあるものですが、多様な立場を理解しようと一生懸命努力すれば、立場の違いは違いとして、たいていの相手には理解していただけることと思います。
これからも色々な立場の利害に配慮されて良いお仕事をされてください。応援しております。