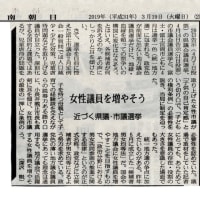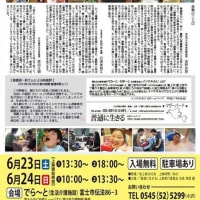たまたま、以前保存しておいた京都新聞の社説を見つけた。
全く同感で、是非読んでほしい。
日本では教育は家庭の責任だが、他の先進国では、教育は国の責任と認識している。
子どもの権利条約では、子どもの最善の利益を謳っている。
傷ついて自信を無くし、自尊感情の低い子は、不登校やうつになりやすい。
子どもたちが安心して成長できる最善の環境を作るのは大人の責任だ。
社説 京都新聞トップ
こどもの日に 教育に競争原理は似合わない
<中学校に入るころは、先生というものをほとんど信用しないようになっていました…先生はぶんなぐるから恐ろしいものだと思っていたのが、急にやさしくなったので変に思いました。それから急に「勝手だべ、勝手だべ」という言葉がはやりだしました>
小学4年で終戦を迎えた中学生が卒業式で読んだ答辞の一節だ。
戦後間もない頃、山形県の山村の中学校教員だった無着成恭さんが編集した学級文集「山びこ学校」(岩波文庫)に納められている。終戦で180度変わった教育に、子どもたちがいかにとまどったかが分かる。
無着さんにとっても、敗戦は大きな衝撃だった。悩んだ末「自分の生き方は自分で考える時代になったのだ。学力とは、自分を生かすための選択力であり、判断力なのだ。その力をつけてやるのが教育なのだ。テストの点数ではない」と気づいたという。
そして始めたのが、ありのままの日常生活と思いを書き記す「生活綴方」だった。東北の山村は貧しく不便で、父親が戦死した生徒も少なくない。厳しい現実にぶつかり、考え抜いた生徒たちの心の声が詰まった「山びこ学校」は、戦後の新しい教育の実践記録として大きな反響を呼んだ。
理想を逸脱する学校
発刊から60年余。学校教育は当時の理想とは全く違う方向に進んできたように見える。
高度経済成長とともに学歴偏重が進み、受験競争が激化した。大学や高校は序列化し、教育は「詰め込み式」になった。
その反省から「ゆとり教育」が導入された。しかし、学力低下の元凶と批判され、教科書は再び分厚くなり、国の教育政策は点数で評価できる「学力」と競争の重視に回帰しつつある。
例えば、教育改革を主導する自民党教育再生実行本部は先ごろ安倍晋三首相に提言を出した。国際競争に勝てる人材養成のために、高度な英語力テストTOEFL(トーフル)の大学入試への導入や理数系科目の強化を求めている。
教育改革をめぐる論議で気になるのは、競争重視だけではない。「人づくりは国づくり」という同実行本部のキャッチフレーズに代表される教育観だ。民主党の野田佳彦首相(当時)も「国づくりの根本にあるのは、人づくり」と国会で答弁している。
当たり前に聞こえるが、「国のための人づくり」という考え方がもし根底にあるとすれば、本末転倒であるばかりか、歴史に鑑みても危険な発想といえよう。
基本法の精神生かせ
教育基本法は前文で、民主的で文化的な国を発展させ、世界平和と人類の福祉を図るとし「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期する」とうたう。
この精神に照らせば、国力増進や日本企業の国際競争力向上に役立つ人材の育成は公教育の主目的になりえない。むしろ、山びこ学校のように生徒と教員が格闘するような実践こそが教育現場で大切にされなければならない。
文部科学省は、本年度から5年間で教員を2万8千人増員し、小中学校で35人学級の実現を打ち出した。教員が子どもと正面から向き合えるようにするのが狙いという。いじめ対策にも少人数教育は有効だろう。大いに歓迎したい。
ただ、学力テストなどの成績だけで教員や学校を評価すれば、競争主義を持ち込むだけになる。その愚は避けねばならない。
今、子どもたちが受けられる教育を左右する大きな要素は保護者の経済力だ。日本社会は全体として豊かになり、高学歴化が進んでいるが、それに伴って必要な教育費用も膨らんでいる。
のしかかる経済的負担
内閣府の3年前の調査では、生活費を含む子育て費用は未就学児で年平均104万円、小学生で115万円、中学生で156万円だった。中学卒業までに1800万円もかかる計算だ。ある損保会社の試算では、大学卒業までに教育費だけで3千万円かかるという。
この費用を保護者が背負えるかどうかで子どもの教育水準が決まってしまうとしたら、教育基本法が定める「教育の機会均等」の実現は程遠いことになる。
家族手当を支給する企業は多いが、成果給の導入などで手当の廃止が相次いでいる。国や自治体から家族手当が支給される欧米とは対照的だ。
民主党政権が掲げた「社会での子育て」は、こうした日本特有の子育て状況に一石を投じる考え方だった。政権は再び自民党に戻ったが、深刻な経済格差の広がりが教育格差に直結しないよう、子育て・教育分野での経済的な支援施策の充実は急務だ。
無着さんは学級文集「きかんしゃ」にこんな詩を寄せている。
<人間を幸せにするという一ツの目的のため、轟然(ごうぜん)と地響きを立てて走るのだ。俺たちは機関車だ! いつも力を合わせて行こう。陰でこそこそしないで行こう。いいことを進んで実行しよう。働くことが好きになろう。何でも、なぜ?と考える人になろう>
さまざまな行政施策は重要だ。そのうえで、教育に最も大切なことは、大人や教師が体当たりで子どもと接することだ。時間をかけることだ。この詩はそう教えてくれているように思える。[京都新聞 2013年05月05日掲載]