
富士市産業支援センター〈f-Biz〉が8月4日オープンしました。新しくビジネスを始めたい、今の事業をさらに大きく成長させたい、夢にチャレンジする人や企業をサポートする新しい拠点です。中央図書館分館の中にあります。
センター長の小出宗昭さんは、静岡銀行を退職して、この仕事を引き受けてくれました。小出さんは産業支援においてはカリスマとよばれ、国レベルの活躍ぶりでした。それを富士市の工業振興課が、退職して富士市に来てくれ、とかなり熱心に口説いたようです。(市も粋なことをするなぁ、ちょっと見直しました)生まれ育った富士市で産業支援をするのも今しかできないと、引き受けたそうです。
10月14日市会議員の有志による勉強会でf-Bizにおじゃまして、小出さんのお話を伺いました。福祉事業諸関係は範囲外かなと思っていたのですが「NPOをはじめ支援を必要としている人すべてが支援の対象」とのお話に、23日、申し込んで相談に行ってきました。
ひと通り簡単に話をした後、小出さんが開口一番「福祉はお金がかかる、これ以上は増やせない」といったことを言われて、実をいうとちょっとひきました。
福祉をすすめると経済が疲弊するというのは全くの迷信です。福祉先進諸国が豊かなことと、日本でも首長を中心に福祉を進めた市町村の財政が傾いているかというと全然そんなことはありません。むしろ、地域再生だ、まちを元気にするんだ、といって国から補助金をもらって、箱物を建てていった市町村が今たいへんなことになっています。財政破綻した夕張市はそのいい例です。
でも、その後、いろいろ話をしていくと、小出さんは、身体に障がいがある人たちや、親たちの起業支援を親身になってやっていたこと、人材の育成が必要なこと、話が弾みました。
でらーとの小林施設長のような人材はそうそうはいません。やっぱり人材を育ててゆくことが第一です。
「福祉関係起業支援セミナー」なるものを開催して、福祉関係に高い志がある人に集まってもらって、経営もでき、事業所をたち上げていく気概を持つ人。を養成出来たらいいのではないかと話がまとまりました。
心して講師を探していきたいと思います。
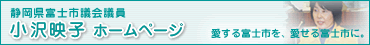
「愛する富士市を、愛せる富士市に」小沢映子公式ホームページ
http://www4.tokai.or.jp/ozawa/
センター長の小出宗昭さんは、静岡銀行を退職して、この仕事を引き受けてくれました。小出さんは産業支援においてはカリスマとよばれ、国レベルの活躍ぶりでした。それを富士市の工業振興課が、退職して富士市に来てくれ、とかなり熱心に口説いたようです。(市も粋なことをするなぁ、ちょっと見直しました)生まれ育った富士市で産業支援をするのも今しかできないと、引き受けたそうです。
10月14日市会議員の有志による勉強会でf-Bizにおじゃまして、小出さんのお話を伺いました。福祉事業諸関係は範囲外かなと思っていたのですが「NPOをはじめ支援を必要としている人すべてが支援の対象」とのお話に、23日、申し込んで相談に行ってきました。
ひと通り簡単に話をした後、小出さんが開口一番「福祉はお金がかかる、これ以上は増やせない」といったことを言われて、実をいうとちょっとひきました。
福祉をすすめると経済が疲弊するというのは全くの迷信です。福祉先進諸国が豊かなことと、日本でも首長を中心に福祉を進めた市町村の財政が傾いているかというと全然そんなことはありません。むしろ、地域再生だ、まちを元気にするんだ、といって国から補助金をもらって、箱物を建てていった市町村が今たいへんなことになっています。財政破綻した夕張市はそのいい例です。
でも、その後、いろいろ話をしていくと、小出さんは、身体に障がいがある人たちや、親たちの起業支援を親身になってやっていたこと、人材の育成が必要なこと、話が弾みました。
でらーとの小林施設長のような人材はそうそうはいません。やっぱり人材を育ててゆくことが第一です。
「福祉関係起業支援セミナー」なるものを開催して、福祉関係に高い志がある人に集まってもらって、経営もでき、事業所をたち上げていく気概を持つ人。を養成出来たらいいのではないかと話がまとまりました。
心して講師を探していきたいと思います。
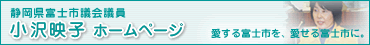
「愛する富士市を、愛せる富士市に」小沢映子公式ホームページ
http://www4.tokai.or.jp/ozawa/










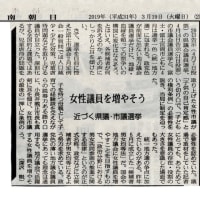

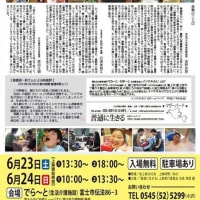







講演とワークショップの2部構成でした。
講演はともかく、ワークショップはセンターが設定した商品のネーミングを考えるといった趣旨のものが毎回続き、まじめな感じがしませんでした。
例題は、消費者向けの商品の名前をキャッチコピーを考え鵜というものばかりだったのですが、商品を売るためにはそれ以前に市場での位置づけや、売ろうとする企業がその商品にどれだけの資源を割り当てられるかという条件でが必要です。条件によっては、商品に分かりやすい名前など必要も無いのです。
参加している経営者の抱えている問題は、もっと根本的な部分です。
実際、私と話し合った参加者はみな、
・そこに集まった参加者の商品を例題にしてくれた方がよほど勉強になる。
・異なる経験を持つ経営者からの意見は貴重だ。参加者同士でお互いの現状を聞きたいのに、駄洒落のワークショップでは時間が無駄だった。
等の意見が聞かれました。
また、小出氏については、
・終止早口で話し続け、区切りも間を置かない。聞いていてい信用できる態度ではない。
・内容も、自分の説明に都合の良い部分だけをとらえているが背景は違っている事が多い。
・実績を強調するが、参加者の目からは”この舞台でその程度?”と感じる。
といった意見もありました。
さらに、公費で実施されているセミナー、講演であるにもかかわらず、参加者からアンケートを取る事もありませんでした。
市の予算をこのようなものに投入しておきながら、結果の調査をしないのは問題が有ると思います。
小出さんは、工業振興課の職員が小出さんの講演話を聞いて、魅力を感じて富士市出身でもあるし、この人に是非来てもらいたいと、口説いたようです。
セミナーは参加した事がなかったので、内容については全然知りませんでした。たしかに多少早口ではあるかなとは思います。(私も早口なので気をつけなければと思っているのですが)
小出さんの魅力は、起動力と顔の広さ多方面の方といろいろなつながりを持っているようです。使える制度にも明るいようです。
ですから、セミナーよりも、個別の支援のほうが小出さんの力を発揮できるのかもしれませんね。
またご感想をおきかせください。
本取り組みは、一見そこにスポットを当てているようですが、実際はヤマカンによるこじつけを行っているだけに見えます。
本取り組みについて、市の財政から支出していると思うのですが、客観的な評価はされているのでしょうか?
1. 相談・セミナー受講において、主催者または市が立場でアンケート等のフィードバックをしている。
2. 相談のうち、実行された支援の件数の検証。
3. 実施された支援の、実施前・後における経済効果の比較。
4. 実施された支援は、継続的な効果があったか?
これらの評価が行われないかぎり、行政となれあったいかがわしい取り組みとの疑いがもたれると思います。
ぜひ、検証をお願いします。
そして、もっと実際的な支援が行われるよう希望します。
でもおっしゃるとおり、もっと詳細についての検証葉必要ですね。
調べてみたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
せっかく市の財政から支出するのですから、f-Bizで行われる講演、セミナー、ワークショップをhttp://www.ustream.tv/やhttp://www.stickam.jp/でライブ放送してみてはいかがでしょうか?
より多くの起業家に情報を与えることで、富士市の産業の活性化に役立つと思います。
新規に購入必要な機材はWebカメラ程度で、3千円くらいから購入できるでしょう。その他は、センター及び市の備品で実現可能です。
技術的にも簡単ですからf-Bizのスタッフには何の問題もありません。
そのあとは、ニコニコやyoutubeに画像データを公開、というのも良いのでは?と思います。
もちろんカットなしです。いいとこだけ編集された動画では、正しい情報の開示ではないからです。
講演などは、講師の方の著作権等難しいでしょうが、センターのオリジナリティ光る企画などにはうってつけと思われます。
施策の透明性のためにも、ぜひご検討お願いします。
+------------------------
議員には関係のない愚痴をひとつ。
以上を他議員のブログに提案しようとしたのですが、スパムフィルターに掛けられてしまいました。
3月でデータを閉めたので、これから分析が出てくるのでもう少し待ってほしいとの事です。
富士市の税金で実施してきた事業を全国に展開し、導入を検討する地方自治体は、その準備段階から有償対応でイドムに講師謝金を支払います。
また、ビズモデルの導入に際して地方自治体はコーディネーターの研修費用をイドムに支払い、毎年イドムに講演代も支払い続ける仕組みです。
富士市の予算による公的機関の受託事業者が、当該案件で得た情報・ノウハウを外販して得た利益となりますので、富士市の歳入に納められるべきものなのではないでしょうか。
もしくはエフビスの予算は減らして、自主財源として会計処理して自立するとか。すべて代表者の懐に収められているのではないでしょうか。
さらに、今般俎上にのっている専門家派遣事業については、派遣事業者(イドム)が派遣先企業に同席しなければならない制度であるにも関わらず、同席せずに申請書類だけ提示したということであれば、不正受給の前段として虚偽申請の責任は問われるはずです。
その点を隠して、まるで他人事(被害者)のように弁明する昨今の報道における代表者のコメントには、疑念が深まるばかりです。