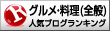・Kの流失Potassium lossかりうむのりゅうしつ
食塩(Na)の摂取量の気になる日々、カリウムを取り入れる量を増減することになり食塩の摂取量が多い傾向からカリウムを取ることによってNa(ナトリウム)の排泄を促し血圧を上昇を抑えることに働きます。Na:K比2:1以下として摂取することを奨励しています。
そんなカリウム(K:kalium)Potassiumの発見は、イギリスのデイビーHumphreyDavyによって1807年植物を燃やして発生した灰からポタシ(苛性カリ)、水酸化カリウム(KOH)を電気分解にすることにより分離していました。ポタシは壺potと灰ashの合成語で、壺の中の灰を指し、カリウムの名称は、カリウム(ドイツ語でKaliumであり、新ラテン語: kaliumでありドイツ語の「Kalium」を経由し日本に伝わっています。日本語で肥料として加里(光合成を助ける)が使われ植物中のデンプン、タンパク質の生成、移動、蓄積に役立ち水分の蒸散作用を調節、根の発育を早め開花、結実を促進します。
食塩も、体内にとってとても大切な働きをしています。浸透圧の調整、食欲増進に関与しNaとしていらいら解消、Cl(塩素)として胃液の成分となっており不可欠な成分です。
最小必要量はNa500mg(食塩相当量1.3g)、この量は自然の食品そのものだけを取ることによって充分に賄える量です。体内の塩分量は、成人の体重の0.3~0.4%、子どもで約0.2%、体重50kgの成人なら、体内の塩分量は約200g程度です。体内の塩分は、主に血液や消化液の体液中に含まれ、1リットルの血液中で約9gの塩分が含まれます。点滴によく生理食塩水が用いられ体液の調整が行なわれます。熱中症などで脱水症状になった場合にうすい塩分を含んだ水、スポーツドリンクを補給しています。
しかしながら過剰摂取が問題になっています。塩分(塩化ナトリウムNaCl)は、水分を貯留する性質があります。日本人は古来より米食中心食でそれに漬物、佃煮類の塩分を多く含む食品と相性良く過剰に食塩を取りやすい環境にあったともいえます。戦前は1日当たり食塩を20~30gも1950年代は、15g摂取していたともいわれ脳いっ血、高血圧症が多発していたのではと推測しています。
カリウムは、魚・肉類、野菜・果物に多く含み小腸で吸収され汗、尿中よりに排泄しています。人体で約0.2%を占め体重50kgでKは100g程度で多くは細胞内に存在します。浸透圧の調整、神経・心機能の調整、利尿作用、タンパク質の代謝、筋肉の収縮に関与し不足することによって筋力低下、腸閉塞、味覚・反射機能の低下がみられています。過剰摂取で吐き気、倦怠感、筋力の麻痺、高カリウム血症(心機能障害)などを起こす事が知られています。食塩(Na)の摂取量によって摂取量を増減することになるのです。カリウムを取ることによってNa(ナトリウム)の排泄を促し血圧を上昇させません。高血圧予防に野菜350g/1日の摂取を奨励しています。腎機能が低下してK制限のある場合Na,K共に制限し腎臓への負担の軽減から魚、蓄肉類、軟弱野菜等は、カリウムは、熱に弱く加熱によって分解、水溶性で水に溶け出すので茹でこぼしによって減少させています。
カリウムはクエン酸で吸収をよくし、その補給は生でとることができる生野菜、フルーツがよいでしょう。バナナ(Na微量,K360mg)、小松菜(Na15mg,K500mg)、鮭(Na40mg,K400mgを含みます。上限量Na(3.94gで食塩10g):K(2g~4g)比で2:1以下、1日の目標量として2~4gとなります。
繊キャベツが、千切りで洗わずにそのままで食べられる宣伝で市販している昨今です。
ここ数年、スーパーやコンビニなどで売り場面積を増やしているカット野菜が多く見られるようになりました。数種類の野菜が1パックになって、忙しくて野菜をとりたい人にとって手軽に料理に使えて便利です。
市販の千切りキャベツ120gエネルギー:23kcal、たんぱく質:1.3g、脂質:0.2g、炭水化物:5.2g、食塩相当量:0.01gとの記載で洗った後でも60%以上の水溶性ビタミンミネラルが残っていることが確認といわれています。千切りにしたキャベツを約15分間、水に浸した後のビタミンC残存率は約85%という結果もあるようです。一般のキャベツではカリウム200mg/100g中で市販の繊キャベツでは60%の残存率で換算すると120mg/100gで144mg/120g中となります。
生キャベツ100g中で21kcal、水分92.7g、タンパク質1.3g、脂質0.2g、炭水化物5.2g、灰分0.5g、ナトリウム5mg、カリウム200mg、カルシウム43mg、マグネシウム14mg、リン27mg、鉄0.3mg、亜鉛0.2mg、銅0.02mg、マンガン0.15mg、ビタミンA:8μg、ビタミンD:(0)μg、ビタミンE:0.1mg、ビタミンK:78μg、ビタミンB1:0.04mg、ビタミンB2:0.03mg、ナイアシン0.2mg、ビタミンB6:0.11mg、ビタミンB12:(0)μg、葉酸78μg、パントテン酸0.22mg、ビタミンC41mg 、食物繊維1.8gを含みます。
市販120gの繊キャベツKのは、およそ生キャベツ100gと同程度ということになります。
食中毒を防ぐための次亜塩素酸ナトリウムが使われている場合がありますが、これは水道水にも使われているもので気になる場合は、サッと洗い流し、さらに加熱で、ほとんど分解するようです。
生鮮野菜と比べれば栄養価は水溶性ビタミン・ミネラルで低く、値段95円/120gも割高で味に多少変化が感じられるといいますが、手間なく手軽に野菜を取り入れたいときには、上手に使って食生活向上に役立ちそうです。
カリウムは、100g中で人参(Na15mg,K340mg)、ほうれん草(Na16mg,K690mg)、小松菜(Na15mg,K500mg)、きゃべつ(Na5mg,K200mg)、🥦ブロッコリー(なまNa7mg,K460mg・茹でNa5mg,K210mg・電子レンジNa8mg,K500mg)、たまねぎ(Na2mg,K150mg)、大根生(Na14mg,K230mg)、みかん(Na1mg,K150mg)、りんご(Na微量,K110mg)、キウイ(Na2mg,K290mg)、ぶどう(Na1mg,K130mg)、バナナ(Na微量,K360mg)、なし(Na微量,K140mg)、うなぎ(Na74mg,K230mg)、かれい(Na110mg,K330mg)、さんま(Na140mg,K200mg)、さば(Na110mg,K330mg)、ぶり(Na32mg,K380mg)、いわし(Na81mg,K270mg)、鮭(Na40mg,K400mg)、湯通し塩抜きわかめ(Na530mg,K10mg)、めかぶ(Na170mg,K88mg)、豚肉(Na50mg,K240mg)、鶏皮付きもも肉(Na62mg,K290mg)、鶏卵((Na140mg,K130mg)、玄米(Na1mg,K230mg%)、白米(Na1mg,K89mg%)、うるち米めし(Na1mg,K29mg)、馬鈴薯では灰分0.9g中の(Na1mg,K410mg)、国産乾燥大豆 灰分5g(4-5%)中(Na1mg,,K1800mg)、水煮缶(Na210mg[塩添加?],K250mg)、とうもろこし茹で(NaTrmg,K290)/100g中です。
むき出しになっている、白米では、洗米で流出しやすく、豆類では流出は少ないようです。洗米は手早く、煮豆は汁ごと利用するのがよいでしょう。そしてカリウムの補給は生でとることができる生野菜、フルーツがよいようです。厚生労働省では、1日あたりの食事摂取基準における野菜と果物の推奨量を野菜を350g以上と果物を200g程度としています。
令和元年国民健康・栄養調査結果によるカリウムの1日の摂取量は平均で2,299.4mgで食品群別の摂取量をみると野菜類からの摂取が最も多く、次いで肉類、乳類、果実類、魚介類でした。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。