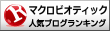◎アブラナ科野菜 あぶらなかやさい
きゃべつ、メキャベツ、白菜、漬け菜類(小松菜・野沢菜など)、大根などのアブラナ科野菜には、身体に良さそうな物質が見出されているようです。どのようなものがアブラナ科野菜に含まれるのか、またまたその野菜の持つ特性、生理活性物質についてまとめてみようと思いました。
アブラナ科野菜には、1.アブラナ、2.大阪白菜(おおさかしろな)、3.カブ、4.からし菜、5.カリフラワー、6.キャベツ、7.京菜、8.クレソン、9.ケール、10.小松菜、11.コールラビ、12.搾菜(からし菜の変種)、13.山東菜、14.すぐき菜、15.タアサイ、16.カイワレダイコン、17.大根、18.タイサイ、19.高菜、20チンゲンサイ、21.唐菜(とうな:ながさきはくさい)、22.薹菜(とうな:ミズカケナ)、23.菜の花、24.野沢菜、25.白菜、26.パクチョイ、27.二十日大根(ラデッシュ)、28.日野菜、29.広島菜、30.ブロッコリー、31.ホースラデッシュ、32.水掛菜、33.ロケットサラダ(ルコラ)、34.芽きゃべつ、35.わさび等がアブラナ科野菜として私たちの食卓を賑わしています。
それぞれ若芽、つぼみ、葉、根が食用としています。七訂食品成分表(2015年)には、2,222食品の成分が記載され、野菜は150種類ほどありますが、その中でアブラナ科野菜は、35種程度、野菜の中で約25%の成分が記載され野菜消費量の大部分を占めていました。
多くが地中海から西アジアにかけた地域から中国を経て渡来したものといいます。
アブラナ科Brassicaceaeは、双子葉(そうしよう)植物に属し、世界で3,000種以上が知られています。花弁(花びら)数は4で花の姿が十字状であるので以前は、ジュウジバナ科とも呼ばれていたといいます。北半球に多く、特に地中海沿岸地帯から西アジアにかけて多くの種類が分布しています。多くが秋に芽生え、冬はロゼット(根から茎が伸びず直接葉が放射状に見える状態)で過ごし、春に開花します。このようなライフサイクルは地中海地方の夏期の乾燥と冬季の温暖多雨という気候条件に適応したものなのです。アブラナ科類の種や植物が一定期間低温にあたると花芽が分化してとう立ちをはじめるため、品種選びと種まきの時期が重要とされています。一般に発芽と生育のための適温は、15~20℃で5℃以下、28℃以上で成長が遅れてきます。10℃以下でとう立ちしやすい傾向です。
消費利用の多い、最近注目の、きゃべつ、メキャベツ、白菜、漬け菜類(小松菜・野沢菜など)、大根などの日本への渡来の歴史、特性などについて探索(たんさく)し、それらの生理活性物質についてです。
キャベツ Cabbage きゃべつ
地中海沿岸にある野生種から、ケール、キャベツ、ハナヤサイなどが分化したとされ、BC2,500年ころから栽培されていたと考えられている。
日本には、江戸時代に伝わり、主に栽培されるようになったのは明治に入ってからという。
肉、魚の揚げ物、焼き物の付け合せとし繊キャベツ、サラダの生でシャキシャキとして歯切れがよく旨みがあり漬物(一夜漬け、糠漬け、サワークラフト[線キャベツを乳酸発酵させた漬物])、和え物、味噌汁の実、スープ、炒め物にする。
カリウム、ビタミンC、K、Uを多く含む。アブラナ科に多いイソチオシアネート(辛味成分)を微量含み香気成分でもあり抗酸化、抗がん、老化防止、生活習慣病予防、殺菌作用が認められる。キャベツから見出されたビタミンU(水溶性)が胃の粘膜を再生保護する作用がある。
芽キャベツ めきゃべつ(Brussel sprout)
日本には、明治以降にキャベツとともに渡来している。キャベツの変種で葉が茎、枝と接する部分(葉腋:ようえき)の腋芽(えきが:わきめ)の変形とし存在する。
茹でてクリーム煮、炒め物、サラダ、肉料理の添え物に利用している。
ビタミンC(コラーゲンの生成に関与)160mg/100g、ビタミンK(血液凝固作用)150μg/100g、葉酸(貧血予防)240μg/100g、パントテン酸(脂質代謝に関与)0.76mg/100g、食物繊維(整腸作用)5.5g/100gと多く含む。
白菜 はくさい
中国、華北原産といわれ山東菜の変種で結球型のもので主に中国、韓国、日本、東洋での生産量がおおい。日本では明治の初め山東菜が導入されたが全国的に普及はしなかった。その後日清、日露戦争で兵士が持ちかえり栽培し全国的に栽培され、盛んになったのは、昭和初期になってからといわれ以外にも新しい。
漬物(塩漬け、糠漬け、麹漬け)、鍋物に冬季の野菜としてなくてはならない。他に、スープ、炒め物、和え物、蒸し物と用途も広い。
栄養的成分は、同じアブラナ科でキャベツ(水分92.7%)に似るが水分が95.2%とありみずみずしさが味わえる。白菜を使ってのキムチ(朝鮮漬け)は、このところのダイエットも手伝って脂肪燃焼(唐辛子、ニンニク、生姜など)効果、食物繊維1.3%~2.7%、乳酸菌発酵による整腸作用もあり今や、たくわんを抜いて急速に生産、消費量とも急増して漬物の王座を占めている。
ブロッコリーBroccoli ぶろっこりー
日本ではミドリハナヤサイの別名がある。結球しないケールより改良されたといわれ日本には明治の初めにカリフラワーとともに渡来していたが昭和30年(1955年)代より栽培が始まりここ20年来急速に普及品種改良され日本全国で栽培している。
緑色の花蕾、若茎部を食用とし花蕾(からい)が密集して重量感のあり色の濃いのがよい。春にはとう立ちして淡黄色の花を咲かせる。茹でて彩りとしてサラダに用いられシチュー、バター炒め、付け合せとしても利用される。
1997年ブロッコリーのスプラウト(新芽)に含まれるスルフォラファン(おもに辛味の成分)の成分がピロリ菌を抑制しガン予防に効果的との発表があった。ブロッコリーで100g中にビタミンA効力130μg、ビタミンE2.5mg、ビタミンC120mg、カルシウム38mg、鉄を1.0mg含む。
漬け菜類(小松菜・野沢菜など)
小松菜 こまつな(ゆきな)
鎌倉時代に中国を経て伝わったといわれ、現在のものとは少し違っていたようで品種改良がされ江戸時代に命名と伝えられる。
あく(しゅう酸の成分)が少なく冬場の野菜として利用範囲が多く漬物、和え物、汁の実、お浸し、煮浸し、炒めに使われる。
カルシュウム(Ca:骨の形成、精神安定作用)が多く吸収はほうれん草よりよいといわれる。
野沢菜 のざわな
長野県野沢温泉付近が発祥、特産とされ、原種は東洋系天王寺蕪(温暖な地域での主要品種)でありお寺の住職が江戸時代中期に京都から持ちかえり導入したと伝えられる。
特有の旨みのある漬物とし浅漬け、古漬けが商品化され出荷される。漬物は、油炒め、お茶漬け、チャーハン、スパゲティー、納豆合えとしてもよい。地元では、生鮮で味噌汁の実、油炒めとして調理され緑黄色野菜としてビタミン、ミネラル、食物繊維の重要な給源となる。秋口にある程度成長させ寒さで鍛えておくと冬季に糖度が上がって耐寒性が高められ寒じめちぢみほうれん草同様、甘味、旨みのある野沢菜が育ち漬物の美味しいのができる。
100g中、生鮮でエネルギー16kcal、タンパク質0.9g、脂質0.1g、炭水化物3.5g、灰分1.1g、ナトリウム24mg、カリウム390mg、カルシュウム130mg、マグネシュウム19mg、リン40mg、鉄0.6mg、亜鉛0.3mg、銅0.05mg、マンガン0.23mg、ビタミンA:200μg、ビタミンD:(0)、ビタミンE:0.5mg、ビタミンK:100μg、ビタミンB1:0.06mg、ビタミンB2:0.10mg、ナイアシン0.7mg、ビタミンB6:0.11mg、ビタミンB12:(0)、葉酸110μg、パントテン酸0.17mg、ビタミンC41mg 食物繊維2.0g。
漬物でエネルギー18kcal、タンパク質1.2g、脂質0.1g、炭水化物4.1g、灰分2.4g、ナトリウム610mg、カリウム300mg、カルシュウム130mg、マグネシュウム21mg、リン39mg、鉄0.4mg、亜鉛0.3mg、銅0.05mg、マンガン0.13mg、ビタミンA:270μg、ビタミンD:(0)、ビタミンE:0.7mg、ビタミンK:110μg、ビタミンB1:0.05mg、ビタミンB2:0.11mg、ナイアシン0.5mg、ビタミンB6:0.06mg、ビタミンB12:(0)、葉酸64μg、パントテン酸0.13mg、ビタミンC27mg 食物繊維2.5gを含む。
大根 だいこん
根菜類。地中海沿岸が原産地といわれる。日本では、古名のすずしろ、おおねが知られるように古くより栽培している。
地面より出ている中まで緑の大根がありビタミンCとクロロフイルの抗酸化、脂肪分解作用をも兼ね備え、葉っぱも緑黄食野菜としての価値がある。おろし、刺し身のつま、酢のもの、漬物、煮物、味噌汁の実、切干大根に毎日の食卓に欠かせない食材としている。
辛味成分(生育初期、根の部分に多い)は、イソチオシアネート(脂肪分解・ピロリ菌撃退作用)で、おろして組織が壊された時に遊離し辛くなる。アミラーゼの消化酵素がおおい。大根アミラーゼは、ph5.5付近、60~65度で最も活性化し漬物では浅漬けの短期のものでは活性化するが長期に漬けこむタクワンにはないといわれる。ビタミンCは、内部より外皮に近いほど多く含む。その他にオキシターゼ(ポリフェノール酸化酵素:蛋白質、脂質分解、発ガン物質〈こげ:ベンツピレン〉抑制、解毒作用)、カタラーゼ(酸化還元酵素:成分損失、変色に関与)、グリコシターゼ(配糖体加水分解酵素:栄養の吸収をよくする)の酵素を含んでいる。
蕪 かぶ
原産地を地中海沿岸説があるが中央アジアとする説が有力視される。我が国古来のアブラナ科の野菜で〈すずな〉、かぶらともいわれ春の七草のひとつでもあり漬物用として用いられることが多い。
漬け物(千枚漬け・糠味噌漬け・麹漬け・辛子漬け)、酢の物、煮物に使われる。葉だけは、炒め煮にするとよい。大きいものは中をくりぬいて挽肉を詰めて煮込む料理もよく、おろして使う蕪蒸しもある。ヨーロッパでは、ラデッシュ(小さい赤蕪)をサラダ、ピクルス(甘酢漬け)として赤のアクセントに欠かせない。
利用のされ方、成分は、大根に似ているが赤蕪の色素はアントシアニン系のシアニン(抗酸化作用)という。ジアスターゼ(消化酵素)、イソチアシアネート(辛味成分:老化防止)を含む。
グルコシノレート類
アブラナ科の植物に含まれる含硫化合物の特有成分で、大根やワサビの辛味成分としても知ら れているがベンジルグルコシノレートは、体内へ摂取した際に分解されてベンジルイソチオシアネートとなる。酵素ミロシナーゼによってイソチオシアネートに分解する。体内の解毒酵素の働きや抗酸化力を高め、抗ガン作用を高める作用を有する。
イソチオシアネート(イソチアン酸エステル)
イソチアン酸のエステル(アルコールと有機酸が結合し水が除かれた化合物)の総称(アリル、メチル、エチル、ベンジルなど)であり野菜(特にあぶらな科、大根、わさび、からし、山椒)に含まれる辛味の成分のひとつで配糖体として含む。耐熱性、揮発性がある。酵素チオグルコシターゼ(ミロシナーゼ)の加水分解作用により、イソチオシアネートに分解する。イソチオシアネートは、辛味、芳香、揮発性があり、発ガン物質を不活性化させる作用を持つ。食欲増進、肝機能強化、殺菌、抗酸化、免疫力強化、褐変防止の作用を有し遺伝子を守る働きをしている。
アブラナ科野菜の大きな特徴は、辛味成分(イソチオシアネート)で、緑色の葉部分では、葉緑素、ビタミン(A・C)、ミネラル(カリウム・カルシウム・鉄)が多く含むことが理解できます。
辛味の成分は、独特な鼻にツーンとくる辛味の原因となっています。それぞれの成分は植物にとっては昆虫や草食動物から身を守り子孫を残すためであり食害を防ぐ意味がありますが、人間にとっては香辛料やハーブとして生理活性物質として活躍、重宝しています。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。