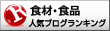◎食物連鎖Food chain しょくもつれんさ
生態系の中で捕食、腐食、分解に分けて考えられています。最も多くいわれていることは食べる(捕食)ものと食べられる(被食)もの、寄生との関係で結びついている連鎖的つながりのことです。1927年にイギリスのエルトンC.S.Eltonによって動物生態学Animal ecologyのなかで初めて自然をピラミッドの体系として明らかにし用いています。
生物は同種、他種を問わず、様々な形で自分以外の生物個体を利用して生き抜いています。最も典型的に見られるのが他者の捕食行為になります。
陸上の生物では、植物(生産者)は昆虫(植食性動物)に食べられ、昆虫は小鳥(小形肉食性動物)に、小鳥は大きな鳥のタカ、ワシ(大形肉食性動物)などに食べられ、それぞれ昆虫は第一消費者、鳥は第二、第三消費者となっていきます。このような生物間のつながりがあります。海水などの水中でも同じように、植物プランクトン→動物プランクトン→イワシ→イカ→マグロ→人などのつながりの捕食行為があります。
このような捕食の食う・食われるの関係をたどっていくと、ある一定の場所の生物間に、1つの鎖状の関係を見いだすことができます。これを一連の鎖として見出し食物連鎖と呼ばれています。このような関係は、関係する生物が可能な行動範囲における同じ場所で行なわれ食物連鎖はある一定の生物群集の中の構造の一つとなっています。
通常、食う側の方が食われる側よりも大きく、この連鎖において、一般に、下位のものほど個体が小さく、その個体数が多い傾向があります。上位にゆくほど数が少なくピラミッド型になり、これを生態ピラミッドといわれています。
現実には複数の種類を餌としており、また複数の種類に食べられることもあり、それらを考慮して図を描くと食べる食べられるの関係の入り乱れた複雑な網目が描けます。このことから食物連鎖全体の構造をあらわす食物網Food webともいわれています。
生物の栄養供給の形態は、さらに寄生する者と宿主の関係もあり寄生者が宿主から栄養を得ている寄生関係による食物連鎖もあります。人体における腸内細菌との関係があります。この場合、寄生する者は宿主より小さいのが普通なので、段階を追うごとに小さくなります。寄生食物連鎖は、通常の食物連鎖ほど段階が多くならならないようです。
腐食系の生物は、死骸や排泄物を食べ無機物化するほか、自ら餌となり、無機物が捕食系の中に組み込まれていきます。分解系の生物は、捕食系・腐食系の生物の死骸や排泄物を分解し、生成された物質は植物の栄養源となります。
植物の枯れ葉、枯れ木となったもの主成分のセルロースやリグニンが分解されていく過程があり、これらを腐食連鎖(デトライタス・サイクル)と呼んでいます。腐食連鎖は水中生態系でも、枯れ葉、枯れ木の植物が大量に流れ込む汽水(きすい)域の河川の河口付近、干潟、マングローブ林などにおいて非常におおきな役割を果たしているのです。
生きている植物を食べることから始まる食物連鎖、即ち生食連鎖(グレイジング・サイクル)とともに腐食連鎖(デトライタス・サイクル)は食物連鎖の2大潮流を形作っています。
すべての生物のエネルギーは、元をたどれば光合成に依存しています。そしてそれを利用するものに、光合成するもの、それを食うもの、さらにそれを食べるもの、のような段階があることがわかります。これを栄養段階と呼んでいます。生産者といくつかの段階の消費者、そして分解者という三者で構成されていることになります。
植物は、太陽の光エネルギーと水と二酸化炭素を利用して光合成をおこない、有機物の合成をして多くのデンプンや糖を作り酸素を放出し、窒素や各種ミネラルを組み合わせて、タンパク質や脂肪などを作り出しています。
多くが植物(生産者)を餌とする草食動物が第一次消費者となり、草食動物を食べる肉食動物が第二次消費者となっていきます。雑食の動物もいるので、消費者間の捕食の関係は複雑になっています。一般に上位にある消費者ほど個体数が少ないのが普通です。
寿命を迎えた生物の死骸やフンなどは、さらにほかの動物に食べられたり、細菌類などの働きによって分解されます。生物を構成していた有機物は、やがて無機物と水と二酸化炭素まで分解されます。
食物連鎖がおこなわれた結果、生物に蓄積しやすい物質が上位捕食者に集中していく生物濃縮という現象が生じます。水産物の毒魚類、貝毒などは、いずれもプランクトンによって合成された物質が筋肉、内臓に蓄積され食物連鎖の過程で濃縮されたものです。
食物連鎖による生物濃縮は、ダイオキシン類、重金属、農薬等の有害物質が問題としてとりあげられることも多くあります。湾内は閉鎖性水域のため、水質汚染の影響を受けやすくなります。人類は地球上の食物連鎖の頂点に位置しており、食物を通して生物濃縮によって蓄積された有害な成分を摂取していることにもなります。
一般には、上位に位置する動物ほど数が少なく、底辺に生存するほど多く生存していることからエルトンは、この現象を数のピラミッドと名づけました。
自家栄養生物の植物は、光合成を行い必要な栄養を合成していることから生産者という言い方もされています。食物連鎖によるピラミッドの最上位、頂点の最終生物の消費者は人ということになります。しかしながら、動物も植物もいずれは、死後に地中の微生物によって分解され、ふたたび生産者である植物の栄養源として、食べられるものと食べるものの関係となる、ひとつのサイクルの食物環を形成しています。自然界では、網目のように複雑で、これを食物網と呼んでいます。この食物網があることによって、地球全体の生物の集団が一定の秩序によって保たれてきました。
生物の進化として
46億年前 地球が誕生し原始地球は、現在の大気層はなく、地表に様々な放射線が降り注いでいたと言われています。
38億年前 生物は放射線の一種となる宇宙線を避けるように深い海で嫌気性細菌誕生したといわれています。
30億年前 酸素非発生型光合成細菌の登場しています。
27億年前 地球磁場の形成により宇宙線が遮蔽(しゃへい)され酸素発生型光合成細菌(シアノバクテリア)が登場しました。やがて糖からエネルギー物質を効率的につくり出す好気性細菌が登場しています。
20億年前 DNAを保護する核を持った真核生物の祖先が誕生しています。地球の酸素濃度上昇によりオゾン層の形成されましたが現在の5分の1程度です。
10億年前 植物の祖先の誕生で徐々に多細胞生物の出現してきました。
5.5億年前 酸素の急上昇により現在のオゾン層の形成に至っています。紫外線の遮蔽により、陸上生物の植物、動物登場してきました。
微生物の中には、太陽光線からの放射線をエネルギー源として炭酸ガスと水から体細胞を合成する光合成細菌の存在が明らかにされています。チェルノブイリ原発周辺では放射線を吸収する菌類が発見されています。植物が光合成によって「可視光線」をエネルギー源にしていると同様、この菌類は放射線を吸収できるように進化して、「放射線」をエネルギー源として利用しているというのです。
食物連鎖の底辺には、一般に自家栄養生物(独立栄養生物)の植物があり連鎖の上位に他家栄養生物(従属栄養生物)の動物がいて、その頂点に人が位置しています。上位の動物ほど数が少ないとしていますが、人為的な行為が入ることによってその体系は脅かされ破壊されています。農薬、工場廃棄物からの汚染物質の無機物は、植物に取り込まれ、やがては人の体内に入り、身体に悪影響を及ぼし公害の発生をみています。
きのこは、菌類であり生態系の重要な役割を果たしており腐葉土(動植物の排出物)に発生し有機物を無機質に変える働きをします。キノコは特に環境汚染の影響を受けやすく汚染物質(金属類)の吸収をし人体に悪い影響を与える物質を蓄積させていることもあります。環境の衛生状態のよいところで自生、栽培されているものを利用するようにしましょう。
大気に放出された汚染物質が拡散し、水や土、農作物に付着します。汚染されている、その土で栽培された農作物には、汚染物質の量が多くなることが予想されます。とくにキノコは汚染物質を吸収しやすいことが知られているので、今後とくに野生のキノコは注意をする必要があります。汚染されているような土地では土壌改良をしないと農作物を現状で作ることは難しくなります。土壌改良の進んでいない地域での山菜の摂取、登山、ハイキングは当分は避けるようにしましょう。
海洋汚染も深刻な問題となってきます。汚染水が、海洋に流れてそれによって水産物の汚染が拡大しています。放射性物質も海底に蓄積、堆積していくことになり、そこに生育、生存する海産物に対し大きな影響が考えられています。
放射性物質以外に津波で被災した工場からの化学物質などで汚染されている可能性もあります。海洋では、海藻類・プランクトン→小魚→大きい魚と捕食される食物連鎖があります。プランクトンなどが取り込んだ汚染物質は小魚や大きい魚に取り込まれていき生物濃縮が起こります。そして私たち人間は、食物連鎖の最終生物としてそれらの海産物として摂取しています。
2011年現在では、やはり、すでに福島原発の周辺で試験採取された沿岸の表層性魚種(コウナゴ、シラス)、沿岸の底層性魚種(アイナメ、カレイ、メバル、ヒラメ)、無脊椎動物(ムラサキイガイ、ホッキガイ、ムラサキウニ、モクズガニ)、海藻類(ワカメ、ヒジキ、アラメ)、淡水魚(アユ、ヤマメ、ウグイ、ワカサギ、イワナ、ホンモロコ[養殖])から暫定規制値を超える放射性物質が検出されていたようです。水産庁での発表です。
主に軟組織に広く取り込まれて分布し、生物濃縮により魚食性の高い魚種(カツオ、マグロ、タラ、スズキなど)での高い濃縮度を示すデータが得られているようです。
汚染されていない海域の底生生物を主な餌とする魚種(カレイ、ハタハタ、甲殻類、頭足類、貝類)では比較的濃縮度は低いとしています。大型の魚種ほど、濃縮度が高くなることが示唆されます。また若い魚や高水温域に生息する魚では代謝が良く排出量が多くなるため蓄積量は少ないと考えられています。
市場に出回っている水産物については、暫定規制値を超えないことを確認した後に漁業を再開しているといいます。
食物連鎖によって魚体内で放射性物質が濃縮、蓄積されて、 他のミネラルと同様に、海水中や餌中に含まれる放射性物質は魚の体内に取り込まれ、その後徐々に海水に排出されていきます。
海産魚中の放射性セシウムの濃度は、周囲の海水中の放射性物質の濃度の5~100倍に濃縮(食物連鎖による影響を含む)することが報告されており、海水中の放射性物質の濃度が上がれば高くなり、逆に、下がれば徐々に排出されて50日程度で半分程度に減少することが、これまでの研究で分かっています。このことから水産物中に含まれる放射性物質の調査に加えて、海水中の放射性物質の濃度のモニタリングが重要で調査が続けられています。淡水魚については、海産魚に比べて放射性物質の排出に要する時間が長いことが知られています。淡水魚についても、広く放射性物質の調査が行れています。知られる水俣病は有機水銀による中毒で脂溶性であり、セシウム、カリウムの水溶性物質より長く体内にとどまりやすく、蓄積し神経障害などの症状が強く現われる結果となりました。水溶性物質は、排出が早いとはいえ食物連鎖を見逃すことはできません。
海産物についてEU執行機関の欧州委員会が2011年8月に 欧州連合(EU)加盟国に対して、福島第一原子力発電所の事故を受けて実施している水産物の放射性物質の検査について、以前に日本近海で捕獲されたものを検査の対象にすることを発表していました。さらに対象地域を南シナ海からアメリカの西海岸沖にわたる太平洋の広範囲に広げ日本以外の国から輸入される水産物についても自主的に検査を行うよう求めています。 太平洋沖で回遊性の高い大規模な回遊を行う生物にはマグロ、カツオ、
ブリ、カジキ、サバ、サンマ、イワシ、アジ、ニシンなどがあります。
捕獲しているロシアや中国の漁獲物にも、福島原発事故で流れ出した放射能汚染水が影響を与えた可能性を排除できないとして、輸入海産物の抜き打ち検査を勧告しました。
今後は、食物連鎖による、生物濃縮も考えられ、食品のモニタリングによる調査を見守っていく必要があります。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。