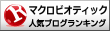◎アレルギーAllergy あれるぎー
そろそろすぎ花粉が舞う時期になってまいりました。目のかゆみ、痛み、結膜炎、鼻水、鼻詰まりの症状が現れ苦しむ人が増えてきています。これは花粉によるアレルギーによるものであることが分かってきました。アレルギー症状を現すものとして、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、胃腸障害のアレルギー疾患がありますが又その原因として大気汚染、食事の多様化、ハウスダクトによるものも多いといわれます。アトピー性皮膚炎で悩まされている人も多いようです。喘息の児童が10年前に比較して倍増しているといいます。特に1970年代後半以降の出生者の過半数に何らかのアレルギー症状がみられるのです。なお牛乳を飲むと下痢する乳糖分解酵素の欠損による乳糖不耐症、鮮度の低下した古い魚貝類の魚臭成分、たけのこ、ほうれん草、山芋、そば等食べ物に含まれる毒素のノイリン、トリメチルアミン、コリン、ヒスタミン等によって起こる一時的な、じんましん、吹き出物のでる仮性アレルゲンによるものとは異なります。
現在のところアレルギー性疾患は、根本的な治療は望めず対症療法が主になっているようです。日本型食事を見直して栄養のバランスの取れた食事をし免疫力を高めていくことがアレルギー改善への第一歩であると考えます。ここで少し花粉症、アトピー性皮膚炎について簡単に触れ食事について気をつけたいことのお話を進めてまいります。
花粉症
欧米で牧草の干草の収納している農夫に鼻炎を起こすことがあり、そこから枯草熱(こそうねつ)と1820年代にいわれていましたが1873年に牧草の干草の花粉によることを明らかにしたものです。それが1961年に牧草のブタクサの花粉であることを報告しています。
日本では春先の2月初旬よりスギ花粉による花粉(アレルゲン)によってアレルギー症状を主に目、鼻に不快なアレルギー症状が現れています。その他にもひのき、ブナ、松などで花粉症が起こりやすくなっています。主に多くが2-5月頃に多く見られます。ひどくなると目から涙が留めどなく流れ出したり、ゴロゴロする、かすむ、まぶしくなる、鼻水が出る、気管支にも症状が現れてくることもあります。治療としては、現在長期的、対症療法(症状を抑える[抗アレルギー・抗ヒスタミン・副腎皮質ステロイド・減感作療法中和療法・食事療法])で症状を軽減することが主な対処法となっています。減感作療法を3~5年続け軽減したということもありますが数年後に再発したいうこともあります。
アトピー性皮膚炎
アトピーとは、ギリシャ語で奇妙な、原因不明のとの意味があります。アトピーの体質、素因があり発症する湿疹をアトピー性皮膚炎としています。家族にジンマシン、気管支喘息炎、花粉症を発症している場合に多いといわれます。素因もさることながら調理器具、食器の不適切な使用、食事、ストレス、物理的皮膚への刺激(衣服の摩擦・皮膚の乾燥、汗・抗原物質物質との接触、洗剤がしみる)が皮膚への症状を示します。乳幼児期に多くみられますが成人になってもアトピー性湿疹、痒み(かゆみ)がみられることも多いようです。IgE(イムノグロブリンE)抗体も高い値を示します。現在のところ根本的治療はなく対症療法に頼っているのが現状といえます。治療には花粉症と同様の薬剤(軟膏)、転地療法、アレルゲン除去食事が行われています。ステロイド剤は、現在注射ではなく内服によって治療しており副作用は少ないといわれますが消化器症状に注意し短期の使用に留めたほうがよいと思われます。関係機関との相談のうえで使うのがよいでしょう。
食事からのアレルギーが考えられる場合には、誘発テストなどを行って反応をみて除去食事法を行いますが特に食事との関連が認められなければ食事の制限はしません。しかし常にバランスのとれた食事内容であることが大切なことです。神経質になりすぎることもよくありません。
水治療がよいとのうわさがありますがph8.5とアルカリ性が強く、それを1日5リットル飲むというもので全身がかゆい、髪の毛が抜ける、肌が赤黒くなったの被害が続出しています。温泉療法でも同様のことが起こっているので自分の体質に合った治療法を見つけることが重要です。
アレルギーは、外部からの異物、異質の細胞が体内に侵入してきた時、体内ではIgE抗体(免疫グロブリン)が肥満細胞(皮膚、消化管、肺に存在)、好塩基球(白血球に存在)を付着させ排除しようとしますが時として免疫力が弱まってくるとIgE(アイジイー:免疫グロブリン)抗体(特定のアレルゲンと結合するタンパク質:免疫機能が弱まってアレルギーを引き起こす)が反応し異物を外に出すのにヒスタミン、シクロオキシゲナーゼ(本来外界からの異物を防ぐ)の異状な過剰分泌を阻止できなく神経、筋肉、血管を刺激し症状を引き起こすことです。アレルギーは、食品、花粉、ほこりを敵とみなし過剰に反応してしまうことなのです。
*肥満細胞:主に皮膚の結合組織に存在し皮膚、消化管、肺に化学伝達物質(プロスタグランジン)であるヒスタミン、ロイコトリエン(シクロオキシゲナーゼ、リポキシゲナーゼにより生成)などを顆粒で貯めている免疫に関する細胞です。過剰に分泌することによってアレルギー反応を起こします。
*好塩基球:白血球には、顆粒球、非顆粒球に分けられるがその顆粒球で染色によりさらに好中球Neutrophil、好酸球Eosinophil、好塩基球Basophilに分類される。IgE抗体に関与し抗原抗体反応で過剰分泌によりアレルギー反応を示す。好酸球は、白血球のひとつであり、白血球の0~10%を占めることが知られ花粉症などのアレルギー反応が起こっている場所に多く集まる性質があります。
日本人の1~2割が花粉症で悩まされているといわれます。診断は、原因とされるアレルゲン特定の為の誘発テスト、問診などが行われています。花粉症に悩まされている人は早めの手当てが大切とか症状が出る2~8週間前から対策を講じておいたほうかよいといわれています。
アレルギー疾患(花粉症、アトピー性皮膚炎、ジンマシン、気管支炎)における一般的に注意しておきたいこと、注意できることとして
花粉症である場合は、花粉の飛散以前より気をつけることが大切で、信頼できる関係機関との相談をし、環境の整備、食事の見直しをしてみることが重要です。
花粉、ハウスダクト(ほこり)の吸入を避ける。花粉は下で舞っていることが多く換気扇より床の掃除、室内を乾燥させた状態にしない。水を張ったバケツを置いておくこともいいでしょう。花粉の舞う時期の外出を避ける。外出時には、マスク、マフラー、メガネをして直接アレルギーの原因とされるものに触れない。外出から帰ったら花粉をよく払い家の中に入れない。
空気の汚れている工場地帯のところでは、大気からの汚染物質、化学物質が発生しやすいのでそのところにとどまらない。そしてそこで成育している汚染されている動植物を口にしない。
ストレスで自律神経のバランスが崩れ免疫力が衰えるのでストレスを避ける。アロマセラピー(芳香のあるものを用いて気分をリラックスさせる)を利用することも試みられています。
アレルギー疾患は、体質的病気ともいわれ体質改善の為の療法がいろいろと試みられていますが自分の体質にあった方法を見出すことが大切なことです。安易な自己判断での行為は症状を悪化させます。
内服、点眼、軟膏、食事療法により症状が回復しても再発することが多いので根気よく治療を続けアレルゲンへの反応が軽減していることの確認をしていくことが重要です。アトピー性皮膚炎においては年齢に応じて特徴的な皮膚の症状の観察を続けましょう。
刺激のあるタバコを避け、酒、刺激の強い香辛料は、控えめとします。
心因性である場合もあるので食品のアレルギー検査を行い、食品に対する正しい知識を得ることも大切なことです。
加工食品、ファーストフードの取り方に注意しバランスのとれた食事とします。
欧米化した脂肪の多い肉食中心、脂肪(リノール酸)と砂糖がふんだんに使われているケーキ類多食の生活がアレルギー疾患の原因ともいわれているので古来の日本食を見直します。油の多い魚(青身魚に多い:いわし、さんま、さばなどの成分EPA、DHA)を日常的に食べていると喘息を患う率が低いことが英国ケンブリッジ大学の研究グループによる発表があります。喘息患者が先進国を中心に増加傾向にあり、魚を以前より食べなくなったことが喘息患者を増加させている一因ではないかと指摘しています。
食事性アレルギーの場合は、原因食品を見出して除去食事として様子をみます。魚、蓄鶏肉の腐敗菌によってヒスチジン(アミノ酸:成長促進、脂肪燃焼作用)がアレルギー性の食中毒を起こすことが知られています。
ヨーグルト、褐藻類(めかぶ・もずく・わかめ・ひじき)に多く含まれるぬるぬるの成分でフコイダン(多糖類・食物繊維)が腸内の悪玉菌を減らすことが解っており日常の食生活に取り入れることも大切です。
ビオチン(ビタミンH・ビタミンB群)が調整粉乳での乳児に不足しがちな成分であり、アトピー性皮膚炎を起こすとされるヒスタミンを抑える働きがあることを解明しつつあります。乳児の推奨量を10~15μgを奨励しています。
食品が原因である場合の食品アレルギー(Food Allergy)について
食品からのアレルギーは、卵、乳、小麦、そば、落花生が示すように昔からある食品ですから当然アレルギーもあったことになります。社会の著しい進歩にもかかわらずいまだに根本的な治療法が見出せず対症療法が主な治療となっているのが現状です。
乳幼児期においての人工栄養(乳糖不耐症)の増加、人工着色剤、抗生物質、食品添加物からの抗原性の強い食品を取ることによって解毒されず過敏に反応しアレルギーとなって現れます。離乳期が早すぎるとアレルギーを起こしやすいことがいわれることがあります。最近では以前に比べ離乳の時期が遅くなっています。早くても生後5ヶ月(体重7kg)とし15cc(大さじ1杯/1日)より開始しアレルギーを起こしにくい食品より与えるのが望ましいのです。乳幼児の13%にアレルギーがありその1割も血圧低下、意識障害、ショック状態、呼吸困難などの症状を経験しているといいます。「即時型食物アレルギー」とされ主に食物に含まれるタンパク質が原因で、食後一時間以内に重篤な症状が出る反応で、半日以上してから皮膚症状が現れる「遅延型」と区別しています。
乳幼児期の卵や乳製品の食物アレルギーは大半が成長につれて治まりますが、その後アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー疾患が継続していくこともあります。 乳児アレルギーの30%が牛乳アレルギー、人口の0.5%に、小児アレルギーの50%が卵アレルギー以下順に牛乳、チョコレート、ピーナツ、大豆、チーズ、そば、かに、海老との報告があります。厚生労働省の2001~2002年の食物アレルギー全国モニタリング調査、食物アレルギーの年齢別で乳児の10%、3歳児の4、5%、学童期に2、3%の割合でいると推定しています。原因別では0歳児で卵が62%、乳製品20%、小麦9%、魚卵3%、その他6%、1歳児で卵が44%、乳製品17%、小麦8%、魚卵6%、その他25%、2~3歳児で卵が31%、乳製品17%、小麦8%、そば6%、その他33%、4~6歳児で卵が25%、乳製品17%、甲殻類8%、果物11%、その他39%、7~19歳児で甲殻類15%、卵18%、そば8%、小麦11%、その他47%となっています。
医療機関に受診する8割近くが6歳以下、すべての患者の10人に一人が命にかかわるアナフィラキシーAnaphylaxis「即時型食物アレルギー」で、ショック症状に陥っているようです。成人では、小麦、果物(キウイフルーツ、バナナ)、魚(さば、鮭)、えび、そばが上位で年代ごとの違いが顕著で全体で卵、乳製品、小麦の順となっています。症状は、主に皮膚症状(じんましん)で、他ぜんそく、舌の脹れ、下痢の順です。
軽度の場合に食品の調理に際して単独で食べた時には、症状が出ないが複数組み合わせることによってアレルギー症状を起こす場合もあるので調理する時の条件も関係するので注意しなければなりません。小麦粉、そば粉では空気中に舞っているのを吸い込むことによってアレルギーを起こすこともあります。乳幼児のひとつの食品を好んで多食している習慣があると、いままでアレルギーの原因とならなかったものでもアレルギーを起こすこともあることを指摘しています。食品を加熱することによってアレルゲンの作用が減少することもあります。大根おろしではアレルギーを起こすが風呂吹き大根では起こさないこともあります。
欧米の脂肪の多い畜肉食中心の食事に日本人の身体は馴染んでおらずアレルギーを起こしやすいともいわれます。ヒスタミン、コリン(いか、えび、オレンジ、かに、さけ、さば、大豆、豚肉、まつたけ、やまいも、りんご、ゼラチン、なす、たけのこ、ごほう、ながいも、ほうれん草)が原因物質ともいわれていますのでそれらを含む食品を避けることも時には必要です。
症状として花粉症、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、胃腸疾患に見られるように多彩です。
食事の進め方については、
アレルギーとされる食品を限定したら、その特定された食品を完全に除去しその食事を続けていくわけですがその期間については、アレルギーの程度によって差があり一定の基準は定まっていません。数年を要する場合もありますしそれ以上に長引くこともあります。数ヶ月ごとに、その原因となっている食品に耐性ができているかどうかのチェックし把握していくことも大切なことです。これは慎重に自己判断は禁物です。
原因食品が確定できない時は、安全度の高い食品である穀類、野菜を用い観察しながら数を増やし、次第にアレルギーを起こしやすいタンパク質性の食品を使ってアレルゲンとなる食品を見出す方法もあります。重篤な症状を呈するのは主に、そばと落花生です。代替の食品もありますし減感作療法(アレルゲンとなっている食品を微量づつ取ってその状態を観察していく)は、卵、牛乳、小麦といった日常に不可欠なもの以外あまり実施していません。
食品ばかりでなくその生活環境にも配慮が必要なことは先に述べたとおりです。
牛乳でアレルギーのあった乳児が6歳になってもアレルギー症状があったのは、2.5%であったとの報告があり一定期間の除去食も有効との考えがあります。よって食事アレルギーについては、除去食がおもな食事法の基本になっています。
加工食品についての表示が義務づけられています。
アレルギーを特に起こしやすい物質の表示が2002年4月より製造、加工、輸入された加工食品及び添加物に義務付けられています。「製造、加工、輸入された加工食品及び添加物に義務付けられています。当初は「卵、乳、小麦、そば、落花生」の五品目でしたがその後エビ、カニが加わり七品目です。卵・乳(牛乳、乳製品)・小麦・エビ・カニは症例が多いもの、そば・落花生は症状が重篤であり生命への危険性があり、 食べて1時間以内に症状が現れる即時型そばアレルギーは、6歳以下の12.6%にあるといわれます。そばは、卵、牛乳、小麦についで多い原因物質であり少量口にしただけで重篤な症状を引き起こし、死亡例も見られます。留意する必要ありとしてこの七品目については、加工助剤、キャリャオーバーの食品についても表示が義務付けられました。しかし容器包装された加工食品だけでばら売りは対象外となっています。あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ(04/6月に追加)、カシューナッツ、ゴマ(2013/6月に追加)の20種は、症例が少なく、化学的知見が少ないとして「表示奨励」とどめています。また患者が安心して食べられるように「特定アレルギー食品を使っていません。」と使用の否定表示を奨励(表示奨励)しています。
可能性の表示は、PL法(製造物責任法)で企業防衛として安易に利用されることも予想され又選択の幅を狭めることにもなり禁止することとなりました。
加工食品に対する表示は五品目以外充分なものとはいえません。原材料がはっきりとしている加工食品を利用していきましょう。内容のはっきりしている強化食品を利用するのもいいでしょう。
同一の食品でも頻繁に、多量に食べたり、体力が衰えて疲れきっている時など体調の変化によって引き起こされたりすることもあるのでバランスの取れた体力づくりも必要になってきます。毎食食べなくてはならない五品目と主要な食品についての代替え食品、一品料理について紹介しました。乳化剤に大豆を使用していたり、設備として卵、小麦粉、落花生を製造しているところでの作業をしていることもあります。加工食品は、製造元にアレルギーであることを告げ問い合わせ確認してから利用していくことも重要です。各々個人個人によって体質が異なり重複してアレルゲンがある場合もありますのであくまでも参考程度にとどめておいてください。
抗アレルギー対策として注目しているものに、ペパーミント(ヒスタミン抑制)、山葵(ワサビチオヘキシルWasabi thiohexyl )、ネトル茶(ヨーロッパ、生臭さがありヒスタミンを微量含み減感作療法として利用)、シジュウム(南米産茶、グァバ:ロイコトリエン[鼻詰まりの炎症物質]を抑制、おいしいという)、凍頂烏龍茶、紅富貴(緑茶)、バナナ(バナナアレルギーの無い人でビタミンB6、ポリフェノール、オイゲノールによる)、赤紫蘇含まれるロスマリン酸(ポリフェノール)、甜茶のGODポリフェノール、プロポリス(ケルセチン)、乳酸菌(花粉症や通年性アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎の症状の緩和効果)、納豆、食物繊維、ペクチンの多いりんごで悪玉腸内細菌を除去、フェノール物質が多く含まれヒスタミンの合成を防ぐ竹酢液(食用)が抗ヒスタミン作用があるといわれ花粉症の軽減改善に役立つといいます。さらにオリーブ油に比べ、ユズ種子油は、ヒスタミン量が少なくなったという報告があります。汚染していない杉の葉をお茶にした杉茶を数年飲みつづけて症状が和らぐともいわれます。体質に合った改善策を探っているのが現状のようです。
以前は、アメリカに多かった花粉症は、日本ではまれだと思われていました。アメリカ在住日系二世も花粉アレルギーにかかることが多かったとの報告もあります。厚生労働省(保健福祉動向調査)によるとアレルギー症状は、町村部より大都市、5~9歳、35~45歳で症状が多くなっています。花粉が多く飛散していることも原因のひとつかもしれませんが、なにかもう一度以前からの日本の伝統的食生活を見なおしてみるのもよさそうな気がします。乳児期からの離乳食、食品添加物、欧米化した畜肉、脂っこいものの多い食事について振り返ってみる必要がありそうです。
※インフルエンザが流行しています。ワクチンを接種される方もおられると思いますが、ワクチンは、卵を培地として製造されている場合が多いのです。卵アレルギーのある場合の接種は、避けたほうがいいですし、充分な注意が必要となります。信頼できる受診機関とよく相談するようにしましょう。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。