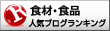・🍙米Rice こめ
近年では、8月末には、早場米と称して新米が市場にみられています。新潟県、北海道、秋田県が主なコメどころとして知られます。原産地は、熱帯アジア、インド周辺といわれており栽培は、紀元前1000年にもなるといわれ、日本への歴史は中国、朝鮮を経て縄文時代の終わり頃に伝来したものと思われます。
米をコメと呼ぶのは、日本に伝来される以前に、日本に全国的に自生していたイネ科の植物・マコモのコモから転化した説が有力ですが、中国ではマコモを菰(こ)や菰米(こべい)とも書き米の語源ともいわれます。こみ(小実)とか、こめ(小目)などという説もあります。古くに米は、普通の人が食べるというより、儀式で多く使われる時代もあり、何か神聖なものがこめられたものといった意味も考えられ「こめ」という言葉は、籠める(つめる、入れる)という動作をあらわしたものではないか、という説が主流になっています。
コメは今日では品種改良により北海道でも栽培できるようになり主産地ともなっています。
イネ科の植物として、2014~2015年で米国農務省によると、トウモロコシ1,008,788千トン、小麦725,122千トンと共に世界の三大穀物の一つになっているのです。世界では年間約4億8,000万トン(精米ベース)もの米が作られています。
世界の米の生産量の多くがアジアで産出し主食として重要な位置を占めています。生産量の第1位は中国の1億4,450万トンで、全体の30%を占め続くインド、インドネシアの上位3カ国だけで、約60%近くにもなります。私たち日本人が食べている米はジャポニカ米(日本型、小粒で丸みがあり粘っこい)ですが、世界で多く生産・消費されているのはインディカ米(インド型、細長くぱさぱさした感じ)です。世界で小麦についで生産量があり栽培種は、1000種以上といわれており、大きくは、インデイカ米(インド型、細長くぱさぱさした感じ)、ジャポニカ米(日本型、小粒で丸みがあり粘っこい)、ジャバニカ米(アジアの熱帯高地・アメリカ・ブラジル・イタリア・スペインやアフリカなどに多い。幅が広く、大粒なのが特徴。味はあっさりして粘りがある)の3種に分けられます。特殊米とし古代米(赤米、紫黒米)、低アミロース米(うるちとモチ米の中間種)、高アミロース米、低グルテリン米(タンパク質難消化性)、巨大胚芽米、低蛋白米(酒造、腎臓食用)があります。水稲(すいとう、栽培の98%)と、陸稲(りくとう、収穫量が少ない、栽培の2%)は、植物学上同一のものとされます。餅米(栽培の5%)と粳米(うるちまい、栽培の95%)との差は糖質、でん粉75%程度であるがアミロぺクチンの含有量が餅米(100%、もち、赤飯、おこわ)と、うるち米(80%、米飯、酒、味噌)で異なっているのです。
日本の生産量は、平成26年(2014年)で年間781万6,000トンで世界第10位です。消費量は796万6,000トンで生産量を上回っていますが、1人当たりの消費量は年間55.2キログラムと他のアジア諸国に比べて圧倒的に少なく、年々減少傾向にあります。
日本人に主食として欠かせないお米で、主食(ご飯85%)として主に用いられ、他に酒造(4%)、種子(1%)、加工食品(ビーフン、上新粉、白玉粉、餅、煎餅、落雁、八つ橋、五家宝、膨化米7%)、味噌、酢(1%)、飼料用に使われます。米ぬかが油脂、ビタミンB剤原料、漬物、飼料、肥料に当てられています。
過去には、豊作、不作の年が繰り返し内地米と食味が似ているアメリカからの輸入米もあります。いままで過剰生産、不作により幾多の出来事を乗り越え今日に至っています。長いあいだ主食であるがゆえに政府の管理化に置かれ保護政策から食管赤字を生みだしたり、世の中が安定してくると今日では自主流通米とし政府を通さずに販売できるようになってまいりました。豊作が続き、国民の主食の多様化により、米離れが進み過剰米を多く抱えるようになり減反制度が取られることとなったのです。その後冷害からの不作により平成5年の外米の緊急輸入備蓄米制度がありました。
日本では、おおよそ4月下旬から5月上旬にかけて発芽力の強い種子(もみ)である比重の重いものを選んで消毒、水に浸し苗代にまきます。5月下旬から6月中旬までの梅雨の時期に本田に移植、田植えを行います。8月に穂が出始め開花、結実し稲穂の垂れる高さ1mに達し受精し子房が肥大した頃の籾米(籾殻20%、玄米80%:糠8%〈胚芽3%〉、精白米92%)の収穫期は、二毛作もありますが一般に9月下旬から11月上旬刈り取りが行われその後1ヶ月ほど乾燥させ貯蔵には籾殻をつけたまま、または脱穀し玄米として保存しています。玄米より糠の部分を取り除く割合によって歩留まりと称し玄米を100として7分づき米(糠を75%とって歩留まりは、94%)、5分づき米(半つき米、糠を50%とって歩留まりは、96%)、白米(糠を100%とって歩留まりは、92%)が得られ、酒造用の米は歩留まり75%まで削られます。精白して食用とするようになったのは江戸時代以降といわれます。
世界で小麦についで生産量があり栽培種は、1000種以上といわれ特殊米とし古代米(赤米、紫黒米)、低アミロース米(うるちとモチ米の中間種)、高アミロース米、低グルテリン米(タンパク質難消化性)、巨大胚芽米、低蛋白米(酒造、腎臓食用)があります。水稲(すいとう、栽培の98%)と、陸稲(りくとう、収穫量が少ない、栽培の2%)は、植物学上同一のものとしています。餅米(栽培の5%)と粳米(うるちまい、栽培の95%)との差は糖質、でん粉75%程度であるがアミロぺクチンの含有量が餅米(100%、もち、赤飯、おこわ)と、うるち米(80%、米飯、酒、味噌)で異なります。
栄養価は、精白米100gでエネルギー356kcal、水分15.5g、タンパク質6.1g、脂質0.9g、炭水化物77.1g、灰分0.4g、ナトリウム1mg、カリウム88mg、カルシュウム5mg、マグネシュウム23mg、リン94mg、鉄0.8mg、亜鉛1.4mg、銅0.22mg、マンガン0.80mg、ビタミンA:(0)μg、ビタミンD:(0)、ビタミンE:0.2mg、ビタミンK:0μg、ビタミンB1:0.08mg、ビタミンB2:0.02mg、ナイアシン1.2mg、ビタミンB6:0.12mg、ビタミンB12:(0)μg、葉酸12μg、パントテン酸0.66mg、ビタミンC(0)mg、食物繊維0.5gを含みます。
精白米47gの米飯100gでの、タンパク質2.5%、炭水化物37.1%で、アミノ酸組成は、スレオニン、トリプトファン、リジン、含硫アミノ酸に欠ける(アミノ酸スコアでは、リジン、スレオニンが不足し65)が他の穀類と比較すると良好で日本人の貴重な蛋白源となっていました。大豆・卵・魚・畜肉類と一緒に取るとよく、緑黄色野菜を加えるとビタミン・ミネラルのバランスがよくなります。
最初のビタミンが、1910年鈴木梅太郎博士により米糠から発見されたビタミンB1(オリザニン)であることは有名です。ビタミンB1は、糠43%、胚芽24%、胚乳33%として含まれます。玄米と精白米を比較すると蛋白質1/3、脂質1/2、ミネラル、ビタミン類の多くが糠として取り除かれ、精白米ではでん粉質の含量が増加することになります。胚芽部分には栄養価値が高く胚芽を残して精白する方法の研究が進み東南アジア、中近東の原住民が常食としているパーボイルドライス、コンバーテッドライスは、籾米を蒸すので糠からのビタミンB類が胚乳に移る部分があるので白米にしてもビタミンB類の含量が多くなります。
2011年3月11日に発生した東日本大震災より福島第一原発の事故で長年に渡って放射性セシウムの米への取り込みが懸念される事態となってしまいました。放射性セシウムは、カリウムと似た性質があります。米について、17都県の基準値(100㏃ベクレル/kg)超過割合は23年産米では2.2%でしたが、24年産米では0.0008%に次第に減少しました。27年産米以降は、全て基準値以内でした。
今まで飼料とし処分されてきた米糠、胚芽、そして新たに発芽のパワーが秘められる発芽玄米、胚芽油、ギャバ健康食品として登場しています。加工品に米麹(甘酒・鮭・酢・味噌など)、上新粉(団子)、白玉粉(求肥ぎゅうひ)、米粉(微細製粉で小麦粉と同程度)、ビーフン、餅、煎餅、ポン菓子など、古くより親しんできた米は、多くの食べ方が知られています。食糧の自給率が40%程度としている昨今に米はほぼ100%の自給できています。近年では日本人のお米を食べる量が減っているので、主食としてのお米を食べる量をふやそうと、小麦粉のような粒子の細かい微粒子粉にして、パンやめんが作られるようになっています。上新粉・白玉粉でパンを作るとふんわりとした感触がなく、もちもちとした団子のような食感と思えるようだそうです。1990年頃から米粉(こめこ)と呼ばれ麺の製造など、米を使った様々の加工品、調理の開発が続けられています。
日本でも紀元前より栽培し、貴重な食糧の座を守ってきた米、現在でもその位置は、変わらないようです。高度成長時代の昭和40年代に脚気の多発、飽食などとも重なり、最近の健康志向で米飯学校給食が始まり、発芽玄米(発芽米)、ギャバ、米麹、米ぬか油、玄米胚芽油と健康によいといわれる成分の見直しをしています。色々と話題の多い米です。精白する事により、失われた栄養素を他の色々の食品を組み合わせて取るか、玄米に近い形にして効率よく栄養素を取り入れ主食だけで全ての栄養が満たされるわけではありませんが、それぞれの持つ食品の特性を知って食生活に生かして行くことが大切なことのように思うのです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
[2019.10.2]