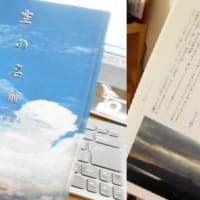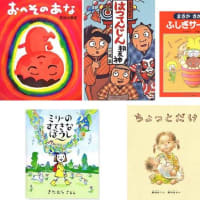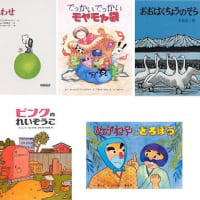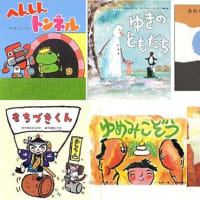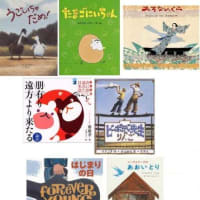子どもも大人も「感情」を上手に扱えなくなっている。特に怒り、落ち込み、不安といったネガティブな気持ちに対応ができない。このことが学級崩壊や少年たちの衝撃的な事件を生んだり、大人の社会でもさまざまな困ったコミュニケーションをひき起こしているように思える。かつて家族のなかで自然に行なわれていた、気持ちを取り扱うための訓練―これからは教育の場で、家庭で、意識的にこころのトレーニングをしなくてはならない。子どもたちの発する気持ちのSOSにどう答えるか、大人の感情トラブルをどう解決するか、実践的なこころの扱い方読本である。(「BOOK」データベースより)
読後の感想は、ひと言「言葉って難しい!」だ。
著者主催の研修会や、カウンセリングでの実例が多く載っているが、同じ言葉がけでも、子供によっての受け取りかたが違う。
「大人が自分の気持ちに気づく練習問題」や、最終章「大人が子どもと話すための練習問題」はなかなか楽しかった。たまには、こういう心理学っぽいテストも良いものだ。
自分がこれまでで一番嬉しかったこと。辛かったこと。悲しかったこと…。自分の「気持ち」を表現するのが、いかに難しいか。語彙の少ない子供なら、なおさらだ。
親も似たように実感した経験と自分のときはどうしたかを話してあげる方が有効だという。そのためにも、まず、自分の気持ちを整理しておくというのだ。
しかし、全部鵜呑みにして、マニュアルとおりにやるのも危険。
自分の子どもの気質(性格)を、まずよく知っておかないといけない。
以下、この本の受け売りですが…自分なりのまとめ(笑)
乳幼児は、「快-不快」が心の動きのベースになっている。
幼児期は、さらにそこに「善-悪」が加わり、小学校入学以降では、知識を得ることを中心とした「正-誤」の世界が広がっていく。しかし、現代では、幼児期からの早期教育でいきなり「正-誤」の世界に入ってしまう。
「快-不快」についてじっくり味わい、感情への対処方法を学ばず、「善-悪」も飛び越して、情緒的なものをたっぷりと体験することが妨げられて、いきなり「正-誤」。
幼児期に存分に「快-不快」を味わい、自分なりに不快な感情やネガティブな感情を持ったときに、その切り抜け方を編みだすことや、気持ちのコントロール法を身につけることはとても大切。
ギャーギャー叫び不快感丸出しになったとき、多くの子どもは、親から与えられるお菓子やオモチャやお子様向けテレビ番組でごまかされてきたことだろう。
それは、親にとって、その子のネガティブな感情に長々付き合うより、楽だからだ。放っておいて、自分で解決させることも大事。「我慢」や「嫌なことでもやらなければならない」ということが育たなくなる。
そういったごまかしを繰り返し、楽してきた親ほど、感情のコントロールのきかない少年期の子供に手を焼く。
気持ちを言葉にするのが、苦手なのは子供だけじゃなく、大人もしかり。
子供だけではなく、大人自身が、自分の感情を無理やり抑制したり、気持ちの扱いに不慣れ。
成果至上主義、効率第一優先の大人社会、「感情より効率」「テキパキやることが大事」「時間との戦い」を、家庭に持ち込んではいけない。
昨今の子供は、大人の都合で、なにかしら時間に追われ、やるべきことに追われ、自分の気持ちをコントロールする機会が少ない。
毎日沸き起こる「感情」「気持ち」を大事に。家族でゆったり会話する。
続編の『○のない大人 ×だらけの子ども』もお薦め。
読後の感想は、ひと言「言葉って難しい!」だ。
著者主催の研修会や、カウンセリングでの実例が多く載っているが、同じ言葉がけでも、子供によっての受け取りかたが違う。
「大人が自分の気持ちに気づく練習問題」や、最終章「大人が子どもと話すための練習問題」はなかなか楽しかった。たまには、こういう心理学っぽいテストも良いものだ。
自分がこれまでで一番嬉しかったこと。辛かったこと。悲しかったこと…。自分の「気持ち」を表現するのが、いかに難しいか。語彙の少ない子供なら、なおさらだ。
親も似たように実感した経験と自分のときはどうしたかを話してあげる方が有効だという。そのためにも、まず、自分の気持ちを整理しておくというのだ。
しかし、全部鵜呑みにして、マニュアルとおりにやるのも危険。
自分の子どもの気質(性格)を、まずよく知っておかないといけない。
以下、この本の受け売りですが…自分なりのまとめ(笑)
乳幼児は、「快-不快」が心の動きのベースになっている。
幼児期は、さらにそこに「善-悪」が加わり、小学校入学以降では、知識を得ることを中心とした「正-誤」の世界が広がっていく。しかし、現代では、幼児期からの早期教育でいきなり「正-誤」の世界に入ってしまう。
「快-不快」についてじっくり味わい、感情への対処方法を学ばず、「善-悪」も飛び越して、情緒的なものをたっぷりと体験することが妨げられて、いきなり「正-誤」。
幼児期に存分に「快-不快」を味わい、自分なりに不快な感情やネガティブな感情を持ったときに、その切り抜け方を編みだすことや、気持ちのコントロール法を身につけることはとても大切。
ギャーギャー叫び不快感丸出しになったとき、多くの子どもは、親から与えられるお菓子やオモチャやお子様向けテレビ番組でごまかされてきたことだろう。
それは、親にとって、その子のネガティブな感情に長々付き合うより、楽だからだ。放っておいて、自分で解決させることも大事。「我慢」や「嫌なことでもやらなければならない」ということが育たなくなる。
そういったごまかしを繰り返し、楽してきた親ほど、感情のコントロールのきかない少年期の子供に手を焼く。
気持ちを言葉にするのが、苦手なのは子供だけじゃなく、大人もしかり。
子供だけではなく、大人自身が、自分の感情を無理やり抑制したり、気持ちの扱いに不慣れ。
成果至上主義、効率第一優先の大人社会、「感情より効率」「テキパキやることが大事」「時間との戦い」を、家庭に持ち込んではいけない。
昨今の子供は、大人の都合で、なにかしら時間に追われ、やるべきことに追われ、自分の気持ちをコントロールする機会が少ない。
毎日沸き起こる「感情」「気持ち」を大事に。家族でゆったり会話する。
続編の『○のない大人 ×だらけの子ども』もお薦め。