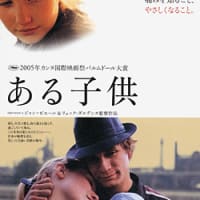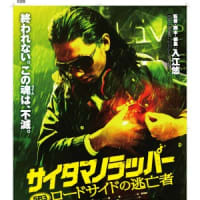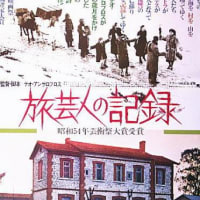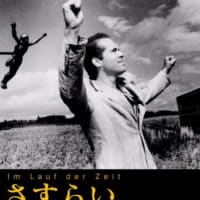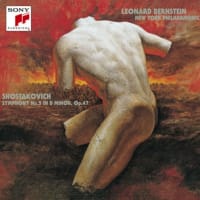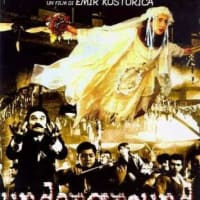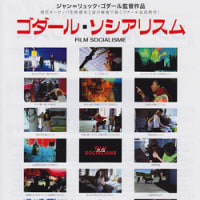★いくつ?:★★★★★
いやー説明不要の名盤なんですが、まあ戯言を。
まずロック史に残る、素晴らしいライブ写真で飾られたジャケット。(僕の説明なんて不要だよな本当は、ジャケも音も)
ニューヨークのライブでのベーシスト、ポール・シムノンのステージアクトを見事にとらえている。
僕の言葉で説明すると、むしろこの写真の素晴らしさが色あせてしまうので、むしろじっくりジャケ写真をみて頂きましょう。
そして名盤の中身!
のまえに、バンドのThe Clashについて。
限られた知識だけど、ロンドンパンクミュージックの先駆けであるSex Pistolsはマネージャーのマルコム・マクラーレンの影響が大きかったと思う。
(ちなみにパンク専門家からの証言では、パンクの発祥の地はロンドンではなく、ニューヨーク。代表的なアーチストは、Ramones、Patti Smith)
彼らに対し、Clashの方は自分たちでバンドをオーガナイズしていたのではないか。それによって、パンク・ロック本来のアンダークラスへの根付きと批判精神、ユーモア、そしてパンクを飛び越えてミクスチャー音楽へ走ることが出来たのではないかと思っている。
のですが、生粋のパンクス、Clash信奉者のひとどうでしょう?
で名盤London Callingの音の方は…
まず皆がよく言うように、この音源はミクスチャー音楽の原点とも言っていい。
ロックミュージックの原点を忘れることなく、そしてパンクのシンプルさも存在している。
そこにレゲエ、スカ、R&B、ディスコ、ダンスミュージックが見事に取り入れられている。
彼らがある一つの枠に収められることを、ハッキリと拒否する精神が見事に体現されている。
そしてパンクの原点であるアンダークラス、ワーキングクラスの精神性。
反体制的アティテュード、批判精神、ユーモア。
パンクに、いやロックに必要なものがこれでもかと詰まっている。
London is drowing 「ロンドンは溺死寸前」というタイトル曲'London Calling'
若者や労働者の背水の切迫感を歌う'Rudie Can't Fail'
ズタズタになった社会や都市のなかでの孤独さを表す'Lost In The Supermarket'
それを言っちゃおしまいよと思わずつぶやく'Death or Glory'
そしてアルバムの最後は、ダンサンブルなビートとグルーブで奏でられているにもかかわらず、歌われている内容は女に捨てられた男の恨み節の'Train In Vain'
ほとんどが負け犬たちへのレクイエムと言える曲、いやClash自身も負け犬たちと遠吠えを叫んでいる。
負け犬の遠吠え、ロックの笑い飛ばすユーモア、この二つがロックに必要な精神性を保ち続けている。
負け犬たちの曲なんだけど、なぜか手放せない。
敵と戦うには、自らのみじめさをまず笑い飛ばすユーモアが必要なんだ。
そう彼らは叫んでいるんだろう。
PS
今度はこの後のアルバムSandinistaを買ってレビューしなきゃ。
あでも今月は思わぬ出費が重なり、お金使うのセーブしなきゃ…