ジャン=ピエール・ダルデンヌ&リュック・ダルデンヌ兄弟監督『ある子供』(L'Enfant 2005年)を鑑賞。
2005年、カンヌ映画祭のパルムドールを受賞。
注目している若手映画監督、竹馬靖具氏に大きな影響を与えた映画。
(竹馬監督は俳優業をしていた時、この『ある子供』のような映画に出たいと思ったそう。しかし、日本ではこのような映画が作られていない。そこで、自ら処女作『今、僕は』を自主製作で完成、上映させている)
映画的構成として、重いテーマを扱い、じっくりと対象に迫る(一見すると地味な作り)ながら、あきさせない。不思議とリズミカルなテンポで映画は進んでいるように思えた。
重い話だが、それを素直に投げかけれられる。人に内在する子供性、無責任と責任。そんなことを考えた。
★いくつ?:★★★★
以下、2回目の鑑賞以降に気づいたこと、思ったこと。
この映画、主人公と(そして主人公の恋人。主な登場人物はこの二人、そして二人の生まれたての子供)のアップショットが非常に多い。やや引いた画でも、画面からは主人公達のみが浮き出てくる。これは主人公達の孤独と、孤立を良く表現している。
そして街が映っているにもかかわらず、映っていない。まず風景としての街の描写はほぼ皆無。そして主人公たちは生きた街との接触しない(家族や街の人との交流)。それがより主人公の孤独と孤立を描き、彼が子供のままでいること、そして犯罪を犯さざるをえない立場であることを説得力をもって語る。
主人公達が生きた街と接触を持たないのは、次の事に表わされるだろう。主人公カップルに子供が誕生したことを祝う登場人物は、いない(例えでなく、劇中0人)。劇中心理としては、ほぼ主人公カップルの一対関係で進む(例外は主人公の年下の盗み仲間。それでも若者たちは孤独)
『ある子供』は、貧困と若者の孤独、そして若年犯罪者という問題を見事にとらえていると言っていいだろう。
主人公たちが、生きた街と接触を持たない、持てないということに関しては、是枝裕和の『誰も知らない』と共通するところがある。二作品ともに、劇中人物たちは「社会・街から見えなくさせられてしまっている」という点に共通項がある。
ダルデンヌ兄弟『ある子供』、是枝裕和『誰も知らない』ともに映画の魅力は社会問題だけではないんだけどね。人が真に存在するとはどういうことかという問題でもある。
現在、ダルデンヌ兄弟の最新作である『少年と自転車』も、アンコール上映が予定されているので、見に行ってみようと考えている。
【憂鬱な追記】
しかし、『ある子供』見たいな映画、は現状の日本では作りにくいだろうな。異常な自己責任論、治安論の盛り上がりのなかで、こんな映画作ったら総叩きにあいそう。片山さつき氏や橋下徹氏が噛みつきそう。「なんでこんな、甘え切った無責任人間を主人公にした映画を作るのか」と。アホくさ
最新の画像[もっと見る]
-
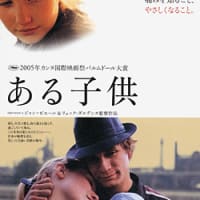 【甘口映画レビュー】ある子供
12年前
【甘口映画レビュー】ある子供
12年前
-
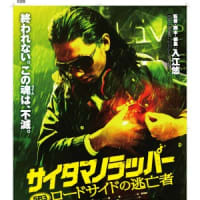 【甘口映画レビュー】SR3 サイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者
12年前
【甘口映画レビュー】SR3 サイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者
12年前
-
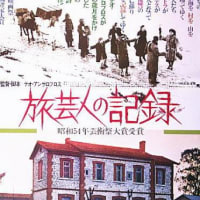 【甘口映画レビュー】旅芸人の記録
12年前
【甘口映画レビュー】旅芸人の記録
12年前
-
 Lou Reed & Metallica "Lulu"は衝撃の名盤!!!
13年前
Lou Reed & Metallica "Lulu"は衝撃の名盤!!!
13年前
-
 R.E.M 解散
13年前
R.E.M 解散
13年前
-
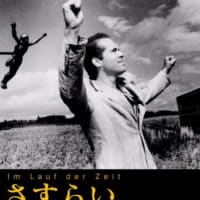 【甘口映画レビュー】さすらい
13年前
【甘口映画レビュー】さすらい
13年前
-
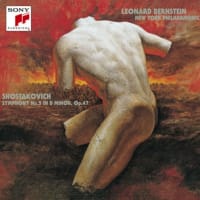 ショスタコーヴィチ:交響曲第5番
13年前
ショスタコーヴィチ:交響曲第5番
13年前
-
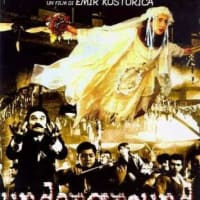 【甘口映画レビュー】アンダーグラウンド
13年前
【甘口映画レビュー】アンダーグラウンド
13年前
-
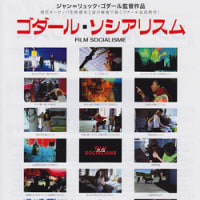 【甘口映画レビュー】 『ゴダール・ソシアリスム』
13年前
【甘口映画レビュー】 『ゴダール・ソシアリスム』
13年前
-
 【甘口映画レビュー】空気人形
13年前
【甘口映画レビュー】空気人形
13年前









