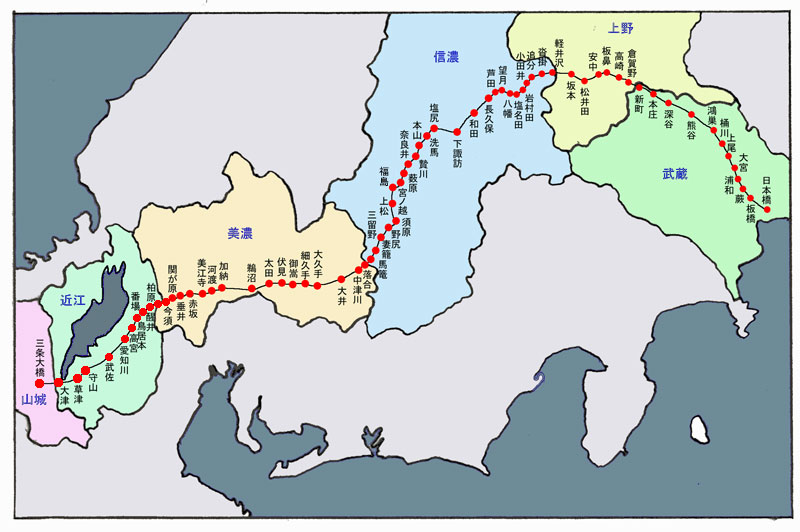[ゴロ]凌さんが/加齢臭だと/淳は警告
(凌雲集(りょううんしゅう)・嵯峨天皇)(文華秀麗集(ぶんかしゅうれいしゅう))(淳和(じゅんな)天皇・経国集(けいこくしゅう))
[句意]凌さんが加齢臭元だと淳は(皆に)警告した、という句。
[ポイント]
1.嵯峨天皇の命で、凌雲集・文華秀麗集が、淳和天皇の命で、経国集がつくられた。
[解説]
1.勅撰漢詩文集とは、天皇の命により撰定・編纂された漢詩文集。嵯峨・淳和両天皇の在世中に撰集された3勅撰漢詩文集がある。嵯峨天皇をはじめ宮廷の漢詩文への強い意欲を反映している。
2.凌雲集(814年成立)は、1巻。最初の勅撰漢詩文集(最初の漢詩文集は懐風藻)。嵯峨天皇の命で、小野岑守(みねもり)(778~830)・菅原清公(すがわらのきよきみ)らが782~814年間の24人の漢詩91首を収載。
3.文華秀麗集(818年成立)は、3巻。嵯峨天皇の命で藤原冬嗣・菅原清公(きよきみ)(770~842)らが編集。嵯峨天皇自ら作品を撰定。「凌雲集」にもれた28人の漢詩143首を伝える。
4.経国集(827年成立)は、20巻(現存6巻)。淳和天皇の命で、良岑安世(よしみねのやすよ)(785-830)らが編集。漢詩・漢文を集録。707~827年間の178人の作品。現存は詩211首(もと917首)、賦17編、対策26編。
〈2016立命館大・全学部2/4:「
問f 下線部5勅撰漢詩集が相次いで編纂されたに関連して、淳和天皇の命により良岑安世らにより編纂された勅撰漢詩集として、もっとも適当なものを下から一つ選べ。
あ『凌雲集』 い『文華秀麗集』
う『経国集』 え『性霊集』」
(答:う)〉〈2014近大・法:「
B 平安遷都後の9世紀前半には文章経国の思想が高まり、c[ 3 ]の治世である弘仁年間には勅撰漢詩集である『凌雲集』や『文華秀麗集』が編纂された。ところが、9世紀後半から10世紀になると大陸との関係も変化し、10世紀から11世紀には日本の風土や日本人の嗜好にかなった優雅な国風文化が生まれた。とくに dかな文学が発達し、e醍醐天皇の時代には最初の勅撰和歌集である『[ 4 ]』が編纂された。その編者のひとりである[ 5 ]は、『土佐日記』の著者としても有名である。
問3 空欄[ 3 ]に入れる天皇名として最も適当なものはどれか。次の1~4のうち一つを選べ。
1.桓武天皇 2.平城天皇
3.嵯峨天皇 4.仁明天皇」
(答:3)〉
問4 空欄[ 4 ]に入れる語句として最も適当なものはどれか。次の1~4のうち一つを選べ。
1.経国集 2.古今和歌集
3.和漢朗詠集 4.新古今和歌集
(答:2)〉
問5 空欄[ 5 ]に入れる人名として最も適当なものはどれか。次の1~4のうち一つを選べ。
1.小野篁 2.在原業平
3.菅原道真 4.紀貫之」
(答:4)〉
問8 下線部c[ 3 ]の在位中に起こったできごととして最も適当なものはどれか。次の1~4のうち一つを選べ。
1.勘解由使を設置し、国司交代の事務手続きを厳しくして不正を防止した。
2.徳政論争とよばれる議論を裁定し、造都と征夷の二大事業を打ち切った。
3.東北や九州を除いて軍団と兵士を廃止し、郡司の子弟や有力晨民を健児として採用した。
4.天皇の命令をすみやかに太政官へ伝えるために、蔵人頭を設けた。」
(答:4)
問9 下線部dかな文学についての文として誤りを含んでいるものはどれか。次の1~4のうち一つを選べ。
1.かな文学が発達する前の9世紀前半には、漢文学の隆盛で和歌はまったく作られなかった。
2.かな文学に用いられた平がなは、万葉がなの草書体を簡略化して成立した。
3.広くかな文字が使用されるようになると、『竹取物語』や『伊勢物語』などのかな文学の作品も次々と著されるようになった。
4.かな文字で著された宮廷女流文学の代表的な作品には、清少納言の『枕草子』や紫式部の『源氏物語』がある。」
(答:1)
問10 下線部e醍醐天皇の在位中に起こったできごととして最も適当なものはどれか。次の1~4のうち一つを選べ。
1.阿衡の紛議 2.遣唐使の廃止
3.安和の変 4.延喜の荘園整理令の発布」
(答:4)〉
〈2012早大・文化構想:「
下線部c平安初期には漢詩文集に該当しないものはどれか。2つ選べ。
ア「文華秀麗集」 イ「懐風藻」
ウ「経国集」 エ「凌雲集」
オ「日本霊異記」
(答:イ・オ)〉