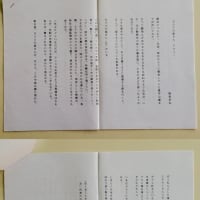鳥は飛ぶ事が出来る。人はそれを「羨ましい」と感じている事だろう。鳥の体は飛ぶ為に無駄がない作りになっており、骨は体重を軽くする為に空洞になっている。翼の作がりも種により様々である。翼の作りによって飛行力に差が出てくるのだろう。もし人が飛ぶ為に翼を付けようとしたら、きっと巨大な形になるだろう。
鳥は種によってその一生のほとんどを上空で過ごす者も存在する。水鳥の中でもミズナギドリが当てはまるだろう。子育ての時以外は大海原を飛翔している。しかし強風吹き荒れているので、羽ばたく必要性はほとんどないらしく、エネルギーを無駄に消費する事はないのだろう。このミズナギドリ類やアホウドリ類は他の鳥のように地面から即座に飛び立つ事が出来ない。ではどうするのかと言うと、ミズナギドリの仲間は決まった枝に登りそこからダイビングするように飛び立つ。アホウドリの仲間は強風に乗るように助走を付けて飛び立つ。結構苦労もあるのである。
カラスやスズメも含め、我々が身近で見ている鳥達は何かあると即座に飛び立つ事が出来る。一瞬の早業のようであり翼の動きを目に留める事さえ難しい。身近な鳥でカモ類がいるのだが、彼らにも飛び立つ時に助走を付ける種がいる。ウミガモと言われる仲間やハクチョウ類がそれに該当する。カルガモやマガモは水面から助走なしで飛び立つ事が出来る。
カラスは直接飛び立つ事が出来る。更に近距離でも旋回する事なしに降り立つ事が出来る。カモメ類やカモ類の一部は目的地に降り立つまでに上空を何回も旋回して徐々に近づいて来る。その光景を見た事がある人も多いだろう。目的地の面積が小さくなればなるほど旋回する頻度が高いようである。鳥によって実に様々である。
では飛行能力と言うか持続性はどうなのだろう?いつも疑問に感じているのである。渡りをする鳥は長距離を移動しなくてはならない。大陸間を移動するだけならば、疲れたら何処か安全な森にでも入れば良いのだろう。しかし海を隔てて渡る場合はそうは行かないと思う。途中で無人島がありそこで休憩しているのかも知れないが、もしもそうならそういった言った情報があっても良いと思うが・・・・・。渡り鳥と留鳥の持続性の違いに付いて調べている人はいないのだろうか?それともそんなに問題視する事でもないのだろうか?
カラスも20~30k移動したという記録がある。相当な距離である。人が簡単に歩いて移動できる距離ではない。カラスは人工物を巧みに利用出来る鳥なので疲れた時でも休憩場所に困らないかも知れない。
飛翔する際の持続性に関してはとても地味な事かも知れないのだが私自身とても気になる。長距離を休みなく飛び続ける種とそうでない種では何らかの違いがあると思う。もちろん途中で力尽き海へと引き寄せられてしまい命を落としている鳥も少なくはないだろう。ただ我々が気が付いていないに過ぎない。
画像:ハシボソガラス(ゴミステの上)
鳥は種によってその一生のほとんどを上空で過ごす者も存在する。水鳥の中でもミズナギドリが当てはまるだろう。子育ての時以外は大海原を飛翔している。しかし強風吹き荒れているので、羽ばたく必要性はほとんどないらしく、エネルギーを無駄に消費する事はないのだろう。このミズナギドリ類やアホウドリ類は他の鳥のように地面から即座に飛び立つ事が出来ない。ではどうするのかと言うと、ミズナギドリの仲間は決まった枝に登りそこからダイビングするように飛び立つ。アホウドリの仲間は強風に乗るように助走を付けて飛び立つ。結構苦労もあるのである。
カラスやスズメも含め、我々が身近で見ている鳥達は何かあると即座に飛び立つ事が出来る。一瞬の早業のようであり翼の動きを目に留める事さえ難しい。身近な鳥でカモ類がいるのだが、彼らにも飛び立つ時に助走を付ける種がいる。ウミガモと言われる仲間やハクチョウ類がそれに該当する。カルガモやマガモは水面から助走なしで飛び立つ事が出来る。
カラスは直接飛び立つ事が出来る。更に近距離でも旋回する事なしに降り立つ事が出来る。カモメ類やカモ類の一部は目的地に降り立つまでに上空を何回も旋回して徐々に近づいて来る。その光景を見た事がある人も多いだろう。目的地の面積が小さくなればなるほど旋回する頻度が高いようである。鳥によって実に様々である。
では飛行能力と言うか持続性はどうなのだろう?いつも疑問に感じているのである。渡りをする鳥は長距離を移動しなくてはならない。大陸間を移動するだけならば、疲れたら何処か安全な森にでも入れば良いのだろう。しかし海を隔てて渡る場合はそうは行かないと思う。途中で無人島がありそこで休憩しているのかも知れないが、もしもそうならそういった言った情報があっても良いと思うが・・・・・。渡り鳥と留鳥の持続性の違いに付いて調べている人はいないのだろうか?それともそんなに問題視する事でもないのだろうか?
カラスも20~30k移動したという記録がある。相当な距離である。人が簡単に歩いて移動できる距離ではない。カラスは人工物を巧みに利用出来る鳥なので疲れた時でも休憩場所に困らないかも知れない。
飛翔する際の持続性に関してはとても地味な事かも知れないのだが私自身とても気になる。長距離を休みなく飛び続ける種とそうでない種では何らかの違いがあると思う。もちろん途中で力尽き海へと引き寄せられてしまい命を落としている鳥も少なくはないだろう。ただ我々が気が付いていないに過ぎない。
画像:ハシボソガラス(ゴミステの上)