インターネットの大海原をゆらゆらと泳いでいたら、
恐竜が大好きな僕に打って付けの占いを見つけました。
 『恐竜占い』
『恐竜占い』
ジュラ紀のアイドル、恐竜に例えて占うよ!
常に当たる上に、かわいいイラストも付いてます!
『恐竜占い』の紹介文より引用。
添えられている恐竜のイラストが凄く可愛くて楽しい占いです。
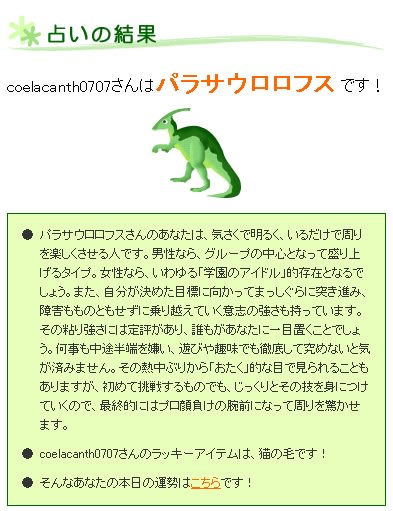
僕の占い結果は、パラサウロロフスでした!
『パラサウロロフス』
恐竜 - 鳥盤目 - 鳥脚亜目 - ハドロサウルス科
英名 / Parasaurolophus
学名 / Parasaurolophus walkeri
生息年代 / 白亜紀後期(約7400万年前)
生息地域 / 北アメリカ、カナダ
体長 / 10~13m
体重 / 約4.5t
食性 / 植物食
奇妙な後頭部の突起が最大の特徴のパラサウロロフス。
この突起は約1~2mもの長さがあり、頭骨の突起の内部は、
鼻腔から後頭部へと複雑に曲がりくねった骨の管が伸びていて、
突起の先端で折り返して頭骨内部に繋がっている構造なのだそうです。
トリケラトプス(Triceratops)の様な強靭な角を持つでもなく、
アンキロサウルス(Ankylosaurus)の様な強固な鎧を身に纏うでもなく、
パラサウロロフスが新化の過程で手に入れたのは、この突起の構造でした。
長い突起を通る管を持ち、鼻腔の表面積を拡大する事により発達した嗅覚。
突起内部の嗅覚細胞を最大限に活用して、外敵から逃れていたのでしょう。
また、この骨の管は鳴き声を大きく響かせる役目もあったそうです。
突起内部の構造をCTスキャンで分析した研究によると、
管の空洞が根元部は6本、先端部は2本に分かれていて、
管楽器トロンボーンやオーボエの様な音が出せる器官だったと言われています。
この特技は、仲間同士の会話や交流、求愛表現に重宝したのかも知れませんね。
奇妙な後頭部の突起は、
武器や鎧を持たないパラサウロロフスが生きる為に手入れた優しい器官。
争いを好まぬ穏やかな性格の恐竜だったのではないかと僕は思います。
生物の新化の過程を覗いてみると、
僕たち"人間"が学ぶ事はまだまだ多いのではないでしょうか。
◆関連リンク◆
A.E.G自然史博物館
CG STAGE:パラサウロロフス
恐竜のイメージ画像集:パラサウロロフスのギャラリー
シーラカンスの憂鬱:『BLOOD LINE -恐竜の図鑑-』
恐竜が大好きな僕に打って付けの占いを見つけました。
 『恐竜占い』
『恐竜占い』
ジュラ紀のアイドル、恐竜に例えて占うよ!
常に当たる上に、かわいいイラストも付いてます!
『恐竜占い』の紹介文より引用。
添えられている恐竜のイラストが凄く可愛くて楽しい占いです。
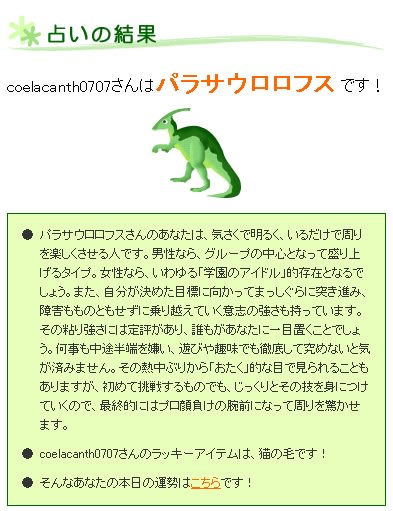
僕の占い結果は、パラサウロロフスでした!
『パラサウロロフス』
恐竜 - 鳥盤目 - 鳥脚亜目 - ハドロサウルス科
英名 / Parasaurolophus
学名 / Parasaurolophus walkeri
生息年代 / 白亜紀後期(約7400万年前)
生息地域 / 北アメリカ、カナダ
体長 / 10~13m
体重 / 約4.5t
食性 / 植物食
奇妙な後頭部の突起が最大の特徴のパラサウロロフス。
この突起は約1~2mもの長さがあり、頭骨の突起の内部は、
鼻腔から後頭部へと複雑に曲がりくねった骨の管が伸びていて、
突起の先端で折り返して頭骨内部に繋がっている構造なのだそうです。
トリケラトプス(Triceratops)の様な強靭な角を持つでもなく、
アンキロサウルス(Ankylosaurus)の様な強固な鎧を身に纏うでもなく、
パラサウロロフスが新化の過程で手に入れたのは、この突起の構造でした。
長い突起を通る管を持ち、鼻腔の表面積を拡大する事により発達した嗅覚。
突起内部の嗅覚細胞を最大限に活用して、外敵から逃れていたのでしょう。
また、この骨の管は鳴き声を大きく響かせる役目もあったそうです。
突起内部の構造をCTスキャンで分析した研究によると、
管の空洞が根元部は6本、先端部は2本に分かれていて、
管楽器トロンボーンやオーボエの様な音が出せる器官だったと言われています。
この特技は、仲間同士の会話や交流、求愛表現に重宝したのかも知れませんね。
奇妙な後頭部の突起は、
武器や鎧を持たないパラサウロロフスが生きる為に手入れた優しい器官。
争いを好まぬ穏やかな性格の恐竜だったのではないかと僕は思います。
生物の新化の過程を覗いてみると、
僕たち"人間"が学ぶ事はまだまだ多いのではないでしょうか。
◆関連リンク◆
A.E.G自然史博物館
CG STAGE:パラサウロロフス
恐竜のイメージ画像集:パラサウロロフスのギャラリー
シーラカンスの憂鬱:『BLOOD LINE -恐竜の図鑑-』











