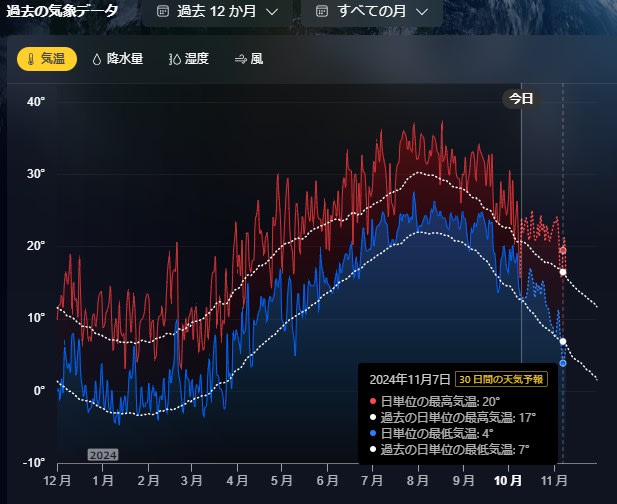ようやく帳簿が終わりまして、いよいよ畑仕事に取り掛かります。
そんな矢先に
(手直しが中途半端になっていて)放置していた電気柵の
通電を切っていたから、イノシシに入られた。Σ(゚Д゚)
杭も電線も頑丈に仕立てたつもりが、
電線下をくぐって侵入されてしまった。
最下部に竹で横棒をくくるまでしていなかったよ (;´д`)トホホ

侵入口が同方向から数か所 穴掘りされているので
複数頭とみてとれる
思うに、
大型の成獣ではなく、小型の幼獣が複数頭で群れているのかもと想像。
幸い
まだ、基肥も種まきも一切していないので
畝を足跡だらけにされた程度で、掘り返されたりの被害はない
ただ... ウン💩を置き配されてました
しかし春風は強い
畑の凍結防止用に畝を枯葉とビニールマルチで被覆していたのですが
毎日のように吹いているので マルチは大暴れ
時々見回りし、手直しや置石もしてたけど
敷き詰めつた枯葉もだいぶ飛ばされてしまったようでした
あ~れ~にぃ~み~える~は ウ~チの~じゃ~ないか?♬😱


去年は近くの柿の木に引っかかり、3m梯子を持って取りに行きましたが
今回は無理です ごめんなさい
そんなわけで枯葉もビニールマルチも片付けた。
まだ風の日は続くのか
乾燥で土質がダメになってしまいそうだ...
次回は防風ネットを準備した方が良いかな
*~ 訪問者様へ ~*
《 引っ越し先のご案内 》
gooblogが今冬終了を迎えるにあたり、移動先のブログを決定いたしました。
urlはコチラ
https://oyasainikki.blogspot.com/ 1a(アール)栽培日誌
ブックマークの移動をお願いいたします。
過去ブログは、時間のある時に少しずつ移行する予定です。
宜しかったらまた遊びに来てください。
by クロヒツジ
《 引っ越し先のご案内 》
gooblogが今冬終了を迎えるにあたり、移動先のブログを決定いたしました。
urlはコチラ
https://oyasainikki.blogspot.com/ 1a(アール)栽培日誌
ブックマークの移動をお願いいたします。
過去ブログは、時間のある時に少しずつ移行する予定です。
宜しかったらまた遊びに来てください。
by クロヒツジ