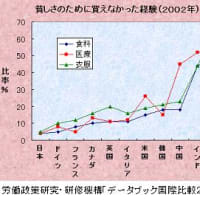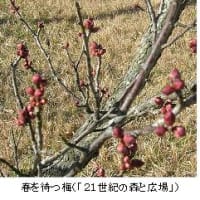≪法諺≫(穂積陳重「法窓夜話」岩波文庫より)
○一方を聴いて双方を裁判するな。
(イギリス)
○裁判官は左右同じ耳を持たねばならぬ。
(ドイツ)
○正義の秤は財布の乗った方へ傾きやすい。
(デンマーク)
∇<「殺害は正義」国連事務総長声明に批判──国連の潘基文事務総長が、米軍によるビンラディン容疑者殺害について「正義が達成され、とても安心している」と声明を出したことについて、職員から批判の声が上がっている。 ある男性職員は「国際人権法に照らして適法かどうか不明の段階で喜ぶのは、国際法を尊重すべき国連のリーダーとしては不適切だ」と指摘した。ある女性職員は「正義が達成された」のくだりに驚いたという。「正義が達成されるためには、人道に対する罪の容疑者として国際刑事裁判所で裁かれるべきだった」。 国連人権理事会で超法規的な処刑問題を担当するクリストフ・ヘインズ特別報告者は6日声明を出し、対テロ戦闘で「殺傷力の行使は最後の手段として許される場合がある」としながら、「今回の作戦で(殺害以外に)容疑者の拘束を認めていたかの確認が極めて重要」と指摘した>(4/8朝日新聞)
∇早速「ビンラディン殺害事件」の火蓋が切られている。上記記事の言葉で言えば、今度の行為が「正義」とされるか否かは、<国際人権法に照らして適法か>と<殺傷力の行使は最後の手段として許される場合がある>という点がキーポイントだろう。老生は国際法に関しては全くの門外漢であるゆえ、論評は控える。たゞ後者について、本居宣長が紀州藩主・徳川治貞の諮問により、古道の大意を述べた書・「秘本玉くしげ」に次の記事が載っていることを述べ伝えておこう。宣長曰く、<刑は可能な限り緩く軽いのがよい。但し、生かしておいては絶えず世に害をなすべき者などは、殺してもよい。>と。穂積陳重「法窓夜話」にもこの死刑論の部分が取り上げられ、<本居宣長翁は徐害主義の死刑論を説き、徴証主義の断訟論を唱えられたようである。>と言っている。<徐害(害のある者を除外する)主義><徴証(証拠にもとずく)主義>で、訴訟を断じるべきだ、とした。なか/\のものである。
∇さて、「司法の正義」の象徴に、ギリシャ神話に出てくる法の女神・テミスに由来する像がよく引き合いに出される。色々な形の像があるが、一般的には右手には正邪を断ずる剣を掲げ、左手には公平をを表す天秤を持っている。しかも天秤の左右の受け皿の大きさは異なる。ブルフィンチの「ギリシア・ローマ神話」(角川文庫)の原作者注には、<アストライアーは……乙女座になりました。テミス(掟)はこのアストライアーの母親でした。それでアストライアーは天秤をかかげた姿で描かれているのですが、それはたがいに相対する者たちの主張をこの天秤で秤るからなのです。>とある。(注:<それで>という文脈から推すと、母親のテミス同様に娘のアストライアも天秤をかかげていた、ということか)。ところで、司法の“テミス像”は目隠しをしているものと、そうでないものがある。上掲の左図が目隠しをした像、右は老生は見た事は無いが、我が国の最高裁判所大ホールにあるブロンズ像だそうである。いずれもGoogle で検索し、拝借したことをお断りしておく。「目隠し」は、見た目に惑わされない公正無私な裁きの象徴とされる。
∇江戸時代初期、大岡忠相の先輩格に、裁決明断を以て知られた京都所司代・板倉重宗がいた。徳川家康の信任厚かった勝重の長男である。職にあること30年余、新井白石が<人の慕ふこと神明の如く、愛することまた父母に似たり。>と「藩翰譜」に書いた程の人物であった。重宗が職にある間、彼は毎日決断所に出る前に、西に面している廊下で遠くの方に向かって拝礼するのが常だった。そして決断所には茶臼を一つ据えて置き、明り障子を閉めて座り、自分で茶を点てて訴訟を裁いた。後にその故を尋ねられると、<教養ある立派な人物なら心を動揺させない度量をもっているが、未熟な自分にはそれができない。だから茶を牽き、一服して心を鎮める。その後やっと訴訟を裁くことができる。又、明り障子を締めて訴訟を聞くのは、相手の面貌に惑わされないためである。一般的にいって、人の顔かたちを見ると、憎憎しげな者あり、可愛そげな者あり、正直そうな者あり、怪しげな者ありで、見た目で心が動いてしまい裁決に正鵠を得ない。実際は外れることも多い。人の心を容貌で決めてしまうことは出来ない。古人はその人の顔色を見て、それで裁いたといわれているが、明徳至誠の人なればこそだ。私如きは見るところに囚われて先入観念に因ってしまう。だから座席を明り障子で隔てて聞くことにしているのである>と。
∇テミス像「目隠し」の意に通じる逸話である。余談であるが、穂積陳重「法窓夜話」には、この話と共に、大岡越前守忠相の「毛抜き」の話が載っている。大正4年に上野不忍池畔に江戸博覧会が催された。その場内に忠相の遺品が出品されていた。説明書に曰く、<大岡越前守忠相が奉行所に於いて断獄の際、常に瞑目して顎鬚(あごひげ)を抜くに用ひたるもの也>と。穂積曰く、<大岡忠相が髭を抜きながら瞑目して訟を聴くのも、板倉重宗が障子越に訟を聴くのと同じ考えであろう。司直の明利が至誠己を空しうして公平を求めたることは、先後その揆を一にすというべきである>と。確かに本居宣長ではないが、<一人にても人を殺す(死刑にすること)は、甚だ重きこと>である。<然るに近来は決して殺すまじき者をも、その事の吟味の難しき筋とあれば、毒薬などを用いて病死として、その吟味を済ますことなども、世にはあるとか受け給はる。いとも/\あるまじきこと也>。全く同感である。そのためにこそ「公正無私」に天秤にかけることが大切である。同時に、先述したとおり、<天秤の左右の受け皿の大きさが異なる>ことの意味を熟考すべきであろう。これについては次回に譲る。
○一方を聴いて双方を裁判するな。
(イギリス)
○裁判官は左右同じ耳を持たねばならぬ。
(ドイツ)
○正義の秤は財布の乗った方へ傾きやすい。
(デンマーク)
∇<「殺害は正義」国連事務総長声明に批判──国連の潘基文事務総長が、米軍によるビンラディン容疑者殺害について「正義が達成され、とても安心している」と声明を出したことについて、職員から批判の声が上がっている。 ある男性職員は「国際人権法に照らして適法かどうか不明の段階で喜ぶのは、国際法を尊重すべき国連のリーダーとしては不適切だ」と指摘した。ある女性職員は「正義が達成された」のくだりに驚いたという。「正義が達成されるためには、人道に対する罪の容疑者として国際刑事裁判所で裁かれるべきだった」。 国連人権理事会で超法規的な処刑問題を担当するクリストフ・ヘインズ特別報告者は6日声明を出し、対テロ戦闘で「殺傷力の行使は最後の手段として許される場合がある」としながら、「今回の作戦で(殺害以外に)容疑者の拘束を認めていたかの確認が極めて重要」と指摘した>(4/8朝日新聞)
∇早速「ビンラディン殺害事件」の火蓋が切られている。上記記事の言葉で言えば、今度の行為が「正義」とされるか否かは、<国際人権法に照らして適法か>と<殺傷力の行使は最後の手段として許される場合がある>という点がキーポイントだろう。老生は国際法に関しては全くの門外漢であるゆえ、論評は控える。たゞ後者について、本居宣長が紀州藩主・徳川治貞の諮問により、古道の大意を述べた書・「秘本玉くしげ」に次の記事が載っていることを述べ伝えておこう。宣長曰く、<刑は可能な限り緩く軽いのがよい。但し、生かしておいては絶えず世に害をなすべき者などは、殺してもよい。>と。穂積陳重「法窓夜話」にもこの死刑論の部分が取り上げられ、<本居宣長翁は徐害主義の死刑論を説き、徴証主義の断訟論を唱えられたようである。>と言っている。<徐害(害のある者を除外する)主義><徴証(証拠にもとずく)主義>で、訴訟を断じるべきだ、とした。なか/\のものである。
∇さて、「司法の正義」の象徴に、ギリシャ神話に出てくる法の女神・テミスに由来する像がよく引き合いに出される。色々な形の像があるが、一般的には右手には正邪を断ずる剣を掲げ、左手には公平をを表す天秤を持っている。しかも天秤の左右の受け皿の大きさは異なる。ブルフィンチの「ギリシア・ローマ神話」(角川文庫)の原作者注には、<アストライアーは……乙女座になりました。テミス(掟)はこのアストライアーの母親でした。それでアストライアーは天秤をかかげた姿で描かれているのですが、それはたがいに相対する者たちの主張をこの天秤で秤るからなのです。>とある。(注:<それで>という文脈から推すと、母親のテミス同様に娘のアストライアも天秤をかかげていた、ということか)。ところで、司法の“テミス像”は目隠しをしているものと、そうでないものがある。上掲の左図が目隠しをした像、右は老生は見た事は無いが、我が国の最高裁判所大ホールにあるブロンズ像だそうである。いずれもGoogle で検索し、拝借したことをお断りしておく。「目隠し」は、見た目に惑わされない公正無私な裁きの象徴とされる。
∇江戸時代初期、大岡忠相の先輩格に、裁決明断を以て知られた京都所司代・板倉重宗がいた。徳川家康の信任厚かった勝重の長男である。職にあること30年余、新井白石が<人の慕ふこと神明の如く、愛することまた父母に似たり。>と「藩翰譜」に書いた程の人物であった。重宗が職にある間、彼は毎日決断所に出る前に、西に面している廊下で遠くの方に向かって拝礼するのが常だった。そして決断所には茶臼を一つ据えて置き、明り障子を閉めて座り、自分で茶を点てて訴訟を裁いた。後にその故を尋ねられると、<教養ある立派な人物なら心を動揺させない度量をもっているが、未熟な自分にはそれができない。だから茶を牽き、一服して心を鎮める。その後やっと訴訟を裁くことができる。又、明り障子を締めて訴訟を聞くのは、相手の面貌に惑わされないためである。一般的にいって、人の顔かたちを見ると、憎憎しげな者あり、可愛そげな者あり、正直そうな者あり、怪しげな者ありで、見た目で心が動いてしまい裁決に正鵠を得ない。実際は外れることも多い。人の心を容貌で決めてしまうことは出来ない。古人はその人の顔色を見て、それで裁いたといわれているが、明徳至誠の人なればこそだ。私如きは見るところに囚われて先入観念に因ってしまう。だから座席を明り障子で隔てて聞くことにしているのである>と。
∇テミス像「目隠し」の意に通じる逸話である。余談であるが、穂積陳重「法窓夜話」には、この話と共に、大岡越前守忠相の「毛抜き」の話が載っている。大正4年に上野不忍池畔に江戸博覧会が催された。その場内に忠相の遺品が出品されていた。説明書に曰く、<大岡越前守忠相が奉行所に於いて断獄の際、常に瞑目して顎鬚(あごひげ)を抜くに用ひたるもの也>と。穂積曰く、<大岡忠相が髭を抜きながら瞑目して訟を聴くのも、板倉重宗が障子越に訟を聴くのと同じ考えであろう。司直の明利が至誠己を空しうして公平を求めたることは、先後その揆を一にすというべきである>と。確かに本居宣長ではないが、<一人にても人を殺す(死刑にすること)は、甚だ重きこと>である。<然るに近来は決して殺すまじき者をも、その事の吟味の難しき筋とあれば、毒薬などを用いて病死として、その吟味を済ますことなども、世にはあるとか受け給はる。いとも/\あるまじきこと也>。全く同感である。そのためにこそ「公正無私」に天秤にかけることが大切である。同時に、先述したとおり、<天秤の左右の受け皿の大きさが異なる>ことの意味を熟考すべきであろう。これについては次回に譲る。