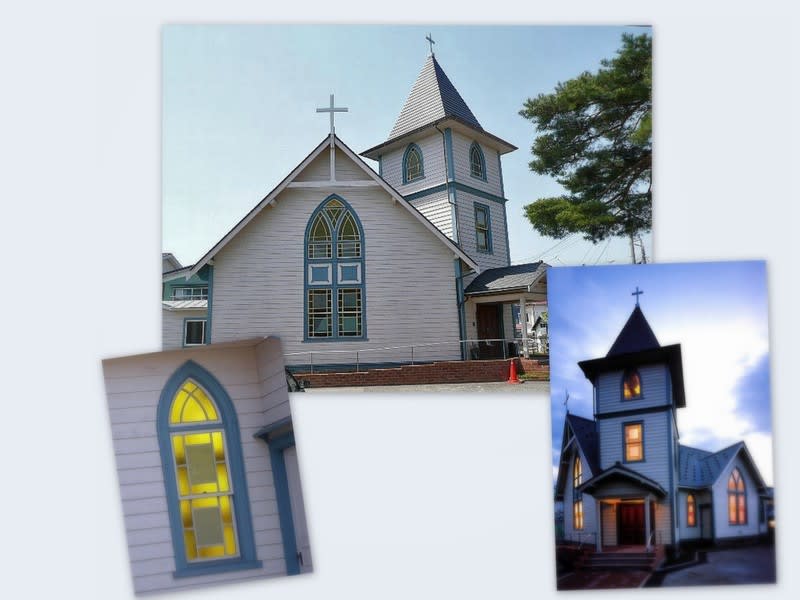杵が森古墳・陣が峯城跡・亀ケ森古墳・鎮守森古墳 会津坂下町【9-2】
25年度、地域の歴史・史跡などの現地学習第9回目の2は会津坂下町の古墳群探訪。
教育委員会の吉田氏に、杵が森古墳・陣が峯城跡・亀ケ森古墳・鎮守森古墳を案内いただきました。
画像クリックでスライドショーへ。BGMの音量にご注意ください。
杵が森古墳・・・
 杵ガ森古墳は、発掘調査以前は円墳と思われておりました。
杵ガ森古墳は、発掘調査以前は円墳と思われておりました。ところが、区画整理事業に伴って平成2年より記録保存のための発掘調査を行ったところ、
前方後円墳であることが判明しました。出土した土師器から、
その築造は古墳時代前期前半(4 世紀)と考えられます。
このため、県内でも最古段階の古墳の一つであること、さらに古墳の周辺に10基の周溝墓と
13軒の竪穴住居跡等を発見し(稲荷塚遺跡)、遺跡の重要性が明らかになったため
当初計画を見直し、前方後円墳と稲荷塚遺跡の周溝墓4基、竪穴住居跡4軒(うち3軒は古墳の墳丘下)
を含む遺跡の中心部分を公園として整備、保存している。
周囲には3世紀から4世紀にかけて連続した定住生活をうかがい知ることが出来る
極めて珍しい複合遺跡という。
墳丘の長さ45.6m、高さは2mほどという。県史跡指定。
陣が峯城跡

陣ヶ峰城は、阿賀(野)川が新潟県に抜ける盆地の出入り口にあたり、
高さ20mほどの段丘に建ち、崖である東辺をのぞく周囲三方向に大規模な堀を二重に堀を巡らす
東西110×南北175mほどの規模の単郭式の方形館。
会津坂下町教育委員会では遺跡の重要性から、平成14年度から3ケ年にわたり発掘調査を行った。
この城跡からは、中国製白磁、高麗青磁、国産陶器、和鏡、馬具や秤の錘などの青銅製品、
などの貴重品が多数出土しました。東側には厨(台所)があったらしく
炭化した椀や盤、包飯などの炭化した食品、炭化した穀物が多量に出土しました。
また、税金の基準となる重さ123.3グラムの権が出土したことから、役所的性格を持っていたようです。
陣が峯城のある一帯は平安時代末期は摂関家領の会津蜷河荘であったことが「近衛家所領目録」により
確認されており、永久2年(1114年)に藤原忠実が伝領している。
そのような経緯より、城の築城者は蜷河荘の管理に携わっていた人物であると思われる。
このようなことから、忠実の孫にあたる九条兼実の日記『玉葉』に登場する「藍津之城(あいづのしろ)」は
陣が峯城である可能性がある。
出土した遺物の大半は焼けており、多数の鏃が伴なって出土したことから戦火にあった可能性が
考えられるという。
すなわち、本城跡は12世紀初頭に築城され、12世紀後半に慧日寺と越後城氏から攻められ焼失し
その後、越後城氏により建てられたから「ジョウノシロ」と呼ばれた可能性が考えられたという。
史跡は平成19年度に国史跡指定、出土遺物は平成21年度県重文指定。
亀ケ森古墳・鎮守森古墳

会津坂下町の青津地区の西側には、いつの時代に誰が造ったは分からない大亀甲館(亀ヶ森古墳)、
小亀甲館(鎮守ヶ森古墳)があり、林の状況から近年の築造ではないようだといわれてきました。
これまでの発掘調査により、亀ヶ森古墳は全長127mの前方後円墳で、墳丘の表面全体に葺石が葺かれ、
後円部は三段築造で、墳頂には埴輪が並べられていました。
また、古墳周囲からは、盾形の周堀の存在が確認されました。
見つかった赤彩された埴輪から築造された時期は4世紀後半と考えられています。
亀ヶ森古墳は、県内で一番、東北地方でも2番目の規模を誇ります。
また、鎮守森古墳は全長55.9mの前方後方墳で、墳丘上には壺形土器が並べられおり、
相似形の周堀の存在が確認されました。
出土した遺物から亀ケ森古墳とほぼ同時代に造られたことが分かりました。
それでは、なぜこの地域に、このような大きな古墳が築造されたのか?
当時の交通は河川を利用した水運が主流だったと考えられ、河川の集中する青津区が
会津盆地西側における交通の要衝として大いに繁栄したからと考えられます。
会津坂下町は青津区の協力をもとに史跡の恒久的保存と学習の場、憩いの場として活用する
歴史公園に整備するため、史跡内の土地の公有化を進めています。昭和51年国史跡指定。
発掘調査中のとこから葺石が葺かれてるのを見ることができました。
1600年前の人々が並べた石!!なんかすごくうれしい気分・・・