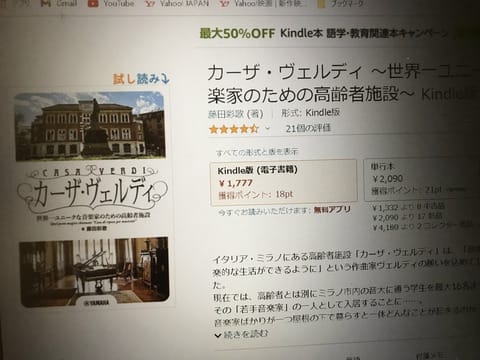NHKクラシック倶楽部の「アレクサンドル・カントロフ ピアノ・リサイタル」を聴いた。
曲目は
- ピアノ・ソナタ第1番、嬰へ短調作品11 シューマン作曲せn
- 巡礼の年第2年「イタリア」からソナタ風幻想曲「ダンテを読んで」 リスト作曲

番組の説明では、アレクサンドル・カントルフ(25)はフランス出身、父はバイオリン奏者で指揮者のジャン・ジャック・カントロフ、2019年に22歳でチャイコフスキー国際コンクールでフランスのピアニストとして初めて優勝、これまでウェルビエ音楽祭、ルール・ピアノ音楽祭など著名な国際音楽祭に数多く出演、演奏活動や録音は各地で絶賛され、フランスピアノ界のホープとして注目されている。
ウィキペディアで調べるとチャイコフスキーコンクールで優勝したときの演目はピアノ協奏曲の2番で、この曲で優勝したのは初めてだったとのこと。先日観た読響プレミアで反田恭平が「カッコイイ曲だ」と言って弾いていたあの曲であり、作家の宮城谷昌光氏が「クラシック千夜一曲」の中で10曲のお勧めの曲を挙げている中の1曲でもある。氏はチャイコフスキーの2番について「1番より断然好きだ、それは品格が高い曲だからだ」と述べているが、世の中的には1番の方が断然人気と演奏機会は多いのでしょう。その2番で優勝したというのだから、カントロフも宮城谷氏と同じような2番にかける熱い思いがあったのでしょう。
インタビューでは、両親がバイオリニストだったので最初に挑戦したのはバイオリンだったがバイオリンは音を出すのが難しく、格闘している感じだった、ピアノは子どもにとってゲームのようだった、初見で弾くのが大好きで、楽譜を見るとすぐに手が行くべき鍵盤を見つけるので夢中だった。しかし、長い間ピアニストが理想の職業とは思えず科学の分野に進むつもりだった、高校に入学してから初めて皆、音楽家という環境になった、友人との共演や初めての舞台でアドレナリンが分泌された、そして演奏家になることを考えた、
作品について番組では、シューマンはこの作品で初めて大規模なソナタ形式に取組み1833年から35年にかけて作曲した、ピアノに新たな効果を発揮させるように意図して書かれ、それまでのピアノ技巧の集大成の作品とも言われている、と説明している。
一方、リストの曲についてカントロフは、ダンテの神曲の地獄編に基づいている、ギュスターブ・ドレのさし絵などを見て全体像をつかみ音に翻訳した、重要なのは通常のピアノの音ではない響きを見つけることができるかだ、本当に時間がかかる、と述べていた。リストの「巡礼の年」はラザール・ベルマンのピアノの全曲(CD3枚)を持っているが大作だ。個人的には第1年スイスの1番「ウィリアムテルの聖堂」が好きだ。
さて、カントロフだが、テレビのインタビューを見るといかにもやさしい性格のおとなしい青年である。ピアノを弾くときは情熱を込めて弾いている姿は見せるが、ピアノから離れるとやさしい好青年である。チャイコフスキーコンクールで優勝するくらいの人だからもっと世界中で活躍してもおかしくないと思うが(してるかもしれないが)、このおとなしそうな性格がビジネスという面で損をしているのではないかと心配になる。SNSの使用状況を見るとインスタグラムはフォロアーがごく少数、Facebookは8千人くらいのフォロアーである。ある程度の頻度で更新しているようだが、もっと積極的にマーケティングしていってはどうだろうか(やっているかもしれないが)。カラヤンくらいになれというのは無理かもしれないが、クラシック演奏家というのは全般的に似たようなものかもしれない。どうであろうか。