シイラの話題が出たのは過去に一度か二度だったと思います。
店が終わってから主人に「さっきお客様と話してた“シイラ”って、シーラカンスのこと?」と訊ねた覚えがあります。
「ちがうよ、シイラっていう魚。シーラカンスと全然別のもの」
と呆れられてしまいました。
「築地ではまず見ないなー、オレも使ったことないし。‥あ、子供の頃オヤジがカンパチの代わりに仕入れたことがあったような‥」
「シイラってポピュラーな魚なの?」
「う~ん‥シイラって知ってるけど関東ではあんまり見ないよね。関西の方が食べられているんじゃない?」
かつてそんな会話がありました。
先日受けたさかな検定の問題にシイラが出てきました。
【関東ではなじみがありませんが、北陸や山陰、九州でよく食べられるこの大衆魚は、刺身や切り身で売られています。ハワイでは“マヒマヒ”と呼ばれるこの魚を選びなさい】
と。
後日送られてきた解説集には
【体長が2m近くにもなり、脂が少なく、水分が多いため、ムニエルやフライなど油を使う西洋料理に向く。卵も珍重される】
とありました。
旬は調べてみると夏から秋のようです。
いつか食べてみたい、と思いました。
わたしの魚(ウォ)キペディア 第40回 ほうぼう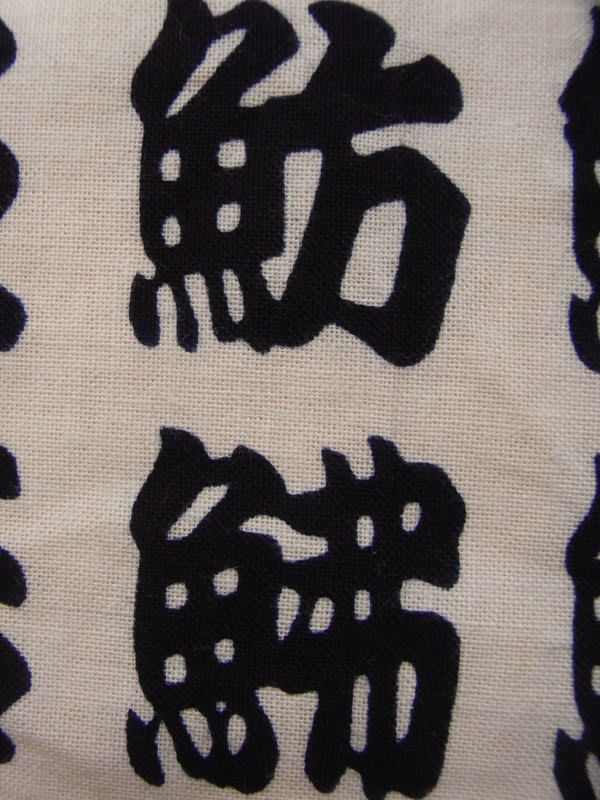
十年近く前のことです。テレビを点けたら、さかなクンがホウボウについて話しているところで、たしかこんなことを言っていたと記憶しています。
・ホウボウという名前は全国のいろんな場所、『方々』でとれるというところからきているという説や、浮き袋を使って鳴く時に『ボー、ボー』っていうのが転じてホウボウになったという説、その他いろんな説がある
・胸鰭の下の方が足のようになっていて、砂地を泳ぎながらエビや貝などを捕獲し、食べている
・気が弱い魚で、砂地を歩いていてバッタリ敵に出くわすと青い胸鰭を開いて正面から見た時に大きい魚に見えるように相手を威嚇し、それでも相手が逃げていかなかったら自分がヒレをたたんで逃げる
それからしばらくして魚のことが載っている食物事典でホウボウを調べると、似た魚のカナガシラとともにブイヤベースの具材に使われていることがわかりました。
過去に二度ほど食べたことのあるブイヤベースの思い出を辿ると、頭をぶつ切りにしたものが入っていたような気がして主人に伝えました。
「歩留まりのよくない魚だからね、ホウボウは。頭がでっかくて身はそんなに取れないし。ブイヤベースみたいに魚を丸ごと使う方が賢明だよ」
と主人は言いました。
寿司屋で白身といってホウボウを使う人はめったにいないそうです。
じゃあどうして仕入れるのと訊くと
「美味いから」
と答えが返ってきました。



















