こんにちは‥(^_-)-☆

今の奈良は、雨の性か11℃と少し寒いですね。
昼間17℃までしか上がらず寒い日に逆戻りですね。
その性かまた下痢に?・・((+_+))
今日は喫茶店の日なんですね・・(^_-)-☆
1888年(明治21年)のこの日、東京・上野(下谷上野西黒門町)に日本初の本格的なコーヒー喫茶店「可否茶館」が開店した。
1階がビリヤード場、2階が喫茶室の2階建ての洋館で、1階ではビリヤードの他、トランプや囲碁、将棋などをすることができた。
珈琲(コーヒー)は、明治の文明開化に花を添えるハイカラな飲み物として、特権階級の人々の間で人気があった。
「可否茶館」での値段は、もりそば1杯1銭の時代にコーヒーが1銭5厘、牛乳入りコーヒーが2銭だった。
また、席料が1銭5厘もした。
値段が高すぎたこともあり「可否茶館」は、3年もたずに閉店してしまった。
その後、1910年代の明治時代末から大正時代にかけて「カフェー」と呼ばれる喫茶店が全国的に普及し、日本において喫茶店ブームとなった。
1950年代後半には音楽も楽しむことができる「ジャズ喫茶」「歌声喫茶」「名曲喫茶」などが流行した。
このような喫茶店が登場・浸透した理由に、当時はレコードが高価で個人では購入が難しかったことが挙げられる。
1960年代から1970年代には、酒類を扱わない、純粋な喫茶店である「純喫茶」が流行した。
「純喫茶」は、酒類を扱い、女給(ホステス)による接客を伴う「特殊喫茶」に対する呼び名である。
店主自らがコーヒーを淹れるようなこだわりがある喫茶店が増えたのはこの頃からである。
日本のタンゴ全盛期の1953年(昭和28年)に創業した「タンゴ喫茶」で、店内には哀愁を帯びたタンゴの音色が響き渡る。
好きな喫茶店の料理といえば?
今は喫茶店でも食事ができるので、私は、食堂代わりに使い、カレーをよく食べますね?・・
そういえば今は音楽もかかっていませんね?・・
昔は、今の中央区で、その当時は南区でした?・・(^_-)-☆
昔は税金徴収の外勤中に時間つぶしに喫茶店をよく訪れましたね。
少し高かったが昔の南区にあった田園という喫茶店は高かったがよく行った記憶がありますね。
そんな若い時代も懐かしく思い出されますね?・・
今はコロナもあって10数年喫茶店らしき場所には行っていないかも?・・
コロナが始まってからは、喫茶店だけでなく飲食店にも行ってないですね。
今朝の血圧は、129-69、脈拍は70、血糖値97でした。
体温は36.1℃でした。
昨日の散歩数は、15552歩でした。
まだ腰痛も残っているので、散歩もこれが限界ですね。
今日も良い日でありますように・・(^_-)-☆










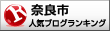

 奈良まほろばソムリエ奈良通2級の18回目の問題です。
奈良まほろばソムリエ奈良通2級の18回目の問題です。



