
万燈(まんどう)
「ご当地ソング」は、主に日本の歌謡曲・ポピュラー音楽や演歌・民謡のジャンルで、タイトルや歌詞に都市名・地方名や各地方の風習・文化・地形に関する事柄などを取り入れることで、地方色や郷愁などを前面に打ち出した楽曲のこと。
さて、俳句でも土地柄を詠むことはあり、月刊『俳句』5月号は「風土吟詠 都道府県四十七人集」を特集している。いわば、俳句版ご当地ソングである。
47句から特色のある句について若干述べる。
【意外に少ない地名入りの句】
「風土吟詠」と謳ったのだから地名を詠み込んだ句はたくさんあるかと思いきや47句中8句は少ないと感じた。明らかに地名を入れた句は以下のとおり。
埼玉:どこまでも秩父往還麦の秋 岩淵喜代子
東京:都心新緑改元の地のことば 対馬康子
志賀:罌粟咲いて近つ淡海の風のなか 田島和生
京都:挙りだす祇園四条の夏めける 鈴鹿呂仁
島根・薫風や出雲の王の墳墓群 栗原稜歩
福岡:走り茶と出す八女よりと言い添えて 寺井谷子
大分:新茶摘む耶麻の日輪濡れしまま 秋篠光広
徳島:木天蓼の花は白いよ歩危の風 西池冬扇
地名をしかと入れたから土地柄は当然出ているものの浅さを拭いきれない印象。地名入りは難しい。8人しか地名を入れなかったことは選ばれた俳人の見識の高さといっていい。
【場所をかすかにほのめかす句】
さすがに編集部に選ばれた俳人だけあって地名をいれずにその土地らしさを詠む工夫をする。それが以下の句。
北海道:リラ冷えの街のあちこち不眠症 源 鬼彦
新潟:霊峰へ行きつ戻りつ田植笠 若井新一
広島:天上に香たてまつり朴の花 八染藍子
神奈川:寺町に遅き昼餉や花曇 星野高士
源さんはリラを出したことで北海道をつよく暗示。若井さんの「霊峰」は、米山(993m)、多宝山(たほうざん633.8m)、八海山(1,778m)といろいろ候補があってあいまいだが全国で有名なのは八海山。土地柄はある。
八染さんの「天上に香」は原爆被災者鎮魂を感じさせ、星野さんの「寺町」は古都鎌倉のイメージを打ち出している。
【場所を示す要素が些末な句】
次に挙げる2句は使った固有名詞が些末すぎたのではないか。
福井:鮮緑の産道なれや瀧谷寺 中内亮玄
ウィキペディアによると瀧谷寺(たきだんじ)は、福井県坂井市にある真言宗智山派の寺院というが、立石寺や延暦寺ほど知名度がない。それに「鮮緑の産道なれや」は「参道」とダブらせた隠喩がすかっとしない。
鹿児島:野海棠火山を出でし水のこゑ 淵脇 譲
野海棠(のかいどう)もウィキペディアで調べるしかなかった。世界で霧島山にのみ自生するバラ科の固有種とか。風土性は出ていても俳句として脆弱。
写真の「万燈(まんどう)」は大國魂神社例大祭(くらやみ祭)の有力な出し物であるがこれを祭という季語の代替にするのは無理。それと同様に薔薇の一品種を季語とするのは無理。
【場所を季語に託した句】
山口:花魁の八文字踏む先帝祭 池田尚文
「先帝祭」は山口県下関市にある赤間神宮の祭事で5月2日から5月4日にかけて行われる。「八文字踏む」は花魁道中などで見せる花魁のくねくねした内股歩きである。この句は土地柄を出すのに宗教関連季語を使って技あり。
【テーマに背いた句】
岡山:新緑や命の水の匂ふ星 奥山登志行
広辞苑は「風土」をその土地の気候・地味など、自然条件、土地柄と解説する。「風土吟詠」なる主旨で俳句を求められたのであれば、やや安易でも地名を入れるのは誠実である。逆に「命の水の匂ふ星」はこのテーマから逸脱する。
ぼくが『俳句』の編集人なら奥山さんに俳句の書き直しをお願いするのだが。
撮影地:大國魂神社(5月4日)










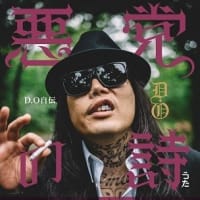



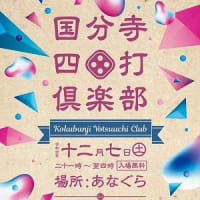
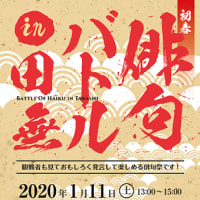


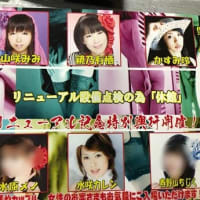

確かにわたるさんのご指摘はごもっともだと思いますが、そもそも中七下五がありがちなフレーズであることに違和感が残ります。