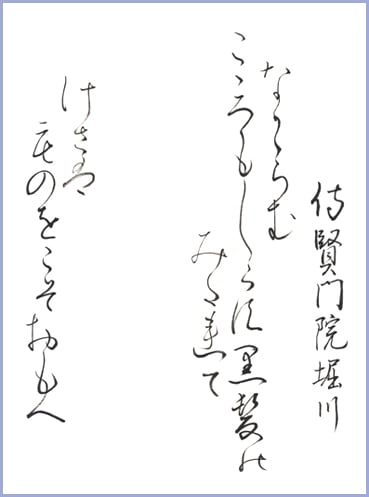
長からむ 心も知らず 黒髪の 乱れて今朝は ものをこそ思へ
歌意: 末長く変わらないという、あなたのお心もはかりがたく、
お逢いして別れた今朝は、黒髪が乱れるように心が乱れて、
あれこれともの思いをすることです。
作者: 待賢門院堀河(たいけんもんいんのほりかわ)
12世紀前半の人。待賢門院に仕える。
院政期歌壇の代表的な女流歌人。
この歌も崇徳院の主催した『久安百首』(77番・79番)で詠まれた歌。
この一首を、男が届けてきた後朝の歌に対する返歌という趣向で詠んでいる。
「長からむ心」は、これからも変わることがないとする誠実な心。
しかしここでの女には信じ切ることが出来ない。
男が去って、ひとりで過ごす時間が経つにつれて、
恋するがゆえの疑いと不安と不審がつのっていくのである。
恋のもの思いを、情感豊かに詠んだ一首である。
※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」
![]()
にほんブログ村ランキング←ポチっとお願いします

































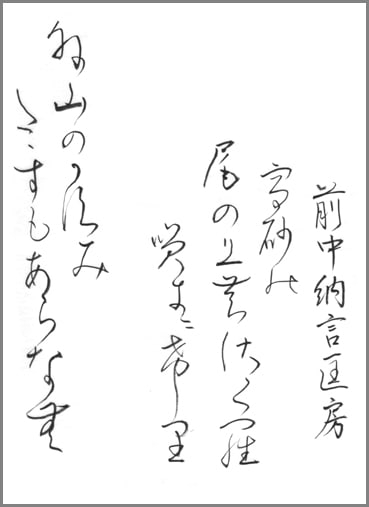

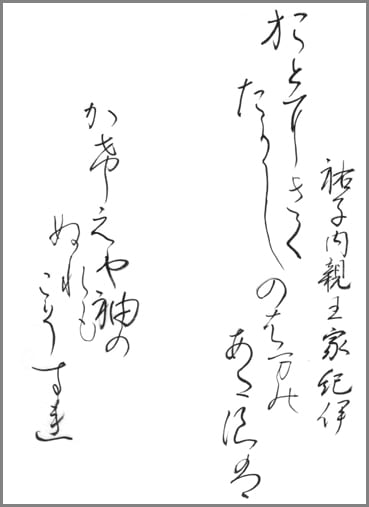

 が流行し始めました~
が流行し始めました~










