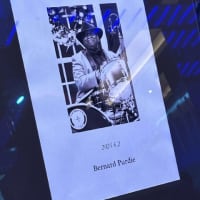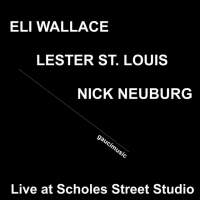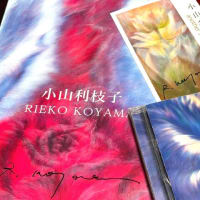サウジ行きの機内で、しばらくの間読み続けていた、ミシェル・フーコー『知の考古学』(河出文庫、原著1969年)を読了。

この膨大なテキストの中から、宇宙論が浮かび上がってくる。文字通りの宇宙論ではなく(本書でも、自らを試す言葉として登場する)、相互に異なるメカニズムを持つパラレルワールドを提示する論である。
さらには、ヨーロッパ的とみなされる統一化・中心化を徹底的に排除しようとする。
フーコーの言う<言説>が個々の宇宙であり、それぞれの宇宙の中では、身振りの常識も、話の展開の常識も、まったく、または微妙に異なっている。宇宙内の構成要素たる<言表>については、フーコーは、最小単位とみなすことを許さない。すいかの種のようなものではなく、形も成り立ちも依拠するものもそれぞれに異なるものなのだ。その意味では、分子のように表現することもあやうい。
植物のイメージが因果関係を表徴するものだとすれば、ここでの宇宙論はまったく植物的ではない。そして、フーコーは、結果的に成立している各々の宇宙たる<言説>同士の差異を見出すことが<考古学>であるとする。フーコー自身もはっきりと否定しているように、フーコーは構造主義的ではないのである。
その意味では、松岡正剛氏による本書評(>> リンク)には違和感を覚える。アーカイヴ(<アルシーヴ>)の奥に潜む構造を重視しているとの見方は、構造主義的に見立てていることに他ならないのではないか。アーカイヴ間を縦横無尽に動き回るとしても、問題とされているのは、アーカイヴの構造ではなく、まるで異なる作り方のアーカイヴが共存している様態なのである。何があるのかないのか、何が連続し断絶しているのか、何と何がリンクしているのか、といった、差異化に向けた働きかけである。
「考古学、それは、諸言説の多様性を縮減したり、諸言説を全体化する統一性を描き出したりすることを目指すのではなく、諸言説の多様性をさまざまに異なる形象のなかに配分することを目指すような、一つの比較分析なのだ。」
また、<言説>は静的なものではなく、常に矛盾を抱え、矛盾を翻訳するとともにそこから逃れるために絶えず続行・再開されるという議論はエキサイティングだ。
「言説は、一方の矛盾から他方の矛盾へと至る道であるということ。つまり、言説が目に見える矛盾を生じさせるのは、言説が自ら隠し持つ矛盾に従うからであるということだ。言説を分析すること、それは、矛盾を消失させ、次いでそれを再び出現させることである。それは、言説における矛盾の作用を示すことである。それは、どのようにして言説が、矛盾を表現したり、矛盾に身体を与えたり、矛盾に束の間の外観を付与したりしうるのかを明示することなのだ。」
『監獄の誕生』が、権力生成のあり様や生政治について描き出した一方で、<パノプティコン>という便利なキーワードを人々に与えたのに対し、本書には特段の便利なキーワードはない。知的ぶった某脳科学者が行っているような、そのようなキーワードを使ってのハッタリが、難しいわけである。しかし、膨大なテキストを通過したあとには、壮大な世界が垣間見えてくるような気にさせられる。

●参照
○ミシェル・フーコー『監獄の誕生』
○ミシェル・フーコー『コレクション4 権力・監禁』
○ジル・ドゥルーズ『フーコー』
○桜井哲夫『フーコー 知と権力』