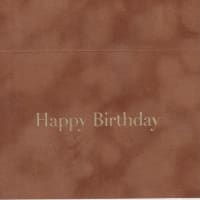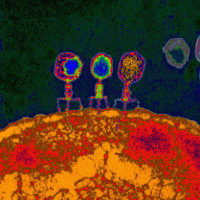青木編集長はワシントンDCでへばっています。
編集部は、MRICのメールニュースで流れていた癌研主催の子宮頸がんの公開講座にでかけてきました。
プログラムをみてみましょう。
【前半】
顧問の土屋先生の挨拶、三原じゅん子議員の挨拶、私立高校の校長先生の話、婦人科医師の講義、患者会からの話、質疑
【後半】
婦人科医師による中高生対象の講義
でした。先着170名ということでしたが、受付の参加者リストはだいたい40名ほどでした。
実際の参加者はもっと少なく、プレス(報道)がかなりいましたので、実際に関心をもって聞きにきている一般の人はどれくらいだったんでしょう・・・。
特に、後半の対象だった中高生は3名のみ。
最後のフロア質問は大学生3名がしていましたが。企画主旨とかみあってはいませんでした。
まあ、夏休みはもう終わっている学校もありますし、夏休みだとしても宿題におわれているかもしれません。正直、「病院に出かけてわざわざ聞く」ほどのことでもありませんし。
聞くなら学校で。そしてひとつのがんの話だけ聞くというのもヘンですしね・・・
◆土屋医師挨拶
7年前にワクチンでHPV感染を予防できるということになったが、昨年くらいまでは一般の方に認知されていなかった。
今年に入って女優の仁科さんが精力的に動いた。しかし、国立がんセンターでも医療者でも誤解をしている人が多かった。そして、一般の人に知ってもらう努力が少なかった。
中学生や小学生の親にだけ話をして、こどもに話をしてなかった、ということにきづき、
大妻嵐山高校の校長の協力で、高校1-2年の生徒さんに話をさせてもらった。
「絶対接種を受けましょう」という講義ではない。正確な情報を当事者に提供することが使命。自分で判断できるように。
(※は編集部注)
※医療者でも誤解している、というのは事実としてあります。
※日本の初交開始年齢を考えると高校1年になる前がよいのかもしれません。
◆三原じゅん子議員
こどもを産めないハンディを追っていきていくのはつらいこと。
がんの中で唯一予防できるワクチン。ほとんどの先進国では接種が国のプログラムに組み込まれ公費補助になっている。全額補助するように取り組んでいる。
※産む産まない産めないというのはセンシティブなので、皆が産むのがフツウというようにとられる発言は注意が必要
※がんを予防できるのは唯一というのはミスリーディング。B型肝炎についてもふれないと。
◆婦人科医 講義
増えているのは子宮体がん・卵巣癌。子宮けいがんは全体には横ばい。若い人が増えている。
年15000人が発症、3500人が死亡(製薬会社のスライド)
※増えているのは病気そのものが増えているのか、健診の影響か。どのステージで増えているのかが重要
性交後に8割がHPVに感染し、90%が自然に消失。
持続感染する要因として、ピル・タバコ・ストレスがいわれている。
婦人科の開業医がピルで利益を得ているのでピルについては今あまりいわないことにしているらしい。
持続感染→10% 高度異形成→子宮頸がん0期 50.3%
診断時がんⅠ期 27% Ⅱ期27% Ⅲ期 6.7% Ⅳ期4.4%
卵巣癌は症状が出にくく、進行してからみつかるのが特徴。Ⅲ期が50%。
子宮頸がんは初期に見つかることが多い。症状が出やすい(性交時の不正出血など)
5年生存率は0期なら100%、Ⅰ期77.9%。
ワクチンの種類。HPVは任意ワクチンだが、ワクチンなんてみんなうっちゃえばいい。
あまり余り深く考える必要は無い。風疹や日本脳炎のワクチンとか説明したり考えたりしない。
せっかくだから性教育このことを、、という考え方もあるが、「頸がんを予防するワクチンだから」とうっちゃえばいい。
※このあたりは保護者や教員から拒否されるとおもいますよ。ひとつは責任問題。もうひとつは当事者へのインフォームドコンセントとしてそれで足りるのか?です。絶対に足りません。
日本の子宮頸がん健診の受診率が低いのは婦人科にいくのがはずかしいから。
HPVをしらべてワクチンをうつほうがいいにきまっている。
健診を皆受けましょうというよりもワクチンを皆にうってしまったほうがいい。
※婦人科医自ら婦人科受診を否定的に語るのはやめたほうがよいとおもいます。
健診に行かない人対象の調査はいろいろありますので、どうすれば行きやすくなるかを考えたほうがよいですね。
--------------------------------以上です。
いくつかの(いえ、たくさんの)疑問。
◆性交開始後の女性に必要な婦人科健診は子宮頸がんのチェックだけではないので、健診にいくよりワクチンをうっちゃったほうがいい、というのは問題じゃないのか?
(この点は日々がんの患者をみている専門医と、ジェネラルに日々女性をケアしている婦人科の開業医の見解に大きな溝があると感じます)
◆HPVワクチンは接種しないという人もいるので、ワクチンと健診というだけでは不十分ではないか。性交開始年齢やパートナー数、コンドーム使用による防御効果についてもいうべきではないのか?
(ふだん、中高生に話をしていない、予防教育や健康教育に慣れていない人にはこのあたりを具体的に説明できないのかもしれない)
癌研の名誉のためにいいますと、この講座には製薬会社はかんでいませんでした。受付も進行も病院のスタッフでした。
製薬会社がつくった子ども向け漫画パンフレットを初めてみましたが、、、ちょっとこれは学校や地域では配れないよ、という内容。
そして講義スライドの半分以上が製薬会社がつくったものなんですよね・・・。
(あたりまえですが、対象にあわせて自分でつくるほうがよいですし、製薬会社のバイアスをかけないように話をするのが専門家には必要な努力)
後半は中高生対象でしたが、保護者と一緒に参加したのは3名のみ。
前半とほぼ変わらないスライドで、話し方を子ども向け言葉にした、というかんじでした。
(思春期層には、子ども扱いせず、ていねい語で話すのが基本ですよ。大人として向き合わなければいけない話を扱うのですから。)
疫学データや癌の詳細などは、思春期の子どもにハタシテ必要なんだろうか?と思う訳です。
また、子宮頸がんのことだけを話すというのも現実的ではなく、土屋先生は、今後産婦人科医の専門団体の全面協力を得て全国でも中高生が専門家から話がきけるようにできるのではないか?という善意の提案をしていましたが、それはウマイ案ではないよな、と思って帰ってきました。
パーツ(臓器)ごとの法律を作ったり、講演会をしたりということは、学校現場のニーズや当事者・保護者のニーズにかみあっていません。
多忙な医師は無料で学校にでかけますかね?外来閉めてでかけたら数万円の謝金が妥当ということになりませんか?
この日、婦人科医が「風疹や日本脳炎なんて説明しないでしょう?(だからHPVも説明しないで接種しちゃえばいいというニュアンス)」・・・はかなり乱暴な話です。
思春期の人達には説明と同意の確認が必要ということは世界や国内のコンセンサスですよ。
小児科のひとたちはそれよりも小さな子どもでも自分が受ける検査や治療についてなるべく理解を得られるように工夫しています。
がんの専門家や婦人科医師が出向くより、保健師や養護教諭をサポートする方が先。
・・・世界で100か国が認可、公費化がすすんでいる、と度々「世界」を持ち出しますが、世界が大切にしている思春期層へのRespect、コンドームを含めた包括的な教育については一切触れないで、とにかく接種してしまおうという日本だけのやり方には何も疑問がないのが、今のところあちこちできく製薬会社と、ふだんこの世代の子ども達に接してもいないひとたちの話の筋。
編集部は、MRICのメールニュースで流れていた癌研主催の子宮頸がんの公開講座にでかけてきました。
プログラムをみてみましょう。
【前半】
顧問の土屋先生の挨拶、三原じゅん子議員の挨拶、私立高校の校長先生の話、婦人科医師の講義、患者会からの話、質疑
【後半】
婦人科医師による中高生対象の講義
でした。先着170名ということでしたが、受付の参加者リストはだいたい40名ほどでした。
実際の参加者はもっと少なく、プレス(報道)がかなりいましたので、実際に関心をもって聞きにきている一般の人はどれくらいだったんでしょう・・・。
特に、後半の対象だった中高生は3名のみ。
最後のフロア質問は大学生3名がしていましたが。企画主旨とかみあってはいませんでした。
まあ、夏休みはもう終わっている学校もありますし、夏休みだとしても宿題におわれているかもしれません。正直、「病院に出かけてわざわざ聞く」ほどのことでもありませんし。
聞くなら学校で。そしてひとつのがんの話だけ聞くというのもヘンですしね・・・
◆土屋医師挨拶
7年前にワクチンでHPV感染を予防できるということになったが、昨年くらいまでは一般の方に認知されていなかった。
今年に入って女優の仁科さんが精力的に動いた。しかし、国立がんセンターでも医療者でも誤解をしている人が多かった。そして、一般の人に知ってもらう努力が少なかった。
中学生や小学生の親にだけ話をして、こどもに話をしてなかった、ということにきづき、
大妻嵐山高校の校長の協力で、高校1-2年の生徒さんに話をさせてもらった。
「絶対接種を受けましょう」という講義ではない。正確な情報を当事者に提供することが使命。自分で判断できるように。
(※は編集部注)
※医療者でも誤解している、というのは事実としてあります。
※日本の初交開始年齢を考えると高校1年になる前がよいのかもしれません。
◆三原じゅん子議員
こどもを産めないハンディを追っていきていくのはつらいこと。
がんの中で唯一予防できるワクチン。ほとんどの先進国では接種が国のプログラムに組み込まれ公費補助になっている。全額補助するように取り組んでいる。
※産む産まない産めないというのはセンシティブなので、皆が産むのがフツウというようにとられる発言は注意が必要
※がんを予防できるのは唯一というのはミスリーディング。B型肝炎についてもふれないと。
◆婦人科医 講義
増えているのは子宮体がん・卵巣癌。子宮けいがんは全体には横ばい。若い人が増えている。
年15000人が発症、3500人が死亡(製薬会社のスライド)
※増えているのは病気そのものが増えているのか、健診の影響か。どのステージで増えているのかが重要
性交後に8割がHPVに感染し、90%が自然に消失。
持続感染する要因として、ピル・タバコ・ストレスがいわれている。
婦人科の開業医がピルで利益を得ているのでピルについては今あまりいわないことにしているらしい。
持続感染→10% 高度異形成→子宮頸がん0期 50.3%
診断時がんⅠ期 27% Ⅱ期27% Ⅲ期 6.7% Ⅳ期4.4%
卵巣癌は症状が出にくく、進行してからみつかるのが特徴。Ⅲ期が50%。
子宮頸がんは初期に見つかることが多い。症状が出やすい(性交時の不正出血など)
5年生存率は0期なら100%、Ⅰ期77.9%。
ワクチンの種類。HPVは任意ワクチンだが、ワクチンなんてみんなうっちゃえばいい。
あまり余り深く考える必要は無い。風疹や日本脳炎のワクチンとか説明したり考えたりしない。
せっかくだから性教育このことを、、という考え方もあるが、「頸がんを予防するワクチンだから」とうっちゃえばいい。
※このあたりは保護者や教員から拒否されるとおもいますよ。ひとつは責任問題。もうひとつは当事者へのインフォームドコンセントとしてそれで足りるのか?です。絶対に足りません。
日本の子宮頸がん健診の受診率が低いのは婦人科にいくのがはずかしいから。
HPVをしらべてワクチンをうつほうがいいにきまっている。
健診を皆受けましょうというよりもワクチンを皆にうってしまったほうがいい。
※婦人科医自ら婦人科受診を否定的に語るのはやめたほうがよいとおもいます。
健診に行かない人対象の調査はいろいろありますので、どうすれば行きやすくなるかを考えたほうがよいですね。
--------------------------------以上です。
いくつかの(いえ、たくさんの)疑問。
◆性交開始後の女性に必要な婦人科健診は子宮頸がんのチェックだけではないので、健診にいくよりワクチンをうっちゃったほうがいい、というのは問題じゃないのか?
(この点は日々がんの患者をみている専門医と、ジェネラルに日々女性をケアしている婦人科の開業医の見解に大きな溝があると感じます)
◆HPVワクチンは接種しないという人もいるので、ワクチンと健診というだけでは不十分ではないか。性交開始年齢やパートナー数、コンドーム使用による防御効果についてもいうべきではないのか?
(ふだん、中高生に話をしていない、予防教育や健康教育に慣れていない人にはこのあたりを具体的に説明できないのかもしれない)
癌研の名誉のためにいいますと、この講座には製薬会社はかんでいませんでした。受付も進行も病院のスタッフでした。
製薬会社がつくった子ども向け漫画パンフレットを初めてみましたが、、、ちょっとこれは学校や地域では配れないよ、という内容。
そして講義スライドの半分以上が製薬会社がつくったものなんですよね・・・。
(あたりまえですが、対象にあわせて自分でつくるほうがよいですし、製薬会社のバイアスをかけないように話をするのが専門家には必要な努力)
後半は中高生対象でしたが、保護者と一緒に参加したのは3名のみ。
前半とほぼ変わらないスライドで、話し方を子ども向け言葉にした、というかんじでした。
(思春期層には、子ども扱いせず、ていねい語で話すのが基本ですよ。大人として向き合わなければいけない話を扱うのですから。)
疫学データや癌の詳細などは、思春期の子どもにハタシテ必要なんだろうか?と思う訳です。
また、子宮頸がんのことだけを話すというのも現実的ではなく、土屋先生は、今後産婦人科医の専門団体の全面協力を得て全国でも中高生が専門家から話がきけるようにできるのではないか?という善意の提案をしていましたが、それはウマイ案ではないよな、と思って帰ってきました。
パーツ(臓器)ごとの法律を作ったり、講演会をしたりということは、学校現場のニーズや当事者・保護者のニーズにかみあっていません。
多忙な医師は無料で学校にでかけますかね?外来閉めてでかけたら数万円の謝金が妥当ということになりませんか?
この日、婦人科医が「風疹や日本脳炎なんて説明しないでしょう?(だからHPVも説明しないで接種しちゃえばいいというニュアンス)」・・・はかなり乱暴な話です。
思春期の人達には説明と同意の確認が必要ということは世界や国内のコンセンサスですよ。
小児科のひとたちはそれよりも小さな子どもでも自分が受ける検査や治療についてなるべく理解を得られるように工夫しています。
がんの専門家や婦人科医師が出向くより、保健師や養護教諭をサポートする方が先。
・・・世界で100か国が認可、公費化がすすんでいる、と度々「世界」を持ち出しますが、世界が大切にしている思春期層へのRespect、コンドームを含めた包括的な教育については一切触れないで、とにかく接種してしまおうという日本だけのやり方には何も疑問がないのが、今のところあちこちできく製薬会社と、ふだんこの世代の子ども達に接してもいないひとたちの話の筋。