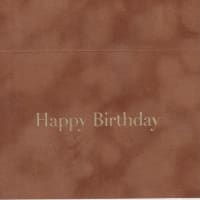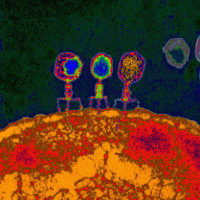HPVに関わっている専門家は誰か。
グラクソスミスクラインのHPVワクチン承認にあわせてか2009年10月16日、日本産婦人科学会、日本小児科学会、日本婦人腫瘍学会の3団体の連名で
「ヒトパピローマウィルス(HPV)ワクチン接種の普及に関するステートメント」
が出ています。
日本婦人科腫瘍学会は、2010年10月22日、厚生労働省医薬食品管理局審査管理課あてに
四価子宮頸がんワクチン早期承認の要望書を提出しています。
(この部署あてに出すのはいいですね)
日本性感染症学会も同じ頃、厚生労働大臣あてに四価HPV枠地早期承認要望書をだしているそうです。
いま、自治体は補正予算で対応をしなくてはならなくなったHibワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、HPVワクチンの予算をどうするのだの騒ぎになっています。
そして、ワクチン導入時に必要な対象者への十分な説明資料・教材・広報の準備、モニタリング(ワクチンに含まれている・含まれていないHPVに関する疫学調査)や、10年後・20年後の効果評価のためのコホートデータ作成の準備、などはまったく手付かずだときいています。
当事者が混乱や理解不足の中におかれることをたいへん心配しています。
また、検診をこのあとどうするのだ?という話もあまりきこえてきません。
HPVワクチンが導入される前から、各国の公衆衛生や医療政策の専門家らは、「HPVワクチンを接種した層としていない層での子宮頸がん検診のアルゴリズムを変えることになる」といっていました。
これは費用対効果その他の判断を含む、きわめて複雑で、Evidence追求型、かつ政治的判断を要するIssueです。
日本産婦人科学会は検診についてのガイドラインも出しています。
http://www.jsog.or.jp/PDF/58/5809-238.pdf
平成16年に2年に一度に変更された子宮がん検診に対して団体は「日本産婦人科医会の子宮がん検診に関する望ましい指針」を厚労相に提出。「子宮頸がんについては, 当面の間は1 年間隔の検診が望ましい.特に若年者においては1 年間隔の検診が必要である」としています。「低受診率にもかかわらず一律2 年間隔とするのは,受診率の低下を招くのみでなく,子宮がん死亡率の上昇が危惧される」からとのことです。
こちらの専門団体が今後どのような推奨をするのかが重要でしょうか。
これとは別に「科学的根拠に基づくがん検診推進のページ」についてのホームページに「子宮頸がん検診ガイドライン」が掲載されています。
ここと産婦人科系の情報との接点はよくわからないのですが、わかっていることは、ワクチンを導入するということは、前後の疫学的なデータの把握システムや健診プログラムの妥当性の検討までそのマネジメントの責任として生じるということです。
縦割りだから知らないよ、ではだめですね。
グラクソスミスクラインのHPVワクチン承認にあわせてか2009年10月16日、日本産婦人科学会、日本小児科学会、日本婦人腫瘍学会の3団体の連名で
「ヒトパピローマウィルス(HPV)ワクチン接種の普及に関するステートメント」
が出ています。
日本婦人科腫瘍学会は、2010年10月22日、厚生労働省医薬食品管理局審査管理課あてに
四価子宮頸がんワクチン早期承認の要望書を提出しています。
(この部署あてに出すのはいいですね)
日本性感染症学会も同じ頃、厚生労働大臣あてに四価HPV枠地早期承認要望書をだしているそうです。
いま、自治体は補正予算で対応をしなくてはならなくなったHibワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、HPVワクチンの予算をどうするのだの騒ぎになっています。
そして、ワクチン導入時に必要な対象者への十分な説明資料・教材・広報の準備、モニタリング(ワクチンに含まれている・含まれていないHPVに関する疫学調査)や、10年後・20年後の効果評価のためのコホートデータ作成の準備、などはまったく手付かずだときいています。
当事者が混乱や理解不足の中におかれることをたいへん心配しています。
また、検診をこのあとどうするのだ?という話もあまりきこえてきません。
HPVワクチンが導入される前から、各国の公衆衛生や医療政策の専門家らは、「HPVワクチンを接種した層としていない層での子宮頸がん検診のアルゴリズムを変えることになる」といっていました。
これは費用対効果その他の判断を含む、きわめて複雑で、Evidence追求型、かつ政治的判断を要するIssueです。
日本産婦人科学会は検診についてのガイドラインも出しています。
http://www.jsog.or.jp/PDF/58/5809-238.pdf
平成16年に2年に一度に変更された子宮がん検診に対して団体は「日本産婦人科医会の子宮がん検診に関する望ましい指針」を厚労相に提出。「子宮頸がんについては, 当面の間は1 年間隔の検診が望ましい.特に若年者においては1 年間隔の検診が必要である」としています。「低受診率にもかかわらず一律2 年間隔とするのは,受診率の低下を招くのみでなく,子宮がん死亡率の上昇が危惧される」からとのことです。
こちらの専門団体が今後どのような推奨をするのかが重要でしょうか。
これとは別に「科学的根拠に基づくがん検診推進のページ」についてのホームページに「子宮頸がん検診ガイドライン」が掲載されています。
ここと産婦人科系の情報との接点はよくわからないのですが、わかっていることは、ワクチンを導入するということは、前後の疫学的なデータの把握システムや健診プログラムの妥当性の検討までそのマネジメントの責任として生じるということです。
縦割りだから知らないよ、ではだめですね。