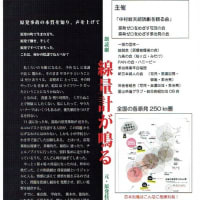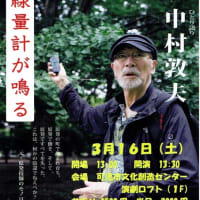週のはじめに考える ソ連崩壊30年後の閉塞
2021年12月26日 05時00分 (12月26日 05時00分更新)
史上初の社会主義革命で誕生したソ連が崩壊したのは、三十年前の一九九一年十二月二十五日。歴史的な出来事をよそに、一般市民は今日のパンをどう手に入れるかという現実に追われていました。お先真っ暗な年の瀬でした。
GDP半減した90年代
市場経済移行に向け翌九二年の年明けに価格自由化が始まると、猛烈なインフレが庶民生活を襲いました。食いつなぐために、自宅から持ち出した古着や生活用品を売る人が、モスクワの目抜き通りに列をなしました。
経済困窮、秩序崩壊、政治混迷が重なった九〇年代。国内総生産(GDP)はソ連時代のピークだった八九年と比べるとほぼ半減しました。これは第二次大戦で日本が被ったダメージに匹敵します。
国家分裂まで危ぶまれた時代でした。しかも出口が見えない。当時のチェルノムイルジン首相は「今度はもっとうまくやろうとしたが、結果はいつもと同じだった」と嘆いたものです。
転機は二〇〇〇年のプーチン政権誕生とともに訪れました。原油高の追い風に乗ってロシアは高度成長時代を迎えます。プーチン氏の最大の功績は社会に安定をもたらしたこと。国力回復に伴い大国の地位も取り戻しました。
半面、共産党独裁体制の崩壊によって生まれた社会の解放感は、メディア締め付けに代表される強権支配によって消えうせました。
シリア内戦への軍事介入やウクライナ国境地帯への大軍動員というようなドスの利いた対外行動も活発で、国外でもこわもてぶりを見せています。
プーチン氏も当初はまったく違う顔を見せていました。九九年の大みそかにエリツィン大統領が突然辞任し、首相だったプーチン氏は大統領代行に就きます。プーチン氏はその日に「千年紀(ミレニアム)の狭間(はざま)のロシア」と題する論文をロシア紙に発表します。
論文でプーチン氏はソ連の共産党政権は「国を繁栄させず、社会をダイナミックに発展させることもなく、人間を自由にしなかった」と批判しました。
今の混乱から抜け出すためには「強い国家権力が必要だが、これは全体主義への呼び掛けではない」と強調。「どんな独裁や権威主義的体制も一過性であることは歴史が証明している。持続性があるのは民主主義だけだ」と主張しました。
そんなプーチン氏は再選を果たした〇四年を機に、内外政ともに強硬路線へ傾斜を強めます。
この年、バルト三国が北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、ロシアはかつての敵の「西側」と国境を接することになりました。ロシアにとっては安全保障上の脅威です。ウクライナでは「オレンジ革命」が起き、親欧米政権が誕生します。ロシアはこの政変劇の裏に米国の影を見ます。
国内ではチェチェン武装グループが子どもたちを人質にとり、三百三十人以上が犠牲となったベスラン学校占拠事件が起きました。
ロシアは西側の一員に仲間入りできる、とソ連崩壊時には欧米もロシア自身も期待しました。それが失望に変わり、プーチン氏の「反動」につながっていきます。
経済低迷、開けぬ展望
ロシアは「安定」と引き換えに、手に入れた「自由」を失い、そして「安定」はいつの間にか「停滞」に変質しました。
ここ十年ほど経済成長率は年平均1%ほどに低迷し、国民所得はほとんど増えていません。石油・天然ガスに依存する偏った経済構造は一向に改善されず、しかもエネルギーなどの基幹産業は多くが国有で、経済に占める国営部門の割合は巨大です。これではイノベーションは起きにくい。
大国復活と言ってもロシアのGDPは日本の三分の一、米国の十四分の一にすぎません。今の大国主義的な対外路線は相当無理をしていると言えるでしょう。
それよりも内政を充実させないと国の展望が開けない。一四年のクリミア併合に対し、欧米はロシアに経済制裁を発動しました。これが経済発展の足かせになっています。制裁解除には欧米との関係改善が必須です。
社会には閉塞(へいそく)感が強まり、国民の不満が募っています。
今年はシベリアで五十人以上が死亡した炭鉱事故や、航空機、ヘリコプターの墜落事故が相次ぎました。名越健郎・拓殖大海外事情研究所教授は既視感を覚えるそうです。ソ連崩壊前も同じような出来事が頻発したというのです。
一見、盤石なプーチン体制。二四年の次期大統領選でもプーチン氏出馬の観測が支配的です。
それでもロシアは時代の変わり目を迎えていて、社会の深層では静かな地殻変動が起きているのかもしれません。