原題:[・・・and the mountains rising nowhere for amplified Piano,Winds,Brass and Percussion]
作曲:ジョセフ・シュワントナー
出版:Helicon Music
この曲は、ピューリッツァー賞など数々の作品賞を受賞しているアメリカの作曲家、ジョセフ・シュワントナーが、1977年にイーストマンウインドアンサンブル・及び常任指揮者ドナルド・ハンスバーガーの為に作曲され、全米芸術基金の作曲賞を得た作品。
タイトルはキャロル・アドラーという女流詩人が1975年に書いた、「アリオーソ」という現代的な詩の中の一句を取った物である。
これは私が中学校1年生の時(1991年/第39回)全日本吹奏楽コンクール全国大会で、埼玉栄高校が演奏したもので、その10年前来日した、アメリカ・カリフォルニア州大学ロングビーチ校の演奏に感動した指揮者が、10年間暖め続けてようやく演奏したまさに「熱演」だっただけに、評価は審査員のほぼ全員がA評価(B評価はわずかに2つ)を叩き出し、トップ金賞を受賞した曲。吹奏楽コンクールではもちろん初演である。
記譜法が自由で、驚くのは小節の長さが「秒」で書いてあること(ここは○秒間、といった具合)。また、水の入ったワイングラス(グラスハープ。7つのグラスに水が入っており、H、D、E、F#、G、A、C#に調律されている。オーボエ奏者4人が使用)の上の淵を指でなでて出る音を使用する、口笛を吹く、ヴィブラフォーンの鍵盤の横やゴングのふちをストリングベースの弓で擦って音を出す、などといった、今までにない斬新な手法を取り入れることによって、独特のムードを生み出している。
曲は、打楽器の強烈なリズムから始まった後、静かな場面が続き、全楽器の複雑なベルトーンが繰り返され、一時の盛り上がりを見せる。
その後、アルトサキソフォンのソロ、オーボエとの絡みを経て、ホルンのメロディーで盛り上がっていく。その後、フルート6人のうち4人がピッコロに持ち替え、さながら自然破壊で逃げ惑う小鳥たちを表現したような、けたたましく啼くような場面が現れる。それに伴い、壮絶な打楽器の打ち込みが展開。さらにトロンボーンなどの勇ましいメロディが綴られ、数回のベルトーンのあと、クライマックスを打楽器のリズムで迎えた後静かになり、最後に、淡く涼やかなハミングの中、ピアノの切ないメロディで曲は静かに閉じる。
ちなみに、使われている打楽器は以下の通り。
シロフォン×2、ヴィブラフォーン×2、グロッケンシュピーゲル×2、マリンバ、チューブラベル、半音階のクロタルズのセット(アンティークシンバルのような小型の金属ディスク)、鈴、ウォーターゴング(小型のゴングをたたき、それを水槽にひたしたり、引き上げたりして音を変化する銅鑼)、シンバル数種、トムトム、バスドラム×3、ゴング、トライアングル。
これを演奏するには、打楽器パートの品揃えをはじめ、ワイングラスの購入からチューニング、通常の吹奏楽編成では考えられないほどの管楽器の数、演奏開始直前の準備などにそうとう苦労するらしく、大変だったとの後日談がある。
吹奏楽曲の現代曲だけに、敬遠する人は多いかもしれないが、この曲が持つタイトルと神秘的な雰囲気は今もなお色褪せる事無く静かな輝きを放っている。
あのような雰囲気を持つ曲は「似たような曲」こそあれど、一つの作品としてみたときに、これは「死別」の際にぜひ演奏して欲しい。そして、多くの人に聴いていただきたい。
参考までに音源をいくつか。
CD番号:CACG-0029
「・・・そしてどこにも山の姿はない」
演奏:神奈川大学吹奏楽部
指揮:小澤俊朗
CD番号:SRCR 8840
「イーストマン・ウィンド・アンサンブル ライブ・イン・大阪」
演奏:イーストマン・ウィンド・アンサンブル
指揮:ドナルド・ハンスバーガー
CD番号:SRCR8703
「第39回全日本吹奏楽コンクール実況録音版 優秀団体編」
演奏:埼玉県埼玉栄高等学校吹奏楽部
指揮:大滝実
(これが、上記の実際の演奏)
作曲:ジョセフ・シュワントナー
出版:Helicon Music
この曲は、ピューリッツァー賞など数々の作品賞を受賞しているアメリカの作曲家、ジョセフ・シュワントナーが、1977年にイーストマンウインドアンサンブル・及び常任指揮者ドナルド・ハンスバーガーの為に作曲され、全米芸術基金の作曲賞を得た作品。
タイトルはキャロル・アドラーという女流詩人が1975年に書いた、「アリオーソ」という現代的な詩の中の一句を取った物である。
これは私が中学校1年生の時(1991年/第39回)全日本吹奏楽コンクール全国大会で、埼玉栄高校が演奏したもので、その10年前来日した、アメリカ・カリフォルニア州大学ロングビーチ校の演奏に感動した指揮者が、10年間暖め続けてようやく演奏したまさに「熱演」だっただけに、評価は審査員のほぼ全員がA評価(B評価はわずかに2つ)を叩き出し、トップ金賞を受賞した曲。吹奏楽コンクールではもちろん初演である。
記譜法が自由で、驚くのは小節の長さが「秒」で書いてあること(ここは○秒間、といった具合)。また、水の入ったワイングラス(グラスハープ。7つのグラスに水が入っており、H、D、E、F#、G、A、C#に調律されている。オーボエ奏者4人が使用)の上の淵を指でなでて出る音を使用する、口笛を吹く、ヴィブラフォーンの鍵盤の横やゴングのふちをストリングベースの弓で擦って音を出す、などといった、今までにない斬新な手法を取り入れることによって、独特のムードを生み出している。
曲は、打楽器の強烈なリズムから始まった後、静かな場面が続き、全楽器の複雑なベルトーンが繰り返され、一時の盛り上がりを見せる。
その後、アルトサキソフォンのソロ、オーボエとの絡みを経て、ホルンのメロディーで盛り上がっていく。その後、フルート6人のうち4人がピッコロに持ち替え、さながら自然破壊で逃げ惑う小鳥たちを表現したような、けたたましく啼くような場面が現れる。それに伴い、壮絶な打楽器の打ち込みが展開。さらにトロンボーンなどの勇ましいメロディが綴られ、数回のベルトーンのあと、クライマックスを打楽器のリズムで迎えた後静かになり、最後に、淡く涼やかなハミングの中、ピアノの切ないメロディで曲は静かに閉じる。
ちなみに、使われている打楽器は以下の通り。
シロフォン×2、ヴィブラフォーン×2、グロッケンシュピーゲル×2、マリンバ、チューブラベル、半音階のクロタルズのセット(アンティークシンバルのような小型の金属ディスク)、鈴、ウォーターゴング(小型のゴングをたたき、それを水槽にひたしたり、引き上げたりして音を変化する銅鑼)、シンバル数種、トムトム、バスドラム×3、ゴング、トライアングル。
これを演奏するには、打楽器パートの品揃えをはじめ、ワイングラスの購入からチューニング、通常の吹奏楽編成では考えられないほどの管楽器の数、演奏開始直前の準備などにそうとう苦労するらしく、大変だったとの後日談がある。
吹奏楽曲の現代曲だけに、敬遠する人は多いかもしれないが、この曲が持つタイトルと神秘的な雰囲気は今もなお色褪せる事無く静かな輝きを放っている。
あのような雰囲気を持つ曲は「似たような曲」こそあれど、一つの作品としてみたときに、これは「死別」の際にぜひ演奏して欲しい。そして、多くの人に聴いていただきたい。
参考までに音源をいくつか。
CD番号:CACG-0029
「・・・そしてどこにも山の姿はない」
演奏:神奈川大学吹奏楽部
指揮:小澤俊朗
CD番号:SRCR 8840
「イーストマン・ウィンド・アンサンブル ライブ・イン・大阪」
演奏:イーストマン・ウィンド・アンサンブル
指揮:ドナルド・ハンスバーガー
CD番号:SRCR8703
「第39回全日本吹奏楽コンクール実況録音版 優秀団体編」
演奏:埼玉県埼玉栄高等学校吹奏楽部
指揮:大滝実
(これが、上記の実際の演奏)

















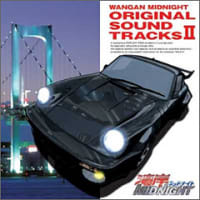

http://www.hmv.co.jp/product/detail/3647456
Naxosなので1,000円程度で買えます。国内アマチュア団体のCDは通常フルプライス(3,000円!)ですから、安価に聴けるようになった、ということは喜ぶべきことだと思います。
かく言う私も、上記CDで初めてこの曲を知りました。今日アマゾンから届いたばかりで、まだほとんど聴いていないくらいです(苦笑)。
コメントありがとうございます。
管理人は、久しくウィンドミュージックから離れておりましたので、大変懐かしく拝見いたしました。
リンクのCDは、まさにアメリカンなアルバムに仕上がっていますね。
ナチに追われてアメリカに移住したパウル・ヒンデミットをはじめ、グレンジャーやホルストの第一組曲も、かのフレデリック・フェネル氏がさかんに録音していた人気のナンバーです。
「山」は、本当に強烈な印象を残す曲です。
管弦楽クラシックファンからすれば、「吹奏楽の現代曲なんて曲じゃない」「音楽性に乏しい」という酷評をする人もいますが、私はそんなことはないと思います。
1977年に書かれたとは思えない究極の曲だと思います。
安かろう悪かろうの印象があったクラシックナンバーでしたが、最近はそうでもないみたいですね。
この演奏団体は初めて知りました。
そして、リンク先で、さまざまなニューリリースにも出会うことができました。感謝しております。
今後、どんなアルバムがリリースされるか、楽しみです。
手持ちのものですと,1978のハンスバーガー・イーストマンのアナログディスクと
North Texas Wind Symphony(これを当時聴きました)のCDがあります。North Texas Wind Symphony版は、「シュワントナーコレクション」の形で現在でも入手可能です。
コメントありがとうございます。
81年と言うと、私はまだ吹奏楽も何も知らない幼い頃でした。
シュワントナーの作品は、他にもたくさんあるのでしょうが、有名な録音があまり出回っていないのと、作品に触れる機会が少ないのとで、ほとんどわかりません。
最近の私は、もっぱら管弦楽クラシックの新録音を買って聴く事の方が多いですが、アナログ時代の録音も、管弦楽・吹奏楽問わずチェックしてみたいですね。
ありがとうございます。参考になりました。
この曲(埼玉栄版)を久しぶりに聴いていたら詳しいことを知りたくなり、
検索してこちらに辿り着きました。
当時、埼玉栄の吹奏楽部に友達がいたんですよー。
こちらで紹介されている「小節が秒表記」「ウォーターゴング」「グラスハープ」のことなど、
そういえば友達から聞いたなぁ・・・とじわじわ思い出してきました。
演奏するのはとても大変そうだったけど、かっこよくて!
うらやましかったです。
うーん、懐かしい!詳しい解説ありがとうございました。
お返事が遅れましてすみません。
こちらも、たった今、埼玉栄高校の演奏を聞きながらコメントを書いております。
ピアノの神秘的なサウンドがたまりませんね。
特にラスト!
埼玉栄の吹奏楽部にお友達がいらっしゃったとは驚きですね~!
全国大会でしのぎを削る超実力派バンドにお友達がいたことが無いので、うらやましいなと思いました。
歯ごたえのある吹奏楽オリジナル曲が最近なかなか出てこなくて淋しい限りだなぁと思っています(探していないだけということもありますが)。
埼玉栄で、・・・そして山の1stホルンを吹いていた者です。
この曲と最初に出会った時、楽譜などを見て???という感じでした。
イメージが全く分からず、楽譜の中身もまったく理解できませんでした。
この曲を徐々に追求していくうちに、自分達も、のめり込んでいった事を覚えています。
ホルンの主旋律のかっこいい場面もあり、本当にこの曲を吹くことが出来て、光栄でした。
打楽器の迫力が半端ないので、打楽器パートの準備も大変でした。
とても懐かしいです。
コメントありがとうございます。
この記事は、いったい何人の人を巻き込んでいくんでしょうか?と感じています。
埼玉栄吹奏楽部のお友達に続いて、今度は実際に演奏した方のコメントが寄せられるとは思いもしませんでした。
わたしが若かりし頃訪れた普門館は、未知の世界で、何から何まで新鮮に映りました。
当時私は、中学校一年生で、「コンクールの全国大会の地・普門館という大舞台で演奏するということがどういうことか、そして、その大会に於ける頂点に立つバンドは、どれだけの実力を持っているのかなど、思いもしなかったころでした。
あの「山」のホルンパートを演奏されたのですね!貴重な書き込みをありがとうございます。
全国大会の大舞台でのプレッシャー、用意の大変な打楽器・・・そしてあの改心の演奏!
素晴らしいと思います。
楽器は今でも演奏されていますか?
自分は、楽器こそ演奏していますが、コンクールの世界からは身を引いています。
しかしながら、あなた様方の名演を聞くたびに、夏のあの頃が懐かしく思い出されます。
歴史に刻まれる名演奏に、栄光あれ!