
すこし昔―
紙芝居屋さんなるものがあった時代―
“紙芝居のおじさん”が居た時代―
そう、自転車に乗り、紙芝居と駄菓子を積んで街頭を回り、拍子木を打って子どもたちを集め…
その時代よろしく、私が師として敬う「のまりん」こと野間先生も、拍子木を打って紙芝居を始めることにこだわっている。
打楽器で言うところのクラベスとは違う、日本の拍子木は、なんと形容してよいか…
同じ「キンキンッ」という木を打ち合わせる音でも
奥ゆかしくも心地よい―
今朝、私が
「図書館に行って紙芝居のネタ仕入れてくる」
と言ったのを機に
母が
「紙芝居屋さんを初めて見たときは『都会だなあ』って思った」
と言った
それを聞いていた私の父
日曜大工ならどんと来い
要領はあまりいいとは言えないけどマメなヒト
「拍子木、作ってやろうか?確か、物置に余りの木材があったから」
で―
完成したのがコレ。
めちゃくちゃイイ音します。
「斜め打ちはすンなヨ。真っ直ぐ打たないと、木に傷が付いてよくないからナ」
とのこと。
いいモノを作ってもらいました。
父さんありがとう―m(_ _)m
トーキーで追われた活弁師などがやっていたかつての紙芝居屋。
私は、お芝居が得意でもなんでもない、ただのしがない指導員ですが―
“拍子木を打って紙芝居を始める人間”には、ようやくなれました。

















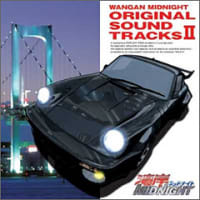

拍子木を打って始まるHibikiさんの紙芝居、みてみたいです(^-^)
コメント、ありがとうございます。
本当にありがたかったです。
紙芝居サークルの中でも「拍子木はいるよね」という話が出ていましたし、さらに一歩進んで「この材質の木を使うといい音出るよ」とかいう話まで出てくるくらいでした。
つい先日、子どもたちにお披露目をいたしました。
「(夜回りの)火の用心で使うヤツだよね?」
と言われましたが、
意外に「紙芝居屋」の存在を知っている子はいたんですよ。
そのことにまず驚きました。
拍子木を打つコトが切欠になるんですよね。
今までの絵本の読み聞かせでは、見られる範囲が狭かったことも反省点なんですが、静かにできないで騒ぎ出す子が大半だったんですよ。
でも、今の子どもたちは舞台を使った紙芝居をするようになってからだんだん視線を向けて静かに見て・聴いてくれるようになって、嬉しく思っています。
近いうちに、図書館の公演に私が参加する機会があったらその時は、ぜひ!
^^V(キラッ!)
コメントのお返事ありがとうございます。
じゃあいつか、図書館での紙芝居をするときは、ぜひ教えてください。
Hibikiさんも季節の変わり目、体調に気をつけてお過ごしくださいませ。