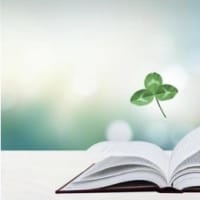顔の輪郭もわからないほどびっしりと黒髪を生やした猿たちが、穴ぐらで群れあって暮らしている。背も丸くあきらかに脚よりも腕の方が長くよく伸びるからだをした彼らだが、その瞳の動かし方はすでにヒトに近い表情をつけていた。このとき、すでに彼らに感情はめばえていたのだろうか?彼らにはまだ言葉はなかった。彼らの伝達は、キィキィと歯をむきだしにして鳴きわめき、砂ぼこりがたつほど足の裏で大地を叩くことであった。リズムが彼らの情動を刻んで伝えていた。だとしたら、ラスコーの洞窟画よりも、猿の音楽の方が数倍すばらしい。この原始的な芸術表現は、いまだにエスキモーなど未開民族の喉笛などに残されている。ほんらい音に民族の優劣などは存在しなかった。だが宗教と経済がじゃまだてして、この音楽は、グレゴリオ聖歌やビートルズとは同等に愛されてはいまい。
数匹の黒猿が棲む荒野に、とつぜんモノリスが突き刺さった。明け染めの太陽の光りを吸いよせた石柱に触れた猿たちは、いちどきに進化した。ある一匹は荒野に転がった野牛の上腕骨を拾いあげ、おもしろいように大地を叩き、牛のあばら骨を砕き、頭蓋骨を割りはじめた。ひとふり腕をふりあげるごとに、からんと軽い音をたてて死の身元証明のかけらが壊れていく。かろうじて、死んだことを示すためだけの存在の漂泊物に、消失のとどめをさす無残な行為。だが、創造は破壊で、存在はなにかを消すことだった。生まれるために、卵の裏側から破り、母親の腹を割り、あたたかい海で憩っていた記憶を棄てて、世界中のいのちから血をすすって生きのびていく。それが文化の掟。
猿がほうり投げた牛の骨は、悠久のときをつないで、黒い宇宙に浮かぶ棒状の宇宙船に変化した──。
リヒャルト・シュトラウスの「ツァラストゥラはかく語りき」の高らかなファンファーレで幕開ける、映画「2001年宇宙の旅」のよく知られた冒頭シーンだ。私の大学の指導教官はこの映画がお気に召したとみえ、いつもいつもこの話を飽くことなくしていた。この導入部は、おぞましい結末──宇宙船を支配するスーパーコンピュターHALがやがて叛乱をおこし、船員を殺す──から考えれば、人類の知能の進化という科学的な黎明をほがらかに謳うものでないことは明らかだ。すなわち、我々の始祖がはじめてつかった道具は、人を殺す道具だったのだと。冒頭には描かれていないが、じっさい黒猿たちがヴァッファローの旨い肉を求めてでなく、つまり口に喰いたいのでなく気に食わないという理由だけで、おなじ顔をした生き物たちの頭を砕いてきたことは、想像に難くはない。そう、たとえば。陽のあたって座り心地のいい場所を譲ってくれない、そんな理由だけで。私たちはともすると、ためらいもなく他人を殴ることができる。
人間はほんらい理性の生き物で、社会的生活を営んでいるぶんには、自身の行動に歯止めがかかる。ところがこの理性のタカが外れてしまうのが、インターネットの世界だ。ここではたとえどんなご立派な学識人ですら、ただの私怨で誹謗中傷をおこなう悪舌の徒に堕してしまう。そして、それは無名多数の大衆もかわりはない。
福田首相をチンパンジーだのなんだのに例え、愚弄する声はよく聞かれる。おそらく国民の怒りを買ったのは、中国を支持する表明を出してからだろう。支持率も急降下で、党内でも孤立化していると伝えられ、日銀総裁でだめ押しをくらわされた民主党の小沢党首に涙目になって訴えるというエピソードは哀れかと思えるほどだ。だが、このひとはそれほど叩かれるべきなのだろうか?
福田首相のかわりに、小泉元首相を推す世論が高まっているが、ライオン宰相はかたくなに拒んでいる。そうだろう、いまさらになって問題が表面化した後期高齢者医療制度だって、下地をつくったのは橋本龍太郎政権下での厚相時代の小泉氏。いま返り咲けば批判の矢面にたたされること必死だ。彼には一匹狼的なすがすがしさはあるが、台詞が短くて、本心が皆目分からない。(無駄な放言をしない点では賢明かもしれないが)また訪米した際にブッシュの足下にひざまづくパフォーマンスをやってのけ、米国の走狗となりさがった媚びる日本という屈辱的な印象をあたえた。
福田首相の弱腰外交というか、父親譲りの親中感情からくる発言は、毒餃子問題やチベットでの虐殺に怒りを禁じえない国民としては不満に思える。が、一国のトップなのだから、うかつに中国を刺激するような言動はできないかもしれない。なにせ、中国に進出している日本企業などが標的にされる恐れもある。(ちなみに筆者の親戚の某家電メーカー社員も中国在住なので心配ではある)中国の軍事力を正確に把握していないが、自衛能力をもたない日本は戦争を恐れているのであり、また中国の巨大な市場に期待しているのもあるのだろう。
以前の記事でとりあげた痛いニュースが、よくgooの編集画面で話題のサイトとしてとりあげられていて見るのだけれど。たまに、見るに耐えず読むに煩わしい中傷だと思うことがある。ここに取りあげた案件は、十中八九コメンテイターが槍玉にあげるために、俎上に乗せられてきたものだ。話題にして議論が活発になるのはいいけれど、いくら正論の反論であっても、野球場の狂ったサポーターのような無意味な野次罵倒の連呼には、いささか口が塞がってしまう。とうしょは面白かったのだが、最近はすこし距離をおいて冷静に眺めるようになった。この反応をそのまま鵜呑みにして記事にすることの恐さがある。多数派が正義だろうか?自分の意見というよりは、すでに茶漉しにかけられて色よく渋みのでた番茶をさしだすことで、安心感を得ているふしが見受けられる。誰もがその苦みを飲んでいる、だからだいじょうぶ。そんな程度の安心感。多いことへの依存。もちろん私論にこだわるからといって、わざと世論に逆流したことをもの申すのもどうかとは思うが。
そこで話題になったものをひとつとりあげよう。
北京オリンピックの聖火リレーへの欧米各国での攻撃が人権意識のすすんだ国だともてはやされていて、長野でもこれにつづけとネットの論者たちははやし立てていた。中国の非人道な行為は目に余る。だからといって、血気に逸って走者に選ばれた星野監督などを襲ってもいいのだろうか?あなたは襲えるだろうか?いくら人道主義を装っても人を傷つけた時点で犯罪者だ。
中国は情報規制を敷いているから、いくら世界各国のネット人口が喚き立てても、どこ吹く風かもしれない。オリンピックをボイコットしない日本人選手は、政治意識が低いのだろうか?その四年間の成果をしめす舞台のための努力も、あるいはそれに絡むスポンサーの思惑も、水泡に帰してしまう。スポーツも芸術表現の一種であるから、こうした社会事象と無縁ではいられない。が、スポーツ競技がかならずしも政治の関与をうけねばならないとは、とうてい思えない。
自分の意見をネットに公開し、反響があるのは喜ばしいことだ。だが、その数字で量ることは好ましいのだろうか。数でみえる反応に甘えて、ブログに賛成意見ばかり集っていると、すっかり自分の意見が公論ではないかと勘違いすることがある。そして押すことが推すことだとも勘違い。あなたの意見は相手の指先を動かしたのか、それとも思考を揺さぶりこころを向かわせたのか。株価のレートとおなじで読者受けのいいものを書いたとしても、すぐに飽きられてしまう。
恥ずかしい話、ブログをやっていると自分がさも一流の論客になったように錯覚してしまうことがある。私たちはウェブ界で下克上をのぞむ。ネットでは誰もが先生になり、アーティストになり、評論家になり、タレントになる。しかし、過去に読んだすぐれた書き物(れっきとした出版物)に目をとおすほど、嫌悪感はつのるいっぽうだ。有名人をこきおろし、犯罪者を不当に貶める(ないしは異常に同情をよせる)ことで、裁定者ぶることもできる。が、人間の感情はネットに依存すればするほど、原始的に退化しているのではないか。
ネットは穴ぐらのなかの生活だ。現実では言えぬ大きなことも言える。感情を爆発させることもできる。現実に満足できないからといって,目立つ人物を狙って袋叩きにし、カタルシスを得る。表では仲良しのふりをしても、裏側では姑息な嫌がらせをしていたなんてよくある話だ。
幼いころ読んでいた小学生向け雑誌には、君たちがおとなになるころには宇宙ステーションが整って、暮らしているという想像図が載っていた。アーサー・C・クラークが筆を執り、キューブリック監督が描いたスペースドラマは現代の科学でもってもまだ遠い未来であり、人類は幅のとらぬ電子の宇宙に精神を移入させはじめた。しかし、その社会に道徳的な住民がつどっているかは疑問視されているのである。そこにあるのは、ローマやギリシアの狭く選ばれた人民による限定的な民主主義ではないのか。社会につらつら不満を申し立てる人びとは暇を持て余した人間で、ほんとうに経済負担が重くのしかかる働きざかり世代の意見、あるいはネットでも発言できない弱者や障害者の意見はすいあげられない。新聞の投書が、専業主婦や年金生活者や学生で占められているのとおなじ。皆がみな、自分の関心領域、自分の不都合でしか発言していないからだ。だから、ネットに本音や国民の総意があるなどと過剰に信奉してはいけない。
現実では沈黙する猿が、凶暴な歯を剥き出しにしてかみつく世界。ネットの世界は自由人にとっての逃げ場であったはずが、いま規制が敷かれはじめようとしている。へたすると戦前戦中の言論統制に近い状態になるかもしれない。
以上の主張は、自身の言動も省みてのもの。反省するポーズはするが、次に生かさないのはやはり猿から進化していない証拠であったり。書くのって気持ちわるいですね。ブログはこれの永久連続。
(〇八年四月下旬 覚え書き)
【画像】
高村光雲『老猿』(一八九三年)
国立東京博物館常設展示室で一度実見しましたが、その大きさに驚きました。てっきり両腕にかかえられる置き物程度のサイズだと勘違いしていましたので。画像は採光角度のせいか、愛くるしい顔つきにみえますが、私の覚えでは威厳があってしかめつらしい風貌でありました。
ちなみにこの作品は、鷲の羽をつかんで取り逃がした悔しさを滲ませるという猿の睨み顔が、当時悪化していた日露関係(ロシア皇室の紋章が鷲)をほのめかしたものとされています。