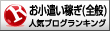<空想、夢想、幻想の歴史ロマン>
『主な登場人物』
<山口家関係>
山口貞清(山口城主) 牧の方(貞清の妻・豊島範泰の娘) 山口武貞(貞清の父) 薫(貞清の母) 和田信春(家臣) 稲村幸正(家臣) 幸若丸と桔梗(貞清の子供)
<尾高家関係>
尾高武弘(主人公・山口貞清の家臣) 小巻(武弘の妻・筒井泰宗の娘) 尾高武則(武弘の父) 栞(武弘の母) 佐吉(武弘の家来) 太郎丸と鈴(武弘の子供)
<藤沢家関係>
藤沢忠則(藤沢城主) 小百合の方(忠則の妻・山口貞清の妹) 藤沢忠道(忠則の父) 藤沢忠宗(忠則の義弟) 志乃の方(忠則の母) 幸と国松(忠則の子供) 詩織(小百合の付き人)
<その他>
上杉氏憲(前の関東管領・法名は禅秀) 足利持氏(鎌倉公方) 豊島範泰(石神井城主・牧の方の父) 筒井泰宗(範泰の家臣・小巻の父) 庄太(山口領の農民)
(注・・・赤字は実在の人物)
(1)
初夏のまぶしい日差しがふりそそぐ田畑や森を見ながら、武弘はうっすらとにじんだ額の汗を手でぬぐった。そして土塁の上で一休みしようと思っていたら、先に行く小百合が声をかけてきた。
「武弘殿、もっと向こうへ行きましょう。どうしたのですか。もう嫌になったのですか?」
「姫、ここで少し休みましょう」
「えっ、疲れたわけではないでしょ?」
「疲れてなんかいませんよ。ただ、ここから山口領をゆっくりと見たくなったのです」
「ふふふふふ、まるで領主のような気分ね。兄上みたい」
「いや、貞清さまとは違いますよ。困ったお人だな、では姫についていくか・・・」
木陰で休むのを諦め、武弘は小百合の後を追うように土塁の上を歩いていった。この男、尾高武弘と言う。先に行く姫とは、この“城”の当主である山口貞清の妹・小百合(さゆり)だ。城と言っても館を土塁などで防備した程度のもので、貞清は関東地方の小さな一豪族でしかない。
今からおよそ600年前、関東の武蔵国(むさしのくに)に山口(やまぐち)という地域があった。その場所は現在の埼玉県・所沢市の一角だが、山口氏が領主となってそういう地名になったのだろうか。くわしいことは分からないが、尾高家は代々山口氏に仕えていた。
先に行く小百合は20歳、武弘はそれより3歳年上の若者だが、子供のころから遊び友だちだった。友だちと言っても、あくまでも主家に仕える“家臣”である。ただ貞清の4人兄妹の中では、末娘の小百合が武弘に最も親しかったようだ。
2人が進む土塁はまだ未完成である。その端に来た時、小百合が草むらに腰を下ろした。武弘もつられるように横に座ると、彼女が話しかけてきた。
「武弘殿、何か面白いことはないのかしら。退屈だわ・・・あ、そうそう、あの空の向こうには何があるかしら」
「えっ、空の向こうにですか・・・姫はいったい何を考えているのです? おかしな人だなあ~」
「だって、そういうことを思わないの? 空にはお日さまやお月さま、お星さまがいっぱいあるけど、その先には何があるのかしら」
「そんなことを聞かれても分かりませんよ・・・あ、そうだ、お寺の住職の話だと無数の仏さま、つまり無数の霊魂があるはずですよ」
「えっ、霊魂ですって? そうか、ご先祖さまの御霊(みたま)だとか」
「ええ、ご先祖さまはもとより、今までにいた人々すべての御霊があると聞いています」
「そうか、すべての人の御霊があるのですね。私も死ねばその御霊の中に入れる、あなたももちろんその中に入れる。現世で一緒になれなくても、私は武弘殿と永遠に一緒になれる。そういうことですね?」
「姫、何を言いたいのですか、おかしなことを言わないでください。姫はいずれ誰か立派な領主と一緒になるのです。それは貞清さまもお望みのはずです」
「武弘殿、私がもしあなたと現世で一緒になりたいと思っていたら・・・どうなるの?」
「ご冗談を! 変なことを言わないでください。だいたい姫の家と私のとでは家格(かかく)が違いすぎます。そんなことは分かっているでしょう!」
「ほほほほほ、そんなにムキにならなくても。冗談ですよ。でも、そういうことを思ったことも・・・やめましょう。 この草むらは気持がいいですね」
突然そう言うと、小百合は土塁の上から身を伸ばし草むらに滑り落ちていった。
「姫、危ないですよ! 無茶なことを」
びっくりした武弘はあわてて彼女の後を追う。数メートル回転して落ちると、小百合は彼を見上げてにっこり微笑んだ。
「ああ、気持ちいい。あなたも転がってみれば、ほほほほほ」
「まったく“おてんば”なんだから、姫は。貞清さまに言いますよ!」
「ふふふふふ、いいですよ。兄は私のじゃじゃ馬ぶりを諦めているでしょう。でも、それももう少しのことですね。私が嫁げば済むことです」
「えっ、姫はもうすぐ嫁がれる・・・」
「冗談です、ただ言ってみただけ。そんなに気にしないでください」
小百合は最後に真顔(まがお)で述べた。しかし、武弘はこのあと『私が嫁げば済むこと』という言葉が脳裏から離れなかった。2人はなおしばらく土塁の辺りで時を過ごしたが、やがて館へと戻った。
(以下は参考写真)


現在の山口城跡(埼玉県・所沢市)


(参考映像・・・https://www.youtube.com/watch?v=WdCmF8l9yDs)
それから1カ月ほどして、山口貞清は妹の小百合を自室に呼んだ。貞清は父の武貞がつい1年ほど前に隠居したので、家督を継いでいたのである。
「小百合、お前にはいろいろ婚姻の話があるが、これまでにない話が舞い込んできた。驚くなよ。 相模国(さがみのくに)の藤沢氏より、ぜひお前に輿入れ(こしいれ)して欲しいとの申し入れがあった。こんなにめでたい話はないと思うが」
「えっ、藤沢家からですか・・・」
小百合もびっくりして二の句が継げなかった。
藤沢氏と言えば、相模国(今の神奈川県)の有数の豪族であり、しかも最近とみに力を付けてきたと評判になっている。山口氏と比べれば格の差は歴然だと言っていいだろう。これほどの家から求婚されるというのは“名誉”なことだ。貞清が有頂天になるのも無理はない。
「どうだ、いい話だろう。お前ももう二十(はたち)だ、ぐずぐずしていると行きそびれるぞ。それに、わが家にとってもこんなにいい話はない。もう腹を決める時だな」
貞清が一方的に話すので小百合は黙っていたが、少し気になることがあったので聞いた。
「兄上、それにしても相模国は遠いですね。父上や母上は何と言っているのでしょうか。私は親や兄姉ともうほとんど会えないのではと心配です。何か事が起きた時など大丈夫でしょうか」
小百合がようやく口を開くと、貞清が改まった感じで答えた。
「父上、母上には異存がないということだ。いや、父上などはむしろ喜んでいる。山口家がようやく世間に認められたと言っていたな。お前もあとで父上、母上にご報告したらいい。ああ、とにかくこんなにいい話はない。お前が素晴らしい娘だということが、広く知れ渡っているということだ。はっはっはっはっは」
貞清は機嫌よく笑ったが、小百合はだんだん気が重くなってきた。兄の話では、藤沢家の当主である忠道の嫡男・忠則(ただのり)との縁談で、彼は小百合より4歳年上だという。小百合には7歳と2歳年上の姉が2人いるが、いずれもすでに嫁いでいる。そうしたことから言うと、彼女の縁談が持ち上がっても何らおかしくはない。
ましてこの当時は武家社会だから、豪族の当主はその子女を一日も早くしかるべき所に嫁がせたいと願っていたのだ。兄の説明を聞いたあと小百合は席を立ったが、すぐに両親の所には行かず自分の部屋に閉じこもった。当たり前の縁談の話だが、小百合が唐突に感じたのも事実だ。それは彼女がまだ“少女時代”の気分でいたせいだろうか。
翌日、小百合は縁談の話を兄から聞いたことを両親に告げた。武貞と母の薫(かおる)は特段のことを言わなかったが、父は一言だけ「良い縁談だ」と述べた。
このまま藤沢家に嫁いでいくのだろうか。武家の娘ならほとんどがそうするだろうが、小百合はいま一つ割り切れない感じがしていた。相手の忠則は立派な武士だそうだが、もちろん顔を合わせたこともない。彼女はいろいろ思いをめぐらせていたが、そのうち、全てのことを尾高武弘に打ち明けようと決心した。
数日後、小百合と武弘は館の土塁の上に立っていた。1カ月以上前に2人はここで遊んだが、今はとても暑苦しい季節になっている。もう真夏になったかと武弘が思っていると、小百合が声をかけてきた。
「武弘殿、どうしても聞いてもらいたいことがあります」
「えっ、改まってどうしたのですか?」
「一身上のことです」
小百合はそう述べてから、兄や両親と話し合った全てのことを武弘に打ち明けた。
「こういうことですが、あなたはどう思って?」
「どう思ってと言われても、私には答える術(すべ)がありません。姫はどう思っているのですか?」
武弘が逆に聞くと、小百合は黙ったままうつむいてしまった。
「ただ一つだけ、良い縁談の話ではありませんか。藤沢氏と言えば、豊かな豪族だと聞いています。それに鎌倉にも近いし、最近は何かと評判の良い一族ですね。姫、素直に受け入れられたらいかがですか」
武弘は正直にこう述べた。すると、小百合はきりっとした眼差しで顔を上げると甲高い声を発した。
「武弘殿、あなたはそう言いますが、本当にそれでいいのでしょうか。みんなが良い縁談だと言います。でも、私は天の邪鬼(あまのじゃく)なのか納得がいきません。そう、私は“じゃじゃ馬”ですね。本当は好きな人の所へ行きたいのです。武家の娘が何を言うかとお思いでしょうが」
これには武弘も返事のしようがなかった。
「でも、中には“駆け落ち”して庶民に身を落とす者もいますよ。好きなら武士の身分も捨て夜逃げする人もいます。それが正しいかどうかは別にして、そういう人も実際にいるのです。私は何を言おうとしているのかしら・・・ 武弘殿、ごめんなさい」
小百合は一呼吸置いて、次に驚くべきことを言い出した。
「幼い頃から、あなたが好きでした。これはどうしようもありません。主家の娘が家臣の男性に嫁いで何が悪いのですか。でも、それは現実に無理です。山口家の家訓にも反します。だから、私は武弘殿と結ばれることはありません。それならいっそのこと、あなたも私も武家の身分を捨て、百姓や商人などになったらいいではありませんか。その方が自由になります。そうなれば、私は武弘殿と結ばれるのです!」
そこまで言って、小百合は涙ぐんだのか顔を覆った。花柄模様の“小袖”がかすかに震えている。武弘は呆気(あっけ)に取られて何も言えなかった。今、小百合の本心を聞いたのだ。沈黙が続く・・・ やがて小百合は袖から顔を上げ、泣き笑いの表情で話し続けた。
「ごめんなさい、本当のことを言って。でも、これで気が晴れました。武弘殿、百姓や商人になる気はありませんか? 私はなってもかまいません。あなたがお望みなら・・・」
ようやく武弘が口を開いた。
「姫、あなたはどうかしています。今日は変です。これ以上はもう言わないでください。私も胸が詰まってきました。話をやめて館へ戻りましょう。そうすれば落ち着けると思います」
武弘はそう言って小百合をうながし、館の方へ歩き始めた。彼女は冷静さを取り戻したのか意外に穏やかな表情だ。逆に武弘の方は、突然の“愛の告白”を受けて心が動揺していた。長い間、小百合の遊び友だちだったのに、こんな経験はもちろん初めてだった。
自分の部屋に戻って武弘はいろいろ考えた。小百合の言うことは本心からだろうが、彼女が武家の身分を捨てることにはどうしても納得がいかなかった。また、自分だってそうだ。「尾高家」を捨てるわけにはいかない。父の武則も母の栞(しおり)も、息子の家督相続を当然だと思っている。
武家の身分を捨て自由に生きることは“夢”かもしれないが、そんな勝手なことが許されるだろうか。ごく一部の人はそれを望んでいるかもしれないが、そんな人はほとんどいない。まれに出家したり連歌師になる人もいるが、そういう人はたいてい武家人生に酷く挫折したからだ。自分は尾高家を守らなければならない。
小百合姫も当然、山口家と武家の本分を守るべきではないか。そう考えると、武弘は覚悟を決めた。彼女にはっきりと言おう。姫は自分に淡い恋心を抱いているかもしれないが、それは武家の本分を忘れた勝手な“迷い心”だ。そのことをはっきりと言おう。
そう決心して翌日、武弘はまた小百合を土塁の上に案内した。真夏の太陽がまぶしく輝き、山口家の山野や田畑に照りつけている。武弘の額にも汗がにじんでいた。木陰を歩く小百合は見るからに可愛く美しい。20歳の若さに輝いているようだ。しかし、どことなく憂い顔にも見える。
「昨日は失礼しました。私が本心を明かしたので驚いたでしょう。でも、忘れてください。本当のことを言ったので気が済みました。あなたにご迷惑をかけましたね」
小百合がささやくように語る。武弘はしばらく無言だったが、やがて重い口を開いた。
「いえ、いいのです。姫の正直な気持が分かり嬉しかったです。でも、びっくりしましたね。このことは決して口外しません。なかったことにして、姫は藤沢家に嫁ぐことに異存はありませんね? 私も心から賛同します」
「ええ、一晩考えましたが、両親や兄の意向に従うつもりです。それに、あなたの考えもそうですから。2人の姉もそうしてきました。私だけが“わがまま”を言うわけにはいきません。昨日のことは一時(いっとき)の迷いだと思ってください。さあ、気持よく散歩をしましょう」
言い終わると、小百合は先に歩き始めた。彼女の吹っ切れた様子に武弘は安堵の気持でいっぱいになった。2人はなおも歩き続ける・・・ やがて、小百合が振り返るとにっこり微笑んだ。
「前にここを滑り落ちましたね。もう一度やってみよう!」
そう叫ぶやいなや、彼女は身を伸ばして土塁から草むらに滑り落ちていった。
「姫・・・」
今度は武弘は小言を言わなかった。小百合が吹っ切れたことに満足し、彼はただ“姫君”の後を追って草むらに入っていったのである。
翌日、小百合は両親と兄に藤沢忠則との婚姻にこころよく応じる返事をした。当主の貞清は自分に決定権があるものの、妹が快諾したことに大満足である。早速、使いの者を相模国の藤沢に派遣し、小百合の婚礼の支度に取りかかった。彼女の輿入れは秋の中頃に予定されたのだ。
こうして“吉事”の準備が順調に進んでゆき、山口家は明るい雰囲気に包まれたが、尾高武弘は必ずしも愉快な気分になれなかった。それは小百合の本心を知った上に、いっさい口外しないという約束があったからだ。武弘もまだ若い、23歳だ。武士とはいえ青春のど真ん中にいたせいだろうか。
ちょうどその頃、母の栞が彼に声をかけてきた。
「武弘殿、あなたもそろそろ身を固める時期に来ましたよ。父上もそれを案じておられます。あなたが妻を娶(めと)れば尾高家は安泰、万々歳ということになりますからね」
母の言葉に武弘は特に答えなかった。子女が年頃になれば、親は誰でもそれを考えるだろう。特に武士の家庭では、嫁と跡取りのことは最も重要である。そんなことは彼も分かっているので、とうとうそういう時期に来たのかと思いを新たにしたのである。武弘は無言のまま母のもとを離れた。
季節は真夏を過ぎ、やがて秋の気配が忍び寄ってきた。山口領内の田畑では農民らが忙しそうに働いている。今年は豊作の稲刈りになりそうだ。そんなある日、小百合と武弘は城の土塁の上に立って、見慣れた風景を眺めていた。さわやかな微風が2人の頬をかすめる。
「姫、もうすぐご婚礼ですね。私も嬉しく思います」
「武弘殿、何かとお世話になりました。この景色とももうお別れですね」
「そんなことはありません。いつでも都合のよい時にぜひ里帰りしてください。お待ちしています」
「ありがとう、兄もそう申していましたよ。藤沢へ行ってもこちらのことは決して忘れません。私の故郷だもの・・・・」
なごやかな会話が続いたが、2人が個人的に会ったのはこれが最後だった。やがて、小百合が輿入れする日がやってきた。その日は秋晴れの素晴らしい天気で、領内も稲刈りで大賑わいの一日だった。全ての人に祝福されるように、花嫁を乗せた輿(こし)が山口の館を出る。
両親や兄ら親戚一同もこれに続き、武弘ら主な家臣も武蔵と相模の国境いまで見送ることになった。武弘は小百合の輿を警護しながら、どうぞいつまでも息災でと祈らざるを得なかった。こうして小百合は藤沢忠則のもとへ嫁いでいったのである。
<参考映像・・・室町時代を偲んだ『照姫まつり』(東京・練馬区)。➡>https://www.youtube.com/watch?v=gKgvmyDuWDM
小百合が山口からいなくなると、武弘は心にぽっかりと空洞ができたように感じた。張り合いがなくなったというか力が抜けたというか、むなしい気持になったのである。彼はそれを忘れるために、これまで以上に仕事に精を出した。農地の管理や農民からの意見聴取、領内の見回りなどに全力を挙げた。
それを見てかどうか分からないが、ある日、主君である貞清が武弘を自室に呼び入れた。彼の側には夫人の牧の方(かた)が同席していたが、彼女は貞清より3歳下(武弘より1歳下)のういういしい若妻である。貞清は領内の出来事などを聞いてきたが、やがて話題を切り替えた。
「武弘、今日はいい話がある。奥(牧のこと)がその方にふさわしい婚姻の相手がいるというのだ。その相手は、豊島家の家臣・筒井泰宗の息女だそうだ。まあ、聞いてみてくれ」
豊島(としま)家は牧の方の実家だが、彼女の話によると、筒井泰宗の次女・小巻(こまき)という娘がその相手だという。武弘より3歳下になるが、とても可愛く美しい娘だそうだ。
「私とは幼なじみで、まるで姉妹のように仲良く一緒に育ってきたのよ。武弘殿とはちょうど良いお相手ではないかしら。一度ぜひお会いになってみてください」
牧の方が熱心に語る。武弘は少し当惑したが、主君ご夫妻が勧める縁談であれば、むげに断わる理由もない。会ってみて、嫌なら婉曲に断わればいい。領主や大名の子女であれば顔を合わさなくても結婚が決まるが、家臣の場合は断わる“自由”がある。その点、家臣の方が気が楽だ。
「かしこまりました。よしなにお取り計らいください」
武弘がそう答えると、牧の方はすでに用意していた書状を取り出し、筒井家を訪問する段取りなどについて説明した。彼女は実家の元家臣に文を出すので、とても生き生きした感じである。懐かしさが込み上げてくるのだろう。こうして、武弘が武蔵国の石神井(しゃくじい)城を訪れる段取りが決まった。
彼がそのことを両親に報告すると、武則も栞も大喜びだった。そして数日後、武弘は供の者1人を連れ馬で石神井城へ向かった。この若者は佐吉(さきち)と言って、親の代から尾高家に仕えていた。年の頃は25~6歳だろうか、雑役なら何でもこなす屈強な男である。
「若殿、よい天気になりましたな。夕方には向こうに着けるでしょう」
「うむ」
武弘は生返事をしたが、少し気が重い感じがしてきた。嫌なら断わればいいが、牧の方が熱心に勧める話だ。やはり粗略にはできない。そんなことを考えながら、武弘は佐吉とともに夕刻には石神井城に着いた。
この城は山口城に比べると一回り大きく、また豪壮な構えをしている。名門の豪族らしいたたずまいの中を、2人はすぐに筒井家の館を訪れた。すると、玄関の式台に1人の娘が現われたが、彼女を見るやいなや武弘ははっとして立ちすくんだのである。
その娘は色が白く実に美しい容貌をしている。彼女は手をついて挨拶しようとしたが、その時、女中頭のような中年の太った女が現われそれを制した。
「お嬢さま、ここは私がうけたまわります」
中年の女がそう言うので娘は奥に下がった。武弘は名前と身分を明かし、牧の方より書状を持参したと告げると、女は急に明るい笑顔を浮かべ丁寧な口調で言った。
「まあ、牧の方さまのお使いですか。それはご苦労さまです。さあ、どうぞお上がりください」
そして、武弘らは女の案内で奥座敷に通され、筒井泰宗とすぐに面会することができた。泰宗は書状に目を通すと、まじまじと武弘を見据えてこう述べた。
「いや~、かたじけない。牧の方さまはお元気ですか。さっそくご返事を書きますので、今夜はゆっくりと泊まっていかれよ」
こうして武弘と佐吉は筒井家で一夜を過ごすことになり、食事や湯浴みなどで手厚いもてなしを受けた。翌朝、武弘が泰宗の書状を携えて筒井家を後にする時、式台に夫人と娘も見送りに現われた。泰宗がほがらかな声で言う。
「これが娘の小巻です。どうぞお見知りおきを」
もちろん、彼女は昨夜会ったその人である。武弘にはもう“わだかまり”は一切なかった。気持よく挨拶して筒井家を後にしたのである。帰り道にすぐ、何かを感づいた佐吉が声をかけてきた。
「若殿、あのお嬢さんは実に綺麗ですね。俺もああいう素敵な人にめぐり合えれば・・・はっはっはっはっは」
大笑いする佐吉を無視するかのように、武弘は馬に強くムチを入れた。馬は飛び跳ねるように疾走する。取り残された佐吉はあわてて武弘の後を追った。広い草原を走りながら、武弘はこれまでにない喜びを感じていたのだ。
それから2カ月ほどして、尾高武弘と筒井小巻は山口の館でめでたく祝言をあげた。親戚一同はもとより貞清夫妻も2人を心から祝福したが、特に牧の方は小巻と再会できて嬉しさもひとしおだった。
「小巻殿、あなたと同じ山口で過ごせるとは本当に幸せです。いつまでも一緒にいましょう」
牧の方の言葉に小巻は小さくうなずいた。彼女も喜びが込み上げてきたようだ。かつて姉妹のように育った2人が、また居所を同じくしたのである。
武弘はそっと小巻の様子を見た。白無垢の花嫁衣装に包まれたその美しさはたとえようもない。そして武弘はふと、先に婚礼の式をあげた小百合姫のことを思い出した。彼女もきっと2人のことを祝福してくれるだろう・・・姫は今頃どうしているのかと思いをめぐらせるのだった。(続く)