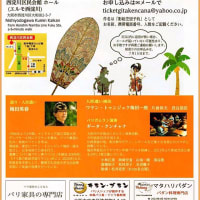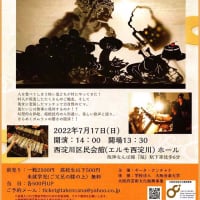今年の春のある日、近所のコンビニに行ったら、こういう剪定の跡があった。
剪定しないと、敷地からどんどんはみ出すし、日も当たらなくなるし、樹木にもよくないからやるんだろうけど、植物の生命力の形というのは、これを見る限り、なり振り構わないというか、過激だね。
それが先日、同じ場所を見てみたら、あっという間にこんなにこんもりと枝や葉が成長していた。びっちりということは、効率よく、かつ、最も高密度で葉がついているということでもある。なんといっても日当りは栄養源だしね。

植物の枝や茎や葉の付き方のことを専門的には「葉序」(ようじょ)というけど、そこには三パターンあるとされている。なんといっても主流は螺旋状に付いていくというパターンだ。
この螺旋の葉序とは、螺旋状に成長しながら、ある角度で葉がついていくというのが基本だ。
要するに、葉は光合成をするわけだから、影にならないことが大切。普通に考えれば、180度とか120度というのが効率的に感じるけれど、それでは2周目以降には真上から見ると葉が重なってしまってよろしくない。
螺旋葉序は、そう単純ではない。実は、絶対、葉が重ならない角度があるんです。

事務所にある植物の葉。典型的な螺旋葉序だ。
これも学生時代に読んだ話だけれど、実際の例でみると、最初の1周目は葉は反対側に1枚でるので1周で2枚、次は120度で3枚、次の螺旋では144度で、つまり2周で5枚、その次が135度で今度は3周で8枚・・・、その次が問題だ。138.46度。急に変な数字になった。でもこれ、5周で13枚ということなのだ。
並べ直すと、1/2、1/3、2/5、3/8、5/13・・・。そう、これ、分母も分子も、前にも書いたフィボナッチ数列だ。
結果、その先、どういう数字に収束していくかというと、137.5度という不思議な数字に近づいていく。
でもこれには黄金比という立派な根拠がある。公式としては、360度÷黄金比の二乗で求められる。つまり、360度÷1.618÷1.618ということだ。わかるだろうか?
ワヤンは残念ながら平面なので、「クプの木」はこのルール外だけど。
それはともかく、自然界が導きだしたこの不可思議な数字は、太陽を求める生命としての植物が生き抜くために必要な命の知恵から生まれた合理なのだ。
やっぱり自然は不思議だね。(は/152)