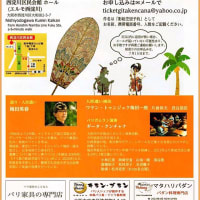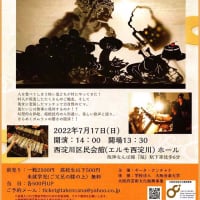幸いにも急きょ、今週の上海出張が延期になり、ちょっと一息ついた。たぶんほんの一瞬のことな気がするけど。
とりあえず、空いた時間はもらった時間のようでもあり、今日はいろいろ雑事を整理することができた。たまにはこういう日もないと、どんどんいろんなものが溜まってきてよろしくない。
ところで、先週の香港は、無事、社長プレゼもうまくいき、いろいろやることも見えてきた。
普段言葉であまり褒めることのない先方の評価は"Very good!!"、だそうだ。まるでカンフーマスターのデザインのようだと後で言っていたらしい。きっと禅の思想のように、都市のなかにあっても、深山幽谷、見えない存在を見て、聴こえない音が聴こえてきたんだろう。デザインプレゼのわりには、どうも哲学的議論をした気がする。
改めておもうが、「存在のデザイン」とは、見た目で決まるものではない。むしろ、諸行無常のなかにあって心身解脱すれば感じることのできる唯一の証のようなものだ。アジアでもやっぱり「我思う故に我在り」なんだろうか・・・?
えっ、なんのこと言ってるのかって? そりゃ、ま、いずれまた。守秘義務あるし。

ところで、香港はイギリスから返還されてすでに20年以上経つが、やっぱり全然中国じゃない。ビジネスエリアで働く人は店員も含め全員流暢に英語で会話しているし、いろんなやりとりを聞いていると、街も人も、感覚的にすこぶるインターナショナルだ。相変わらず、空港にでも行かないと日本語は聞こえてこない。
人口800万が狭い土地にひしめき合い、ある角度からはニューヨークのようにも見え、ある角度からはサンフランシスコのようにも見え、誰もせわしなく動いている。不動産価格は東京の3倍だそうだ。
ある人が言っていたが、香港人は「せっかち」だそうだ。
たしかに言葉もマシンガンのようだし、エレベーターもエスカレーターも浜松町の2倍くらいにとっても早い。
ここもやっぱり"Time is money"なんだろう。

ともかく早い。子供やお年寄りはいったいどうするんだろう・・・?
あとは、馴れ、だろうか。
そんな街もよく見るとアートで溢れている。
ニューヨークやロンドンにある有名ギャラリーがいくつか進出していて、今回はそのめぼしいところを最終日に一通り観て回わることができて刺激的だった。写真は今度。
そんななか、街で見つけたのが、イギリスの彫刻家アントニー・ゴームリーの作品群だ。香港サイドのあちこちにあって、街中にちりばめられている。
間近の写真がなくて申し訳ないが、たぶん、彼自身のコピーだろうが、彫刻の存在が彼自身の存在、まるで、あちらの世界とこちらの世界をつなぐ「場」や「痕跡」に見えてくる。
ゴームリー自身の言葉を借りるなら「人体とは記憶と変容の場所そのものである」(うろ覚えだがたしかこんな感じ)だそうだ。
物質と場所、生と死、西洋と東洋・・・あらゆるものがダブルイメージになっている。つまりテーマはきっと「存在」なのだ。

ビルの上に人が立っているように見えるのが、ゴームリーの作品。
たぶん、等身大か少し大きいくらい。ビルの上にもあるし、歩道の真ん中に唐突にあったりする。

ちょっと逸れるけれど、街のなかのショップにあったディスプレイ。凝っている。
一方、別途打合せもした新しいミュージアムの「M+」の仮設展示も、中国40年の現代アートをやっていた。たとえばこんな感じ。

かの有名なアイ・ウェイウェイの作品「静物」。石斧を千個展示している。
これも、古代の記憶というものだろうか。

キュウ・シーフゥアの作品。典型的なアブストラクト。
小さく見えないくらいに赤い点がゴミのようについている。
これも観る人や気分によっては如何様にも見えることだろう。まるで能のオモテのようだ。

ノーコメント。見ればわかる系。

作者は確認しなかったけど、たぶん、山水画を写真で表現したんだろう。これも価値と視覚の転換か?
でも、なんとも品がいいとは言えない系だ。
これらも、アブストラクト(抽象芸術)やコンセプシャル・アート(概念芸術)を介在させることで、自由主義と共産主義、前衛と後衛、伝統と現代、芸術と反芸術など、価値が逆転したり、対比的に重ね合わせている。
こういうものが街のあちこちで見られるということは、現実の街を見ながらその背後のイメージを連想してしまうということでもある。つまり、そこは狭くて巨大な都市の幻影を担っているようにも感じてしまうのだ。
熱でもあったのかなぁ。なんだかブログも抽象的になってしまった・・・スミマセン。
まあでも、バリを出るときもいつもそうおもうが、飛行機が飛び立って、だんだん島が視界から消えていくと、さっきまでガヤガヤ騒がしくしていたあの「場所の体験」が、夢のあと、幻影だったかのように感じてしまうことがある。
「存在」は、そうして次第に脳裏のなかで「存在学」として言葉と記憶を重ねていくことになる。
いや、だから、バリも香港も、アートや芸能がインターフェイス、"Ontological City"なのだ。(は/209)
とりあえず、空いた時間はもらった時間のようでもあり、今日はいろいろ雑事を整理することができた。たまにはこういう日もないと、どんどんいろんなものが溜まってきてよろしくない。
ところで、先週の香港は、無事、社長プレゼもうまくいき、いろいろやることも見えてきた。
普段言葉であまり褒めることのない先方の評価は"Very good!!"、だそうだ。まるでカンフーマスターのデザインのようだと後で言っていたらしい。きっと禅の思想のように、都市のなかにあっても、深山幽谷、見えない存在を見て、聴こえない音が聴こえてきたんだろう。デザインプレゼのわりには、どうも哲学的議論をした気がする。
改めておもうが、「存在のデザイン」とは、見た目で決まるものではない。むしろ、諸行無常のなかにあって心身解脱すれば感じることのできる唯一の証のようなものだ。アジアでもやっぱり「我思う故に我在り」なんだろうか・・・?
えっ、なんのこと言ってるのかって? そりゃ、ま、いずれまた。守秘義務あるし。

ところで、香港はイギリスから返還されてすでに20年以上経つが、やっぱり全然中国じゃない。ビジネスエリアで働く人は店員も含め全員流暢に英語で会話しているし、いろんなやりとりを聞いていると、街も人も、感覚的にすこぶるインターナショナルだ。相変わらず、空港にでも行かないと日本語は聞こえてこない。
人口800万が狭い土地にひしめき合い、ある角度からはニューヨークのようにも見え、ある角度からはサンフランシスコのようにも見え、誰もせわしなく動いている。不動産価格は東京の3倍だそうだ。
ある人が言っていたが、香港人は「せっかち」だそうだ。
たしかに言葉もマシンガンのようだし、エレベーターもエスカレーターも浜松町の2倍くらいにとっても早い。
ここもやっぱり"Time is money"なんだろう。

ともかく早い。子供やお年寄りはいったいどうするんだろう・・・?
あとは、馴れ、だろうか。
そんな街もよく見るとアートで溢れている。
ニューヨークやロンドンにある有名ギャラリーがいくつか進出していて、今回はそのめぼしいところを最終日に一通り観て回わることができて刺激的だった。写真は今度。
そんななか、街で見つけたのが、イギリスの彫刻家アントニー・ゴームリーの作品群だ。香港サイドのあちこちにあって、街中にちりばめられている。
間近の写真がなくて申し訳ないが、たぶん、彼自身のコピーだろうが、彫刻の存在が彼自身の存在、まるで、あちらの世界とこちらの世界をつなぐ「場」や「痕跡」に見えてくる。
ゴームリー自身の言葉を借りるなら「人体とは記憶と変容の場所そのものである」(うろ覚えだがたしかこんな感じ)だそうだ。
物質と場所、生と死、西洋と東洋・・・あらゆるものがダブルイメージになっている。つまりテーマはきっと「存在」なのだ。

ビルの上に人が立っているように見えるのが、ゴームリーの作品。
たぶん、等身大か少し大きいくらい。ビルの上にもあるし、歩道の真ん中に唐突にあったりする。

ちょっと逸れるけれど、街のなかのショップにあったディスプレイ。凝っている。
一方、別途打合せもした新しいミュージアムの「M+」の仮設展示も、中国40年の現代アートをやっていた。たとえばこんな感じ。

かの有名なアイ・ウェイウェイの作品「静物」。石斧を千個展示している。
これも、古代の記憶というものだろうか。

キュウ・シーフゥアの作品。典型的なアブストラクト。
小さく見えないくらいに赤い点がゴミのようについている。
これも観る人や気分によっては如何様にも見えることだろう。まるで能のオモテのようだ。

ノーコメント。見ればわかる系。

作者は確認しなかったけど、たぶん、山水画を写真で表現したんだろう。これも価値と視覚の転換か?
でも、なんとも品がいいとは言えない系だ。
これらも、アブストラクト(抽象芸術)やコンセプシャル・アート(概念芸術)を介在させることで、自由主義と共産主義、前衛と後衛、伝統と現代、芸術と反芸術など、価値が逆転したり、対比的に重ね合わせている。
こういうものが街のあちこちで見られるということは、現実の街を見ながらその背後のイメージを連想してしまうということでもある。つまり、そこは狭くて巨大な都市の幻影を担っているようにも感じてしまうのだ。
熱でもあったのかなぁ。なんだかブログも抽象的になってしまった・・・スミマセン。
まあでも、バリを出るときもいつもそうおもうが、飛行機が飛び立って、だんだん島が視界から消えていくと、さっきまでガヤガヤ騒がしくしていたあの「場所の体験」が、夢のあと、幻影だったかのように感じてしまうことがある。
「存在」は、そうして次第に脳裏のなかで「存在学」として言葉と記憶を重ねていくことになる。
いや、だから、バリも香港も、アートや芸能がインターフェイス、"Ontological City"なのだ。(は/209)