ボルドー品種(カベルネソヴィニョン、ソヴィニョンブラン、カベルネフラン、メルロなど)のワインには、メトキシピラジン(=(略称)MIBP、=(正式名称)2-メトキシ-3- イソブチルピラジン))と呼ばれる物質が含まれ、ピーマンの香りに代表される青臭い香りがある。その爽やかなニュアンスをプラス要因として積極的に取り込む生産者もいるが、一般には未熟果に由来する香りとされワインのマイナス要因と考えられている。
以前投稿したが、MIBPをコントロールするために、ブドウの房の周りの除葉することで、MIBPの生成を抑制できることが知られており、1980年代後半から徐々に除葉が取り入れられてきた。カリフォルニアでは90年代には一般的になったが、ボルドーでは2000年代頃から本格的に取り入れられている。
MIBPはどこで生成されるか?
除葉がMIBPの生成を抑制するのであれば、MIBPは葉で生成されるのか?この仮説を否定できる興味深い研究が行われていた。MIBPが含まれる品種の房を、MIBPが含まれない品種の樹に接ぎ木したものと、その逆の組み合わせの比較実験が行われた。
- A) マスカットオブアレキサンドリア(MIBPなし)の樹に、カベルネソヴィニョン(MIBPあり)の房を接ぎ木する
- B) カベルネソヴィニョン(MIBPあり)の樹に、マスカットオブアレキサンドリア(MIBPなし)の房を接ぎ木する
実験結果は顕著で、Aの実には多量のMIBPが含まれていたが、Bには検知可能なMIBPは含まれていなかった。
この実験が示唆することには、MIBPはブドウの実で生成さるのであって、葉で生成されたMIBPが実に運ばれることはないということである。
なぜ除葉がMIBPを抑制するか?
MIBPは、熱や紫外線によって分解されることが知られている。新世界の温暖な地域のカベルネは、その暑い気候のためにMIBPがそもそも抑制されている。さらに、フルーツゾーンの除葉によって紫外線が果実に当たり、MIBPの分解が促進されるようだ。
MIBPはどのように生成されるか?
これについては研究途上にあるようだが、ブドウ生育期の湿度、特に、結実から果実が色づくヴェレゾンまでの湿度が大きく影響するそうだ。確かに、ナパの降雨量は6月から9月まではほとんどゼロだが、フランスは毎月50㎜の降雨はあるようだ。
日本のワイン
ボルドーのメルロとカベルネソヴィニョンを比べるとカベルネソヴィニョンにはMIBPが顕著だが、メルロのMIBPはそれほど強くはない。一方、日本のメルロではMIBPの香りが顕著に表れている。日本の場合、6月中旬~7月中旬は梅雨の最中で、月間降雨量は100㎜をはるかに超える。MIBPが生成されやすい時期に湿度が最も高くなることが、日本のMIBPを厳しいものにしていると思う。
最近、いくつかの日本のカベルネフランを飲む機会があった。カベルネフランとソヴィニョンブランが自然交配してカベルネソヴィニョンが生まれたとされているだけあって、カベルネフランもMIBPが多く含まれているはずである。(少なくともロワール地方のカベルネフランからはピーマンが強く香って来る。)しかし、日本のカベルネフランからは強いMIBPを感じなかった。何故か?
これ以降は全くの私見ではあるが、メルロとカベルネフランの生育サイクルの違いに起因すると考える。メルロはかなり早く収穫できる品種で、8月の終わりには摘み取られる。秋雨前線や台風の影響を軽減できるとして日本で推奨されてきた。しかし、その分結実やヴェレゾンの時期も早いのでMIBP生成にとってはマイナス要因になっているのではないか。
一方、カベルネフランの収穫はメルロよりも数週間遅い。もし、結実やヴェレゾンのタイミングも遅いのであれば、MIBPが生成される時期の後半では梅雨が明けて、湿度も低下していると思われる。秋雨前線や台風のリスクが高まるかもしれないが日本においてはMIBP抑制には向いた品種なのかもしれない。










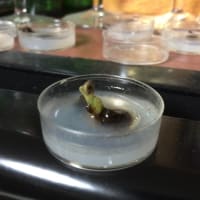















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます