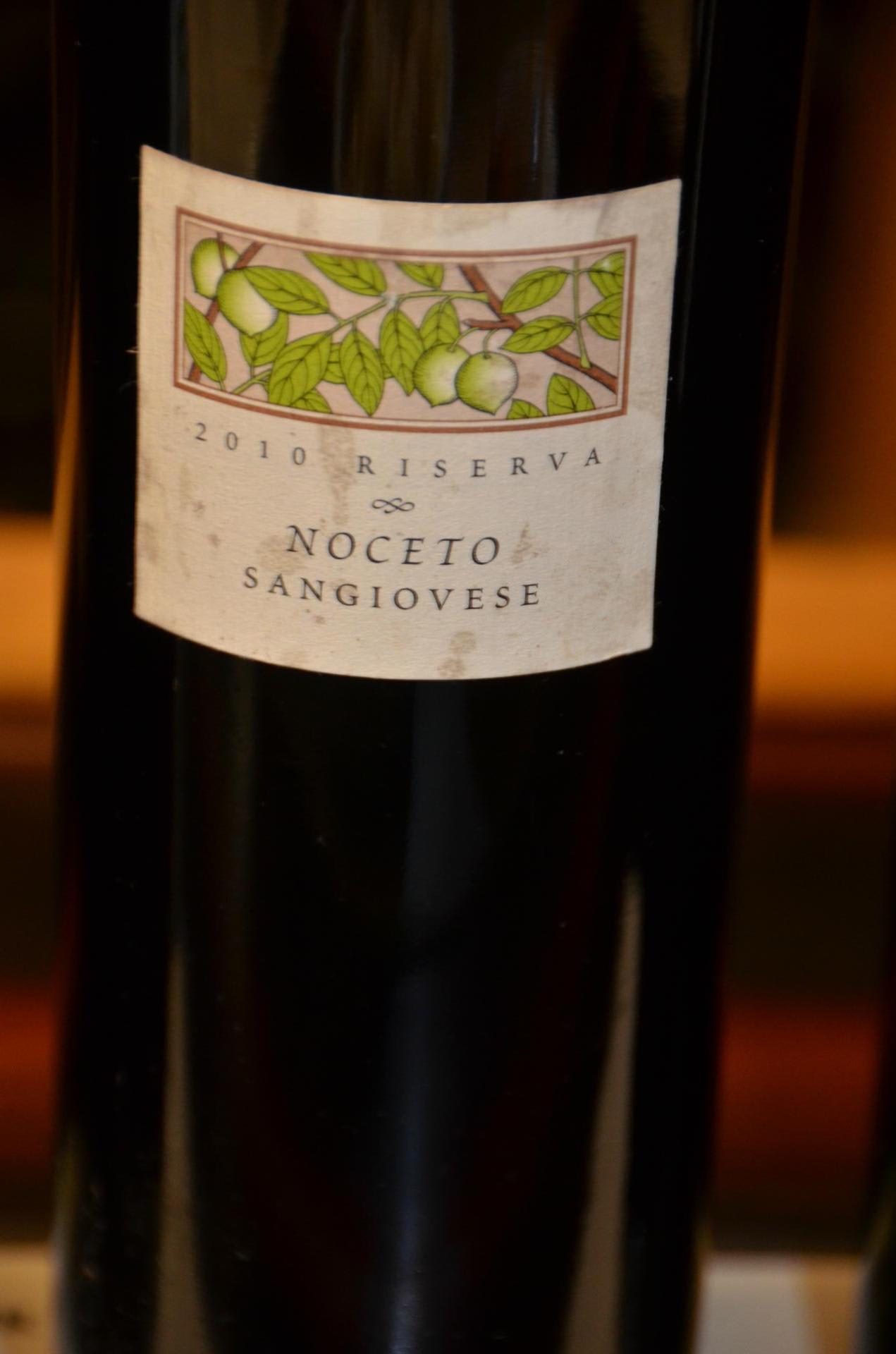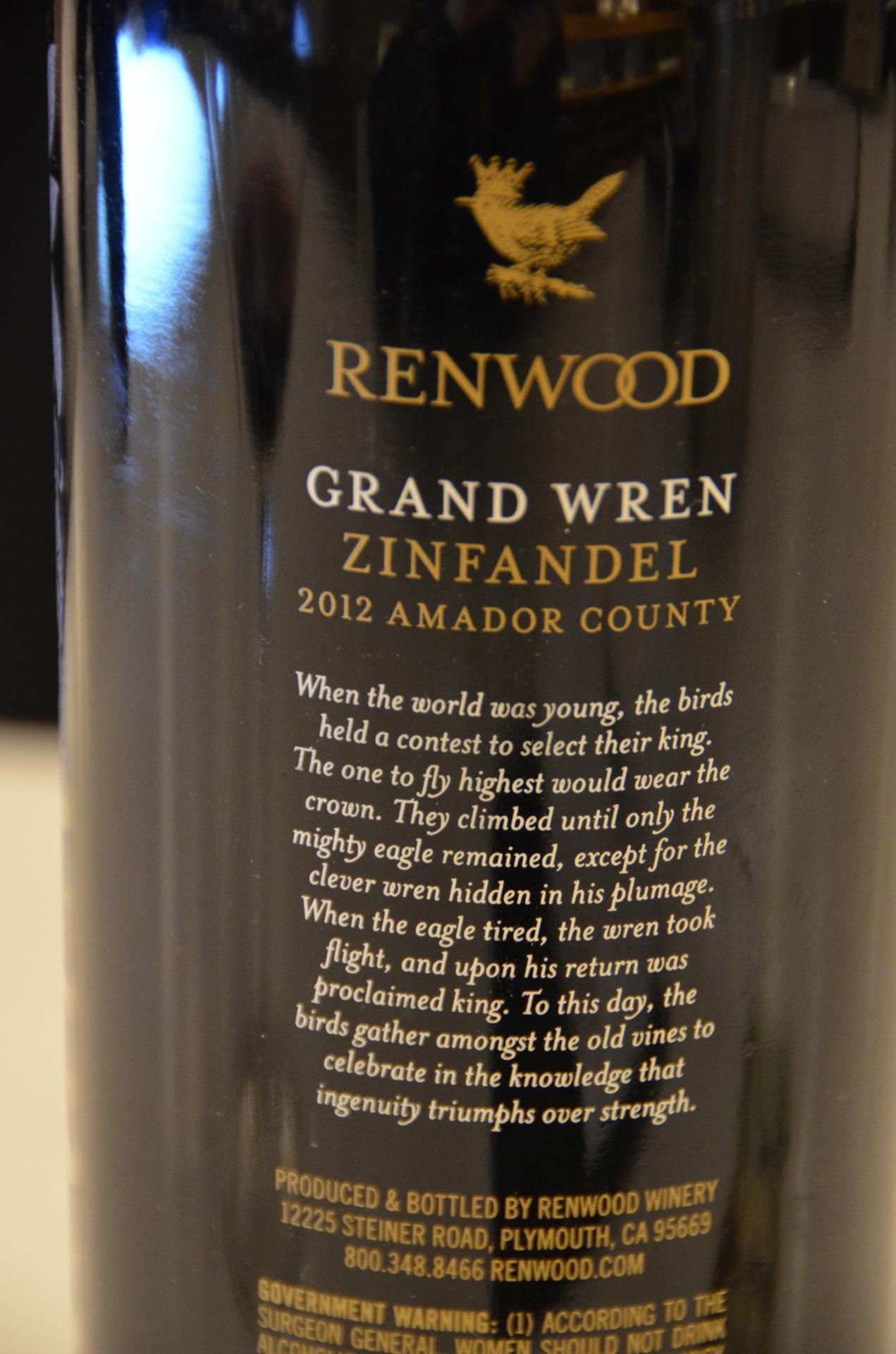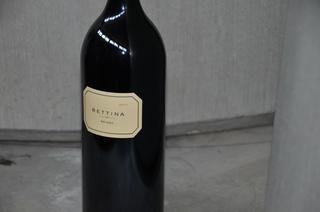北海道の岩見沢近郊に知る人ぞ知る「10Rワイン」(トアールと読む)がある。
このワイナリーを経営し、自らワインを造るBruce Gatlove氏は、UC Davisを卒業後、ワイン造りを指導するために栃木県のココファームに招聘された。短期間のつもりが滞在日数が延び、日本に居着いてしまった。ココファームの経営に携わる一方、自らのワインを造るべく北海道の岩見沢市の隣、栗沢町にワイナリーを立ち上げた。
訪問日(12月8日)の前日は吹雪に見舞われ、札幌から岩見沢まで余すところなく銀世界に包まれていた。幻想的な風景の中をタクシーで進むのだが、このワイナリーには看板もなければサイトに地図も掲載されていない。10Rワインに電話をかけて、ナビゲーションをしてもらいやっとたどり着ける。したがってワイナリーには、テイスティングルームなどの洒落た設備はなく、事務所と醸造設備があるだけである。「観光ワイン」とは一線を画すという強いメッセージを感ぜずにはいられない。一般visitorを受け入れないカリフォルニアのカルトワインやフランスのガレージワイナリーを彷彿させる。
Bruceのワインに対するこだわりは、場所の選定から始まっている。当初は、海外でのワイン造りも考えていたが、日本の長野・山形・北海道にポテンシャルを感じたそうだ。なぜ北海道か?ここであれば平地でワインを造れる、山形だと標高400㍍は必要で、長野であれば標高700㍍でなければ目指すワインができないとの意見を拝聴した。特に北海道では、積雪が多いことがヴィニフェラワインの生育に重要で、初冬にまとまった雪があれば枝先まで雪に埋めることで、風雪による気温の低下に伴うブドウ樹の壊死から守れるそうである。山を隔てた十勝地方は、雪が少ないためワイン樹が風雪にさらされ、ワイン樹が死んでしまうそうだ。確かに、大学では、マイナス20~25℃でブドウ樹は死ぬと習った。十勝では、耐寒性に限界があるヴィニフェラのブドウ樹を諦め、ヴィダルといった寒冷地用のブドウ樹を用いるとのこと。それにしても、マイナス40℃に達する旭川にそう遠くない。正確には名寄が最北のワイナリーであるそうだが、岩見沢はまさに日本のブドウ生育の北限との印象を受けた。
ブドウは斜めに仕立てるそうだ。これにより、積雪が少なくてもブドウ樹を雪に埋めやすいそうだ。北海道の余市周辺で最初に考案され、広く使われるようになった仕立て方らしい。個人的には、そんな不格好な仕立てで良いブドウが実るか疑問を感じる。VSP仕立てで上に樹を伸ばし、高さを抑える方が真っ当なブドウ樹に育つと思うのだが。Bruceの意見は、「そうかもしれない。やってみるといいよ。」試すしかないのかも。
剪定方法は、先進的な手法が採用されている。Double Pruningと呼ばれる、年2回の剪定を行っている。1回目は収穫後に行われ、長く伸びた枝を余裕をもって切り、2日目は春先に行われ、残す新芽のすぐ上を切り落とす。1回目は雪による枝折れ防止も兼ねている。日本の場合、除葉も必要で実践しているとのこと。
防かび剤、殺虫剤を利用していることについての意見は率直だった。日本の高い湿度で防カビ剤なしは厳しいとの意見。殺虫剤も使用を止める方向だが、収穫できなくなると元も子もないので、入念な観察と調整を続けているそうだ。私がジャックセロスを2012年に訪問した際、雹害とベト病に見舞われてブドウ樹が壊滅しそうになった時、農薬を用いたと説明してくれた。アンセルムが「自分の子供が死な時に親であれば、可能性のある投薬を認めるのと同じだ。」と説いていたことをBruceに伝えたところ、激しく同感してくれた。
自分のワイナリーのため、収穫に対するこだわりは強い。日本のワイナリーは、フランスのカレンダーを真似て早く収穫したがる。霜が降りる直前まで待って糖度を上げるべきだと言うことがBruceの意見。日本のブドウは糖度が低く青臭いのは、収穫が早すぎるということはその通りとも思う。幸いにして北海道を通過する台風が少ないのでそれができるとのコメントもごもっともで、そこが北海道にポテンシャルがある論拠の一つなのであろう。
寒い場所のため、Stuck Fermentationは大きな問題のようだ。いくつかの桶では、発酵が止まったままとのこと。それでも、温度を上げて発酵を促すこともせず、そのままにしている。来年のワインの醸造時に発酵中のワインを入れてスタートさせたいと考えているそうだ。
SO2の添加量についての話は興味深かった。UC Davisでは、pHの値に応じて必要となるSO2の量が変化することを教えられる。この理論に異論はないが、推奨SO2添加量については、安全性を優先しすぎた値とBruceは考えている。かつてUC Davisのフィールドトレーニングで同席したBryant Familyの醸造責任者でもあるToddも同意見で、推奨値よりもかなり低い添加量をBryant Familyでは添加しているとのこと。SO2添加量もpHに応じて一律に決まるものではなく、さまざまな戦略がありそうだ。
高い志とともに、栽培・醸造に関わる設備の調達方法などのpracticalなアドバイスと全てにわたり、多くを学び刺激を受けた。