
4月。日本は新学期。入学そして進級の季節です。新しいランドセルにちょっとはにかみながらも、おおいに張り切っているぴっかぴかの一年生たち。今週はそんな新入生に贈る『新学期に読みたい絵本』をご紹介しましょう。
いよいよ入学。はじめての学校は、楽しみなような、実はちょっと不安なような……。「もういくつ寝ると」と指折り数えて(countdown)、あれこれ準備しながら待っている”新入生”親子の気持ちはアメリカも日本も同じです。
でも、アメリカと日本では学校制度が異なり、こちらでは小学校入学前に、子どもを---学校という集団生活に慣らすための準備期間---として一年間の『幼稚園(Kindrgarten)』が置かれ、ここからが義務教育のはじまりです。ですから、アメリカで”はじめての学校”とは『幼稚園』。親子ともドキドキの、ぴっかぴかの一年生は、実は幼稚園の新入園児です。
従い幼稚園は義務教育の一環で、小学校入学準備のためのもの。ですから普通、幼稚園は小学校の敷地内に隣接し、組織的にも小学校の一部として扱われます。出入り口も一緒で、グラウンドや講堂も、時にはランチを食べるテーブルも小学生たちと共有。『全校集会』に小学生と並んで出席することもあります。校長先生も小学校と同じなら事務室も一緒。先生方も小学校と幼稚園を通して人事異動があります(幼稚園教諭は小学校教員資格と区別がない)。これは日本とはまったく違うところですね。
ちなみに、では義務教育の終了はというと、日本では”中学校卒業”までですが、アメリカは”18歳になる”まで。学校は幼稚園の一年間と、小学校が1-6年生まで(または1-5年生まで。学校または学校区によって異なる)、中学校が6-8年生(または7-8年生)、高校が9-12年の4年間。義務教育制度のことを略して『K-12 (k to twelveと読みます)』というのは、日本で「小中高」というふうに省略するのと同じ表現です。日本と違うのは、『学年』を正式に言うときには、通常、小学校1年生からはじまる”通し番号”で呼ぶことで、たとえば高校1年生は9年生といいます。それぞれの学校で何年生か---を示す表現は別にあり、特に高校以上では、一年生は Freshman、二年生は Sophomore、三年生は Junior、四年生は Seniorと呼ばれます。これは大学も同様。
アメリカでも、18歳は高校卒業の年齢です。が、厳密に言うと、保護者には「高校を”卒業させる”義務」はありません。義務は「18歳まで”就学”させておく」こと。通った学校を卒業するか否かは、いわば"子ども自身の責任"(という訳でもないでしょうが)、ともかく保護者の義務からは切り離されています。実際、詳しい学歴を書かされるような場面では、『出身高校』の記入欄に、通学した高校(卒業した、ではない)の名前と、『卒業資格の有無』をそれぞれ別に記入するように求められ、日米の制度の違いを実感させられます。以前このブログにも書きましたが、アメリカでは高校卒業資格を得ないままドロップアウトしてしまう子どもが少なからずいて、社会問題になっています。(ブログ記事:『スーパーマンを待ちながら‥‥』)
さて、新学期に読みたい絵本の話題に戻りましょう。
「一年生になったら‥‥ともだち100人できるかな?」という歌があります。なんといっても新しい学校に行く楽しみと期待は、新しいお友達ができること。どんな子がいるのかな? 何して遊ぼうかな?と考えると、入学の日が待ち遠しい。子どもたちのそんな期待を思いきりかき立ててくれるのが「On my very first school day, I met...」です。イラストからして最高!おもしろいこと請け合い、ちょっとくらいの不安は忘れて学校に行くのが楽しみになることも請け合い!の絵本です。
でも一方では、幼稚園に行ったら…学校に行ったら…、お母さんがいないから、何でも一人でやらなくちゃいけないよなぁ。トイレだって失敗したら恥ずかしいよなぁ。給食に嫌いなものや食べられないものが出たらどうしよう‥‥。心配と不安でいっぱいになっている子もいるはず。もう時効だから書いてしまいますが、親友の息子は一年生になっても毎晩の『おねしょ』が止まらず、「学校や友達宅で『お泊まり』があったらどうしよう‥‥」というのが親子そろっての深刻な悩みでした。ウチの娘の場合は、初めての学校が、右も左もどころか言葉までわからないアメリカだったので、ケガしないで帰ってくるだろうか、トイレにちゃんと行けるだろうかと本当に心配しました。
もちろんアメリカの親も子どもも、それなりに悩んで神経質になるようです。「Count Down to Kindergarten」は、あと10日で幼稚園に入園するというのに、「まだ一人で靴ひもが結べない‥‥」と悩んでいる女の子のお話です。毎日毎日、一生懸命練習しますが、とうとう靴ひもが結べないまま入園の日が来てしまい‥‥。ところが、ドキドキで幼稚園に行ってみたら‥‥なぁ~んだ!クラスのお友だちもみんな靴ひもが結べないんだって!
この「なぁ~んだ!」「ドキドキして損しちゃった!」「あんなに心配することなかったんだ!」という、"ホッと安心"体験を先取りさせて、それとなく「心配しなくても大丈夫!」と語りかける絵本がたくさん出ています。とっくに学校に行っているお姉ちゃんの手前、内心では心配でたまらないのに、いまさら不安だの心配だのと言いにくくて強がっている男の子が主人公の「Kindergarten Rock」もおすすめの一冊です。
ちょっと変わったところでは、不安だったり心配だったり、親子の別れが辛いのは、子どもだけでなく実は親もなんですよという、意外な結末がついている絵本「 The Night Before Kindergarten」。おまけに、いえいえ実は先生だってものすごく不安なんですよ「First day Jitter」という絵本もあります。
でも、大丈夫! たいていは、行きたくないのは初日の朝だけ。学校って案外楽しいんです、よね? なにしろ友達はいっぱいいるし、先生はやさしいし、ちょっと勉強したら意外に自信もついちゃうし。そんな経験をスプラットとシェアしましょう。「Splat the Cat」は、一日目は、学校に行くのがいやで早く目が覚めたのでしたが、二日目には学校に行くのが楽しみで早く目が覚めちゃったふわふわ猫のスプラットのお話です。
学校では、友達も楽しいけど、先生もすごい! 先生は、子どもたちひとりひとりをちゃんと覚えて、親しみを込めて名前で読んでくれます。だけど、クラスメートが全員同じ名前だったらどうなるんだろう? いや、きっと大丈夫.先生はちゃんと区別して覚えてくれるに違いありません(「Mathew A.B.C. 」)。だって、クラスに双子が何人いたって間違えたりしないんですから。(ブログ記事:『ここにもふたご!そこにもふたご!』)。先生、だいすき!
















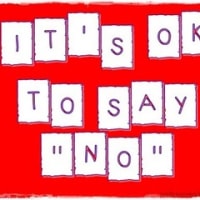
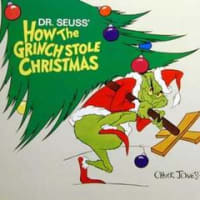

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます