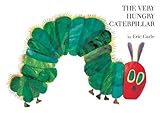文月メイさんの「(紙芝居)ママ」というタイトルのYouTubeの映像が100万回以上アクセスされていると友人が教えてくれました。聞きました。かなしくて、繰り返しては聞けませんでした。

お母さんに虐待され、殺されて棄てられた男の子が「(それでも)僕はママが大好きだよ」と歌っている紙芝居です。
学生時代、バークレーの弁護士事務所でボランティアをしていた娘が毎日言っていました。「子どもってね、すごく虐待されていても、それでも虐待しているお父さんやお母さんが『大好き』なの。だから、絶対に親を悪く言わないの。みんな、自分が悪いんだって言うの。だからね、どうやって助けたらいいか・・・プロでもわからないことがあるんだよ。悲しすぎるよね」
日本で、親による子どもの虐待がそれまでのメディア社会面のニュースの枠を超え、文学の世界で大きな話題となったのは天童荒太さんの「永遠の仔」がベストセラーになった1999年から2000年頃からでしょうか。
「巣鴨子ども置き去り事件(1988年)」を映画化した是枝裕和監督の「誰も知らない」で長男役を演じた柳楽優弥さんが第57回カンヌ国際映画祭で史上最年少および日本人として初めての最優秀主演男優賞を獲得し、世界的な話題となったのが2004年です。この映画はアメリカでも "Netflix" で見られます。

アメリカは社会問題山積の国ですから、「追いつめられたときのホットライン」があります。UNITED WAYが開設しているダイヤル211です(上の写真)。
「困ったことがあったら211に電話して!」とテレビでも新聞でも街角のポスターでも広告しています。「この番号に電話してください。食事でも、寝るところでも、医療(保険)でも、高齢者ケアでも、子どもの保護でも、職業訓練でも、法律相談でも、どんな相談にも応じます」という、まさに万能(One Stop for All)ホットラインです。
アメリカでは、子どもの人権と安全のために必要だとみなされた場合、生みの親であっても親権を剥奪される場合があり、そのような場合には、子どもは強制的に親と隔離された安全な場所に保護されます。"Families Change" は、そういう強制措置によって保護された子どもたちの現実を、子どもにもわかるように書かれた絵本です。