
アメリカでも日本でも『5月の第2日曜日』が母の日(Mother's Day)。今年は5月8日ですね。母の日は世界各国で祝われていますが、実は、国により、起源/由来また日付に違いがあるそうで(参照:wikipedia「母の日の由来」)スペインやポルトガルでは5月最初の日曜ですが、スウェーデンでは5月最後の日曜日。同じ北欧でもノルウェーでは2月の第2日曜日なのだそうです。
母の日の朝、アメリカの家庭では子どもたちがブランチを作ってお母さんのベッドまで運んできます。お母さんはパジャマのまま、ベッドで新聞や本を読んだり、テレビを見たりしながら待っています。こぼさないかしら?などと、内心ではひやひや……。でも、この日ばかりは、絶対に起きていかない!のが鉄則。
大きくなった娘や息子は、お母さんをブランチに誘い出します。評判のお店は早くから予約でいっぱいになり、レストランやカフェは、ミモザ(オレンジジュースで割ったシャンペン)を添えた"母の日スペシャル"で大歓迎します。
消費大国アメリカでは言わずもがな、母の日は『消費の増加する日』のひとつです。花とともに、カードが飛ぶように売れるので、『”母の日”とは”ホールマーク(Hallmark:大手カード会社)の日”』などと揶揄されたこともあるとか。時代は遷っても、カードを贈る伝統は生きていますが、最近ではeメールで送る”電子カード”で写真も声も音楽も画像まで贈れるようになりました。かつては『長距離電話回線が込み合う日』のひとつと言われたものですが、今日ではSkypeなのでしょうか?
さて、今週は母の日に読みたい絵本の特集です。
お留守番の心細さを覚えていますか?「すぐ帰ってくるからね」と言われたのですが、待っていると、その”すぐ”の長いこと! 永遠のように感じられました。そんなお留守番している子どもの心境……暗く静まり返った夜の森の木のほらにある巣の中で、お母さんの帰りを待つフクロウきょうだいを、けなげで可愛い会話だけで描き出しているのが『Owl Babies』です。イラストもお話もすばらしい作品です。このブログで、読者の反響が最も大きかった絵本のひとつでもあります。
お留守番の寂しさ、心細さは、保育園のこどもたちも同じです。お母さんはお仕事だとわかっていても、友達だってたくさんいるんだけれども、でも、時々ちょっと泣きたくなったりもします。そうして誰かが泣き出すと、最初は慰めていた他の子もだんだん悲しくなって一緒になって泣き出してしまう……なんてこともよくあります。そうして最後は皆に伝染して……みんな揃って、あ~ん!あん! あんまり泣いたら、涙の海で、子どもたちはお魚になっちゃった……という、ちょっとシュールな絵本は、日本の作家せなけいこさんの作品で、英訳『Wah, Wah』もあります。でも、大丈夫! 仕事帰りのスーツ姿のお母さんが、しっかり網で救い出して助けてくれます!
お留守番は時にはちょっと寂しいけれど、子どもたちにとって”はたらくお母さん”は、素敵でまぶしい憧れの存在でもあります。そう、ハイヒールはいたママはかっこいい!のです。『Mommy's High Heel Shoes』は、表紙の絵を見るたびに子育て時代が思い起こされて、微笑ましく思う気持ちに、ちょっと苦笑が混じります。赤ちゃんを抱っこしながらお姉ちゃんの手を引き、仕事鞄やハンドバッグと子どもの荷物をまとめてもって、おまけに犬のリーシュまでしっかり引いているお母さんに、思わず「がんばってね!」って声をかけたくなります。
「アメリカ中のお母さんが泣いた」と言われている絵本が『Love You Forever』です。ひとりっ子のお母さんは、彼がまだ赤ちゃんの時にはもちろん、いたずらっ子で手を焼かせたときにも、うるさくて汚し屋のティーンエイジャー時代にも、おとなの男の人になってからも、毎日毎晩、眠っている彼を膝に抱きあげ「ずっとずっと大好きよ(I love you forever)」と囁きかけて育てました。でもある日、年をとったお母さんはもう彼のところに行けなくなってしまった自分に気づいて、その子に電話します。「もう行かれないの。だから今度はあなたが訪ねてきて……」 いまでは自分もお父さんになっている男の子は、お母さんを訪ねます。そうして、いつのまにか小さくなってしまったお母さんを、これまでお母さんが彼にしてくれたように膝に抱き上げて「ずっとずっと大好きだよ(I love you forever)」と囁くのでした。なんの衒いもない、素朴なまでにストレートな、お母さんの愛情に満ち満ちた絵本です。
でも、お母さんとは因果な商売で、いつもいつも「あなたが大好きよ」とやさしく囁いてばかりではいられないのが辛いところです。子どもを可愛いと思うほど、育てる責任も重く感じるもの。その結果、現実は「愛してるわ」どころか、むしろ一日中、子どもを追い回しては「だめ!」「いけません!」「やめなさい!」と叫んでいた……なんてことも。絵本『No, David!』は、そんなお母さんと子どもの毎日を、子どもの視線から描いて大人気。それもそのはず。実はこの絵本は、自身がいたずらっ子だった作家のデイビッドが、"David"と"No"の二つの単語しか綴れない幼い時代に描いた一連の絵が元になった作品。それらの絵を、デイビッドが成長してアーティストになるまで大切にとっておいたお母さんとのコラボレーションの作品でもあります。
やさしいお母さんと毎日楽しく過ごす子どもたちが、おうちを離れて幼稚園や学校に行くことに抵抗があるのは、むしろ自然なことかもしれません。それまでなんでも「そうね、そうね」と受け入れてくれたおかあさんも、学校のことになると妥協せず、甘ったれな子どもたちを驚かせます。学校に行きたくない子を、叱りはしないけれども、やさしいままに毅然として送り出す……『The Kissing Hand』のアライグマお母さんはななかのロールモデルです。それから、そう『Splat, the Cat』のお母さんも、なかなかお見事ですね。
さて最後は、お母さんと子どものいかにも楽しいかかわり---”かくれんぼ”を描いて大人気の絵本です。いたずら子犬のスポットが、あちこちに隠れてはいなくなってしまうのを「あら、スポットはどこかしら?」と言って、お母さんが探してくれるというお話です『Where's Spot?』。子どもは「あれ、どこへ行っちゃったかな?」と探してもらうのが大好きです。「ここかな?」「あっちかな?」「あれ、いないなぁ」などと、わざと時間をかけて探しまわる振りをしてやると、もう嬉しくて嬉しくてくすくす笑いを我慢できないくらい。そんな情景は、幼いときの一時期。かくれんぼが大好きな頃の、親子の楽しい思い出です。子育て真っ最中のお母さんはきっと、「探して、探して」と言われることに、時々うんざりしているととも思いますが、でも、そう言われるうちに大いに楽しんでおいてください。子どもはすぐに大きくなって、かくれんぼの鬼のことなどすっかり忘れて、どこかに行ってしまいますから。
子どもを持つと、母の日は『祝われる日』になってしまいます。でも、そんなお母さんにも、やっぱりお母さんがいます。子育てで忙しいお母さんたち、あなた自身もお母さんの小さな娘だった頃を思い出して、今年の母の日には、お母さんに絵本を贈ってみるのはいかがですか?
















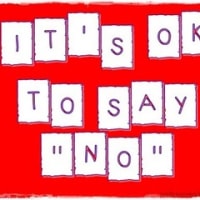
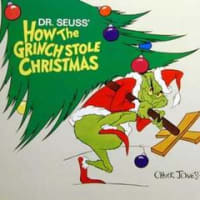

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます