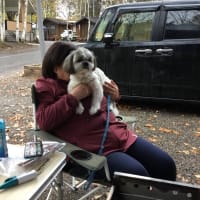その頃ヨアンナは前年までのロシア革命後の混乱と当時の革命ロシアの有力政治勢力であるボリシェヴィキ、メンシェヴィキ間の政争やその後の反革命軍(白軍)との闘争で無人と化し、荒れた農場の無人の小屋に、ヨアンナを世話してきた2家族6人と身を寄せていた。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
※ ボリシェビキ:ロシア一国の単独革命を目指す一派。
メンシェビキ:世界同時革命により、世界中を共産主義化しようという一派。
反革命軍(白軍):革命側(赤軍)に対し、ボリシェヴィキの10月革命に反
対する一派。但し白軍はその10月革命以前のロシア革命の発端となった2月革
命には反対していない。
なので、正確には反革命軍という名称は当たらない。反ボリシェヴィキ軍と
呼ぶべきである。
最終的にはボリシェヴィキが勝利し、盟主レーニンの死後、後釜に悪名高いス
ターリンが座り、恐怖による独裁政権を確立、ドイツ・ナチスのヒトラーより
多くの国民や征服した外国人を殺戮、悪政の限りをつくした。
因みに、世界一多くの人類を虐殺したのは、けた違いのダントツ一番である中
国共産党の毛沢東です。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
その家族はヨアンナの父の最後を目撃したが助ける事も出来ず、結果、見殺しにしてしまった罪の意識から、残されたヨアンナを成り行き上、連れ歩いたのだった。
そんなある日の午後、一脚の馬車が小屋の前で止まった。
少しの間、何やら話す声が聞こえ、粗末なドアがノックされた。
部屋の中の誰もが固唾を呑んだ。
もう一度強めのノックに勇気を出して返事をした。
「ここにポーランドからの孤児がいると聞いてやってきた。
もし居るのなら助けに来たのでドアを開けてほしい!」
ロシア語ではなくポートランド語が聞こえた。
助けとの言葉に反応し、急いでドアを開けると、ふたりの男が立っていた。
ひとりはポーランド人、ひとりは軍服を着た東洋人。
ポーランド人は極東救済委員会のメンバーのひとりで、孤児の捜索と通訳を兼ね同行していた。
彼が手短にここに来た事情を伝え、ヨアンナを連れ出すのを納得させた。
残る家族に当面の食料と金を残し、納得させた上で。
しかしヨアンナの目は不安で一杯だった。
私に用なの?
何処に連れて行くの?
お母さん、お父さん助けて!!
心の中で叫んだ。
東洋の軍人さんは怖そうだったが、救済委員会の人は跪きヨアンナに優しく語りかけた。
「お嬢さんの名前はヨアンナって言うんだね?
おじさんはロベルト。
ヨアンナを助けに来たんだ。もう大丈夫。
何も心配は要らないよ。
おじさんたちと一緒に食べ物の心配のいらない所に行こう。
可愛そうに・・・・、お腹が空いているだろう?
いつから食べていないの?」
「昨日のお昼。」
「じゃあ、昨日の夜も、今日の朝も何も食べていないんだね?」
ウンと頷いた。
軍人さんがヨアンナを馬車に乗せると、用意してあったパンとミルクを与えた。
馬車が走り出し、次第に小屋から遠ざかる。
とうとうヨアンナにとって、知っている人が誰もいない孤独な旅が始まった。
数日かけイルクーツクの日本軍の駐屯所からウラジオストクの救済委員会が手配した宿泊所などに泊まる。
数日後次第に集結した孤児たちで賑やかさが増すと、日本行きの船の出航の準備が整った。
その孤児たちの中に、ヨアンナと同い年のエヴァという少女がいた。
エヴァは酷くやせ細ってはいるが、透き通った青い目が人懐っこさを湛え、ヨアンナの一番の友達になれそうな予感を持たせてくれる。
「おはよう、ヨアンナ!昨日のオートミールも美味しかったけど、今朝のご飯も
良い匂いがするね。
楽しみだわぁ・・・、今朝のメニューは何かしら?」
満面の笑みで語りかけてくるエヴァは、もう何年も前からのヨアンナの友であるかのように、自然に接する術を持っているようだ。
「フフフ、エヴァったら、頭の中は食べ物でいっぱいなのね。
でも昨日のオートミールは半分も食べられず残したじゃない?
今朝のご飯だってチャンと食べられるかどうか分かんないでしょ?」
「だって私、今までいつもほんの少ししか食べていなかったでしょ?
お腹がびっくりしてそんなに食べられないじゃない。
でも、今まで食べた中で一番美味しかったのはホントよ!
ああ、あんな幸せな食べ物を毎日食べられるのだったら、私の身体は全部食べ物で出来ていても良いわ。
ねぇヨアンナ、そう思わない?」
「・・・・・思わない・・・・。」
そしてヨアンナはもう一人、奇跡の出会いをその宿泊所で果たした。
それは近所の家にいたあの「いたずらヤン」である。
彼はヨアンナを見つけると、目を見開き、クシャクシャな笑顔で、とても嬉しそうな顔になった。
しかし彼は重いチフスに罹り床に伏している。
彼には渡航は無理であるのが誰の目にも一目瞭然だった。
彼をここまで連れてきたのは、せめて最後くらいはできるだけ手厚い看護と、同世代の孤児達と触れ合えば、きっと元気が貰えるだろうとの児童救済委員会と日本の捜索隊の温情と気配りの特別なもてなしの結果であった。
彼は力なく言う。
「ヨアンナ、ごめんよ。僕・・・。
ヨアンナにまた会えてうれしいよ。
元気になったら、僕、ヨアンナと遊びたいな。
ごめんね、いつも意地悪ばかりして。」
ヨアンナはあの日までの嫌なことを一瞬で忘れた。
そして今、唯一よく知っていた人に会えたことを素直に喜んで、
「また会えてよかったわ。
ヤン、一緒にお船に乗れるのね。」
・・・だがそれは叶わなかった。
ヤンにとってウラジオストクが短い人生最後の地となった。
それを知らないヨアンナは未知の不安と希望に満ちた日本行きの船に乗る。
つづく