(いま書いてる同人誌『栗本薫全著作レビュー JUNE・BL篇』のために書いた文章ですが、よく考えたらこの本の感想アップしてなかったし、全体的にはこういう感じに書き直してますよ、というサンプル代わりに読むといいです)
今作は九五年より連続刊行されたJUNE全集(全十二巻)の第一巻である。当然のようにトップバッターであるのは貫禄というべきか。
この全集は『JUNE』および『小説JUNE』に掲載された各作家の作品のうち、代表的なものと単行本未収録作品を中心に編集されたもので、この栗本薫の巻に関しても単行本未収録作が多く収録されている。
しかしこと栗本薫に関しては、単行本未収録だったのには長さやタイミングの他にもやんごとなきくだらない理由がある。
というのも初期JUNEは作家の層が薄く、漫画家は二十四年組界隈がいたのでまだしも、小説家に関しては榊原姿保美のデビューや吉原理恵子の成長を待たねばならず、ひっじょ~~に人材が不足していた。そこでJUNE編集部および栗本薫がどうしたかと云うと、栗本薫が変名で一人何役もこなす、というふざけた、もとい面白いことをしたのだ。そんなわけでこの全集にはその変名で書かれた作品を中心に収録されている。
巻末には雑誌掲載時に使用された挿絵の数々がしっかり収録されているのも全集ならでは。
フランスの詩人ジュスティーヌ・セリエが書き、あかぎはるなが訳したという設定になっている作品群は、もう作者名からしてわかるように竹宮恵子の『風と木の詩』のオマージュというかパロディというかそういう話はがりで、挿絵も当然のごとく竹宮恵子が担当している。まあ初期のJUNEはこれに限らずけーこたんと薫ばっかりだったんだけどね。
『薔薇十字館』は日本の画家が肖像画を描く事を請われて訪れた薔薇十字館という貴族邸で、天使か悪魔のように美しく、そしてお約束のように色キチガイな双児に出会う話。まずタイトルのルビが「シャトー・ド・ロゼクロワ」という時点で素敵すぎるし、文中でも牧神(フォーヌと読みます)だ半獣神(サテュロスだってお)と素敵な単語が頻発するのでもうノックアウトされざるを得ない。
『DOMINIUEQ』は子爵家の若い子息ラウールが、気まぐれで訪れた場末の見世物小屋で見つけた少年ドミニクにたちまち恋をしていろいろあってみんな死ぬ話。ラウール・ド・モリニャックだのアンリ・セバンチャン・ラファルジュだの素敵すぎる名前ばかりで、そしてその名前をこれ見よがしにフルネームで連呼するのがたまらない。
『聖三角形』はともに良家の子息であり良きライバルでもあったモーリスとサン=ジャンが、ジプシーの血をひく少年ポールをめぐって争い、いろいろあってレイプしてみんな死ぬ話。いろいろあってみんな死ぬで説明できるのが栗本JUNEのいいところですね。
作品そのものよりも付記として「原題は~~だがそのまま訳してもわかりにくいので意訳した」「ジュスティーヌ・セリエは大学に入った」「いま処女長編を連載中らしい」などもっともらしいことを書いてあるのがうける。
『獣人』は近所の店によく来る少年ジュリアンに恋してしまったけど、とんだ淫乱だって噂をきいて家までつけていったらせむし男みたいなのとチュッチュッしてたので思わず殺したよ、という話。これのみは竹宮恵子風というよりは受けがジルベールなだけでストーリーは栗本薫のいつものだった。そのせいでジュスティーヌ作品の中ではあまり笑えない。慣れてるから。
自殺したアメリカの作家アラン・ラトクリフ作という設定の『鍵のかかる部屋』は、旅の美青年を閉じこめて調教する老人の話。気持ち悪い変態性犯罪者であるところの老人が、本当に気持ち悪い。しゃべったらダメ、人間じゃなくて獣として蜘蛛と蝶の捕食関係じゃないと嫌、と終始無言でハードプレイを押しつけ、苦しんでいる姿をみては「かわいそうに」とフル勃起する姿はまさに美学をもった最強の変態。あまりにも一方的で気持ち悪くて目が離せない魅力がある短編。ほんに不細工ストーカーの内面を描かせたら栗本先生の右に出る者はおらへんでぇ。
文体もこだわりを感じられる抑えた筆致が変態的で素晴らしく、ストーリー的には逃げられる理由がうっかり寝て鍵とられた、というのがあまりにもやっつけではあるが、勝手にSMプレイをやり返してもらえるとワクテカしてたら、期待とまったくちがう復讐をされるラストまで綺麗におとめている。
そして最後に書かれたアラン・ラトクリフの爆笑せざるを得ない経歴まで含めて、見事にやりきった感のある一作。
神谷敬里は妻子あるリアルホモという設定。
『少年――展覧会の絵より――』は身体の弱い少年が、やたらと自分をいじめてくるマッチョな同級生の、自分と正反対の脳筋具合に惹かれていたら、意外と繊細で憎くなる話。肉体的強者への憧れと屈託が、乙女チックなリアルホモっぽい。
『棘――展覧会の絵より――』は怪人赤マントと噂されている近所の物静かな学生の家に連れ込まれ、いろんなところペロペロされたけど、結核のその青年から「死」の暗さと魅力を教えられて、ぼく大人になっちゃった、という話。「あー、はいはい」という感じで、特に感想らしい感想は抱かなかった。
『松虫』は殿が死にそうで殿大好きな小姓が思いつめてて、その小姓大好きな若者も思いつめてて、とりあえずぐだぐだ云って小姓を押し倒した話。やたら短くストーリーらしいストーリーもないので、やはり「あー、はいはい」としか思わなかった。
『稚児』は昭和初期の旧制学校を舞台とした、病弱な主人公が傲慢な転校生に出会うなり突然「お前は僕の稚児になれ」と云われストーキングされたり調教されたり心中未遂したりする中編。文体もストーリーも栗本薫そのものであり、これでごまかせると思っていたのだろうかと疑問に思わないでもないが、いつもの栗本薫だし古い作品なので文体も崩れておらず、それなりに面白い。
改めて読むと、舞台設定こそ大きくちがうが、『終わりのないラブソング』の原型であったのかと思わせる部分が多い。ことにだれよりも傲慢でひどく凶暴でめちゃくちゃ我侭だが、じつは傷つきやすく不器用で可哀相な攻めの鷹彦は、連載初期の竜一そのまんまと云ってもいい。
ようやく二人が愛に目覚めて逃避行をはじめるが、はじめて早々に「どこに行けばいいのかわからんしやりようもない」と途方に暮れるのも同じで、そこからさっさと心中にいって終わらせてしまうのも栗本薫いつものアレ。ただし未遂に終わって、生き残った主人公の独白で終わるのはなかなか悪くない。
おわラブの場合、途方に暮れてから心中したり殺したりせず、その先を書こうとしたがそんな力量も作品構想もまったくなかったので残念なことになったんだよなあ……
『特別手記 ある同性愛者の告白』は、タイトルの通り作者のホモ生活の告白手記。当然、中の人が栗本薫だということを知って読むとアホらしいなんちゃって告白手記にしか読めないが、したり顔で「女性の書くJUNEはアナル・セックスを重視するが僕をはじめとして関係をもった人のほとんどはペニス重視で、入れてこようとはしなかった」みたいなことを語っているのが微笑ましくて、ある意味面白い。「彼の名を書くことはできない。というのは、彼は、名を言えば誰でも知っている有名な歌手で、俳優でもある男だからだ」とか、存在もしない相手のことをよくもまあ書くものだと、アホらしさに感心してしまう。
手記の大筋はただ一人だけ強引にAセックスしてきたサドがいて、ドMに目覚めそうで怖かったから逃げたという、栗本薫が年がら年中書いてる「強引なセックスこそが真実の愛、でもそんなの怖い」とまったく同じ。
こういうところ、栗本薫は女性的ではなくいじめられっ子の男みたいな感覚があるので、意外と男設定の方がしっくりくるかもしれない。まあその後を書くと受けがお姫さま化するので、いずれにしろ支離滅裂になりますが。
滝沢美女夜の二作は『元禄心中記』に収録されているのでそちらの項で扱った。ちなみに美女夜という名前は木原敏江の漫画『摩利と新吾』に出てきた美女の名前からとっている。好きな漫画の美女から名前をとるとか、いろんな意味で神経が図太すぎてとうてい真似できない荒業だ。
同じく沙羅の『元禄無頼』は独立して単行本化しているのでそちらの項へ。
栗本薫名義の五作はいずれも『小説道場Ⅲ 実践篇』に収録されたのでそちらの項へ
中島梓名義の『悪徳の栄え「哀しきチェイサー」始末記』は二ページの短いエッセイ。『七人の刑事』という往年のテレビドラマで、栗本薫の小説を原作として栗本薫自身が脚本を書いた「哀しきチェイサー」という回があり、これの収録現場がどれだけ楽しかったか、というエッセイ。
このドラマ自体は自分は未視聴だが、原作だと二人組のチンピラが騙されて野垂れ死ぬ話で、基本的にはそのまんまのストーリーのようだ。その二人組の兄貴分を内田裕也が、弟分を沢田研二が演ずるという、両者のカップリングに萌え萌えだった栗本薫にとって夢のようなドラマであったので、とにかく「ひわーいやらしーいいかがわしーい」といいまくっているだけのエッセイだ。しかしこの頃はエッセイの一人称が「ぼく」で男ぶっていた時代だつたので、なとも云えない変な感じになっている。が、基本的には無邪気な萌え萌えエッセイであって微笑ましい。そりゃ自分のホモ小説を理想のカップリングで映像化されて悶えない腐女子などおるまい。
『ハムレット』は中島梓が脚本を手がけた舞台『ロックオペラ ハムレット』より、お気に入りのシーンのセリフを抜き出して、竹宮恵子のイラストをつけた六ページばかりのもの。舞台の方は観たことがないが、これを読むかぎり、いつもの栗本作品のようにハムレットを特別な輝ける存在と解釈し、ホレーシオもオフィーリアもとにかくハムレット周囲の人間すべてが「ハムレット、おおなんという……」と始終うめきつづけている、そんな作品としか受け取れない。
『美少年学入門[第一回~第四回]』と『中島梓の小説道場[第一回]』はそれぞれが続きの分と合わせて単行本化しているので、『栗本薫全著作レビュー 中島梓篇』にて紹介することにする。
『世界&日本JUNE文学リスト あかぎはるな編』は、ある意味この全集の目玉と云ってもいいかもしれない堂々たるリスト。まだ名前も『コミックJUN』であったJUNE創刊二号、三号に収録されたこのリストは、JUNE的なるものが一般化されていない時代に、若かりし中島梓が読みまくり調べまくった少年愛作品の紹介リストだ。
ただタイトルを羅列するのみでなく、それぞれを「必読」「マニア向け」「ちょっとだけJUNEシーン」「入手困難」「読まないでもいいホモポルノ」とランク分けし、短い文章の中で鮮やかに軽やかに紹介している。
七十年代以前、市民権を得ていなかった腐女子たちがどのような作品からどのような萌えを得ていたのか、どれほどささいな萌えホモポイントを逃さなかったか、その苦労と歴史を感じる資料として当時よりもなお貴重なリストではなかろうか。
いま見直してもこの読書量と文学少女ぶり、にも関わらず出てくる言葉と論じている内容の低俗的で読みやすいことには、憧れを感じざるを得ない。
小冊子のエッセイ『解放区』の頃は、JUNE創生期の普通の思い出話が三ページほど。JUNEの名物の一つとして長いこと続いた、恥ずかしいポエムがたくさん載っているコーナー「黄昏詞華館」もまた、栗本薫が作ったコーナーであり、初期には栗本薫作のポエムばかりであったという衝撃の事実が語られている。
そういうことも含め、当時のJUNEがプロの作家たちがほかではできないことを好き勝手にやっている同人誌めいた場所であり、それゆえに楽しかったし、いまのアナーキズムを失ったJUNEはなんか違うな、というお話。
あかぎはるなによる神谷敬里、石原豪人、中島梓へのインタビューは、栗本薫のなりきりがばかばかしく、同一人物であるということを知って読むと、中島梓が「はるなちゃん」と親しげな先輩面で呼びかけている姿は白々しく、また純代少女の一人遊びっぷりがしのばれて、なんか可哀想な気すらしてくる。ちなみに唯一の別人である石原豪人へのインタビューはしごく短い。
ちなみにこれ以外にも、JUNE本誌ではサングラスをかけた神谷敬里のインタビューなどもあり、栗本薫のかっこうの遊び場となっていたことがよくわかる。しかしこういうお遊びは大好きだ。なによりプロが忙しい中で全力を出して遊んでいる感じがいい。
ジュスティーヌ・セリエの経歴はアホらしいの一言。「第二詩集ビジュウ・ノワール」「ル・シャトー・ド・ロゼクロア」「セリ・ロゼ新人短編賞」など、なめきった造語の数々が非常に素晴らしい。栗本薫のネーミングセンスは、本気を出すとダサいだけだが、お遊びの時にはやたらいいセンスを発揮することがあるのを忘れてはならない。
栗本薫の一人特集号ともいえる全集だが、やはりJUNEの中心は栗本薫であったのだな、ということがよくわかるほど、JUNEのいろいろな面が堪能できる素晴らしい、というか愉快な全集に仕上がっている。
定価が三五〇〇円もし、また流通量が少ないためいまさら手に入りにくい本ではあるが、興味のある方は他の巻ともども、なんとかして読んでみてほしい。

今作は九五年より連続刊行されたJUNE全集(全十二巻)の第一巻である。当然のようにトップバッターであるのは貫禄というべきか。
この全集は『JUNE』および『小説JUNE』に掲載された各作家の作品のうち、代表的なものと単行本未収録作品を中心に編集されたもので、この栗本薫の巻に関しても単行本未収録作が多く収録されている。
しかしこと栗本薫に関しては、単行本未収録だったのには長さやタイミングの他にもやんごとなきくだらない理由がある。
というのも初期JUNEは作家の層が薄く、漫画家は二十四年組界隈がいたのでまだしも、小説家に関しては榊原姿保美のデビューや吉原理恵子の成長を待たねばならず、ひっじょ~~に人材が不足していた。そこでJUNE編集部および栗本薫がどうしたかと云うと、栗本薫が変名で一人何役もこなす、というふざけた、もとい面白いことをしたのだ。そんなわけでこの全集にはその変名で書かれた作品を中心に収録されている。
巻末には雑誌掲載時に使用された挿絵の数々がしっかり収録されているのも全集ならでは。
フランスの詩人ジュスティーヌ・セリエが書き、あかぎはるなが訳したという設定になっている作品群は、もう作者名からしてわかるように竹宮恵子の『風と木の詩』のオマージュというかパロディというかそういう話はがりで、挿絵も当然のごとく竹宮恵子が担当している。まあ初期のJUNEはこれに限らずけーこたんと薫ばっかりだったんだけどね。
『薔薇十字館』は日本の画家が肖像画を描く事を請われて訪れた薔薇十字館という貴族邸で、天使か悪魔のように美しく、そしてお約束のように色キチガイな双児に出会う話。まずタイトルのルビが「シャトー・ド・ロゼクロワ」という時点で素敵すぎるし、文中でも牧神(フォーヌと読みます)だ半獣神(サテュロスだってお)と素敵な単語が頻発するのでもうノックアウトされざるを得ない。
『DOMINIUEQ』は子爵家の若い子息ラウールが、気まぐれで訪れた場末の見世物小屋で見つけた少年ドミニクにたちまち恋をしていろいろあってみんな死ぬ話。ラウール・ド・モリニャックだのアンリ・セバンチャン・ラファルジュだの素敵すぎる名前ばかりで、そしてその名前をこれ見よがしにフルネームで連呼するのがたまらない。
『聖三角形』はともに良家の子息であり良きライバルでもあったモーリスとサン=ジャンが、ジプシーの血をひく少年ポールをめぐって争い、いろいろあってレイプしてみんな死ぬ話。いろいろあってみんな死ぬで説明できるのが栗本JUNEのいいところですね。
作品そのものよりも付記として「原題は~~だがそのまま訳してもわかりにくいので意訳した」「ジュスティーヌ・セリエは大学に入った」「いま処女長編を連載中らしい」などもっともらしいことを書いてあるのがうける。
『獣人』は近所の店によく来る少年ジュリアンに恋してしまったけど、とんだ淫乱だって噂をきいて家までつけていったらせむし男みたいなのとチュッチュッしてたので思わず殺したよ、という話。これのみは竹宮恵子風というよりは受けがジルベールなだけでストーリーは栗本薫のいつものだった。そのせいでジュスティーヌ作品の中ではあまり笑えない。慣れてるから。
自殺したアメリカの作家アラン・ラトクリフ作という設定の『鍵のかかる部屋』は、旅の美青年を閉じこめて調教する老人の話。気持ち悪い変態性犯罪者であるところの老人が、本当に気持ち悪い。しゃべったらダメ、人間じゃなくて獣として蜘蛛と蝶の捕食関係じゃないと嫌、と終始無言でハードプレイを押しつけ、苦しんでいる姿をみては「かわいそうに」とフル勃起する姿はまさに美学をもった最強の変態。あまりにも一方的で気持ち悪くて目が離せない魅力がある短編。ほんに不細工ストーカーの内面を描かせたら栗本先生の右に出る者はおらへんでぇ。
文体もこだわりを感じられる抑えた筆致が変態的で素晴らしく、ストーリー的には逃げられる理由がうっかり寝て鍵とられた、というのがあまりにもやっつけではあるが、勝手にSMプレイをやり返してもらえるとワクテカしてたら、期待とまったくちがう復讐をされるラストまで綺麗におとめている。
そして最後に書かれたアラン・ラトクリフの爆笑せざるを得ない経歴まで含めて、見事にやりきった感のある一作。
神谷敬里は妻子あるリアルホモという設定。
『少年――展覧会の絵より――』は身体の弱い少年が、やたらと自分をいじめてくるマッチョな同級生の、自分と正反対の脳筋具合に惹かれていたら、意外と繊細で憎くなる話。肉体的強者への憧れと屈託が、乙女チックなリアルホモっぽい。
『棘――展覧会の絵より――』は怪人赤マントと噂されている近所の物静かな学生の家に連れ込まれ、いろんなところペロペロされたけど、結核のその青年から「死」の暗さと魅力を教えられて、ぼく大人になっちゃった、という話。「あー、はいはい」という感じで、特に感想らしい感想は抱かなかった。
『松虫』は殿が死にそうで殿大好きな小姓が思いつめてて、その小姓大好きな若者も思いつめてて、とりあえずぐだぐだ云って小姓を押し倒した話。やたら短くストーリーらしいストーリーもないので、やはり「あー、はいはい」としか思わなかった。
『稚児』は昭和初期の旧制学校を舞台とした、病弱な主人公が傲慢な転校生に出会うなり突然「お前は僕の稚児になれ」と云われストーキングされたり調教されたり心中未遂したりする中編。文体もストーリーも栗本薫そのものであり、これでごまかせると思っていたのだろうかと疑問に思わないでもないが、いつもの栗本薫だし古い作品なので文体も崩れておらず、それなりに面白い。
改めて読むと、舞台設定こそ大きくちがうが、『終わりのないラブソング』の原型であったのかと思わせる部分が多い。ことにだれよりも傲慢でひどく凶暴でめちゃくちゃ我侭だが、じつは傷つきやすく不器用で可哀相な攻めの鷹彦は、連載初期の竜一そのまんまと云ってもいい。
ようやく二人が愛に目覚めて逃避行をはじめるが、はじめて早々に「どこに行けばいいのかわからんしやりようもない」と途方に暮れるのも同じで、そこからさっさと心中にいって終わらせてしまうのも栗本薫いつものアレ。ただし未遂に終わって、生き残った主人公の独白で終わるのはなかなか悪くない。
おわラブの場合、途方に暮れてから心中したり殺したりせず、その先を書こうとしたがそんな力量も作品構想もまったくなかったので残念なことになったんだよなあ……
『特別手記 ある同性愛者の告白』は、タイトルの通り作者のホモ生活の告白手記。当然、中の人が栗本薫だということを知って読むとアホらしいなんちゃって告白手記にしか読めないが、したり顔で「女性の書くJUNEはアナル・セックスを重視するが僕をはじめとして関係をもった人のほとんどはペニス重視で、入れてこようとはしなかった」みたいなことを語っているのが微笑ましくて、ある意味面白い。「彼の名を書くことはできない。というのは、彼は、名を言えば誰でも知っている有名な歌手で、俳優でもある男だからだ」とか、存在もしない相手のことをよくもまあ書くものだと、アホらしさに感心してしまう。
手記の大筋はただ一人だけ強引にAセックスしてきたサドがいて、ドMに目覚めそうで怖かったから逃げたという、栗本薫が年がら年中書いてる「強引なセックスこそが真実の愛、でもそんなの怖い」とまったく同じ。
こういうところ、栗本薫は女性的ではなくいじめられっ子の男みたいな感覚があるので、意外と男設定の方がしっくりくるかもしれない。まあその後を書くと受けがお姫さま化するので、いずれにしろ支離滅裂になりますが。
滝沢美女夜の二作は『元禄心中記』に収録されているのでそちらの項で扱った。ちなみに美女夜という名前は木原敏江の漫画『摩利と新吾』に出てきた美女の名前からとっている。好きな漫画の美女から名前をとるとか、いろんな意味で神経が図太すぎてとうてい真似できない荒業だ。
同じく沙羅の『元禄無頼』は独立して単行本化しているのでそちらの項へ。
栗本薫名義の五作はいずれも『小説道場Ⅲ 実践篇』に収録されたのでそちらの項へ
中島梓名義の『悪徳の栄え「哀しきチェイサー」始末記』は二ページの短いエッセイ。『七人の刑事』という往年のテレビドラマで、栗本薫の小説を原作として栗本薫自身が脚本を書いた「哀しきチェイサー」という回があり、これの収録現場がどれだけ楽しかったか、というエッセイ。
このドラマ自体は自分は未視聴だが、原作だと二人組のチンピラが騙されて野垂れ死ぬ話で、基本的にはそのまんまのストーリーのようだ。その二人組の兄貴分を内田裕也が、弟分を沢田研二が演ずるという、両者のカップリングに萌え萌えだった栗本薫にとって夢のようなドラマであったので、とにかく「ひわーいやらしーいいかがわしーい」といいまくっているだけのエッセイだ。しかしこの頃はエッセイの一人称が「ぼく」で男ぶっていた時代だつたので、なとも云えない変な感じになっている。が、基本的には無邪気な萌え萌えエッセイであって微笑ましい。そりゃ自分のホモ小説を理想のカップリングで映像化されて悶えない腐女子などおるまい。
『ハムレット』は中島梓が脚本を手がけた舞台『ロックオペラ ハムレット』より、お気に入りのシーンのセリフを抜き出して、竹宮恵子のイラストをつけた六ページばかりのもの。舞台の方は観たことがないが、これを読むかぎり、いつもの栗本作品のようにハムレットを特別な輝ける存在と解釈し、ホレーシオもオフィーリアもとにかくハムレット周囲の人間すべてが「ハムレット、おおなんという……」と始終うめきつづけている、そんな作品としか受け取れない。
『美少年学入門[第一回~第四回]』と『中島梓の小説道場[第一回]』はそれぞれが続きの分と合わせて単行本化しているので、『栗本薫全著作レビュー 中島梓篇』にて紹介することにする。
『世界&日本JUNE文学リスト あかぎはるな編』は、ある意味この全集の目玉と云ってもいいかもしれない堂々たるリスト。まだ名前も『コミックJUN』であったJUNE創刊二号、三号に収録されたこのリストは、JUNE的なるものが一般化されていない時代に、若かりし中島梓が読みまくり調べまくった少年愛作品の紹介リストだ。
ただタイトルを羅列するのみでなく、それぞれを「必読」「マニア向け」「ちょっとだけJUNEシーン」「入手困難」「読まないでもいいホモポルノ」とランク分けし、短い文章の中で鮮やかに軽やかに紹介している。
七十年代以前、市民権を得ていなかった腐女子たちがどのような作品からどのような萌えを得ていたのか、どれほどささいな萌えホモポイントを逃さなかったか、その苦労と歴史を感じる資料として当時よりもなお貴重なリストではなかろうか。
いま見直してもこの読書量と文学少女ぶり、にも関わらず出てくる言葉と論じている内容の低俗的で読みやすいことには、憧れを感じざるを得ない。
小冊子のエッセイ『解放区』の頃は、JUNE創生期の普通の思い出話が三ページほど。JUNEの名物の一つとして長いこと続いた、恥ずかしいポエムがたくさん載っているコーナー「黄昏詞華館」もまた、栗本薫が作ったコーナーであり、初期には栗本薫作のポエムばかりであったという衝撃の事実が語られている。
そういうことも含め、当時のJUNEがプロの作家たちがほかではできないことを好き勝手にやっている同人誌めいた場所であり、それゆえに楽しかったし、いまのアナーキズムを失ったJUNEはなんか違うな、というお話。
あかぎはるなによる神谷敬里、石原豪人、中島梓へのインタビューは、栗本薫のなりきりがばかばかしく、同一人物であるということを知って読むと、中島梓が「はるなちゃん」と親しげな先輩面で呼びかけている姿は白々しく、また純代少女の一人遊びっぷりがしのばれて、なんか可哀想な気すらしてくる。ちなみに唯一の別人である石原豪人へのインタビューはしごく短い。
ちなみにこれ以外にも、JUNE本誌ではサングラスをかけた神谷敬里のインタビューなどもあり、栗本薫のかっこうの遊び場となっていたことがよくわかる。しかしこういうお遊びは大好きだ。なによりプロが忙しい中で全力を出して遊んでいる感じがいい。
ジュスティーヌ・セリエの経歴はアホらしいの一言。「第二詩集ビジュウ・ノワール」「ル・シャトー・ド・ロゼクロア」「セリ・ロゼ新人短編賞」など、なめきった造語の数々が非常に素晴らしい。栗本薫のネーミングセンスは、本気を出すとダサいだけだが、お遊びの時にはやたらいいセンスを発揮することがあるのを忘れてはならない。
栗本薫の一人特集号ともいえる全集だが、やはりJUNEの中心は栗本薫であったのだな、ということがよくわかるほど、JUNEのいろいろな面が堪能できる素晴らしい、というか愉快な全集に仕上がっている。
定価が三五〇〇円もし、また流通量が少ないためいまさら手に入りにくい本ではあるが、興味のある方は他の巻ともども、なんとかして読んでみてほしい。













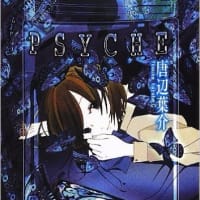







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます