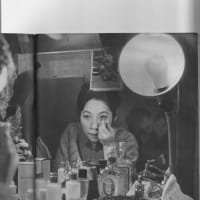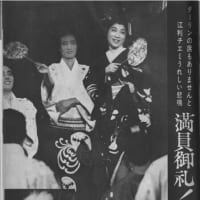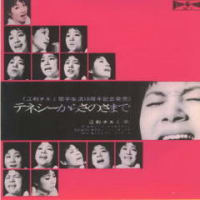![木遣りくずし [EPレコード 7inch] - 江利チエミ](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqG1CROubRnqp0a8lc9vDDS-lAY7AB0-ZjPxi7Xye_xu0wm9U4TgWke3wHS2oRWPNFsksEpgq_mqmVmsqSyg7ci7LhOhyFdxDzFUBYVtDvkAfwo8LKF6AjTRFPEJVogbdhDv4mxuUZYmlqg83lCUvBzGt3ZThxQVSSX3ufNQ7XrTK6P9BRdGb6MY4vF0HYTZemqkekV0_8ZSBF_28vJYy2-4-cFYXbZSco3cbCoCDJ8i5l8L9h8wy1hgv-cdrV9DJSSLEUQ6r11Zg2DE1w2TtavIw=/415rqd9v2yL._AC_SY355_.jpg)
木遣りとは 材木を掛け声をかけながら運ぶ事で その時に唄うのが[木遣り]です。それが 祭りの山車をひく時や祝儀の際にも唄われる様になっていった。
※わたしは川崎の下町生まれなので、お祭りの宮入だの、新築のタテマエだので、よく耳にして育ちましたが、山の手の方...には馴染みがないかもしれません。
「くずし」とは 調子を変えて陽気に演奏する事で この曲は幕末の頃 寄席で初代・三升屋勝次郎が唄い始めたと伝えられています。
初代の勝次郎師匠のことは詳しくわからないのですが、二代目三升家勝次郎師匠も偉大な方だったようです。
昭和に入り五代目古今亭志ん生が十八番にした「代わり目」は、大正期に音曲噺として新内、都々逸をまじえてこの2代目勝次郎師匠が演じていたものだった...とか。
※勝次郎師匠:寄席の「いろもの」の有名な芸人さん...です。
柳屋三亀松師匠、都家カツ江師匠、玉川スミ師匠...と同業。
ちなみに、この志ん生十八番「替わり目」とは、次のようなお噺です...
>ぐでんぐでんに酔っぱらって、
夜中に帰ってきた亭主。
途中で車屋をからかい、
家の門口で梶棒を上げさせたと思ったら、もう下りた。
出てきた女房はハラハラし、車屋に謝って帰ってもらうと、
ご近所迷惑だからいいかげんにしとくれと文句を言う。
亭主、聞かばこそ、てめえは口の聞きようが悪い、
寝酒を出さないから声が大きくなると、からむ。
しかたなく酒を注ぐと、今度は
何かサカナを出せと、しつこい。
「何もありません」
「コウコがあったろう」
「いただきました」
「佃煮」
「いただきました」
「納豆」
「いただきました」
「干物」
「いただきました」
「じゃあ……」
「いただきました」
うるさくてしかたがないので、夜明かしのおでん屋で何か見つくろってくるから
と、女房は出かける。
その間に、ちょうどうどん屋の屋台が通ったから、
酔っぱらいのかっこうの餌食に。
ずうずうしく燗を付けさせた挙げ句、
てめえは物騒ヅラだ、夜遅くまで火を担いで歩きやがって、
このへんにちょくちょくボヤがあるのはてめえの仕業だろう
と、からむので、うどん屋はあきれて帰ってしまう。
その次は、新内流し。
むりやり都々逸(どどいつ)を弾かせ、
どうせ近所にびた一文借りがあるわけじゃねえ
と、夜更けにいい気になって
「恋にこがれーてー、鳴く蝉よりもォ……」
と、うなっているところへ女房が帰ってくる。
ようすを聞いてかみさん、顔から火が出た。
外聞が悪いので、うどん屋の荷を見つけると、
「もし、うどん屋さーん」
「……おい、あそこの家で、おかみさんが呼んでるよ」
「へえ、どの家で?」
「あの、明かりがついてる家だ」
「あっ、あすこへは行かれません」
「なぜ?」
「今ごろ、お銚子の代わり目時分ですから」
木遣りくずしとは寄席から生まれ、お座敷でも歌い継がれた粋な江戸を代表する流行歌です。
前年昭和33年のチエミの民謡集の中のメイン楽曲:さのさ...の次にこの曲を江利チエミが二作目の民謡LP(チエミの民謡・Ⅱ)のメインに取り上げたのがよくわかる気がします。
♪格子造りに ご神燈下げて 兄貴ゃ家かと 姐御に問えば
兄貴ゃ二階で木遣りの稽古 音頭取るのは アリャ 家の人
エンヤ~ラ エンヤラヤ エンヤラヤレコノセー
サノセー アレワサ エンヤラヤー
※ちなみにこれまたチエミ十八番「深川くずし」の「くずし」も同じです。