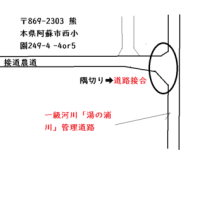※ 以下、校正は為して無いので誤字脱字、文章に誤りを見付けたら是非ご一報を。
魂 魄 の 宰 相 第三巻
四、諸家を兼ねる
王安石が全経を獲得する為に儒学の良し悪しを判定し無いようにしたことには理由があって、これに儒家以外の各家の持っている更に寛容な態度を用い、主導的な立場として各家の学説を自分の理想の為に意識的に吸収して使った。
王安石の異なる学に対する態度は一貫して比較的沈着で公平なものであったが、先の節で述べている思想に類似することもあって、彼の《泣水軍淳化朴院経蔵記》中で指摘するならば: 道が一つで無く成ってから久しいが、人は、天下が教え後世に伝えるべきとすることを「善」とする。 後世の学者は、或いは、身を置く所に殉じ、或いは世に迎合し、或いは心の赴く侭に、そんな訳で聖人の大切な理が分裂する確率は八、九割となっていた。 大志を抱く人が見聞を広くするのは当然なことであるが、飛び立つための冀が終始力不足で為す術も無く、結局何も得られず終って仕舞った。 中国の老子や荘子、或いは西域の仏陀などは、思いを自然に任せて眼を見張るもの何も無くても、それを隠すことも無い儘にして作為を加えることも無く、寂然として動か無かった。 彼らは、その後の世の信者に伝える為に、実に公平で隔て無く、そして嫉みが出無いよう、質を静かにして頼むこと無く、天下に「仁を以って嫉むことは無く、義を以って求めるものも無い」を教え込んで来ていたのだ。 士の誇りを根こそぎ奪い盗っておき乍、自分は何も無い人が世に多くいるが、超然としている高蹈、己の情を重んじるこのような人もいるので、所謂、賢くも無い者が発言者となるとは如何なるものか?
彼は聖人の大切な理(全経)が分裂する確率は八、九割に成って、『先王の道』が太古に統一して来たことが持続出来無くなっていることを自覚していた。 遍く多く知っている人(実は自分のことを言う)を眺めて観ると、その維持を守って行けることを期待したが、然し、力不足は否めず、結局はその維持を全うすることが出来無かった。 これは明らかに彼の若い頃の感慨で、それから彼は一所懸命各家の本を読んで、自分は「間違い無く凡そを知ることが出来た」と信じることが出来るように成った。 また、信者の寛平は、物静かで、人を嫉むことも無く、利欲を求めることも無く、丸で儒家の重んじる情そのものを持っていたが、何時も仏陀を身近に置いていたので無理に作為を加え無くとも自然に任せて道の一端とも得ることが出来た。 当時、王安石は自分が儒家の一員に成れたかを量る為、彼の所に足蹴く通っていたことで、彼が「仏老を堅持し、仏老は古いと排斥する必要は無い」と説くことに感化され、仏老はいつ何時も儒家の様に成ってはいけ無いと思い始めた。
仏陀と老子の信者が情を重んじるように成れたのを賞賛した後に、王安石は、儒学者の多くが派手で重厚さも無く、おまけに、汚職が盗んで奪うことと同じだと思っていたのに、更に、彼らは自分だけのことを思って他人のことも顧みず汚職をし、私利私欲を貪ることまでしていたので、儒学者に対して厳しく批判をした。 彼ら、儒学者の道徳的な節操は仏陀や老子の信者に遠くて及ぶことが無いのだ。 王安石は儒家は仏徒ほど歴史が無いからでは無く、『先王の道』を得て実行して、僧は言ったからには言行一致を守るので、僧が言うことに勝てず儒学者を嘆いても、儒家は自粛する力も無いので、それら儒学者に謹んで決まりを守らせた。 このことは仏徒が常時においても軽率な行動をしてはいけ無いということの裏返しであった。
王安石は大儒の身として、彼自身が例外だと言う勇気が無かったが、儒学者がずっと自己批判の精神を亡くしていたので、そこで学者が儒家を批判しにくると直ぐに儒学者は反論する愚を犯し続けていた。 学者は直接孔子を批判する外、歴代の大儒の全てを批判の対象にし、王安石が大いに尊び崇めた孟子と揚雄をも含んでいた。
改めて人数を数えると、孔子の弟子三千、賢者七十二、居候の英才が一か所に集まっていたのだ。 然し、孔子に対しては十分な敬意を表したが、その弟子達は大いに見縊られて来た。 彼は、孔子の弟子が師と余りに違いがあり過ぎると見られたのは、伝統の観点から出来うる限りの誇張を何度も繰り返して来たからだと力説した。 《原性》の中の一文には、彼は「孔子作の《春秋》を指摘して、すぐ旅立つので、夏は別れも告げることが出来無かった」と記しており、子の旅行のとき、子は孔門下でも良く知られた夏のような門徒、更に感慨を覚えるものがある。 《孔子》一詩の中で、彼は「顔は己れ自ら測ること出来ぬと回顧して、我が身の労も忘れ研鑚に耽って死に至る」と記しており、道に連なる門徒の顔ぶれについて思い巡らすと、このような孔子一門の中で一つ高い地位に着いて賢く成っても、家に篭って歯が抜け落ちるまで死に物狂いになって孔子を学ぶ為、早いうちに若死にした者がいたのだと記す。 《自訟》一詩在って、彼は指摘している: 「孔子が南子に会うことについて、子路は反対したかった。 公山氏から請われて、勃郁が色辞を見た。 万物は漆黒でも、道は天空を貫く藍のようだ。 弟子尚不信に駈られたのも、余りに才が乏しい資質の為か」。 子路は一本気で取り入ることを知ら無いので、師に接しても、変わること無く率直で、孔子は猥らな南子にお目にかかって、また謀反の公山に拘ら無いで往くことをと箴言し、その他の人は皆言う勇気が無くて、ただ子路のみ怒りを顔に露にしたのだが、孔子を弄ぶ後世の知識人も『誓を呪文に賭ける以外無く』とこの時の孔子の行動はもともと美点と見做し、王安石さえ彼の知力に及ばず、十分に孔子を理解出来て無かったのだと決め付けた。 勿論、王安石は、孔子の偉大さ迄届か無かったいと表面では孔子の道が蒼天のようであることを誉め称えるかも知れないが、実際には彼が腹心の弟子の箴言の意味さえ悟ることが出来無いことを風刺したものだ。
孔門のお弟子さんの中で、王安石は聯貢への批判が最も厳しい。 《子貢》の一文の中で、彼は、《史記》の子貢の事についての記述が誤って伝えられたものだったのかもしれないと思っていたので、それならば子貢は儒学の為にはなら無いと考えて、子貢を儒学の門徒の外に殆ど排除したのと同じ扱いで記述した。 子貢は孔子の命を奉じて、舌先三寸に任せて、意外にも山東に居た者を招いたのは愚かであったので、晋を強くし、斉を乱して、呉を破滅させ、越を覇者にした結果、天下の仕組みの変化を進め、孔子の両親の母国を保護する望みを適えたのだが、これらの事業と功績はもともと儒学者にとっての栄耀に傷を付けることになり、王安石は激しくこれを悪評して、孔子、子貢も普通の人間だなと思って、その位の価値しか無い者で、政を顧みず、独り善がりに顔を売ること頻りで、天下の心配事と苦しみも意に解さず、況してや両親の国を食い物にしたと思うと尚更で変乱に因って他人の国になって仕舞った母国に、「己の欲望に従って執り行う者」が人に教える資格は無いのだ。 王安石は子貢がこのようにしたことを在ってはいけ無い事だと思ったが、孔子が彼にこのようにするように教えたのならば尚更の事だ。 王安石がこのように孔子が道に反すると説く批判をしたのは一回のみで、如何なる証拠も無い状況下で《史記》の記録を否定したが、孔子と子貢の隠れた部分に対する批判では、その最中に自然と湧起る苦しい胸の内があったのだが、併し王安石を表現すると屡独断的であるということも言うことが出来る。 王安石はこのように孔門の諸子を批判して、後世の蔡卞の上に躊躇無く孟子を置き、顔子と対等にし、子貢、子路はすべて問題外にした為、後代の人に頗る誹られたのだ。
王安石は荀子が孟子を批判した為、荀子の批判に対して最も厳しくしたのであるが、更に二つ目は荀子の儒家の仁義徳を人の心の本来内在する性とはせず、外在させ副次的なものに荀子が替えた性悪説の為であるという。 荀子の性悪説と仏教の性格の相反を議論して、仏教は人には皆仏性があるとし、仏性はまた人心に属して、本心を発露しさえすれば、性に依って成仏することが出来るのだとした。 孟子は誰もが全て尭と舜であることが出来ると言って、性善論を堅持し、仏徒の言うことと相応し、恐らくこのことで揚孟が荀の齎した重要な思想を貶すことになったのだと王安石は感じたのだ。
王安石が歴代の大儒に対しては貶すのを称賛する者は少なく無かった。 一つは彼への評価が極めて高かった為、二番目は儒学者に自らの傲慢な態度を取り除く意図を以て自ら反省するように促して、外部の心情を排斥する心を和らげることに依って、多くの他家の美点を吸収するように諭したからであった。 宋代では、儒家と彼との関係に依る緊張の主な責任を儒家に押付けたのは、仏教と道教に儒家を排除させる訳では無く、儒家の力を釈迦と老子に並ぶようにする為だったのだ。 儒家の勢力が最も大きく、亦支配的な地位を占め、生殺与奪、人の災いと福に関係する思想でもあったのに、如何して不振だったのかは、他家の排除に繋がって仕舞うからでは無く、保守的で進取の精神が無い為で、新しい考えを取り入れず、又、言行を一致することが出来無いからであったのだ。 そこで単に儒家のみを変えるだけで、漸く各家の間の関係を改善することが出来て、諸家を互いに連合させて、共同して発展し、統一するある種の学説を打ち建てようと『先王の道』を回復して、全経を再建しょうとしたのだ。
王安石は《楊墨》一文の中で二家を比較して、「仁に親しみ恩顧の一端を得た楊子は道を継ぐ者は自分だと改めて思った」と記した; 義に親しみ偉大な禹の一端を得た墨子も道を継ぐ者は自分だと改めて思っていた。 然し、それら二家が傾いたのは夫々、楊子は、天下の利を以って一角を抜こうとしたが抜け無かった責任は、他人では無く只自分のみにあると言い、墨子は一身を顧みず苦労して天下に役立てようとしたが失敗した責任は、全て他人にあり、自分には無いと言った。 比べて見て、王安石は楊子の儒学を善とし、墨子から遠ざかった。 ここでは彼は明らかに庄子の影響を受けて、人の命を重視し、自分の性を受け容れるように促し、他人に干渉することを諌めるようになり、そこで墨子が只管、利益を人の性の本質とすることに対して彼は不満の意志を表して、利を是とする思想は実際には人に百害を齎すと考えた。
王安石には法家に対しての批判もあったのだが、吸収すべきものもあった。 彼は礼、楽、刑、政が王道の構成部分だと考えて、重い徳と軽い法とすべきで無く、厚い賞と薄い刑を善とする(如何かな?)。 彼は単に刑名を羅列するだけの法家に不満を表すが、法家の代表の人物の商鞅に対しては尊重して、彼の《商鞅》一詩の中では次のように指摘している:「大金を大事にするという古来より人々が信じ込んでいる一言は軽い。 現代の人が商鞅について未だ結論を出すべきでは無く、商鞅の令政は必ず効以って為されるだろう」と法家が法制を重視して、法令を厳しく執行したことを、彼も賞賛している。
王安石も軍事家については賞賛していたので、彼は孫の軍事も道と合う所が在ると思っている。 縦横家が唯利を求めるだけの者達だったかもしれないし、只尚弁舌の才、節操に欠けること多いので、彼らに対して王安石は余り強く興味を示さ無かった。 邵博の《邵氏聞見后録》は王安石が蘇軾の制度を良く思わず鞭打つと語り、そのことが、まるで戦国の縦横家の振る舞いと思ったと述べているが、ことの真偽は調べてみなければ分から無い。
要するに、王安石は全ての諸家に対してあらゆる面で内容性質が違ったものでも粗全て吸収したので、決して片手落ちになら無かった。 彼は各家全て洩れなく取捨選択をし、又、その取捨選択の標準は相手によって如何にするかと考えていたので、全てに対して全部のものを格別に吸収し無くても良いのだ。 注意を要したのは、王安石は諸子百家の行為の道術の一つの構成部分と同等に扱ったように仏教を決して外へ排斥することは無く、夷狄のものとは見なさ無かった。 確かに彼は、どんな夷狄のものであっても認めるべきものは認めて、偏屈に盲目的に排斥はして無かったのだ。
五、新学と仏陀
王安石は十七歳で志を立て儒学を始めてから、儒家を振興するために数十年間も奮闘して来たのに、彼は如何して、亦、人知れず新しい学問に転向して力を尽くすのか? 新学と儒学とは大きな隔たりが在るので、新学は新しい儒学として認めるかどうかということに適切な答えを出すことは至難なことである。 王が学ぼうとしている新学は、幾つかの道家の観点に於いて儒学以外のものであると政敵から一蹴された。 蘇軾は王安石の学説と政見に対しては、堪えず不快の念をもっていたので、《王安石贈太傅制》中で次のように述べている: 「王安石は官と成って、孔孟を齧った程度しか学んで無くて、瞿耳を晩年師とした。 手腕ある故人達の六経の原稿を網羅して、自分の意見を持って無い; 価値の無い衆知の事柄を、然も新しいことであるかのように、この人が言うが」。 彼は、王安石が仏陀と老子のことを晩くに学んだのを皮肉って、既に孔孟の徒で無いのにも拘らず自分の思いが未だ六経に有るように見せ掛け、衆知である事を切ったり貼ったりして新学として創立したと嘲った。 彼は《六十一居士集叙》の中でもまた「古くは欧陽子が仏陀は十年も持つことはあるまいと言って、士は新しい学問を始めるようになったのだが、周孔の真を乱したのみだった」。 仏老は儒学を何時も混乱させると公然と罵って新しい学問を攻撃し、新しい学問を認めない儒学の立場を明らかにすると同時に、新しい学問には仏学の成分をおり込んでいるとはっきりと非難したのだ。
蘇軾が偽って悪口を言った言葉を全く信じて仕舞い、曾鞏も王安石が転向して仏教学に関係したことを怪しく思った。 前述した通り、曾鞏は、王安石が経典を読んで勉強するよう彼に勧めたことを疑い、更に彼は親しい友人が仏教にのめり込んでいくことに気を揉んで、続けざまに手紙を差し送り、経は矢鱈に世を乱すものだと伝えた。 王安石は返信の手紙の中で仏教の問題を避けて通ろうとして、唯中国の聖人の教えを通して彼の経についての説を強調しただけなのであると説得しようとしたが、併し、王安石は各々の価値を否定して無いので、曾鞏が経は矢鱈に世を乱すと記しているのを見ても、認めるわけにはいか無かったのだ。
それでは、このように転向することを促す面において仏教がどのように作用し、力を発揮したのか、或いは仏教の如何なる部分が新学に吸収されたのか?
先ずは、仏教が栄えるような刺激の作用を目指す。
六祖恵能と師弟の努力を経て、禅宗が理論の上で目指したものは熟していて、そして実践の上で要領を得て大いに華開き、著しい効果を見せ、唐朝末期の五代の戦乱があったけれども、禅宗を主流とした仏教は衰えること無く依然として栄え、然も、徐々に俗世間に溶け込んで、影響は益々深くなって、人の心を変えただけでは無くて、その上因習も変えたのだ。 仏教は徐々に接近して来たことに直面して、儒学は悪口を言い合うことしか手の打ちようが無く、所謂、華と夷狄を弁別したり、老子をやっつける為に古傷に触るような有効な兵器として人倫を壊すと言触らしたり、甚だしきに至っては政権の援助に依って抑え込もうと試みたりして、全く君子の風格を失っていたのだ。 王安石は確かに始め儒学を振興しょうと、数十年奮闘して仏教に対抗して来たが、最終的には彼が全身で援護してきた儒学が余り役に立つことが無いことを感じ始め、その上仏教学と較べて依然として形勢不利なので、彼は如何しても新しくやり直さなければならないと思うように為ったが、更に生命力に富んだ『先王の道』(経学)を説いても世間一般の習わしに虚しく抵抗してするだけのものであると考え始めていたのだ。
換言すれば、若しも仏教の圧力に直面し無かったなら、若しも儒学の栄えている一時代で生まれたなら、王安石は恐らく博学の大儒として結局その一生を終えたろうが、疑われ、怒鳴りつけられ、誤解を被ってまで危険を冒して別の新機軸を打ち出そうとしたのだ。 窮して変化を求めざるを得無く、仕方無く改革したのであるが、時代を先取りする改革者は全てこのようなものだ。
その次に、仏教の寛容な精神が皆の意見を積極的に摂り入れたことに彼が感染して、彼に狭い儒学から離れることを決心させた。
儒家は、孔子が間違いを犯すことが多かった卯を誅したとの伝説に儒家の一部が拘るのを終始一貫して許さ無かった筈なのに、卯についてのこんな伝説を伝える異端の分子の首を切ることになったのだ。 その上、儒家は人を罵って、ややもすれば意識的に異なる学に属するものを揶揄する「郷願」、「小人」と罵って、儒家が言うことが出来るのは一点の君子の風格であって、全く優しさに厚い気風は見られなかった。 孔子は行いの正しく無かった卯を誅して、孟子は楊墨に並んで、揚雄は申韓を打って、韓愈が仏老を避けて、といったことを全て儒学者は道の為に称賛して、力が異端に並んでいることを誇示するのは儒家の一貫した伝統だった。 異端に完全に並んだ分だけ力を得て一線を画すよりも、相手が理に適っているかどうかを見定めることが大切である筈なのに、全く理解出来無いか、少なくとも立場の不安定さを思い、修正して変わろうとすると同化されて仕舞うと疑ることになり、この伝統は今なお続いていて、異端の持つ粘り強い生命力を改めて思い知ることになった。 このような伝統の制約の下では、異なる学の合理的な成分を吸収出来ることはあり得無いのだ。
仏教は道以外も排斥するけれども、然し諸家の中で比較的に寛容だ。 仏教は異端に対してずっと腕力(武力)に訴えるようなことはして無くて、暴力に頼らず布教して、中国に伝わった後にも、余所者の身であるので、更に温和になった。 道教と儒家の攻撃に直面しても、仏教徒は直接に反撃したことは無く、出来るだけ自分と相手が直接決して対立することが無いように配慮し、然も、出来るだけ自身を補充する意味合いで相手の学説を吸収して、相互の対立を緩和することに努め、衝突を減らした。 宋の後半の時代に入って、多くの学者は仏教の繁栄を不満に思って、直接悪口を言ったが、然し、仏教は決して儒家を排斥し無かった。
王安石は仏教の立場から儒学の致命的な欠陥を見た。 儒学は更に異端を排斥しようとしたので、自ら首を締めて、遂には孤立して仕舞った事から、益々相手を攻撃することになったが、それでは相手の優れたところをより多く吸収することが出来無い一方、相手は儒学の優れたところを吸収することが出来て相手の言論を逆手に取って見解の矛盾をつくことで儒学を益々不利な地位に陥らせ、儒学は益々後を採って仕舞ったのだ。
王安石は以上のことを全て呑み込んだ上で、「死んでもこれらの後進的な信条に頑固にしがみついて放さ無いならば、全く進歩はあり得無く、発展して栄えようなどと言う資格は全く無くなり、創業時の事業さえ盛り立てることが出来無くなるのは自明なことと為って仕舞う」と思い、その為彼は決心して先王に帰って、詰り、経学に帰って、再び儒家の源流を発見して、皆の意見を取捨選択して一つに纏めて新しい経学(どの異端も並ぶことが出来無い新しいもの)を創立したのだ。
第三に、仏教は変化の観点をもって発展して来たことで彼に影響を与え、それに拠って王安石は儒家の保守的で進取の精神が無い限界を知って仕舞ったのだ。 儒家は継承を重視して、再び変化することは無かった; 安定を重視していては、再び発展は無くなる。 孔子は三年間の父の喪中は何もするなと言っているので、後に儒学者は「天下は何も変わらず、道は更に不変だ」と言った。 其のため儒家は変革に反対し、革新について当然全く協力する気も無く、常時妨害して、抑圧した。 教育の面で儒家は変化しつつあって、発展を思う師が弟子に対して先生を追い越すそうとは思わないかと説くと、祖を滅ぼすもので欺きの師と呼ばれ、大逆無道という烙印まで押されて仕舞う始末だ。 その為学者は革新を話す勇気を無くし、凡そ押並べて「古に頼み改制する」ことしか出来無くなって仕舞うのは、先人を上回る勇気が無くなって、結果一世代経つ毎に先人から遠ざかることに為って仕舞ったのだ。
そうで成らない為には、仏教のように、一方では世の中の諸法が総て常に変わって一定し無いのだと考えて革新を奨励して変化して行くのを認めなければ成らないのだ。 教育の方面で、禅宗は「余りに頻繁に師と会っていると師と同じ程度の能力に為って仕舞い、師の徳の半分が無く為って見え、大方が教える立場に為る」という意見もあるが、今まで通り創業の事業を盛り立てていくことしか出来無いのであれば、先生が人材を選べ無くなることが明かになり、逆に先生と弟子の能力が同じ程度に為って、師の徳も損なって仕舞うのだが、只師が仏教を発展させ栄えさせることが出来るような見解を探し当てれば、先生の能力が弟子を上回って、漸く伝授することが出来るようになるのだ。 将に、このような教育に対する観念を持っていたので、禅宗は漸く一世代毎に勝ち取って行き、益々繁栄して発達するようになったのだ。
王安石は、禅宗の歴史を、目覚ましい発展変化の成り行きを目の当たりで観察していて熟知していたので、彼は先王の意向も法に応じて、祖先の足跡を守るのでは無く、時代が変わるに従い、法令も後を追って調整するべきで、古い仕来りに固執してはいけ無いのだと強調した。 それは新学という名を以って、革新を強調する為、彼自身は儒家の伝統の態度に拘ら無いで、人より勝る胆力と識見を現したのだ。
第四として、仏教は「義に従わず無い言葉に従って、法に従って人に従うことは無い」とし、禅宗は更に以心伝心の心の不文律を吹聴したが、然し一方、役立たずの学者達は、これと鮮明な対比を形成するが如く、章節と句読をきっちり守って伝える一辞一句を重んずる手法を敢えて強調した。
漢唐の経学は章節と句読を固く守る重い文を伝承することのみ重視し、筋道を立てることを考慮し無かったので知られている。 只先人に追随して、重いだけの経文は筋道が不明で理解し難い。 宋初に至って、このような習慣はやっと少し変えられた。 筋道を付けることに腕を奮うことを重視して、禅宗の影響を明らかに受けて少し自分達の拘りを捨てたのだ。 王安石は漢唐の経学の欠陥をはっきり心に刻み付けていたので、その評価に対しては高く無かった。 彼は儒学は先王の言葉を借りることしか出来無いのだ、後代の人に遺す自由闊達な活動を展開出来る領域も小さくて、更に、それ自身の制限が多いことが分かっていたので、復古で新機軸を打ち出して、顕発の先聖の微妙な言葉に含まれた重要な意義の目的を達成することを決したのだ。
王安石が性と運命論によって先王の理を集大成し、人心の為に性と理を纏めたことは、間違い無く仏教の禅宗の影響を受けて為されたものなので、経に禅を執り入れ、儒学に仏経を執り入れて儒学を変えることになった為に、伝統の儒家が捉えてきた所謂先王の理とは明らかに開きがあった。
第五、仏教は内部で学ぶことを重視する以外に、外の学問を吸収することも心掛けるように促しているので、世の中のすべての知識を学ぶに尽きると主張している。 儒家は聖人が知ら無い者は無いと言うが、実際は只倫理だけを重視して、その他の知識に対して卑しめる態度があるので、その知識の範囲は狭かった。
森羅万象の知識を身に着けていたとして儒家が尊敬した博学の士として孔子に勝るものは無かった。 孔子が一介の俗世間の人に記載した歴史と伝記について、その知識の範囲も可也限定されたものであるのは仕方無く、過度に非難するに値し無いのにも拘らず、その人が返答に窮すると、孔子はその知識不足に対して卑しめの言葉を吐くのだった。 樊は孔子に農業生産のやり方のいくつかの知識を教えて貰おうと頼んだが、孔子が答えられなかったので孔子の下から離れて行ったことに対して、孔子が大いに樊を罵ったことは全く小人の為せることであり、更には孔子が全く耕作や園芸などの実用的な知識を身に着けることを軽蔑していたことを明かにしたのだ。 子貢は商工業の経営に精通していて、儒学の門徒では珍しく商業に特に優れた才能を持っていて、然も、実際多くの金儲けを為し、それらを彼の自分の生活水準を保つ為に使っていただけでは無く、孔子の門徒の日常生活費の支払いにも充てていたにも拘らず、孔子は貢を誉め労うどころか、一方では彼の出資援助をも受け入れておいて、逆に一方では彼が従順で無いことを批判して、誉めるどころか安んじて貧困に帰すことを喜んで話す始末で、このように弟子が偉過ぎると却って弟子(子貢)の良い行いを無視して誉める言葉も無いばかりか感謝もして無かったことに深い苛立ちを覚えるのは当然のことである。
孔子の知識は六つの技術全を通して比較的に広くに亘っていると結論づけられるが、その技量はそれ程のことも無く、唯、謠を大胆に謡う勇気があって、健康については余り神経質に拘ることが無かった儒学者だった。 後に儒学が益々状況が悪くなったのには、訳があった。 利が小人の道とする為、利益を言うことを恥とし; 情を重んじる道に背くこととしている為、兵を言うことを恥ずかしがって; これが小役人の事の為、刑を言うことを恥ずかしがって; 道化役者の業によって笑うことすら恥ずかしいと言い、甚だしきに至っては泣たり笑わせるのさえ、儒学者の尊厳を損なうことと恐れて、殆ど一枚の板のような能面顔をして、恭しく畏まるのみで、仁義徳の決まり文句を言う以外全く取得の無いものに為って仕舞ったからだ。
将に、儒家のこのような自らを封じた意識の伝統は中国に十分に揃っていなければ為らなかった情報知識活用の仕組みを長い間不足させ、儒家の以外その他の知識は総て抑圧を受け、限られた知識以外知識を増やすことが出来無く為って、在るが儘にあろうとする精神に打撃を与え、全く価値の欠片も見出せ無いものであったのだ。
仏教はそんなことは無く、宗教の立場からも仏教徒が全ての知識を備えていることを強調して、世の中の森羅万象の知を備えて世に眠る者(儒者)を超えたのだ。 仏教は三つの知を強調して、全ての知をより速く得て、全ての知を理解し、知を理解することを理とした。 全ての知とは、全ての物事の共通の有様(共通性、普遍性)そのものであり、全ての知で全ての物事の共通の有様を理解し、また全ての物事は内部(特殊性)に本質があり、理として智を理解するのは即ち事物のことを理解する方法を知ることであり、その為には三智を具えることが必要と為り、凡て知識は何々具えると言うことと同義であり、智を得る才能は仏を菩提と為し悲願を達することに匹敵するとしたのだ。
仏教は更に五明、つまり内明、声明、精巧の明、医者の処方の明、因明があると言う。 内明は内に学ぶ、詰り、仏教の自身の知識であり、言語学の知識を声明とし、精巧の明は器物を作ることの知識に関連するもので、同じく応用科学も含み、医者の処方の明は即ち医学の知識、因明は、詰り論理学の知識と説く。 五明は粗古代の総ての知識の範囲を含んでいて、仏教が十分に揃えた知識情報を得る仕組みを体現したものである。
仏教は全ての知識を際限無く求めると言うが、如何実行し始めるかは困難なことで、中国には学問ある僧が可也居るが、然し、だからと言って本当に目標と成る人がそう多くは居る筈も無く、更に禅宗は文に表さ無いことを吹聴しており、特に南宗の六祖は字を読むことが出来無いことを好んで宣伝して、経を学問とすることに余り興味を示さ無かった。 王安石は世間の全ての知識を修得することを目論んで天下の全ての書を読み尽くすことを企んでからというもの、殆ど寝食を忘れ、とうとう五十歳に成った時に基本的にはこの目標を実現したのであって、この成果は未曾有の快挙を成し遂げたと感嘆させられるものであった。 彼は孔子の女人、農夫を卑しめる古い規則を打ち破って、農夫、女性や労働者さえ謙虚に教えを乞うた。 その為彼が後に為す法律(制度)の変革は、新学を創立する為に得た森羅万象を含む十分な知識の基礎の上で作り上げたもので、暫く考えた後にふと思い付いたものでは無かったのだ。
第六に、仏教は平等を主張して、階級制に反対して、結果、広範に受け入れ外の学問も学べる条件も創り出したが、一方、儒家の等級は厳重で、内と外も明確に区別していたのだ。
王安石は庶民感覚に近い感覚の持ち主だったので、等級の観念は強く無く、上と渡り合う時も諂わず、下とは気さくに交際した。 彼は教えを請うのを恥とし無いで、農夫、女性にも謙虚に教えて貰った。 普通の読書人ならば軽蔑した小役人についても彼は表彰し、甚だしきに至っては行商人を朝堂へ招き政治を議論して貰ったこともあったが、無論、これらの美点も立場の違いにより道が分かれて互いに図りごとを廻らすこともあり、意見が異なる政敵には欠点だと見なされて攻撃の対象になった。 正統的な儒家の等級の観念は極めて強くて、人に会う度いろいろな等級に分け、然も、等級によって厳格に事を進めて行こうとするので、偶々大いに誹られる事があったと言われている。
儒家は父と子君臣の関係の変化、特に君と父の絶対的な権威を最も強調していたので、この方面で王安石は大いに或る種柔軟な態度を表していたので、儒学の汚れた病気を護る輩の反発が余計に大きくなった。
王安石は決して君主の絶対的な権威を否定するものでは無く、甚だしきに至っては総ての権力が天子様の権威の下に集まることを強調し、逆に彼は数多の君臣が互いに庇いあって何もし無いと主張し、義利で付き合うばかりであった。 彼が孔孟を受け継いでからの道は君の思想より高くて、只管、君臣を分けることに固守することが決して正しかったとは思って無かったのだ。
儒家には一つの伝統的難解の提示があって、詰り、湯の武力革命は一体合理的かどうかの問題である。 道義の上から言って、湯の武力は天意に添い人心に適い、武力に訴えても桀紂のような暴君に対するものは悪とは言えず完全に合理的なものとなる; 名分上から言えば、湯は臣下の武力であり、桀紂は君で、臣が君に背いて、詰り目上の人に楯突いたのであり、また大逆無道、君臣の大義に背くこととなる。 儒家は一方では大いに君臣の大義を説明するにあたって、君臣の関係を父と子の関係のようなものだと説明するが、一方では亦、仁義徳の関係だと説いて仕舞うと完全に暴君の専制の道具として使われて仕舞うが、民衆の利益の代弁者を気取りたい思いもあり、そこでこの机上の論争は一種跋が悪くどちらも難しい立場にあった。
伝統の儒家も大部分は湯の武力の命令を受けるのは天の理を堅く護ることに等しく、それを肯定することは理性に違い無いが、然し、後に一時(点)の上で未だに躊躇するところがあったのだが、長い間我慢してやっと立ち上がって反逆して、凡そ湯王の武力をやむを得無いものと説くに至ったのだ。 王安石は《非礼之礼》の一文で、湯の武力の革命の善し悪しの結論に達するには、解釈次第で変わるので、時事の便宜上だけで結論に達し無いで、君臣の大義が常に必要であることを指摘して、湯の武力が君臣の関係の暗い部分に根差すものであったかどうかという原因についての情報が不足していると感じたのだ。
彼は「貴方のことが可愛く思っている目上の人に臣が楯突いてはいけ無い」ということが万世堅持する大義であることを指摘して、若し、君が人の操縦法が下手ならば、必ず権力者が替わることを思い知ることになり、替わろうと動く者が出ると、直ぐに交代されて仕舞うのだ。 この点では彼と孟子の見方は一致しており、詰り、君は臣の忠実さに対して十分報いることが出来るときは、君が愚直で忠誠心を求めることが下手でも、臣が君に善く忠実で、実際、道義を重んじるものであるのだ。
湯が武力蜂起した事件の経緯は、亦、伯夷と叔斎との評価の問題とも関連するのだ。 聞くところによると馬諌と武王とが紂を伐って、武王が後に天下を周と帰して、伯夷と叔斎の二人の義士は周粟を食らわず、首陽山の下で餓死したと言われている。 道義の標準に照らして、愚直な二人の暴君への忠心に対して、時代遅れをだと一笑に付す事も出来るが、再び紂を助けるかたちに成るのは罪業だと言う事だ。 他方、見方によっては、二人は亦忠臣の士とされよう。
王安石は《史記》の中の孟子の言葉を引用して力辯する記述を眉唾だと論評したのだ。 孔子は言う: 「旧悪を咎め無いで、首陽山の下で隠者となり、空腹に耐えたことこそ仁愛の心からであり、それこそ仁である」。 この話からは、伯夷と叔斎とが揃って武王が紂を討つことを諌めたかどうかを見てとれ無いが、それでも君の旧悪を不問に付すとは言って無く、確かに二人は商の遺民であって、周の施しを受けずに首陽山に隠棲し空腹に耐える義理があったのだ。 孟子は言う: 「伯夷の非は悪人を朝廷の主に立て無い為に其の君に事を為さ無かった事で、紂を避けて居を北海の浜に構え、目には凶悪な色を見させ無いようにすることは不肖な事で無く、さすれば百世に亘る師と成れたのだ」。 孟子はただ暴君に事を為さ無かった一事のみで判断するのでなく、商紂と相協力し無かったことのみで、百世の模範と成り得るとし、十分に見習うことであったと言った。 孔孟の言葉は相反しているのは明らかで、孔子は、雅に伯夷は忠君の手本として、君の凶悪さに目を瞑り、自らの意志で商朝の為に節操を貫き、国が滅びて遺民と為って、自分を犠牲にしてまで義を採って、死ぬまで悔いが無かったのだと言う; 孟子は伯夷のとった行動を、臣としての大義の為と知った上で暴君の朝廷側に味方することが無かったからには、愚直な忠誠心で無く、君の模範と為ると見た。 こうして孔孟が言わんとすることを全て文章の断片から意味を汲み取ると、孔子の考えは、前朝の商に忠誠を守った老人の生き様を賛美したと言えよう; 孟子は、伯夷のその以前の半生から読み取り、潔白を守って皆の良い手本とした。 王安石は孔孟の対立を全然取り合う事無く、専ら孟子の言を採り、道は「孔孟は紂の凶悪さ知っていたので、その仁を思うと伯夷を責めるのは忍び無く、飢えを凌ぎ、自降の辱めを受けず、世の大掃除が済むのを身を縮めて待っていので、号は丸で聖人の耳(老子)だ」とし、実は伯夷の「空腹で避ける」とは周を避けるということで、それが空腹なのは周粟を食べない為で、紂の王朝商が滅びた後にあって、前朝の紂を非難するのは矛盾があったのだ。
王安石は、前半生の伯夷は只管賞賛するが、後半生の伯夷が好きで無かったので孔子を曲解した。 このように思うだけで無く、更に彼は仇のように悪を憎んでいたので、伯夷に紂を誅して貰いたかったのだ。 彼は西伯(文王)が老人の面倒を善くみるという事を叔斎と伯夷が耳にしていたという故事に思いを馳せれば、伯夷が西伯の志を一心に思う事と、姜大公が紂を伐そうと思う事とを如何して異なることであると言えようか! 大公は武王が紂を討伐したのを助けたのに、伯夷が如何して大公に下ることが出来よう! その時二人は共に八十歳の老人であったのだが、凡そ伯夷は大公ほど幸運では無かった。 西伯は進軍の途中で何時死んでも良いと覚悟を決めていたとも考えられるが、武王の時代には伯夷も亡くなっており、既に亡くなった西伯がひょっこり現れ出たとすれば、西伯程の才人は恐らく大公に文才を独り占めさせるようなことは無かったろう。
王安石の既定の解釈を覆す文章は、一般の人の全く思いもつくことが無いもので、絶賛を浴びた。 何故彼はこのように解釈したのかというと、君の理念を道で以って強化する事を謀って、天下の人民の利益の上に君権を置くことに反対して、君善を主張して、君が凶悪であったならば、愚直な忠誠心を起こすことに反対する。 愚直な忠誠心の典型としての伯夷に喝采することは、逆に愚直な英雄を攻撃する事に為って仕舞うといことで、愚直な忠誠心を賛美する一派に対する最も痛烈な皮肉と成ったのだ。
王安石は揚雄、馮道のなど人物の評価に対しても彼のこの観方を体現していた。 揚雄(前5から西暦紀元18年)、字の子雲、前漢の文学者、哲学家、言語学者、蜀郡の成都(今四川に属する)の人。 若い時は学問に親しみ、広く読み漁って知識を多く吸収し、然し、訥弁で、口下手だった。 彼の人と為りは贅を好まず、虚名を求めなかった。 四十数歳の時に首都に遊学し、大司馬の王音に官として推薦され給事黄門の次官に任命された。 彼が成帝、哀帝、平帝の三帝に仕えたが、終始、昇進し無かった。 王莽の新朝の時に、大夫として校書天禄閣に任じられた。 或る者が王莽を侵犯したので、揚雄は巻き添えを食らった。 自分の潔白を証明する為、彼は圖投閣で自殺を試みたが、未遂に終った。 後に、王莽は、彼が何も関係無いことを知り、大夫に任じたのだ。 揚雄は一世代の大儒であり、王莽のことを《劇秦美新論》で観ると、「揚雄を信じ無い王莽に追い駆けられ揚雄は殺されると恐れ、せっぱ詰まって天禄閣から跳び下りた」というのは、史臣が出鱈目を書いたものだと王安石は思っている; 王安石は甚だしきに至っては、揚雄が〈劇秦美新論〉一文を書いたということに一層否定的な立場に立ち、これは後代の人が揚雄を虚言の者と決めつけ書いたのだと言ったのだが、何れにしても揚雄がこのような文章を書く筈が無いと思っていた。 多くの人、特に後世の道学の学者達はこれを揚雄の一の大きい汚点としたことを、王安石は納得することは出来ず、その真意を知っていたので楊雄を庇ったのだ。 彼の《答龍深父書》中は「楊雄は官吏に成り、孔子のどうでもよい義に合う」、君子の出所進退には、全て其の道が有る。 深遠な儒学を知ることが出来たのだ。
王安石が五代の名相馮道の評価に対して更に準備した典型的な意義を見出した。 馮道、字から言うと、瀛州の人である。 晋の初期の事、王は李克を河東部の節度使の書記として遣わした。 唐庄宗の即位、財政部の次官に礼拝して、翰林学士を担当する。 明宗の即位の時、端明殿の学士に任じられ、兵部の次官に移って、冬に中書侍郞、同じく中書門下の平書事を拝し、その時から十数年経って、天下は平穏で、更にその後哀帝は、帝を廃棄される。 晋滅して唐になり、馮道は天下に王たる者として相進むのは晋の高祖のような帝であると言った。 契丹が晋を滅ぼし得たのは、馮道は「耶律徳光の輔佐があったからだ」と言った。 漢高祖立つは、太師のお蔭だとした。 周滅し漢興り、ここでは周太祖のこと、太師に礼拝して、兼ねてより書の中に著したことであるが、世宗が七十三歳で死去した時に、瀛王は文懿と諡をおくって、死後に爵位を与えた。 馮道の人と為りは骨身を惜しまず節約家であったが、父を亡くして偶々故郷に帰った時、その年飢饉が起こり、郷里の窮状を救おうとしたが、耕作し植え付けてから作物が枯れ、甚だしきに至っては徳観も無くし人知れず他人の耕地を黙って耕す者も出始める始末であり、亦、軍中にある者は一軒の茅葺小屋に住み、童僕の召使いと同じものを食べ共に飲んでいたが、諸将は妾にする為手当たり次第掠め盗った美人を献上させるほどのお粗末さあった。 馮道は何度も大臣に就き、古い徳観を以って祈祷の習慣を捨無かったが、乱世の人心に少しく安らぎを得させたので、乱世の時代の人々は、賢愚を問わず、全て仰ぎ見て、その兵、時人は共に孔子と同寿をと祈って、このように名声が在ったことで有名であった。
馮道は多くの君に仕えたが、媚び諂って御機嫌をとった事は無い。 周の太祖は兵を以って漢に叛き、首都を陥落させたのだが、馮道は特別顧みること無く旧来通りの儘で良いと思っていたのだが、漢の大臣は必然の推戴を思っており、甚だしきに至っては何事も無かったように太祖の周を受け入れる始末だ。 周世宗が自ら出征したいと言い出した時、馮道は駄目だと思ったが、世宗が唐の太宗の例を挙げたので、馮道は「陛下が唐の太宗の例を挙げるべきで無い」と率直に言ったので、更に世宗は「この度の旅軍は敵に会っても山で卵を押えるようなものだ」と反発したが、馮道は「陛下が大山になるとは限ら無い」と言って、仕舞いには世宗を怒らせて仕舞うことを恐れ無かった。
馮道は乱世に会うが、天下の庶民を救うことを自分の務めとして全うした。 契丹は晋を滅ぼしたが、その時晋の馮道が繰り返し契丹の威勝を抑えたので、契丹の首領の耶律徳光は頗る怒って中国人を皆殺しにすると凶悪に脅したのを恐れて、人々が恐怖に慄いていたので、馮道は感慨深く「徳の光を当てるのは都の軍隊(耶律徳光の軍隊を言う)であって、徳光が光を当てる責任は彼らに在り」と彼は冗談任せに言って、信用を勝ち取った。 聞くところによると徳光は道を探って尋ねたという: 「天下の庶民はどのように救う?」 馮道はその言葉が依然として中国の人に対する憎しみの表れであると知っていて、諧謔の言だと思ったが: 「こんな時仏陀と雖救うことは出来ず、ただ皇帝のみが救えるのだ!」 と徳光を非常に喜ばし、忽、漢人を皆殺しにする思いを捨てさせた。 馮道は中国を救う為には全く労を惜しまず、道化役者を装って自身を振る舞い、それが我を折って人民を救う仁の心と正義の心を引き出したことは明らかである。
馮道は四姓を経て、その間十人の君があったので、役に立ち得無い儒者と道学の学者達から言わせれば、全く清廉潔白とは程遠く恥を知る心の無い代表であると言ったが、王安石は、彼が乱世に生まれた事が不孝の始まりで、本来持っていた大いなる節操は乱世では発揮することが出来難いにも拘らず、社会を比較的安定させた功労まで奪われたが、彼の「我を折って他人の利益を図る」を思うと、「諸仏の菩薩へ行く」という信念があったのだと確信していたが、新法派の唐介はこの確信に対して不満であって、道は「事もあろうに十人の主君、更に四姓、如何して言うことが許されるだろうか純臣と」と反発したが、此れに対し王安石は伊尹を以って更に反駁して、「伊尹は五回湯に就き、桀の五事をしたのに其れでも純臣と言えるのか」と指摘したので、唐介ははたまた反対して互いに誹るように、道は「伊尹の志がある」と言っているのにと王安石に濡れ衣を着せるような言い方をしたので、王安石は顔色を変えて大いに怒ったのだ。
道義と天下の庶民の利益を基本として、馮道は心豊かで犠牲的精神をもつ元気な大いなる慈善家と言える; 所謂、君臣の大義、一人の臣が事において二君に仕えず、馮道は無論忠臣であって、純臣では無い。 王安石は馮道を表彰して、彼は天下の庶民の利益を君主個人の利益の上に置かれるものであることを明かにして、人民を愛するのが則忠君で、国にとって有利となるのは則忠君で、如何しても一姓に忠実にあるべきとは限ら無いので、事において一君に仕えるのだ。
王安石は君臣の上から下までが完全に固定した関係に無いと主張して、君にとって臣民は凡庸を可とするが、公卿大夫には威を使って、処罰は刑罰で殺戮し、亦此れ認めるべきで、待つのは殊更の礼遇で、主客がとって代わる。 このように主は臣民に対して徳的な学識の高低で異なった待遇をするのか。 彼は、あれらの「道は盛んで徳の駿馬のような者」について、天子と雖、同じく北の方にお聞きして、と互いに主客の立場、常に臣下でじっと我慢しているものでは無いと思っている。 これは彼の一貫した道が、権力や徳より重くて思想の体現より高いのだ。 天子を尊重するのは、徳が在るからでは無く、若し臣民の中に徳盛んな駿馬者がいたならば、天子は当然謙虚に抑圧する事から降りるのが特殊な礼遇の例であろう。
王安石が、正に威勢によって君臣の位を決めることを決して主張せずに、君主に比較的に平等な態度で臣下に対応するように求めて、適切に臣下の利益と尊厳を配慮して、比較的柔軟な方式で君臣の関係を処理することを主張したので、「犬馬を養うようなものだ」と、後世の腐れ儒者が汚く罵る酷い仕打ちを受けることに為った。 邵博《邵氏聞見后録》は陳灌(灌は誤字)の言葉を載せて、王安石は北方の天子が言う通りの思想を持つ者であると攻撃して、道は「天尊く地卑しい、乾坤(天地)必ず、法則は直してはいけ無い」、「南方の天子、北面の侯公」の尊卑は上から下まで決して揺るがすことは出来無い筈なのに、安石の性と命の理を怪しく思って、甚だしきに至っては安石のことを歌って「自ら王安石が、凡そ五十年来その儘の説を道として謡う、国家の大計の根源、覆う兆ここにある 」、北宋国が滅びた原因を王安石の性と命の理に罪を擦り付けて、それは悪辣な下心が見て取れる。
程頤も王安石に対して《易》を説明することによって、臣が暴君の運命についての見方を変える為に不満の意を表すことが出来ると説明する。 十干の掛の中の九三爻は臣下の位であり、九五爻は君主の位である。 王安全石は所謂「九三位に在る者は九五の位に至ることが出来ることを知っている」と言い、この説は九十三爻に在る者が九十五の位が決して高く届か無いのでは無く、九五の位に昇って行くには一歩ずつ昇進を重ねるべきで、その努力が上位に伝わることで結局上位に昇っていけるということで、このことを「至ることを知り至る」と解釈すれば、湯の軍事が暴君に取って代わるのは全く理に適うことと説明が出来ると言った。 程頤はこの説明が納得出来ず、湯の武力の「至るを知り至る」を以って、「至る」の其れは「至って無い其の位に至る」ことで、臣が「知っている」を要するだけでは無くて、道(君臣の大義)に至って至るということを知っていて、その上「結局は至るを知っている」ということで、最終的に臣の位に止まって、「克服でき無い臣下の本分」、王説の「大きい邪気の壊事」と極め付け、「常に臣にこの心を抱かせて、大いに道を乱す」とした。
王安石が未だに官僚主義的な体制の中で等級を付けるのが不満で、官と小役人の品格が異なることがあるべきで無いと思っている。 彼は、「孔子は嘗て季氏の官吏で、官吏であっても士と認められたように、官吏は決して一段劣っているものでは無く、そこで官吏に対しても平等に士と対応すべきで、士大夫は官吏を辱めるようなことをしてはいけ無いので、小役人を活用することを堕落だなんて言わ無いで、小役人の品格を高め、大官や大夫へ栄転する機会も可能とすべきだ」と指摘している。
王安石は等級の意識を希薄にして、あわよくば君臣の平等、官と人民の平等、士と官吏の平等を主張して、学派の間の平等をも主張している。 彼のこのような観念は儒家が全く相容れるものの筈が無く、矢張り、仏教や道家の影響が在ったものと考えられる。
道家は万物を同じくし、道に是非や善悪が無いとして、大通を廃止し、所謂、善悪、是非、上下の差別を無くす。 王安石はこの観念を受け入れて、将に、貴賎無く、最高の境界として分別を無くし、これは明らかに儒家と異なったのだ。
仏教は最も平等を重視する。 印度の仏教の等級制度、衆生の平等を主張することに反対することで有名だが、仏教が中国へ伝わった後には、仏教のこの種の平等の意識が俗世間に大きく影響した。 東晋の高僧慧遠は印度の仏教の伝統を維持することを強く主張して、門徒を民衆に堅持したので王には尊重されず、そのことが逆に仏教の為に人々の地位と尊厳を守ることが出来て、同じく本土で最も不足していた平等意識を中国人に受け入れさせた。
王安石は、仏教の平等な観念を受け入れていたので、更に階級制度を概観してみたが、どちらかというと君臣に依って希薄化されて来た先王の政治と未だに完全には確立して無い階級制度とが関連しており、更に君臣への格付けが封建的な専制制度に相応しい儒家思想によって雁字搦めにされていることが気に食わなかった。 要するに仏教は王安石が儒学から経学に転向する面においても重要な役割を発揮したので、多くの仏教の要素が確実に把握され新学の中には既に入っていたので、この為、曾鞏は経には矢鱈に品が無くなったというのは理で、更に蘇軾が仏老を以って周孔を改めるなどと言うのが我慢出来無かったのだ。 (第四章に続く)