ちょうど1年前は、韓国世界遺産の旅の真っ最中でした。
そのブログ記事は、次のようにアップしましたが、韓国南西部とソウル周辺部
が残っていましたので、忘れないうちに再開します。
★良洞民俗村、安東河回村(2017.2.7投稿)
★慶州 その1(2017.1.17投稿)
★済州島 その4 城邑民俗村、城山日出峰(2016.12.31投稿)
★済州島 その3 万丈窟、サングムプリ噴火口(2016.12.29投稿)
2016.10.20(木)朝、全州市のホテルから歩いて10数分の食堂で、「全州コンナムルグッパ(もやしのスープ御飯)」
をいただく。 朝の7時15分、食堂内には朝食をとる作業員やサラリーマン風な方が結構いました。

朝食後、全羅北道の高敞(コチャン)へバス移動。
高敞支石墓博物館に到着。 壁面パネルに、密集した支石墓の写真。


韓国の世界遺産マップが展示されていました。
今回の現地ツアーガイドの朴明淑(パク ミョンス)さんの熱心な説明。
高敞支石墓遺跡の位置は、ガイドさんの顔の左側のところになります。
ただ、2015年に世界遺産に登録された百済歴史遺跡地区は、載っていません。
百済歴史遺跡地区は、ガイドさんの頭の左上のところになります。

高敞支石墓の特徴や形式などの、写真パネル説明。

博物館の屋上からの展望。 中央に高敞川が流れ、その向こうの山麓に支石墓が連なっています。
野外展示場には、先史時代の村などがありました。


山麓部を望遠で撮影。重機や人影から、支石墓が結構、大きいことがわかります。


支石墓は、西ヨーロッパや中国、日本でも見られますが、世界の支石墓の半数が朝鮮半島にあるといわれ
2000年に、高敞、和順、江華の支石墓群が世界遺産に登録された。
またバス移動で、次は益山(イクサン)の百済歴史遺跡地区、百済弥勒寺址です。
広大な敷地の中央に、九重の石塔、左に建築工事の覆いのようなものが見えます。

7世紀初頭に建てられた百済最大規模の寺で、三塔(木塔1、石塔2)と三金堂からなる。
当時の想定復元模型が展示されているようですが、私たちのツアーでは見学せず。
ブログサイト「韓国古代山城探検!」から模型写真を転載。

弥勒寺址の俯瞰写真。 1990年の写真で、右の白い石塔(東塔)は、この年に復元して建てたもの
中央は木塔址のみ。 左の塔(西塔)は国宝で、唯一現存するが、崩壊や傷みが激しいため、解体復元中。

東塔。かなり大きい。

西塔は、1915年に統治していた日本により、補修工事が行われた。 補修後の写真。


1910年の補修前の写真と、補修の設計図。 崩壊が激しいが、建築遺跡として確かに価値は高い。

解体復元工事の覆いの中です。
あれっと思ったのは、創建当時を復元しているように見えたためです。
実際のところは、よくわかりませんが、解体前の姿で補修・復元してもらいたいと強く思いました。

ブログサイト「韓国古代山城探検!」から、2008年当時の復元工事中の写真を転載。

上の写真は解体中の1階部分になりますが、2009年1月に柱石の中から、舎利荘厳具が発見された。
舎利荘厳具は、石塔を立てる際に奉納されたもので、舎利壺や舎利奉迎記、各種貴金属など貴重な資料となった。
昼食は益山の食堂で、海鮮カルグッス(平打ち麺)
店の看板の中央には”しゃぶしゃぶ”と書いています。(ハングルを勉強中なので、ここだけ読めます)

丸ごとのイカは、ハサミで切ってくれました。
海鮮具材を食べた後に、麺を入れて食べるのは、日本と一緒。

昼食後、百済の都があった扶余へ
扶余のマップです。

世界遺産・百済歴史遺跡地区の扶蘇山城の百花亭からの眺め。
眼下の白馬江(錦江)は、古代中国、日本との交易路の役割を果たしていた。
丁度、クルーズの黄布帆船がやってきました。


百花亭は、、唐と新羅の連合軍に攻められて、百済が滅亡(660年)するとき、宮廷の女性達が節義を守るため、身を投げた場所で
落花岩という崖の上にあります。 韓国の子供たちが、静かに眺めていました。

百花亭、宮女たちの慰霊のため1929年に建てられた。

続いて、扶蘇山城の麓の定林寺址へ来ました。
百済時代に都だったサビ城(地図の中で、羅城で囲まれた区域)の中心に建っていた寺。
百済時代の遺跡として残っているのは、石塔のみ。(国宝)

石塔の奥の伽藍にある石仏。 660年に、百済の滅亡とともに焼失した定林寺、高麗時代の1028年に新しく建てられ、その
本尊仏となった石仏。 頭部は後代に造られたものとのこと。

韓国の昔の国家が造った巨大寺院(新羅の皇龍寺、百済の弥勒寺、定林寺)は、大半が破壊、焼失していることにウーンでした。
次は公州へバス移動。 宋山里(ソンサルリ)古墳群で、7つの王陵がある。
5、6号墳と7号墳(武寧王陵)のレプリカがある模型展示館に入ります。

6号墳の断面 四神が描かれている。

武寧王(第25代の百済王)の胸像

武寧王陵は、1971年に排水路の工事中に偶然発見された。 他の陵墓はすべて盗掘されているが
奇跡的に1500年前の状態で発掘された。 被葬者がわかる唯一の王陵。

王と王妃の木棺は、国立公州博物館に展示されているので、Webサイトから引用。
木棺は日本特産の高野槙(コウヤマキ)で作られているそうだ。

武寧王陵の石室内壁もレンガ製で、描かれている模様は蓮の花。

実際の武寧王陵の石室入口です。

この日最後は、公山城です。
百済の創建は、紀元前に、今のソウルである漢城(ハンソン)から始まったとされ、北方の強国、高句麗に悩まされた。
西暦475年、高句麗の侵攻によって熊津(ウンジン/現在の公州市)に都を移す。 その山城が公山城(コンサンソン)。
熊津時代に再び力をつけた百済は、538年、泗沘(サビ/現在の扶余)に遷都した。
錦西楼という楼門への道を登っていきます。

城壁上の道から市街の眺め。 時刻は17時58分

一周して、錦西楼に戻ってきました。


夕食は公州市内の食堂で、蓮の葉包み御飯定食。

公州から宿泊先の大田市までバス移動。 夜9時前、ホテルの部屋の窓から市内を撮影。
セブンイレブンが見えたので、買物に行き、身振り手振りで何とか買えました。

部屋のなか。 スマホの歩数計を見ると2万歩! 風呂に入ってバッタンキューでした。


















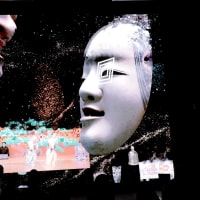










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます