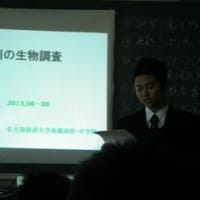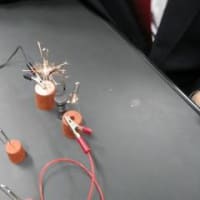11月14日(月)
今日は、理科部で飼育している淡水魚の水槽の掃除をすることになりました。
12月になると、気温も低くなり、大量の水を扱う水槽の掃除は大変になるので、この時期に行います。

まずは、職員室の前にある水槽の掃除から始めます。
この水槽は90センチメートル水槽なので、水は100リットルくらい入ります。
だから、何人かで手伝わないと、水替えは大変です。

理科部の秘密兵器です。
大きなバケツと水を抜くためのホースです。

水を抜いた水槽は水アカとコケでいっぱいになっています。
職員室は2階にあります。
だから、この水槽を1階にある水洗い場までみんなで運びます。
運んでから、水槽の中の砂と水槽のガラス面をきれいに洗います。
これがなかなか大変な作業なのです。

半分くらい水を抜いた水槽全体です。

水槽から水を抜いているところです。
ホースが役に立ちます。
バケツで水を抜くと、服がぬれて大変になります。

水槽の中の砂を取り出し、ざると洗面器とバケツを使ってきれいに洗います。

砂を洗う様子です。

ざるが足りないので、洗面器に水を入れてお米をとぐ要領で洗う人もいます。
少ない道具で工夫をしていますね。

何度も何度も洗います。

職員室の前にあった水槽が運ばれてきました。
ガラスを洗うには、雑巾(ぞうきん)を使います。
ひたすら磨(みが)くのです。

今度は、外に置いてある2つの90センチメートル水槽です。
これを時間短縮のため、ガラス面を磨きながら水を抜いていきます。

2台あることが分かりますね。
丁寧(ていねい)に時間をかけて磨きます。

こちらでは、水を抜いています。

左の水槽はほとんど水がなくなりました。
この時に、魚をすくって水の入ったバケツに入れます。

まだ磨いていますね。

外の水槽の砂を洗っています。

まだまだ磨きます。

今度は、水を入れていきます。
水道水です。
水槽に入っていた水は、1割ほどしか戻しません。
普通、3分の1ほどは水槽の水を入れますが、この魚たちは水道水に少しずつならしてきているので、
1割ほどで大丈夫です。
しかも、水道水の塩素の消毒の力で、病気になりにくいという利点もあります。

バケツに入っている魚たちです。

水槽に水を戻したところです。
とても濁(にご)っているように見えますが、大丈夫です。
明日になれば、きれいに澄んだ水になるはずです。

魚を戻しているところです。

修学旅行に行っていた高校2年生は、シャボン玉の実験をやっていません。
そのために、今日はシャボン玉と水槽の水替えに分かれて活動しました。
シャボン玉の後片付けが終わったので、手伝いにやってきました。

片づけをみんなで行います。
人数が増えると、あっという間に片付きます。

帰る準備をしています。
水槽の水替えをしている人の荷物は、「シャボン玉組」が持ってきました。

今日のミーティングは、時間も遅くなってしまったので、外で行います。
内田先生は、今日一日の反省と感謝の言葉を言ってくれました。
少し嫌なことも続けていくことが大切だという言葉が印象に残りました。
今後も頑張って活動していきたいと思います。
今日は、理科部で飼育している淡水魚の水槽の掃除をすることになりました。
12月になると、気温も低くなり、大量の水を扱う水槽の掃除は大変になるので、この時期に行います。

まずは、職員室の前にある水槽の掃除から始めます。
この水槽は90センチメートル水槽なので、水は100リットルくらい入ります。
だから、何人かで手伝わないと、水替えは大変です。

理科部の秘密兵器です。
大きなバケツと水を抜くためのホースです。

水を抜いた水槽は水アカとコケでいっぱいになっています。
職員室は2階にあります。
だから、この水槽を1階にある水洗い場までみんなで運びます。
運んでから、水槽の中の砂と水槽のガラス面をきれいに洗います。
これがなかなか大変な作業なのです。

半分くらい水を抜いた水槽全体です。

水槽から水を抜いているところです。
ホースが役に立ちます。
バケツで水を抜くと、服がぬれて大変になります。

水槽の中の砂を取り出し、ざると洗面器とバケツを使ってきれいに洗います。

砂を洗う様子です。

ざるが足りないので、洗面器に水を入れてお米をとぐ要領で洗う人もいます。
少ない道具で工夫をしていますね。

何度も何度も洗います。

職員室の前にあった水槽が運ばれてきました。
ガラスを洗うには、雑巾(ぞうきん)を使います。
ひたすら磨(みが)くのです。

今度は、外に置いてある2つの90センチメートル水槽です。
これを時間短縮のため、ガラス面を磨きながら水を抜いていきます。

2台あることが分かりますね。
丁寧(ていねい)に時間をかけて磨きます。

こちらでは、水を抜いています。

左の水槽はほとんど水がなくなりました。
この時に、魚をすくって水の入ったバケツに入れます。

まだ磨いていますね。

外の水槽の砂を洗っています。

まだまだ磨きます。

今度は、水を入れていきます。
水道水です。
水槽に入っていた水は、1割ほどしか戻しません。
普通、3分の1ほどは水槽の水を入れますが、この魚たちは水道水に少しずつならしてきているので、
1割ほどで大丈夫です。
しかも、水道水の塩素の消毒の力で、病気になりにくいという利点もあります。

バケツに入っている魚たちです。

水槽に水を戻したところです。
とても濁(にご)っているように見えますが、大丈夫です。
明日になれば、きれいに澄んだ水になるはずです。

魚を戻しているところです。

修学旅行に行っていた高校2年生は、シャボン玉の実験をやっていません。
そのために、今日はシャボン玉と水槽の水替えに分かれて活動しました。
シャボン玉の後片付けが終わったので、手伝いにやってきました。

片づけをみんなで行います。
人数が増えると、あっという間に片付きます。

帰る準備をしています。
水槽の水替えをしている人の荷物は、「シャボン玉組」が持ってきました。

今日のミーティングは、時間も遅くなってしまったので、外で行います。
内田先生は、今日一日の反省と感謝の言葉を言ってくれました。
少し嫌なことも続けていくことが大切だという言葉が印象に残りました。
今後も頑張って活動していきたいと思います。