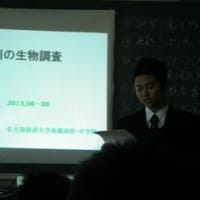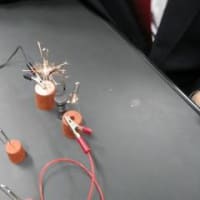5月2日(月)
昆虫が苦手な部員も、大好きな部員もいる私たち理科部ですが、せっかく頂いた「命」は大切に育むのがこの理科部の方針です。
苦手な人は、生物実験室の掃除や、容器の洗い物に回ったりします。

男子は、昆虫が好きな人が多いようで、すぐに容器の周りに集まってきました。

衣装ケースの中に100匹ちかくの幼虫がいます。
こんなかんじで飼育しています。

マットをさわると、すぐカブトムシの幼虫が出てきました。

手のひらにのせると、その大きさが分かります。
小さいときにカブトムシの幼虫を触ったことのない人も勇気を持って触ります。
これも「経験のうち」です。

どんどん幼虫が出てきました。

競って手に取ります。

嬉しそうですね。

大きさと雄か雌を確認します。

中学一年生が楽しんでいる中、後ろではマット作りと洗い物をしています。それぞれができることを見つけます。衣装ケースの中のマットはカブトムシの糞(ふん)でいっぱいでした。ふるいで糞とマットに分けます。糞は校庭の木の根元にまきます。良い肥料になります。残ったマットはまたケースの中に入れて再利用します。新しく入れるマットも、一度クワガタムシが食べたカスを与えます。

マットの中にクワガタムシの幼虫と割り出した木くずを入れます。

こんな感じで完了です。

掃除も完了し、一息ついています。

次の実験の相談です。今日はこれで終了しました。
【感想】(一部抜粋)
・カブトムシの幼虫が思ったよりも大きくてビックリしました。[中1]
・カブトムシの幼虫の生態が詳しく分かって良かったです。[中3]
・あまりにもたくさんの幼虫がいたので、気持ち悪かったです。[高1]
・衣装ケースのマットの中にあった、フンの多さを考えると一匹の幼虫がたくさんマットを食べるのだと実感しました。[高2]
・今日は自分なりに頑張ったつもりでしたが、カブトムシの幼虫を触ることは無理でした。その分、マットを作り、上にかけてあげたり、掃除をしたりして、自分なりに協力しました。もう少し、自分からいろんなことができるようにしたいと思いました。
カブトムシの幼虫の「部屋」がきれいになり、えさであるマットも十分になり、一安心しました。[中2]
昆虫が苦手な部員も、大好きな部員もいる私たち理科部ですが、せっかく頂いた「命」は大切に育むのがこの理科部の方針です。
苦手な人は、生物実験室の掃除や、容器の洗い物に回ったりします。

男子は、昆虫が好きな人が多いようで、すぐに容器の周りに集まってきました。

衣装ケースの中に100匹ちかくの幼虫がいます。
こんなかんじで飼育しています。

マットをさわると、すぐカブトムシの幼虫が出てきました。

手のひらにのせると、その大きさが分かります。
小さいときにカブトムシの幼虫を触ったことのない人も勇気を持って触ります。
これも「経験のうち」です。

どんどん幼虫が出てきました。

競って手に取ります。

嬉しそうですね。

大きさと雄か雌を確認します。

中学一年生が楽しんでいる中、後ろではマット作りと洗い物をしています。それぞれができることを見つけます。衣装ケースの中のマットはカブトムシの糞(ふん)でいっぱいでした。ふるいで糞とマットに分けます。糞は校庭の木の根元にまきます。良い肥料になります。残ったマットはまたケースの中に入れて再利用します。新しく入れるマットも、一度クワガタムシが食べたカスを与えます。

マットの中にクワガタムシの幼虫と割り出した木くずを入れます。

こんな感じで完了です。

掃除も完了し、一息ついています。

次の実験の相談です。今日はこれで終了しました。
【感想】(一部抜粋)
・カブトムシの幼虫が思ったよりも大きくてビックリしました。[中1]
・カブトムシの幼虫の生態が詳しく分かって良かったです。[中3]
・あまりにもたくさんの幼虫がいたので、気持ち悪かったです。[高1]
・衣装ケースのマットの中にあった、フンの多さを考えると一匹の幼虫がたくさんマットを食べるのだと実感しました。[高2]
・今日は自分なりに頑張ったつもりでしたが、カブトムシの幼虫を触ることは無理でした。その分、マットを作り、上にかけてあげたり、掃除をしたりして、自分なりに協力しました。もう少し、自分からいろんなことができるようにしたいと思いました。
カブトムシの幼虫の「部屋」がきれいになり、えさであるマットも十分になり、一安心しました。[中2]