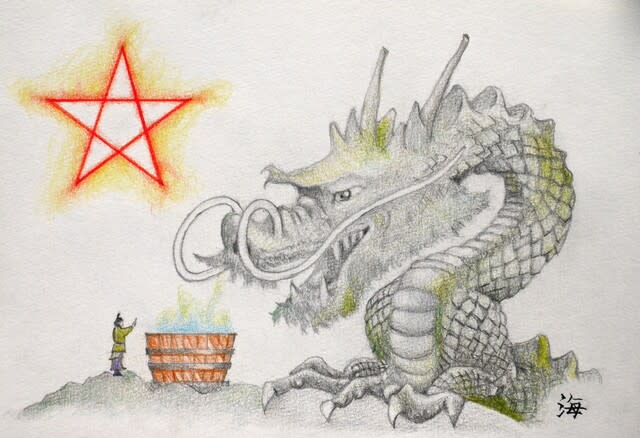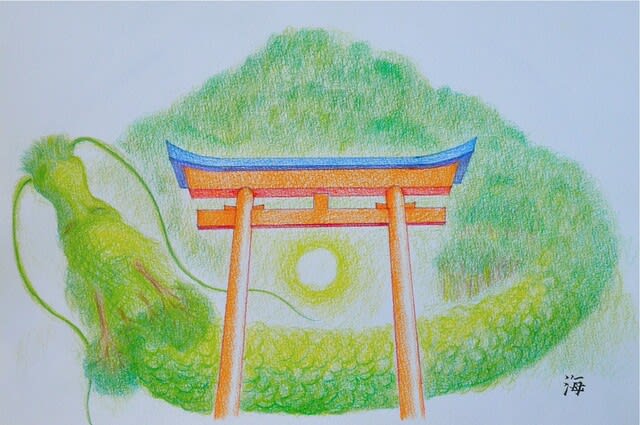「猪が出ます。
見ても無視すれば襲いません。」

なんかこうジワジワきます・・・が、
反射神経の働きと “ 感情 ” というものを持つ人間にとっては、
この「見ても無視」することが結構難しいのであります。
というわけで、今回早川が訪れてまいりましたのは、
イノシシが出没するような山間部。
奈良県は、近畿日本鉄道の信貴山下駅からバスで約20分、

信貴山・朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)へ。

上掲の鳥居をくぐって参道を登ってゆきますと、

信貴山のシンボル、“ 大寅 ” あり。
その隣には、二体の “ 小寅 ” あり。

信貴山を参拝致しましたのは、実に12年ぶりですが、
12年前に訪れた際には “ 小寅 ” は設置されていませんでした。



本年令和4年は “ 寅年 ” に当たります。
“ 寅 ” との縁深き信貴山では、
12年に1度巡り来る寅年の限られた期間内において、
全山挙げての伝統儀式が執り行われるとあって、
その儀式に参列すべく訪れたわけであります。
信貴山は、歴史と由緒のある有名寺院でありますので、
もはや書かずもがなのこととは思いますが、
今を去る1440年前の敏達天皇11年(582)、
聖徳太子(574~622)が偶々分け入った山の中において、
“ 毘沙門天王 ” を感得し、心願成就を祈ったところ叶えられます。
そこで太子は、この山のことを、
「信じ貴ぶべき山」として「信貴山(しぎさん)」と名付け、
寺伝では、この年を “ 信貴山開創 ” の年としています。
又この年が、
十二支と十干(じゅっかん)の組み合わせで謂うところの、
“ 壬寅(みずのえ とら) ” の年回りであり、
更に太子が毘沙門天王を感得したのが寅の月・寅の日・寅の刻と、
“ 寅づくし ” であったことから《毘沙門天王・信貴山・寅》は、
言わば “ 三点セット ” 、切っても切れない結びつきとして、
広く世の中に知られるようになったとも伝わります。
先に「本年令和4年は “ 寅年 ” に当たり」と書き、
信貴山開創は「1440年前の敏達天皇11年(582)」と記しました。
つまり本年令和4年は、
聖徳太子が毘沙門天王を感得した “ 寅年 ” から数えて、
120回めの “ 寅年 ” であり、
24巡めの “ 壬寅(みずのえ とら) ” ということであります。
《巷間既知のことながら一応簡略に書かせて頂きますと、
十二支(子・丑・寅など12種)十干(甲・乙・丙など10種)を、
その組み合わせで表したもの、
例えば甲子(きのえ ね)乙丑(きのと うし)等々は、
古来「十二支・十干暦法」として年々に当てはめられ、
この暦法では、同じ組み合わせが、60年に一度巡ります。
生まれ年の「暦」が、60年の歳月を経て再び巡り「還」るため、
「還暦」とされます。上記の場合、1440年 ÷ 60年 = 24巡 》
こうした節目の中の節目に厳修される法会・法要とあって、
信貴山には大勢の参拝者が訪れ、儀式に臨んでおられました。
只、この日の奈良は朝から天候不順。
儀式後は、信貴山を隈無く巡拝しようと思っていたのですが、
雨強くして足元おぼつかず、幾つかの堂宇参拝にとどまり、
また片手に傘、片手に授かり物で、カメラの構えようもなく、
上掲写真以外には撮ることも出来ず山を下りてまいりました。



信貴山は山全体が一つの寺院であり、言わば「山岳伽藍」。
こちらは信貴山で配られているMAPですが、御覧のように、

朝護孫子寺の本堂、千手院、成福院、玉蔵院、本坊の他、
開山堂、三宝堂、虚空蔵堂を始め、大小の祠堂が林立していて、
それらの全てを参拝し、なお弁財天の滝や奥の院まで巡るとなれば、
半日でも足りるかどうか。
歳月人を待たず、光陰矢の如し。
前回から12年という歳月を経ての参拝となってしまいましたが、
出来れば早い時期に再訪したいと思います。
“ toward the Light ”

皆様、良き日々でありますように!






見ても無視すれば襲いません。」

なんかこうジワジワきます・・・が、
反射神経の働きと “ 感情 ” というものを持つ人間にとっては、
この「見ても無視」することが結構難しいのであります。
というわけで、今回早川が訪れてまいりましたのは、
イノシシが出没するような山間部。
奈良県は、近畿日本鉄道の信貴山下駅からバスで約20分、

信貴山・朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)へ。

上掲の鳥居をくぐって参道を登ってゆきますと、

信貴山のシンボル、“ 大寅 ” あり。
その隣には、二体の “ 小寅 ” あり。

信貴山を参拝致しましたのは、実に12年ぶりですが、
12年前に訪れた際には “ 小寅 ” は設置されていませんでした。



本年令和4年は “ 寅年 ” に当たります。
“ 寅 ” との縁深き信貴山では、
12年に1度巡り来る寅年の限られた期間内において、
全山挙げての伝統儀式が執り行われるとあって、
その儀式に参列すべく訪れたわけであります。
信貴山は、歴史と由緒のある有名寺院でありますので、
もはや書かずもがなのこととは思いますが、
今を去る1440年前の敏達天皇11年(582)、
聖徳太子(574~622)が偶々分け入った山の中において、
“ 毘沙門天王 ” を感得し、心願成就を祈ったところ叶えられます。
そこで太子は、この山のことを、
「信じ貴ぶべき山」として「信貴山(しぎさん)」と名付け、
寺伝では、この年を “ 信貴山開創 ” の年としています。
又この年が、
十二支と十干(じゅっかん)の組み合わせで謂うところの、
“ 壬寅(みずのえ とら) ” の年回りであり、
更に太子が毘沙門天王を感得したのが寅の月・寅の日・寅の刻と、
“ 寅づくし ” であったことから《毘沙門天王・信貴山・寅》は、
言わば “ 三点セット ” 、切っても切れない結びつきとして、
広く世の中に知られるようになったとも伝わります。
先に「本年令和4年は “ 寅年 ” に当たり」と書き、
信貴山開創は「1440年前の敏達天皇11年(582)」と記しました。
つまり本年令和4年は、
聖徳太子が毘沙門天王を感得した “ 寅年 ” から数えて、
120回めの “ 寅年 ” であり、
24巡めの “ 壬寅(みずのえ とら) ” ということであります。
《巷間既知のことながら一応簡略に書かせて頂きますと、
十二支(子・丑・寅など12種)十干(甲・乙・丙など10種)を、
その組み合わせで表したもの、
例えば甲子(きのえ ね)乙丑(きのと うし)等々は、
古来「十二支・十干暦法」として年々に当てはめられ、
この暦法では、同じ組み合わせが、60年に一度巡ります。
生まれ年の「暦」が、60年の歳月を経て再び巡り「還」るため、
「還暦」とされます。上記の場合、1440年 ÷ 60年 = 24巡 》
こうした節目の中の節目に厳修される法会・法要とあって、
信貴山には大勢の参拝者が訪れ、儀式に臨んでおられました。
只、この日の奈良は朝から天候不順。
儀式後は、信貴山を隈無く巡拝しようと思っていたのですが、
雨強くして足元おぼつかず、幾つかの堂宇参拝にとどまり、
また片手に傘、片手に授かり物で、カメラの構えようもなく、
上掲写真以外には撮ることも出来ず山を下りてまいりました。



信貴山は山全体が一つの寺院であり、言わば「山岳伽藍」。
こちらは信貴山で配られているMAPですが、御覧のように、

朝護孫子寺の本堂、千手院、成福院、玉蔵院、本坊の他、
開山堂、三宝堂、虚空蔵堂を始め、大小の祠堂が林立していて、
それらの全てを参拝し、なお弁財天の滝や奥の院まで巡るとなれば、
半日でも足りるかどうか。
歳月人を待たず、光陰矢の如し。
前回から12年という歳月を経ての参拝となってしまいましたが、
出来れば早い時期に再訪したいと思います。
“ toward the Light ”

皆様、良き日々でありますように!